たとえば、ジェンダーのこと。“魔法の国のお姫様”の下界生活物語である『魔法使いサリー』(1966年)や、周りの子どもとはひとりだけ違うおしゃれな洋服を着、洋風の豪邸に住む“お嬢様”が魔法を使って人助けする『ひみつのアッコちゃん』(1969年)は、アニメを見ている一般的な女の子たちの生活からはかけ離れた憧れの存在を描く作品。同時に、この時期は70年代のウーマン・リブ運動前夜であり、両親、男女の先生や友達の姿には、社会が求める理想的な「男性らしさ・女性らしさ」がハッキリと表現されていました。
それは『魔法天使 クリィミーマミ』や『カードキャプターさくら』などを経て、2000年代の『おジャ魔女どれみ』『プリキュア』シリーズになると、視聴者の女の子たちと近い普段着の魔法少女たちが活躍するようになります。仲間の中にはおしとやかな子もボーイッシュな言葉遣いの子をいて、多様な個性の女の子たちがスーパー戦隊さながらにチームで戦う姿も描かれるのです。
特に2004年の放送開始以降ヒットし続けている『プリキュア』シリーズでは、魔法で可愛らしい衣装に変身しては肉弾戦を繰り広げ、丸っこいブーツを履いて両足を踏ん張る作品も。そこには「男のくせに・女のくせに」というくくりが子どもの可能性を潰しかねないという製作陣の思いがあり、ちょうどこの頃から男の子も女の子もランドセルの色を自由に選べるようになったように、それぞれに理想の女の子像を抱ける自由をくれたのです。
◆ケトル VOL.32(2016年8月12日発売)


















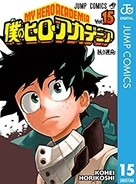











![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








