だいたいは兵士が手で持って鳴らすのが「横山三国志」の一般的な登場の仕方ですが、本物の三国志通を目指す者としては、これを一生に一度は鳴らしてみたいもの。しかしそもそも現代では残っていない可能性もあります。実態を確かめるため、都内にある中国楽器専門店を取材することにしました。
向かったのは十条駅(東京都北区)にある中国屋楽器店。店長さんに案内してもらうと、次々と出て来る大きさの違う銅鑼の数々。ここに三国時代に使われたものと同じ銅鑼があるのでしょうか?
「いや、三国時代の銅鑼とは全然違うものです」
え、そうなの? いったい何が違うんですか?
「使用目的の違いが大きいです。銅鑼に限らず太鼓などの打楽器は、合図など人に情報を伝える手段として使われたのが始まりです。その後、芝居などの娯楽が発達していくに従い、楽器として使われるようになりました」
戦争に使われていた銅鑼は、月日が経つにつれ楽器として進化していったということですね。
「1978年に発掘された西漢(前漢)初期の銅鑼が、現存している最古のもとのいわれています。紀元前2世紀から中国の内陸に伝わり、当時は主に軍事用でした。
そして最大の問題、これって買うことはできるのですか?
「できますよ! 当店で扱っているのは22cmから130mの銅鑼ですが、22cmだと800円、一番大きいものになると49万8000円です」
小さいものなら買えないこともないものの……。そもそも現代では、この銅鑼はどのように使われているのでしょうか?
「大きいものになると低周波(人間の耳では聞き取れない音)が発生するので、治療器具として使用しているところもあるようです。また、当店の銅鑼はプロレスの開会式やパチンコ店のオープニングイベントなどによくレンタルされていますね」
もちろん楽器として使われているんですよね? 三国志キッカケの人はいるのでしょうか?
「銅鑼はあんまりいないです。中国楽器だと二胡と古筝を習いに来られる方が多いです。以前『三國無双』というゲームの声優さんが古箏を習いに来たこともありましたよ」
取材後、実際に銅鑼を叩かせてもらいましたが、たしかに「ジャーンジャーン」としか形容できない音が出ました。横山光輝先生もこの音を聞いて、あの擬音を描いたのでしょうか。しかし、これは現代の楽器用の銅鑼ですから、戦争用の銅鑼がどんな音だったのかは依然謎に包まれたまま。本当の「ジャーンジャーン」は、どんな音なのでしょうか。
◆ケトル VOL.37(2017年6月14日発売)




























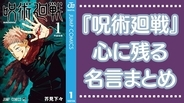
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








