- 2025 Japan All AWS Certifications Engineers147名
- 2025 Japan AWS Top Engineers30名
- 2025 Japan AWS Ambassadors 3名
- 2025 Japan AWS Jr. Champions1名
そんなクラスメソッドに根付いている、“社員が自然と情報発信に取り組む文化”、そしてそれを支える“DevelopersIO”。アウトプットを歓迎する風土と、発信が信頼や価値に直結する実感が、技術者たちの意欲を後押ししています。
今回は、今年「2025 Japan AWS Ambassadors」を受賞した3名に、クラスメソッドの文化についてインタビューします。
共通する入社理由は、クラスメソッドの発信力への信頼から
— まず、皆さんのこれまでのご経歴や現在の業務について教えてください。山本:私は新卒でSIerに入社し、最初の2年はオンプレミスの仮想化基盤の運用・保守をしていました。当時はクラウドとは無縁でしたが、「若手はクラウドに挑戦すべし」という社内の支援もあり、高知県から東京に転勤になり、初めてAWSやAzureに触れるプロジェクトに参加しました。プロジェクトには恵まれた前職でしたが、技術的なトピックを相談できる仲間が少ないことが少し寂しい環境でした。そこで、思い立って「DevelopersIO」などの発信から、技術について語れる仲間がいると感じ、クラスメソッドへ転職。入社後はAWSを軸にコンサル・設計・構築など、幅広く担当しています。
筧:私は元々、前職ではセキュリティ関連のチームに所属していて、クラウドに直接的には関わっていませんでした。ただクラウドにはずっと興味があったので、クラウドに強いクラスメソッドに転職し、最初はテクニカルサポートに配属。その中で「もっと開発がやりたい」と手を動かし始め、ツール開発や自動化に取り組むうちにAI案件にも関わるようになりました。今はAI-Starterという生成AI関連プロダクトを主軸に、社内外展開や顧客向けのコンサルティングを担当しています。
高国 :私は2020年に新卒で前職に入社し、オンプレ等は経験せず、クラウド一筋のキャリアです。AWSやAzureの設計・構築していました。よりAWSのキャリアに寄せたい思いも芽生え、私も以前からブログ等で知っていたクラスメソッドへ2022年に転職。入社後は、新規顧客を中心に、AWS導入の支援や最新技術の導入を一緒に進めています。今は案件以外にも、社内向けツール開発やAWSとのPoC(概念実証)、SDP認定の取得支援なども担当しています。

アウトプットは通貨?発信が信頼につながるエンジニアにとって理想の環境?
— クラスメソッドでは、なぜこれほど情報発信が活発に行われているのでしょうか?山本:他の企業だと「業務と直結することしか業務時間中に取り組みづらい」という暗黙のルールがあるものだと思います。しかし、クラスメソッドでは技術を探求することに制限がなく、ブログ執筆やコミュニティ活動等が歓迎されています。むしろ、そうしたアウトプットが営業資料として使われたり、実際の案件につながったりすることもあります。実際、私もお客様との初期打ち合わせでブログを紹介して、それがきっかけで案件を受注できたことがありました。
高国 :私は「アウトプット=通貨」みたいな感覚を持っていて、発信すればするほど信頼が蓄積されて、別の仕事がしやすくなると感じています。例えば、社内で何か新しいことを始めたいときでも、「この人なら任せても大丈夫」と思ってもらえるのは、過去のアウトプットがあるからだと思います。
筧:たしかに、情報発信が“信頼の貯金”になっているという感覚はありますね。私も、登壇やブログがきっかけで「この人に相談してみよう」と思ってもらえることが増えましたし、実際にブログを営業資料として使ったり、提案時の参考資料として活用されたりしています。
高国 :以前、私が書いたブログが海外のプロダクトチームの目に留まり、PoCの依頼をいただきました。たまたまその領域の記事を書いている日本人がほとんどいなかったという背景もありますが、まさかこのような形で業務とつながるとは思わず、発信の力を改めて実感しました。
— そのアウトプットが、皆さんが入社するきっかけにもなっているんですよね。
山本:「DevelopersIO」などを通して、自分と近い考え方を持った仲間がいるだろうなと、あらかじめわかっていたので、期待して入社できましたね。今まで外部のイベントへの登壇などは、会社からブロックされたこともありませんし、AWS re:Inventのような、海外で行われるイベントへの出席への後押しも大きいです。
筧:基本的にやりたいと申し出たら、制限されることは何もありません。イベントの登壇やコミュニティ活動だけでなく、ツールの使用など、さまざまな面で自由にやらせてもらえるので、エンジニアにとっては理想の環境かもしれません。
— 理想の環境である反面、厳しさを感じる面もあるのでしょうか?
筧:入社当初は、周囲のレベルの高さに無力感を持ってしまうこともありました。ただ、情熱さえあれば自己成長しやすい仕組みが整っているのがクラスメソッドの良さです。公開ナレッジや発信文化、挑戦を歓迎する空気があり、学びの導線が明確です。
高国:最近では、アウトプットをしなくなると怖くなる、という感覚があります。
山本:このような会社なので、自ら働きかけるアクションをしないと埋もれてしまう感覚はあります。自分ならではの強みを作り、他者との差別化できるポイントを考えて行動した結果、今回のような受賞があったと思っています。
— 日頃はどのように技術情報をキャッチしていますか?
山本:日頃からAWSのTOPエンジニアの情報をRSSやXで追っているので、タイムラインにはほしい情報が集まりやすくなっています。トレンドを追いつつ、得た情報を咀嚼し、自分の言葉で言語化することを意識。知識を定着させるには言語化することが重要だと考えています。
高国:朝にRSSでAWSのアップデートを確認しています。興味ある分野は、手を動かして試し、解像度を上げてブログにまとめることで、知識として定着させています。
筧:AI分野を中心に、Xで発信者をリスト化して定点観測しています。気づきは社内チャンネルで共有し、議論することで解像度をあげています。ビジネスに繋がりそうなことは即時検証・実装し、外部発信することでナレッジとして昇華します。

手を挙げればチャンスが巡ってくる環境
— このような文化が根付いている背景には、組織的な支援や仕組みがあるからなのでしょうか?山本:入社したら必ず1本ブログを書くので、そこでブログの作法やシステムの操作方法は学びますが、特筆すべき制度のようなものはありません。発信や登壇を制度でコントロールするのではなく、「やりたいなら、やってみよう」という風潮ができています。ちゃんと手を挙げてアピールすれば、自然にチャンスが回ってきます。また、若手にも機会を作ってあげようとする空気もあるので、挑戦しやすい環境になっていると思います。
高国 :情報発信が当たり前になっているのは、社長自身がエンジニアで発信者でもあることが大きいと思います。トップがそうだから、現場にも自然と広がる。私は、アウトプットが認められ、次につながる構造がしっかりあることが一番大きいと感じます。
筧:加えて、「発信が認められないかもしれない」という不安がないことも大事だと感じます。クラスメソッドには「発信すれば認められる」という共通認識があるからこそ、皆が自然と情報を外部に共有しようというマインドを持てる。この環境に感謝しています。
山本:そうですよね。だからこそ、上司を説得するための材料集めのようなことに時間を割く場面を経験したことがありません。
— このような情報発信がクラスメソッドのビジネスに結びついている感覚はありますか?
山本:ブログなどのアウトプットは自己紹介代わりになっています。結果、商材や提案の一つになっています。お客様との定例でも、ブログを紹介することで信頼感や期待感が生まれ、商談のスピードも上がります。
筧:検索やSNSで見つかりやすくなり、第一想起される存在になる一因になっていると考えます。また、発信によって、我々のスキルの透明化や合意形成の加速が可能になり、「相談しやすい・任せやすいエンジニア」としての信頼を構築できていると思います。
高国:あらかじめ技術を試し、自分の中で腹落ちしている/説明できる状態を作っておくことでお客様の技術課題への提案力が向上していると感じます。ブログが「技術の共通言語」として機能しているので、お客様も私たちの技術観や課題解決のアプローチを事前に把握でき、打ち合わせの質も向上します。私たちがどんな技術観を持っていて、どういうアプローチで問題解決するかを、事前に確認できることはお客様の安心感につながっているはずです。
— 今回、AWS関連の受賞を受けて、何か周囲から反応はありましたか?
筧:前職の同僚などからも声をかけてもらったりすることもあり、皆さんがみているんだなと実感しています。こういう活動がお客様への信頼にもつながるんだろうと思います。
高国 :社内から声をかけてもらうことがありました。
山本:AWSや会社から発信してもらえるので、それをみた妻から褒められますね(笑)一方、受賞したことを自分自身のプラスだけで終わらせず、会社にとってプラスにしていかなければいけないと、より一層思うようになりました。

個人の技術力を会社の成長へと繋げたい
— 皆さんが次に挑戦していきたいことがあれば、教えてください。山本:このような従業員の技術的な活動について応援してもらえるのは、前提として会社が健全に成長しているからだと思います。これからもクラウド技術の領域に閉じず、セキュリティやDB周りなどの技術も学びながら、お客様に最適な提案ができるよう技術の“引き出し”を増やしていきたいです。
高国 :よりお客様の課題に寄り添ったソリューションを提案するための手札を揃えるためにも、より幅広い技術知識をつけていきたいですね。せっかくアンバサダーにも任命いただいたので、この名前を活用して、社内の育成やSDPの認定取得支援といった仕組みづくりなど、より会社をよくすることにも力を入れていきたいです。
筧:現在注力している生成AIを軸にしたサービス開発・コンサルティングの事業を、ゆくゆくはクラスメソッドの新しい柱になるビジネスとして育てたいです。AWSだけのクラスメソッドではないことを名実共に示していきたいですね。
— これからも皆さんの活躍に期待しています!
ーーー
クラウド事業本部コンサルティング部 山本 涼太(のんピ)
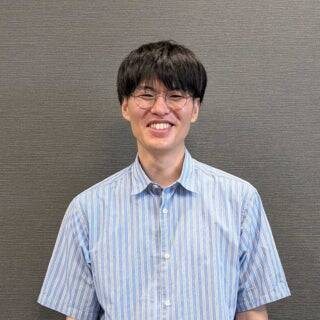
メーカー系SIerにてオンプレミスの仮想化基盤の構築、運用保守およびAWSへの移行プロジェクトに従事。2021年4月にクラスメソッド入社。現在はプリセールス、PM、アーキテクトとして案件規模関わらずAWSに関する領域全体を担当。得意領域はネットワーク、ストレージ、IaC。
受賞実績:
- Japan AWS Top Engineers 2022 ~ 2025
- Japan AWS All Certifications Engineers 2022 ~ 2025
- Japan AWS Ambassadors 2023 ~ 2025
- NetApp Advanced Solution Leading Award 2023 ~ 2025
新規事業統括部 生成AIインテグレーション部 筧 剛彰
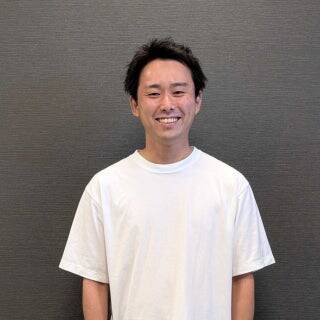
2019年10月、クラスメソッド入社。生成AIを中心に、企画・開発から導入コンサル、伴走支援までを担当するソフトウェアエンジニア。自社プロダクト「AI-Starter」のサービスオーナー。著書に「ビジネスのためのChatGPT活用ガイド」。
受賞実績:
- Japan AWS Ambassadors 2025
- Japan AWS Top Engineers 2021 ~ 2023
- Japan AWS All Certifications Engineers 2022 ~ 2023
クラウド事業本部コンサルティング部 高国 真之介

SI事業を主軸とした AWS パートナー企業にて、AWS・Azureクラウドの設計・構築業務に従事した後、2022年1月にクラスメソッド入社。現在は PoC など、スピード感を持って新しいものを生み出していくプロジェクトや、得意領域を活かした長期のコンサルティング支援を担当。得意領域はコンテナ、生成AI、IaC。
受賞実績:
- Japan AWS Ambassadors 2025
- Japan AWS Top Engineers 2022 ~ 2024
- Japan AWS All Certifications Engineers 2022 ~ 2024
- HashiCorp Ambassadors 2023 ~ 2024























