謎多き伝説の俳優、ジョン・マルコヴィッチ。変人、狂人と言われるマルコヴィッチだが、共演者や関係者は彼を愛して止まない。
今から9年前の2010年、ローリングストーン誌の依頼でジョン・マルコヴィッチにインタヴューするため、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏にある彼の自宅を訪れた。当時はちょうど、彼の出演した新作『RED/レッド(原題:RED)』(LSD中毒の元CIAエージェント役)と『セクレタリアト/奇跡のサラブレッド(原題:Secretariat)』(気難しい調教師役)の2本が公開される時期だった。両作品でマルコヴィッチは有名な変人を演じ、どちらもヒットした。しかしどういう訳か、同インタヴュー記事が公開されることはなかった。出版業界特有の気まぐれか、ローリングストーン誌の編集者による突飛な思いつきだろう。本記事は、改訂して公開されるのを暗い蔵の中でじっと待っていたのだ。
しかし、今日になってついに公開できることとなったのは、内容が改訂されたからではない。現在に至るまでの俳優の素晴らしいポートレートを表現するのに、内容の変更はほとんど必要ないことに気づいたからだ。彼はその後、多くの作品に出演している。ショウタイムで放送されたヘッジファンダー対司法を描いたテレビドラマ『ビリオンズ(原題:Billions)』で極悪非道なロシア人新興実業家を演じ、BBCで放送されその後Amazon Primeでも視聴可能となった『ABC殺人事件(原題:The ABC Murders)』では、アガサ・クリスティー作品ではお馴染みの探偵エルキュール・ポワロを演じた。
65歳になったマルコヴィッチは、ひと息つくような気配を全く見せない。自分を取り巻く環境は変化しているかもしれないが、マルコヴィッチは揺るぎないように見える。しなやかな常緑樹のように、どこでも常に彼らしい存在感を出す。ここに私が9年前に書いた彼のインタヴュー記事があるが、以上のような理由で内容は改訂されていない。当時の彼と今の彼は、ほとんど変わりがないのだ。もちろん米中西部で過ごした少年時代とは全く容姿が異なる。当時の彼は、体重が標準より30kgオーバーで”ふとっちょ”などと呼ばれることもあったという。靴に矯正具を付けて歩く彼はよく、スリムで格好良いスカーフを巻いたイタリア人のプレイボーイ”トニー”になりきることがあった。その後あらゆる役を演じることとなる彼の初めての演技経験といえる。
フランス郊外の閑静な雰囲気に囲まれた自宅の外で、ジョン・マルコヴィッチは遠くを見渡していた。
草木の綿毛が舞い、彼の目が追う。タバコをつまみ上げて火をつける。ついに彼は、面白がって見下した態度を取る時によくやるように唇を動かし、ずっと頭の中で練ってきたことを口にする。彼自身や彼の性格に対するはっきりとした洞察と言えるだろう。簡潔かつ的を射て反論の余地もない、マルコヴィッチによる自己評価といえる。
出演した映画の多くでマルコヴィッチは、魅力がにじみ出る掴みどころのない人間や、素敵で恐ろしい役を演じてきた。どの役柄でも、性交後の疲労感とお世辞を含んだ脅し文句、極端に気味悪く元気のない様子、オリーブ色の目の表情や冷酷さを表現し、奇妙でこの世のものとは思えない印象を与える。ほとんど熱心な無益論者の態度だ。そして彼の頭蓋骨は、丸く膨らんだ頭頂部から顎へ向かって先細る大きく格好悪い球体で、両耳はダンボのように大きい。全体的には意外に印象深く稀に見る傑作といえるが、それは彼の生き様、特に彼の性格にも当てはまる。彼がかつて、ボウイナイフで男性を脅したことは有名な話だ。またある時は、注文したシャツの出来上がりが少々送れたことでテーラーに怒鳴り込んだりもした。さらに、バスが止まらなかったことに腹を立てて窓を叩き割ったこともある。
「彼との仕事は、私のキャリアの中でも貴重な経験だった」とダスティン・ホフマンは言う。ホフマンは、マルコヴィッチ初のブロードウェイ作品であるアーサー・ミラーによる『セールスマンの死(Death of a Salesman)』(1984年)で共演している。「オーディションで初めて会った時、彼はまるでホームレスのような身なりだった。サンダル履きで足がとても汚く、髪もボサボサだったように記憶している。ささやくような声で話し、とにかく見た目が酷かった。第一印象はそんな感じで、風変わりな男だ。私は唖然とした。当時はわからなかったが、彼は自分のキャリアに傷が付こうが成功しようが執着しないピュアなアーティストだ。それが彼にとって重要であり、彼が表現してきたことなんだ。」
キャリアの初期から続くマルコヴィッチの演技を、「凶暴なヴィジョンの虜となった、冷酷で妄想的な美学だ」と、彼に魅了されたある評論家は表現した。

『危険な関係』で共演したミシェル・ファイファーと
photo: Snap/REX/Shutterstock
しかし実際に彼を目の当たりにすると、彼の印象はやや異なる。かつての農場を利用した彼の家は、飾り気がなく広々としている。
彼は普段着でインタヴューに応じた。今日は着慣れたルーズなジーンズの裾を折り返し、白のソックスにブルーのオールスターのハイカットスニーカーを履いている。上はゆったりとしたグレーのTシャツで、カジュアルなスタイルだ。赤ワインを好むが、飲む量は人並みだ。「毎日少し飲んでいるかって? それが”少し”かどうかわからない。ボトル半分ぐらいか? それで満足できる夜もあるが、もっと進む夜もある」とマルコヴィッチは言う。数年間禁煙していた彼だが、2008年のある晩、ネットサーフィンをしながら悪徳投資家バーニー・マドフが手錠をかけられた写真を見つけた。「ちょっと出かけてくる」と妻に告げると、車で店に行きタバコを1箱買って帰った。彼はマドフに多額の金を預けていたのだ。マドフの事件は、マルコヴィッチに喫煙を再開させただけでなく、もっと仕事を増やす効果もあった。「クアラルンプールかどこかで演じるように、軽い感じで仕事に取り組んでいる場合ではなかった。」
米国? 彼はその考えを気に入らないだろう。ナンセンスだ。「米国は何から何まで不快だ。多くの文化的な不協和音、政党同士の誠意のない意見交換、そして礼儀の悪さ。あるテレビ番組で2人が怒鳴り合っていた。あれでは問題は解決しない。一種の病気といえる。ある種の奇妙な精神病だ。私の言っているのはある意味で戯言かもしれない。私はテレビを見ないし新聞も読まず、投票にも行かないから。しかし本当に、どう嫌いになればいいのだろう? 29歳の時、私はワーナー・ブラザースにオフィスを構えていたし。」
あらゆる意味で、彼は葛藤を乗り越えて活動しているようだ。時には高尚なレベルに達し、どんなものからも酸素を絞り出せるなどと彼は過去に言ったかもしれない。例えば彼はかつて「一般大衆に認識されているものはクソだ。彼らの考えにも吐き気がする。映画は金のためだけにやっている」と発言したという。しかし今日の彼は「そんなことは言っていないと思う」と言うと黙り込み、それ以上は口を開かなかった。元妻のグレン・ヘドリーについてはどうだろうか。ヘドリーは、マルコヴィッチが『危険な関係』で共演したミシェル・ファイファーと不倫を始めたため、彼の下を去った。ヘドリーはマルコヴィッチを「諸悪の根源」と表現したという。「ああ、ただの皮肉だろうと思った」と彼はのんきに語る。「ミシェル・ファイファーが私に挨拶したとは信じがたい。彼女が印象的でないという訳ではないが、神のみぞ知る、だ。私はある意味遮断した。つまり、私が他人のことを考える時、自分が相手に関わっているとはみなさない。私が他人を堕落させることはない。私の存在で相手に迷惑をかけることはない、ということだ」と彼は言う。「おそらくその言葉通りだが、自分のことを堕落の根源だと思っているかというと、全く違う。たぶん辛辣なんだろう。しかし我々は時折、フォークナーの言うように、一連の出来事とそれが引き起こす悪影響についてよく考えるべきだ。」
どういう意味だろう。彼についての真実や嘘、或いは少なくとも思いがけないことだろうか。話が広すぎて、ややまごつくかもしれない。「私は専門家ではないが、かなりの人々が私のことを冷酷、知的、傲慢、そして妙な理由から変人だと思っているのだと思う。自分のことをよく知る人たちは、私が冷酷だとか知的だとは思わないだろう。たぶん傲慢だと感じていると思う。自分としては、全く変人ではないと思っている」とマルコヴィッチは相変わらず陽気に話す。吐き出したタバコの煙に一瞬隠れた彼は、周辺を舞う草木の綿毛のひとつになったようだった。そうして彼は再び口を開く。「私は極めて普通の少年時代を送ってきたと思う」と本音を語った。

『コン・エアー』で共演したニコラス・ケイジと
Photo: Moviestore/REX/Shutterstock
最も知っておくべきは、マルコヴィッチの少年時代が”普通”とはかけ離れており、トニーという名の架空の人物になりたがっていたということ。彼は、イリノイ州にある小さな炭鉱の街ベントンで育った。父親は『イリノイ・アウトドアーズ』という自然保護雑誌を発行し、母親は主婦として椅子に座って本を読む生活だった。彼女は感謝祭用の七面鳥をオーブンに入れたままスイッチを入れ忘れるようなそそっかしい人で、ジョン、3人の姉妹、兄のダニーはよく怒り狂っていた。母親は、しわがれた声で話すところから”カエル”というあだ名で呼ばれていたという。「彼女はいわゆる普通の母親とは違っていた。彼女はまるで、同居する愉快で奇妙な友人のようだった。両親は完全な放任主義だった。”宿題をしなさい”とか”昨日の夜はどこにいたの?”などと言われたことがない」とマルコヴィッチは証言する。その代り家の中では食べ物が飛び交い、兄のダニーがマルコヴィッチの顔にオナラをして起こしたり、思うようにならないことに腹を立てたマルコヴィッチが、血が出て傷になるまで車の窓に頭を打ち付けたりといった感じだった。学校でのジョン・マルコヴィッチは、1年生の時に担任を”motherfucker”(或いは”cocksucker”だったかもしれないが本人はよく覚えていない)と罵り、イースターエッグ探し大会に負けると学校を飛び出したこともある。彼は気性が激しく、手に負えなくなった時は家から締め出され、二階の窓から「この狂人め!」と家族から罵声を浴びせられた。
時には、リベラルな知性派でかつて第82空挺師団に所属したマルコヴィッチの父親が、ベルトや鉄拳で制裁を加えることもあった。マルコヴィッチは言うことを聞かない子どもで、母方の祖父による無謀ないたずらに便乗したりしたため、よく怒られていた。祖父のスティーヴは炭鉱での作業中に片足を失っていたが、死の直前に糖尿病でもう片方も失った。「彼は競馬好きの似非アーティストで、作品は過大評価されていた。基本的に彼が教えてくれたのは”相手が誰であれ負けるな、皆の上を行け”ということだった。私は彼が大好きだった」とマルコヴィッチは言う。彼は微笑み、クスクス笑いながら思い出を語っている。子どもだからということで何でも許されたマルコヴィッチにとって、どれも苦い思い出だが。
ある時彼は、今乗っているのよりも格好良い3段変速ギア付き英国製レース用自転車に買い替えて欲しいと思った。彼は自動車の窓に頭を打ち付けて父親にせがんでいたが、ある日ついに祖父のスティーヴが堪忍袋の緒を切らした。「うるさい、いい加減にしろ。いいか、明日今の古い自転車をドライブウェイに倒しておけ。俺が車で轢いてやる。そうすればお前の父親は、3段変速ギア付きの英国製レース用自転車を買ってくれるだろう」と言う。孫を車に乗せたスティーヴは、実際に古い自転車を轢いたものの、策略を見破ったマルコヴィッチの父親は息子を車から引きずり下ろして彼を殴り始めた。「それ以来、私は自転車を持たせてもらえなかった」とマルコヴィッチは語る。
またある時マルコヴィッチは医者から、内反足を治すために矯正用の靴を履くように言われた。矯正靴を購入して家へ帰る途中、彼はひどく抵抗した。「大きな金属製矯正具の付いたずんぐりした靴だった。叫びながら狂ったように車の窓へ頭を打ち付けた。祖父が私の方を向き、”こんなものが気に入らなければ窓を開けて放り出してしまえ”と声を出さずに口の動きだけで伝えた」という。「投げ出した靴が地面に着くかつかないかのうちに車は急停止した。私は走って逃げ出したが無駄だった。父親は私を車へ引き戻し、靴で私を殴った。父親に関して間違った印象を与えたくないが、私自身の中には母親の占める割合が大きく、祖父のスティーヴの影響も少なからずある。私の中で父親の存在はそう大きくない。しかし父親はとても魅力的な人間で、彼には純粋に愛を感じる。精神的な葛藤は全くない。家族は皆、少しばかり粗雑なだけだ。私が不公平な扱いを受けたことは決して無かった。おそらく私は、本来得られるもの以下しか与えられていなかったのだ。」

映画『マルコヴィッチの穴』(1999年)より
Photo Melissa Moseley/Universal/Kobal/REX/Shutterstock
13歳になる頃までにマルコヴィッチの身長は約6フィート(約183cm)に達し、体重は標準より30kg以上オーバーの太った体型だった。Dairy Treatで一緒にたむろするような友人はいなかったが、いつでもガールフレンドはいた。また彼はアスリートとしても優秀で、野球ではピッチャー、フットボールではディフェンスタックルを務めた。しかしある時彼は、自分のぜい肉をどうにかしなければと思い始めた。その後6カ月間彼はJell-O(ゼリー)だけしか口にせず、ぜい肉を全部落とした。体型のせいで”ふとっちょ”、”ファットボーイ”、”子ブタ”などと呼ばれることもあったが、彼自身は太っていることを気にしていた訳ではない。「自分自身には、自分のキャパシティ以上に感受性を持てるとは思わない」と彼は明るく言う。こうやって彼は、並の愚かな人間を無力化しそうな多くのものを退けている。「全然辛くはなかった。ただうんざりしていただけだ。」
マルコヴィッチが8歳の頃に話を戻そう。彼は”トニー”という名のもうひとりの自分を作り出す必然性を感じていた。「ほとんどの人が、いや、ほとんどではないか。とにかくたぶん多くの人が今とは別の人生を送りたいと願っているだろう。特に若いうちは」と彼は言う。架空の世界のトニーはジョン・マルコヴィッチとは異なり、スリムなおそらくイタリア人で、全く人当たりがよく、首にスカーフを巻くなどおしゃれで粋な人間だった。大抵の場合、トニーになりきっている時のマルコヴィッチはひとりだった。本人は、周囲の何人かに自分を”トニー”と呼ぶように言ったと記憶している。時には、ジョンでなくトニーになりきってピッチャーのマウンドに上がったが、チームの監督だった父親は気に入らなかったようだ。「帽子の折り目に気を遣う半分でもピッチングに向ければ、本当に凄いピッチャーになれるだろうに」と父親は嘆いたという。ある意味でトニーは、マルコヴィッチにとって初めての大役であり、自分自身から離れて他人になりきる初めての経験だった。
ある土曜日、マルコヴィッチは近くの街で行われたフリーマーケットへ出かけた。ベッドルームのドアノブを探していたのだ。「今付いているドアノブはツルツルしてとっても固いから」だという。何人かの友人と会いフランス語で会話したが、話題のほとんどは舞台劇についてだった。彼が興味を持ち続けてきたのは映画でなく舞台の方だったからだ。
マルコヴィッチの両親としては、彼の高校卒業後にパークレンジャーになってくれるのを期待していた。しかし彼はイリノイ州立大学へ進学し、初めて演劇に興味を持つことなる。1976年にはシカゴでジョーン・アレン、ゲイリー・シニーズ、後に妻となるグレン・ヘドリーと共にステッペンウルフ・シアター・カンパニーの設立に協力。上演したサム・シェパード脚本の『True West』はその後ニューヨークへ展開し、マルコヴィッチはオビー賞を受賞した。1984年のブロードウェイ・デヴュー作『セールスマンの死(Death of a Salesman)』ではビフを演じ、共演者の中にはダスティン・ホフマン(ウイリー役)がいた。
オーディション当日、ホフマンと脚本家のアーサー・ミラーはブロードハーストシアターの6列目に座り、あまり期待せずにボサボサ頭で足の汚い奇妙な男が演じるのを見ていた。ホフマンの記憶によると、マルコヴィッチは「私に興味はないでしょうが、その時は私に向かってうなずいてください。私は退場します」と言って演技に入ったという。
「私のシナプスにぴったり当てはまった瞬間だった」とホフマンは証言する。「彼は手に持ったタバコを吸い、とてもソフトに台詞を読み上げ始めた。私は魅了された。彼の演技は、他の誰もしたことのないものだった。初めは赤面した詩人のようでありながら、労働者階級の特徴をよく伝えている。アーサーは私の方を見て驚きの表情でただ頷いてみせた。もうそれで十分だった。以上だ」とホフマンは深く息をつく。「正直に言うと、あの時の事を思い出すとこみ上げてくるんだ。」
同年、映画でも大役を得た。『プレイス・イン・ザ・ハート(Places in the Heart)』で彼は盲目の下宿人を演じ、初めてオスカーにノミネートされた。サリー・フィールドは彼を祝福し、彼女の出演するテレビ番組のスピンオフとして製作されたアルバム『The Flying Nun Sings』を贈った。もらって嬉しいと思う人間は多くないと思うが、彼女は「冗談でしょ? 彼は気に入ってくれたわ! 彼は”早く家に持ち帰って聴きたい”と言っていたわ。彼は大切にすると言ってくれたの。私はとにかく彼に贈らなきゃと思ったの。彼はとてもユニークな人よ。」
その後数年間、マルコヴィッチは『危険な関係』をはじめその後の『マルコヴィッチの穴』でマルコヴィッチ・コールが起きるほどカルト的な魅力の中心となるまで、当初はややぼんやりとしながらも着実に歩みを進めた。脚本家のカウフマンにとって、この流れは不思議な事ではなかった。「彼を初めて見たのは『True West』の録画テープだった」とカウフマンは言う。「”これは一体何だ?”と驚いた。私にとってマルコヴィッチは、ロバート・デュヴァルが(マーロン)ブランドを見た時に思ったように”そんな風にもできるのか?”という感じだった。刺激を受けた。さらに彼が”私は女性らしさを持っているが軟弱な訳ではない”というような発言をしているのを読んだことがある。私はその発言にも衝撃を受けた。彼には女性らしさも感じるが、同時に強くたくましい男らしさも明らかに持っている。風変わりな人だ。彼がステージに立つと目が離せない。」

映画『ザ・シークレット・サービス(In The Line Of Fire)』(1993年)より
Photo by Columbia TriStar/Kobal/REX/Shutterstock
同じ頃マルコヴィッチは、彼の傍若無人で常軌を逸した行動や発言が評判になり始めた。ある時、ニューヨークの街角で絡んできたホームレスに腹を立てたマルコヴィッチは、家に帰って綺麗なスーツを着替え、大きなボウイナイフ(彼曰く「父親からもらった唯一のもの」)を手に街へ戻り、「お前は何と言った? 俺にはわからなかった。俺が歩道を歩いちゃいけないって? 御婦人は歩道を使ってはいけないのか? 歩道はお前だけのものか? ちゃんと説明してみろ」と脅した。
「そんなところだ」とマルコヴィッチは今日のインタヴューで認めた。「彼のような人間は、精神的に病んでいたり何らかの事情がある事はわかっている。でもうんざりなんだ。彼のような人々は、社会に大混乱をもたらしている。」
フリーマーケットをぶらぶら歩きながら彼はついに気に入ったドアノブを見つけ、30ユーロ(約3700円)で購入した。「馬鹿みたいに高かった。模造品だったし」と彼は鼻を鳴らす。その後自分のアウディに乗って食料品店へ向かい、子どもたちのために惣菜を買い込んだ。途中立ち寄ったガソリンスタンドではポンプが壊れていた。彼の息子が自分の車を借りて出かける時は、ガソリンを補充しておくように何度も言っていたのだが、もう諦めた。「自分の子どもたちは『マルコヴィッチの穴』を観たかって? 俺は知らない。彼らに聞いたこともない」と言う。車寄せに入り駐車してから家の中へ入る。鏡の前で彼は不快で惨めな気分になった。
「自分の頭の形はどうだろう? 綺麗な丸型の頭蓋骨だ。私は好きだと思ったことはないが、嫌っている訳でもない。頭の形について考えたこともなかった」と彼は言う。
マルコヴィッチは振り返り、キッチンの方へ向かう。「鏡はほとんど見ないんだ。興味がない。作りものの鼻や何かを付けた時は別だけどね」と彼は続ける。「自分の存在を”こうあるべき、あのようにあるべき”と固定観念で捉える人が多いが、私はそうでない。あるオーディションで一緒になった女優が、監督がちょっと席を外した時に俺に言ったんだ。私の出演した『危険な関係』を見ながら3回トイレに行ったという。私は”何だそれ?”と思ったが、彼女はマスターベーションしに行っていたんだ。私はただ”教えてくれてありがとう”と思うしかなかった。演じた役柄通りの人間だと思われることも多い。自分としては『二十日鼠と人間(Of Mice and Men)』の役柄の方が近い」と言う。演じたレニーが精神薄弱の巨漢だったことを考えると、とても自虐的な選択だが。「しかし、どう思おうがその人の勝手だ。私は米中西部出身の人間だが、”自分はこういう人間だ”という考えは全く持っていない。もっとも自分自身が認識している訳ではないがね。」
ミシェル・ファイファーとの不倫の末にグレン・ヘドリーとの結婚生活が破綻した後の数年間、マルコヴィッチは自分の精神状態を落ち着かせるため精神分析に通った。彼曰く、有益な経験だったという。「私はくよくよする人間ではないので、最初の1年半は医者のオフィスへ行っても何も話さず、医者が”とても残念です”と言い私が”ありがとう。ではまた木曜に”という感じだった。自暴自棄になっていたかというと、自分ではわからない。とても落ち込んでいたのは事実で、彼は私の命の恩人だと思う」と語る。「私自身がテーマで、ハードだったように思う。私がどう感じようが、どうでもいいことだろ? それに対して私はとても中立的だ。ポパイのように”俺は俺”という感じ。つまり、自分のいかなる点も嫌いではないし、また好きになることもない。ニュートラルなんだ。そこに意味はない。」
マルコヴィッチは、ビジネスについても時間を割いて語っている。2002年から彼は、メンズウェアのデザインを始めた。Technobohemianから現在はJohn Malkovich Fashionと名称変更したブランドで、イタリアとスペインのクールな生地を使った(彼は「生地に目がない」と証言している)シャツ、パンツ、コートを提供している。しかし同時にフラストレーションが溜まり苛つく原因にもなっている。「思い通りの生地が手に入らなかったり、あれやこれやの法外な価格で私から搾取しようとする時、私は本当に叫び声を上げたくなる。ファッションビジネスを続けるのは、並大抵のことではない」と彼は言う。(彼はいつか女性向けジュエリーのデザインも始めるかもしれない。彼は「その他のいろいろな事と同じく、私には何の知識もない」と言う。さらに彼は、フランスに所有する土地でシャルドネの生産を手がける可能性もある。「上手くいくか、自分がまた間抜けになるかのどちらかだ。」)
淹れたてのコーヒーを彼は裏のベランダへ運び、人生におけるささいな事についても話してくれた。
お気に入りの歯磨き粉はトムズオブメインのプロポリス&メイラで、あまり好きでないのはアクアフレッシュ。「何色にも分かれている歯磨き粉なんて必要ない。イライラする。」
マルコヴィッチは”dude”という単語がお気に入りで、メールでもよく「Dude, WTF?(おい、なんてこった)」などと使っている。彼曰く「ただ便利だから」だそうだ。
恐怖症…「たぶん世界屈指のネズミ嫌いだろう。追いかけっこをしたことがあるかって? 追いかけっこと言えるかどうかわからないが、いつも結末がよろしくない。なぜかというと、野球のバットのせいだ。」
マルコヴィッチのリアルな趣味は、皿洗い。「皿を洗うのが大好きだ。アイロン掛けも好きだ。」
彼がおそらく唯一、時々摂取するドラッグがエクスタシーだ。「何だろうが気にしない。”いいね、試してみたいな”という類のもののひとつだ。しかし私は常に働いている。ドラッグで飛んでいる暇がどこにあると思う?」
マルコヴィッチの発言が新たな世界の不思議を示しているに違いない、と考える人も多いが、本人は否定する。「そんなことを聞くのは耐えられない。我慢ならないんだ。ゾッとする。」
彼は周囲の木々や空を流れる雲に目を向ける。「乾燥している。カラカラだ。ここ数日間は雨が降って欲しかったが、どうしていいかわからなかった。北から風が吹いている。たぶん横風も。木々が傾き始める様子が見えるだろう。風が全部の雲を吹き飛ばす。風が雲に負けることは滅多にないから、雨が降らないんだ」とマルコヴィッチは語る。20分後、彼はまた木々の観察を始めた。「横風かどうかを見極めようとしているんだ」という。彼は満足げに天気を予想している。一番満ち足りているように見える。サミュエル・ベケットの戯曲『エンドゲーム(Endgame)』に「Youre on Earth, theres no cure for that」という台詞がある。マルコヴィッチのお気に入りのひとつだ。彼はベケットの言わんとするところをよく理解している。彼がボトル半分のワインでは満足できないと悟った夜のようだ。彼は頑張り続けている。
自身の子ども時代や気まぐれな性格から”ジョン・マルコヴィッチ”であることについてまでを語った、9年間もお蔵入りしていたローリングストーン誌のインタヴューがついに日の目をみた。マルコヴィッチ・ワールドへようこそ。
今から9年前の2010年、ローリングストーン誌の依頼でジョン・マルコヴィッチにインタヴューするため、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏にある彼の自宅を訪れた。当時はちょうど、彼の出演した新作『RED/レッド(原題:RED)』(LSD中毒の元CIAエージェント役)と『セクレタリアト/奇跡のサラブレッド(原題:Secretariat)』(気難しい調教師役)の2本が公開される時期だった。両作品でマルコヴィッチは有名な変人を演じ、どちらもヒットした。しかしどういう訳か、同インタヴュー記事が公開されることはなかった。出版業界特有の気まぐれか、ローリングストーン誌の編集者による突飛な思いつきだろう。本記事は、改訂して公開されるのを暗い蔵の中でじっと待っていたのだ。
しかし、今日になってついに公開できることとなったのは、内容が改訂されたからではない。現在に至るまでの俳優の素晴らしいポートレートを表現するのに、内容の変更はほとんど必要ないことに気づいたからだ。彼はその後、多くの作品に出演している。ショウタイムで放送されたヘッジファンダー対司法を描いたテレビドラマ『ビリオンズ(原題:Billions)』で極悪非道なロシア人新興実業家を演じ、BBCで放送されその後Amazon Primeでも視聴可能となった『ABC殺人事件(原題:The ABC Murders)』では、アガサ・クリスティー作品ではお馴染みの探偵エルキュール・ポワロを演じた。
またNetflixの『ベルベット・バズソー:血塗られたギャラリー(原題:Velvet Buzzsaw)』では画家を演じ、2019年秋に封切り予定の『Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile』には、テッド・バンディの殺人事件の裁判を担当する判事役で出演している。さらに映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインの盛衰を描いた、デヴィッド・マメット監督によるブラックコメディ『Bitter Wheat』を、ロンドンの舞台で上演すべく準備も進めている。
65歳になったマルコヴィッチは、ひと息つくような気配を全く見せない。自分を取り巻く環境は変化しているかもしれないが、マルコヴィッチは揺るぎないように見える。しなやかな常緑樹のように、どこでも常に彼らしい存在感を出す。ここに私が9年前に書いた彼のインタヴュー記事があるが、以上のような理由で内容は改訂されていない。当時の彼と今の彼は、ほとんど変わりがないのだ。もちろん米中西部で過ごした少年時代とは全く容姿が異なる。当時の彼は、体重が標準より30kgオーバーで”ふとっちょ”などと呼ばれることもあったという。靴に矯正具を付けて歩く彼はよく、スリムで格好良いスカーフを巻いたイタリア人のプレイボーイ”トニー”になりきることがあった。その後あらゆる役を演じることとなる彼の初めての演技経験といえる。
フランス郊外の閑静な雰囲気に囲まれた自宅の外で、ジョン・マルコヴィッチは遠くを見渡していた。
遠くにかすかに見える丘の上には、偉大なマゾヒストだったマルキ・ド・サドがかつて管理し、今はピエール・カルダンの所有する美しい城がある。風が吹いて雲が動き始め、遠くの景色に陰がさす。マルコヴィッチは飾り気のない金属製の椅子に腰掛けて足を組み、コーヒーを啜っている。彼はミミズのように薄い唇をすぼめ、ペラペラとよくしゃべる。何ひとつ変わっていない。彼には、現在世界にアピールするものや、世界がどうなるだろうかという彼の意見を聞きたいと思った。彼はエレガントに両手を重ねて首を傾げ、まるで大学教授のような仕草で答えを探す。
草木の綿毛が舞い、彼の目が追う。タバコをつまみ上げて火をつける。ついに彼は、面白がって見下した態度を取る時によくやるように唇を動かし、ずっと頭の中で練ってきたことを口にする。彼自身や彼の性格に対するはっきりとした洞察と言えるだろう。簡潔かつ的を射て反論の余地もない、マルコヴィッチによる自己評価といえる。
肩をすくめて彼は「全くわからない」と言う。しばらく考えて口にしたのがこれだけだ。彼は満々の笑みを浮かべる。そうしてまた彼は、とても満足げに遠くを見つめた。
出演した映画の多くでマルコヴィッチは、魅力がにじみ出る掴みどころのない人間や、素敵で恐ろしい役を演じてきた。どの役柄でも、性交後の疲労感とお世辞を含んだ脅し文句、極端に気味悪く元気のない様子、オリーブ色の目の表情や冷酷さを表現し、奇妙でこの世のものとは思えない印象を与える。ほとんど熱心な無益論者の態度だ。そして彼の頭蓋骨は、丸く膨らんだ頭頂部から顎へ向かって先細る大きく格好悪い球体で、両耳はダンボのように大きい。全体的には意外に印象深く稀に見る傑作といえるが、それは彼の生き様、特に彼の性格にも当てはまる。彼がかつて、ボウイナイフで男性を脅したことは有名な話だ。またある時は、注文したシャツの出来上がりが少々送れたことでテーラーに怒鳴り込んだりもした。さらに、バスが止まらなかったことに腹を立てて窓を叩き割ったこともある。
そんな彼でも、共演者をはじめ周囲の人々に愛されている。「ただただ彼を敬愛している」と、マルコヴィッチの初出演映画作品『プレイス・イン・ザ・ハート(Places in the Heart)』(1984年)で共演したサリー・フィールドは言う。「彼は自分のルールブックにのみ従って演じている。私たちの多くが執着するようなことでも、彼は少しも気に掛けない。」
「彼との仕事は、私のキャリアの中でも貴重な経験だった」とダスティン・ホフマンは言う。ホフマンは、マルコヴィッチ初のブロードウェイ作品であるアーサー・ミラーによる『セールスマンの死(Death of a Salesman)』(1984年)で共演している。「オーディションで初めて会った時、彼はまるでホームレスのような身なりだった。サンダル履きで足がとても汚く、髪もボサボサだったように記憶している。ささやくような声で話し、とにかく見た目が酷かった。第一印象はそんな感じで、風変わりな男だ。私は唖然とした。当時はわからなかったが、彼は自分のキャリアに傷が付こうが成功しようが執着しないピュアなアーティストだ。それが彼にとって重要であり、彼が表現してきたことなんだ。」
キャリアの初期から続くマルコヴィッチの演技を、「凶暴なヴィジョンの虜となった、冷酷で妄想的な美学だ」と、彼に魅了されたある評論家は表現した。
『危険な関係(Dangerous Liaisons)』(1988年)で演じた冷酷な色魔は当たり役だった。『ザ・シークレット・サービス(In the Line of Fire)』(1993年)でのカメレオン的な暗殺者役は、オスカーにノミネートされている。ジェリー・ブラッカイマー製作の『コン・エアー(Con Air)』(1997年)で演じたシリアルキラーのサイラス・ザ・ヴァイラスは、仲間の殺人犯に「お前の仕事を気に入った」と言う。また時には、『アートスクール・コンフィデンシャル(Art School Confidential)』の変わったアーティスト、『ザッツ★マジックアワー ダメ男ハワードのステキな人生(The Great Buck Howard)』の風変わりな奇術師、コーエン兄弟の『バーン・アフター・リーディング(Burn After Reading)』で演じた変わり者のように、邪悪さを抑えて変人さを強調した役も演じている。そしてチャーリ・カウフマン脚本、スパイク・ジョーンズ監督のシュールな『マルコヴィッチの穴(Being John Malkovich)』(1999年)は、自分自身を演じるという珍しい作品だった。「マルコヴィッチ意外に考えられなかった。彼は不可知な存在で、作品にフィットすると思った。彼の目を直視することができず、彼の頭の中で何が起きているかもわからない。遮断されてしまうのだ」とカウフマンは言う。彼は正に、シチュエーションや映画作品にかかわらず、ハリウッドの生んだ代表的な変人といえる。

『危険な関係』で共演したミシェル・ファイファーと
photo: Snap/REX/Shutterstock
しかし実際に彼を目の当たりにすると、彼の印象はやや異なる。かつての農場を利用した彼の家は、飾り気がなく広々としている。
ステンレスで作ったキッチンやタイル張りの大きな暖炉付きのダイニングルームがあり、寒いとまでは言わないが涼しい感じがする。玄関ホールから彼は、キッチン、エスプレッソマシン、マールボロライトの箱、裏庭のパティオに目を移す。パティオでは、20年来のパートナーであるイタリア系フランス人のニコレッタ・ペイランとランチを共にする。アジア文化の学者でもあるペイランは1989年、『シェルタリング・スカイ(The Sheltering Sky)』の撮影現場で監督のベルナルド・ベルトルッチのアシスタントをしていた時にマルコヴィッチと出会った。彼らの2人のティーンエイジの子どもたちアマンディンとルーイも、パティオに姿を現す。彼はとても上品かつ礼儀正しく、誰も耳にしたことがないような言葉で時折優しく話しかける。「私の部屋にスズメバチがいるの」と訴えるアマンディンに対して彼は、「ああハニー、どうすればいいかわかるだろ? 懐中電灯で叩いて殺してしまえばいいんだよ」と答える。彼の言葉の中には、暴力的な響きは全く感じられなかった。
彼は普段着でインタヴューに応じた。今日は着慣れたルーズなジーンズの裾を折り返し、白のソックスにブルーのオールスターのハイカットスニーカーを履いている。上はゆったりとしたグレーのTシャツで、カジュアルなスタイルだ。赤ワインを好むが、飲む量は人並みだ。「毎日少し飲んでいるかって? それが”少し”かどうかわからない。ボトル半分ぐらいか? それで満足できる夜もあるが、もっと進む夜もある」とマルコヴィッチは言う。数年間禁煙していた彼だが、2008年のある晩、ネットサーフィンをしながら悪徳投資家バーニー・マドフが手錠をかけられた写真を見つけた。「ちょっと出かけてくる」と妻に告げると、車で店に行きタバコを1箱買って帰った。彼はマドフに多額の金を預けていたのだ。マドフの事件は、マルコヴィッチに喫煙を再開させただけでなく、もっと仕事を増やす効果もあった。「クアラルンプールかどこかで演じるように、軽い感じで仕事に取り組んでいる場合ではなかった。」
米国? 彼はその考えを気に入らないだろう。ナンセンスだ。「米国は何から何まで不快だ。多くの文化的な不協和音、政党同士の誠意のない意見交換、そして礼儀の悪さ。あるテレビ番組で2人が怒鳴り合っていた。あれでは問題は解決しない。一種の病気といえる。ある種の奇妙な精神病だ。私の言っているのはある意味で戯言かもしれない。私はテレビを見ないし新聞も読まず、投票にも行かないから。しかし本当に、どう嫌いになればいいのだろう? 29歳の時、私はワーナー・ブラザースにオフィスを構えていたし。」
あらゆる意味で、彼は葛藤を乗り越えて活動しているようだ。時には高尚なレベルに達し、どんなものからも酸素を絞り出せるなどと彼は過去に言ったかもしれない。例えば彼はかつて「一般大衆に認識されているものはクソだ。彼らの考えにも吐き気がする。映画は金のためだけにやっている」と発言したという。しかし今日の彼は「そんなことは言っていないと思う」と言うと黙り込み、それ以上は口を開かなかった。元妻のグレン・ヘドリーについてはどうだろうか。ヘドリーは、マルコヴィッチが『危険な関係』で共演したミシェル・ファイファーと不倫を始めたため、彼の下を去った。ヘドリーはマルコヴィッチを「諸悪の根源」と表現したという。「ああ、ただの皮肉だろうと思った」と彼はのんきに語る。「ミシェル・ファイファーが私に挨拶したとは信じがたい。彼女が印象的でないという訳ではないが、神のみぞ知る、だ。私はある意味遮断した。つまり、私が他人のことを考える時、自分が相手に関わっているとはみなさない。私が他人を堕落させることはない。私の存在で相手に迷惑をかけることはない、ということだ」と彼は言う。「おそらくその言葉通りだが、自分のことを堕落の根源だと思っているかというと、全く違う。たぶん辛辣なんだろう。しかし我々は時折、フォークナーの言うように、一連の出来事とそれが引き起こす悪影響についてよく考えるべきだ。」
どういう意味だろう。彼についての真実や嘘、或いは少なくとも思いがけないことだろうか。話が広すぎて、ややまごつくかもしれない。「私は専門家ではないが、かなりの人々が私のことを冷酷、知的、傲慢、そして妙な理由から変人だと思っているのだと思う。自分のことをよく知る人たちは、私が冷酷だとか知的だとは思わないだろう。たぶん傲慢だと感じていると思う。自分としては、全く変人ではないと思っている」とマルコヴィッチは相変わらず陽気に話す。吐き出したタバコの煙に一瞬隠れた彼は、周辺を舞う草木の綿毛のひとつになったようだった。そうして彼は再び口を開く。「私は極めて普通の少年時代を送ってきたと思う」と本音を語った。

『コン・エアー』で共演したニコラス・ケイジと
Photo: Moviestore/REX/Shutterstock
最も知っておくべきは、マルコヴィッチの少年時代が”普通”とはかけ離れており、トニーという名の架空の人物になりたがっていたということ。彼は、イリノイ州にある小さな炭鉱の街ベントンで育った。父親は『イリノイ・アウトドアーズ』という自然保護雑誌を発行し、母親は主婦として椅子に座って本を読む生活だった。彼女は感謝祭用の七面鳥をオーブンに入れたままスイッチを入れ忘れるようなそそっかしい人で、ジョン、3人の姉妹、兄のダニーはよく怒り狂っていた。母親は、しわがれた声で話すところから”カエル”というあだ名で呼ばれていたという。「彼女はいわゆる普通の母親とは違っていた。彼女はまるで、同居する愉快で奇妙な友人のようだった。両親は完全な放任主義だった。”宿題をしなさい”とか”昨日の夜はどこにいたの?”などと言われたことがない」とマルコヴィッチは証言する。その代り家の中では食べ物が飛び交い、兄のダニーがマルコヴィッチの顔にオナラをして起こしたり、思うようにならないことに腹を立てたマルコヴィッチが、血が出て傷になるまで車の窓に頭を打ち付けたりといった感じだった。学校でのジョン・マルコヴィッチは、1年生の時に担任を”motherfucker”(或いは”cocksucker”だったかもしれないが本人はよく覚えていない)と罵り、イースターエッグ探し大会に負けると学校を飛び出したこともある。彼は気性が激しく、手に負えなくなった時は家から締め出され、二階の窓から「この狂人め!」と家族から罵声を浴びせられた。
時には、リベラルな知性派でかつて第82空挺師団に所属したマルコヴィッチの父親が、ベルトや鉄拳で制裁を加えることもあった。マルコヴィッチは言うことを聞かない子どもで、母方の祖父による無謀ないたずらに便乗したりしたため、よく怒られていた。祖父のスティーヴは炭鉱での作業中に片足を失っていたが、死の直前に糖尿病でもう片方も失った。「彼は競馬好きの似非アーティストで、作品は過大評価されていた。基本的に彼が教えてくれたのは”相手が誰であれ負けるな、皆の上を行け”ということだった。私は彼が大好きだった」とマルコヴィッチは言う。彼は微笑み、クスクス笑いながら思い出を語っている。子どもだからということで何でも許されたマルコヴィッチにとって、どれも苦い思い出だが。
ある時彼は、今乗っているのよりも格好良い3段変速ギア付き英国製レース用自転車に買い替えて欲しいと思った。彼は自動車の窓に頭を打ち付けて父親にせがんでいたが、ある日ついに祖父のスティーヴが堪忍袋の緒を切らした。「うるさい、いい加減にしろ。いいか、明日今の古い自転車をドライブウェイに倒しておけ。俺が車で轢いてやる。そうすればお前の父親は、3段変速ギア付きの英国製レース用自転車を買ってくれるだろう」と言う。孫を車に乗せたスティーヴは、実際に古い自転車を轢いたものの、策略を見破ったマルコヴィッチの父親は息子を車から引きずり下ろして彼を殴り始めた。「それ以来、私は自転車を持たせてもらえなかった」とマルコヴィッチは語る。
またある時マルコヴィッチは医者から、内反足を治すために矯正用の靴を履くように言われた。矯正靴を購入して家へ帰る途中、彼はひどく抵抗した。「大きな金属製矯正具の付いたずんぐりした靴だった。叫びながら狂ったように車の窓へ頭を打ち付けた。祖父が私の方を向き、”こんなものが気に入らなければ窓を開けて放り出してしまえ”と声を出さずに口の動きだけで伝えた」という。「投げ出した靴が地面に着くかつかないかのうちに車は急停止した。私は走って逃げ出したが無駄だった。父親は私を車へ引き戻し、靴で私を殴った。父親に関して間違った印象を与えたくないが、私自身の中には母親の占める割合が大きく、祖父のスティーヴの影響も少なからずある。私の中で父親の存在はそう大きくない。しかし父親はとても魅力的な人間で、彼には純粋に愛を感じる。精神的な葛藤は全くない。家族は皆、少しばかり粗雑なだけだ。私が不公平な扱いを受けたことは決して無かった。おそらく私は、本来得られるもの以下しか与えられていなかったのだ。」

映画『マルコヴィッチの穴』(1999年)より
Photo Melissa Moseley/Universal/Kobal/REX/Shutterstock
13歳になる頃までにマルコヴィッチの身長は約6フィート(約183cm)に達し、体重は標準より30kg以上オーバーの太った体型だった。Dairy Treatで一緒にたむろするような友人はいなかったが、いつでもガールフレンドはいた。また彼はアスリートとしても優秀で、野球ではピッチャー、フットボールではディフェンスタックルを務めた。しかしある時彼は、自分のぜい肉をどうにかしなければと思い始めた。その後6カ月間彼はJell-O(ゼリー)だけしか口にせず、ぜい肉を全部落とした。体型のせいで”ふとっちょ”、”ファットボーイ”、”子ブタ”などと呼ばれることもあったが、彼自身は太っていることを気にしていた訳ではない。「自分自身には、自分のキャパシティ以上に感受性を持てるとは思わない」と彼は明るく言う。こうやって彼は、並の愚かな人間を無力化しそうな多くのものを退けている。「全然辛くはなかった。ただうんざりしていただけだ。」
マルコヴィッチが8歳の頃に話を戻そう。彼は”トニー”という名のもうひとりの自分を作り出す必然性を感じていた。「ほとんどの人が、いや、ほとんどではないか。とにかくたぶん多くの人が今とは別の人生を送りたいと願っているだろう。特に若いうちは」と彼は言う。架空の世界のトニーはジョン・マルコヴィッチとは異なり、スリムなおそらくイタリア人で、全く人当たりがよく、首にスカーフを巻くなどおしゃれで粋な人間だった。大抵の場合、トニーになりきっている時のマルコヴィッチはひとりだった。本人は、周囲の何人かに自分を”トニー”と呼ぶように言ったと記憶している。時には、ジョンでなくトニーになりきってピッチャーのマウンドに上がったが、チームの監督だった父親は気に入らなかったようだ。「帽子の折り目に気を遣う半分でもピッチングに向ければ、本当に凄いピッチャーになれるだろうに」と父親は嘆いたという。ある意味でトニーは、マルコヴィッチにとって初めての大役であり、自分自身から離れて他人になりきる初めての経験だった。
ある土曜日、マルコヴィッチは近くの街で行われたフリーマーケットへ出かけた。ベッドルームのドアノブを探していたのだ。「今付いているドアノブはツルツルしてとっても固いから」だという。何人かの友人と会いフランス語で会話したが、話題のほとんどは舞台劇についてだった。彼が興味を持ち続けてきたのは映画でなく舞台の方だったからだ。
マルコヴィッチの両親としては、彼の高校卒業後にパークレンジャーになってくれるのを期待していた。しかし彼はイリノイ州立大学へ進学し、初めて演劇に興味を持つことなる。1976年にはシカゴでジョーン・アレン、ゲイリー・シニーズ、後に妻となるグレン・ヘドリーと共にステッペンウルフ・シアター・カンパニーの設立に協力。上演したサム・シェパード脚本の『True West』はその後ニューヨークへ展開し、マルコヴィッチはオビー賞を受賞した。1984年のブロードウェイ・デヴュー作『セールスマンの死(Death of a Salesman)』ではビフを演じ、共演者の中にはダスティン・ホフマン(ウイリー役)がいた。
オーディション当日、ホフマンと脚本家のアーサー・ミラーはブロードハーストシアターの6列目に座り、あまり期待せずにボサボサ頭で足の汚い奇妙な男が演じるのを見ていた。ホフマンの記憶によると、マルコヴィッチは「私に興味はないでしょうが、その時は私に向かってうなずいてください。私は退場します」と言って演技に入ったという。
「私のシナプスにぴったり当てはまった瞬間だった」とホフマンは証言する。「彼は手に持ったタバコを吸い、とてもソフトに台詞を読み上げ始めた。私は魅了された。彼の演技は、他の誰もしたことのないものだった。初めは赤面した詩人のようでありながら、労働者階級の特徴をよく伝えている。アーサーは私の方を見て驚きの表情でただ頷いてみせた。もうそれで十分だった。以上だ」とホフマンは深く息をつく。「正直に言うと、あの時の事を思い出すとこみ上げてくるんだ。」
同年、映画でも大役を得た。『プレイス・イン・ザ・ハート(Places in the Heart)』で彼は盲目の下宿人を演じ、初めてオスカーにノミネートされた。サリー・フィールドは彼を祝福し、彼女の出演するテレビ番組のスピンオフとして製作されたアルバム『The Flying Nun Sings』を贈った。もらって嬉しいと思う人間は多くないと思うが、彼女は「冗談でしょ? 彼は気に入ってくれたわ! 彼は”早く家に持ち帰って聴きたい”と言っていたわ。彼は大切にすると言ってくれたの。私はとにかく彼に贈らなきゃと思ったの。彼はとてもユニークな人よ。」
その後数年間、マルコヴィッチは『危険な関係』をはじめその後の『マルコヴィッチの穴』でマルコヴィッチ・コールが起きるほどカルト的な魅力の中心となるまで、当初はややぼんやりとしながらも着実に歩みを進めた。脚本家のカウフマンにとって、この流れは不思議な事ではなかった。「彼を初めて見たのは『True West』の録画テープだった」とカウフマンは言う。「”これは一体何だ?”と驚いた。私にとってマルコヴィッチは、ロバート・デュヴァルが(マーロン)ブランドを見た時に思ったように”そんな風にもできるのか?”という感じだった。刺激を受けた。さらに彼が”私は女性らしさを持っているが軟弱な訳ではない”というような発言をしているのを読んだことがある。私はその発言にも衝撃を受けた。彼には女性らしさも感じるが、同時に強くたくましい男らしさも明らかに持っている。風変わりな人だ。彼がステージに立つと目が離せない。」

映画『ザ・シークレット・サービス(In The Line Of Fire)』(1993年)より
Photo by Columbia TriStar/Kobal/REX/Shutterstock
同じ頃マルコヴィッチは、彼の傍若無人で常軌を逸した行動や発言が評判になり始めた。ある時、ニューヨークの街角で絡んできたホームレスに腹を立てたマルコヴィッチは、家に帰って綺麗なスーツを着替え、大きなボウイナイフ(彼曰く「父親からもらった唯一のもの」)を手に街へ戻り、「お前は何と言った? 俺にはわからなかった。俺が歩道を歩いちゃいけないって? 御婦人は歩道を使ってはいけないのか? 歩道はお前だけのものか? ちゃんと説明してみろ」と脅した。
「そんなところだ」とマルコヴィッチは今日のインタヴューで認めた。「彼のような人間は、精神的に病んでいたり何らかの事情がある事はわかっている。でもうんざりなんだ。彼のような人々は、社会に大混乱をもたらしている。」
フリーマーケットをぶらぶら歩きながら彼はついに気に入ったドアノブを見つけ、30ユーロ(約3700円)で購入した。「馬鹿みたいに高かった。模造品だったし」と彼は鼻を鳴らす。その後自分のアウディに乗って食料品店へ向かい、子どもたちのために惣菜を買い込んだ。途中立ち寄ったガソリンスタンドではポンプが壊れていた。彼の息子が自分の車を借りて出かける時は、ガソリンを補充しておくように何度も言っていたのだが、もう諦めた。「自分の子どもたちは『マルコヴィッチの穴』を観たかって? 俺は知らない。彼らに聞いたこともない」と言う。車寄せに入り駐車してから家の中へ入る。鏡の前で彼は不快で惨めな気分になった。
「自分の頭の形はどうだろう? 綺麗な丸型の頭蓋骨だ。私は好きだと思ったことはないが、嫌っている訳でもない。頭の形について考えたこともなかった」と彼は言う。
マルコヴィッチは振り返り、キッチンの方へ向かう。「鏡はほとんど見ないんだ。興味がない。作りものの鼻や何かを付けた時は別だけどね」と彼は続ける。「自分の存在を”こうあるべき、あのようにあるべき”と固定観念で捉える人が多いが、私はそうでない。あるオーディションで一緒になった女優が、監督がちょっと席を外した時に俺に言ったんだ。私の出演した『危険な関係』を見ながら3回トイレに行ったという。私は”何だそれ?”と思ったが、彼女はマスターベーションしに行っていたんだ。私はただ”教えてくれてありがとう”と思うしかなかった。演じた役柄通りの人間だと思われることも多い。自分としては『二十日鼠と人間(Of Mice and Men)』の役柄の方が近い」と言う。演じたレニーが精神薄弱の巨漢だったことを考えると、とても自虐的な選択だが。「しかし、どう思おうがその人の勝手だ。私は米中西部出身の人間だが、”自分はこういう人間だ”という考えは全く持っていない。もっとも自分自身が認識している訳ではないがね。」
ミシェル・ファイファーとの不倫の末にグレン・ヘドリーとの結婚生活が破綻した後の数年間、マルコヴィッチは自分の精神状態を落ち着かせるため精神分析に通った。彼曰く、有益な経験だったという。「私はくよくよする人間ではないので、最初の1年半は医者のオフィスへ行っても何も話さず、医者が”とても残念です”と言い私が”ありがとう。ではまた木曜に”という感じだった。自暴自棄になっていたかというと、自分ではわからない。とても落ち込んでいたのは事実で、彼は私の命の恩人だと思う」と語る。「私自身がテーマで、ハードだったように思う。私がどう感じようが、どうでもいいことだろ? それに対して私はとても中立的だ。ポパイのように”俺は俺”という感じ。つまり、自分のいかなる点も嫌いではないし、また好きになることもない。ニュートラルなんだ。そこに意味はない。」
マルコヴィッチは、ビジネスについても時間を割いて語っている。2002年から彼は、メンズウェアのデザインを始めた。Technobohemianから現在はJohn Malkovich Fashionと名称変更したブランドで、イタリアとスペインのクールな生地を使った(彼は「生地に目がない」と証言している)シャツ、パンツ、コートを提供している。しかし同時にフラストレーションが溜まり苛つく原因にもなっている。「思い通りの生地が手に入らなかったり、あれやこれやの法外な価格で私から搾取しようとする時、私は本当に叫び声を上げたくなる。ファッションビジネスを続けるのは、並大抵のことではない」と彼は言う。(彼はいつか女性向けジュエリーのデザインも始めるかもしれない。彼は「その他のいろいろな事と同じく、私には何の知識もない」と言う。さらに彼は、フランスに所有する土地でシャルドネの生産を手がける可能性もある。「上手くいくか、自分がまた間抜けになるかのどちらかだ。」)
淹れたてのコーヒーを彼は裏のベランダへ運び、人生におけるささいな事についても話してくれた。
お気に入りの歯磨き粉はトムズオブメインのプロポリス&メイラで、あまり好きでないのはアクアフレッシュ。「何色にも分かれている歯磨き粉なんて必要ない。イライラする。」
マルコヴィッチは”dude”という単語がお気に入りで、メールでもよく「Dude, WTF?(おい、なんてこった)」などと使っている。彼曰く「ただ便利だから」だそうだ。
恐怖症…「たぶん世界屈指のネズミ嫌いだろう。追いかけっこをしたことがあるかって? 追いかけっこと言えるかどうかわからないが、いつも結末がよろしくない。なぜかというと、野球のバットのせいだ。」
マルコヴィッチのリアルな趣味は、皿洗い。「皿を洗うのが大好きだ。アイロン掛けも好きだ。」
彼がおそらく唯一、時々摂取するドラッグがエクスタシーだ。「何だろうが気にしない。”いいね、試してみたいな”という類のもののひとつだ。しかし私は常に働いている。ドラッグで飛んでいる暇がどこにあると思う?」
マルコヴィッチの発言が新たな世界の不思議を示しているに違いない、と考える人も多いが、本人は否定する。「そんなことを聞くのは耐えられない。我慢ならないんだ。ゾッとする。」
彼は周囲の木々や空を流れる雲に目を向ける。「乾燥している。カラカラだ。ここ数日間は雨が降って欲しかったが、どうしていいかわからなかった。北から風が吹いている。たぶん横風も。木々が傾き始める様子が見えるだろう。風が全部の雲を吹き飛ばす。風が雲に負けることは滅多にないから、雨が降らないんだ」とマルコヴィッチは語る。20分後、彼はまた木々の観察を始めた。「横風かどうかを見極めようとしているんだ」という。彼は満足げに天気を予想している。一番満ち足りているように見える。サミュエル・ベケットの戯曲『エンドゲーム(Endgame)』に「Youre on Earth, theres no cure for that」という台詞がある。マルコヴィッチのお気に入りのひとつだ。彼はベケットの言わんとするところをよく理解している。彼がボトル半分のワインでは満足できないと悟った夜のようだ。彼は頑張り続けている。
編集部おすすめ





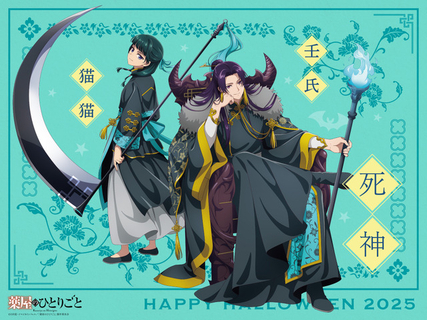








![【Amazon.co.jp限定】温泉シャーク【Blu-ray】「湯呑」付コレクション(オリジナル特典:ロッカーキー風アクリルキーホルダー 付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/5105bIK3vVL._SL500_.jpg)
![オッペンハイマー 4K Ultra HD+ブルーレイ(ボーナスブルーレイ付)[4K ULTRA HD + Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51H-qygmyaL._SL500_.jpg)

![【メーカー特典あり】言えない秘密 Blu-rayコレクターズ・エディション(2枚組)(A4サイズクリアファイル付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41j553zPZGL._SL500_.jpg)
![男はつらいよ 4K ULTRA HD Blu-ray (数量限定生産) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KXWYlFAUL._SL500_.jpg)





