特筆すべきは、きくおは海外で人気を誇り、リスナーの数も日本より圧倒的に圧倒的に多いということだ。歌詞は全て日本語。北米やヨーロッパのトレンドに合わせた音楽性でもない。アコースティックな歌モノから実験的なエレクトロニカまで多彩かつオリジナリティあふれる曲調で、どこか不穏さやダークさを漂わせる作風も特徴だ。レーベルや事務所に所属せず、インディペンデントな形で活動を行ってきたきくおは、なぜ海外にファンダムを築き上げることができたのか。詳しく聞いた。
きくお
1988年生。2003年、音楽制作を開始。ゲーム音楽や、BMS・Muzie等のインターネット音楽に浸りながら、ゲーム音楽、アイドルソング、東方アレンジなど、裏方としての楽曲提供を中心に活動。2010年、ボーカロイド楽曲初投稿。2017年、高等学校用教科書「高校生の音楽1」(教育芸術社)、きくお feat. 初音ミクとして楽譜と顔写真掲載。
―Spotifyで「愛して愛して愛して」が1億再生を突破した実感は?
きくお:正直、あまり実感はないんです。何故かと言うと、国内の人たちに騒がれなさすぎなんじゃないかって思って。数字的には結構すごいことだと思うんですけど、それについてメディアに突っ込んで訊かれた機会が驚くほどない。海外の人たちの熱量はすごいんですけど、国内にいる状況ではあまり実感がわくことはないんですよね。
―Spotifyではどの国のリスナーが多いんでしょうか。
きくお:一番多いのがアメリカです。次にメキシコ、ブラジル、イギリス、カナダ、フィリピン、日本と続きます。日本のリスナーはチリと同じくらいでかなり少ないですね。
―「愛して愛して愛して」を最初に作ったときは、海外に向けた意識はありましたか?
きくお:もちろんなかったです。
―ミュージックビデオの公開は2015年3月ですが、それ以前に曲は発表していた。
きくお:そうですね。まず雑誌のコンピレーションCDの企画のために作って、その後『きくおミク3』という同人アルバムに収録して、MVとして公開したのがその2年後でした。
―実は今回、この曲がなぜ海外で聴かれるようになったのか、僕なりに仮説を立ててきたんです。
きくお:そうなんですね。それは僕も聞きたいです。
「異質な存在で驚かせたい」
Bandcampが一つのきっかけに
―その前にいろいろと時代背景を振り返りたいんですが、まず、きくおさんがYouTubeにチャンネルを作ったのはいつ頃のことでしたか?
きくお:かなり前ですね。登録したのは2006年、今残っている最初の動画が2011年12月に投稿したアルバム『KIKUOWORLD』のクロスフェードです。
―先ほど仰っていたように、この頃のボカロ曲のプラットフォームはニコニコ動画で、YouTubeに投稿してもあまり反応はなかったのではないかと思います。
きくお:性格的に良くも悪くも開拓者精神が旺盛な方で。誰もやってないことで盛り上がりそうなものに先に手をつけようという野心は常に強いんです。そのうちの一つでした。
―また、2013年頃のボカロ界隈は「千本桜」や「カゲロウプロジェクト」といったメディアミックス作品が脚光を浴びて、ボカロPが商業的な成功をおさめていく時期だったと思います。ただ、きくおさんはそれ以前からボカロ曲の投稿を始めている。つまり、ボカロPのほぼ全員がアマチュアで、ボカロで曲を作って生計を立てるということにほとんどリアリティがなかった時代から携わってらっしゃるわけですよね。
きくお:まさにそうです。鋭いですね。
―振り返って、その変化を当時どんな風に感じていましたか?
きくお:ボカロを始めた2010年の頃から、自分はプロの作曲家だと名乗ってたんですよ。当時は「ボカロPが金儲けをするなんて何事だ」みたいな感じで叩かれたりもしてました。ただ、ボカロPとしていろんな受注を受けて曲を作ってお金を稼いでいくっていうのも、当時は誰もやってないから先に手をつけておこうと思って。
―当時からボカロシーンの人気やメインストリームのトレンドに乗っかっていく発想はなかったわけですね。その理由はどういうところにあったんでしょうか。
きくお:もともと、たまというバンドがすごく好きで。『いかすバンド天国』という番組で、周りがみんなコテコテなロックバンドの中にすごく異質な存在が入って、それで一気に話題になった。それがすごく格好いいなと思ったんです。だから、メインストリームの人たちと同じことをするより、その中に入ってくる異質な存在みたいな感じで驚かせたいという気持ちがありました。
―さらに遡ると、きくおさんはボカロ以前にも同人音楽などで楽曲を発表していますよね。
きくお:そうですね。個人的な事情なんですけれど、そもそも、小学1年生か2年生の頃から、自分は創作をすることでしか社会で身を立てられない存在なんだって確信していて。だから、自分に合った創作表現ってなんだろうって、いろんなことを試したんです。絵もやったしGIFアニメもやったしプログラミングもやった。いろいろやった中でDTMだけが残ったんですね。なので、ネットに曲を発表する以前、最初に曲を作る時からお金にするつもりでやってました。
―「愛して愛して愛して」のMVを公開した2015年頃の体感についても聞かせてください。この頃はボカロシーンが停滞期にあったというか、ニコニコ動画の盛り上がりが少し落ち着きを見せてきた時期だったと思います。そのあたりはどんなことを考えていましたか?
きくお:ボカロ以外にもいろんな受注の仕事を受けたりしていましたね。歌手の方に曲を作ったり、ゲーム音楽を作ったり、あらゆるところに可能性を広げていて。ただ、いろいろやっていく中で、受注の曲を作ることが自分に全く向いてないことがわかったんです。それで自主制作の方に切り替えていったっていうのはありますね。
―わかりました。その上で僕の仮説なんですが、きくおさんがBandcampに音源を置くようになったのが、今考えると伏線の一つになっていたんじゃないかと思うんです。
きくお:面白い。その切り口は初めて聞きました。

きくおのBandcampページ(https://kikuo.bandcamp.com/)
―きくおさんがBandcampをスタートさせたのはかなり前のことですよね。
きくお:そうなんですよ。いつ登録したのかはパッとわからないんですけれど。
―いろいろ調べたんですが、きくおさんは2015年2月9日に「Bandcampで海外向けにDL販売している『きくおミク4』がボーカロイドのカテゴリで人気トップになっている」ということをツイートしています。この時点でBandcampで音源をダウンロード販売しているボカロPは少なかったんじゃないかと思います。
きくお:そうですね。ほぼいなかったし、ボカロリスナーのコミュニティもおそらくなかったと思います。そもそもBandcampになぜボカロ曲が置かれないかって、レーベルが嫌がったんですよ。Bandcampはインディの音楽がすごく多くて、そこに対してアンテナを張っている人たちが沢山いたんですけれど、その中にボカロが来たっていうのが驚きとして捉えられていた。そういう肌感覚はありましたね。
バズったときのための準備
「組み合わせ」で個性を追求
―きくおさんの実感として、YouTubeやSNSに英語圏からのリプライやコメントが多くなってきたと感じたのはいつ頃のことでしょうか?
きくお:それはもう、「愛して愛して愛して」のバズと同じ時期ですね。アナリティクスで見ると、バズの第1波が2020年3月ぐらいで、第2波が2021年3月ぐらいです。
―きくおさんのすごくユニークなところは、日本にずっと拠点を置いて、日本語で曲を発信しているんですが、「愛して愛して愛して」のバズが海外から起こったということですね。
きくお:面白いですよね。アメリカとか英語圏で人気を得るためには英語の歌詞を書かなきゃいけないのかと思ってたんですよ。そうしたら日本語のままウケるんだと思って。それは本当に思いもしなかったことですね。バズるというのも運でしかない。「こうすればバズる」みたいな正解とか法則なんかどこにもないっていうことの証明ですよね。
―バズに気付いた時はどういうことを考えていましたか。
きくお:なんとなくその当時、TikTokでバズってるよっていう話は耳に挟んでたんで、じゃあ一瞬でパッと終わるだろうなと思ってたんです。でも、そこから不思議なことにずっと人気が持続してるんですよ。ピークの数字をほぼそのまま維持してるんです。それはやっぱり、運が舞い込んできたという。それを上手くキャッチすることができたというか、上手くキャッチする準備をちゃんとしてたのが良かったなって思いますね。
―準備というと?
きくお:たくさん曲をリリースしていたというのはまず一つありますね。一つの曲から興味を持ってくれた人がアーティストを見に行って、そこに100曲ぐらいリリースあったら、みんな結構それを聴いてくれる。そこからまた次のバズのネタを探してくれる人もいる。あとは各国語の字幕の設定をオンにしていたので、海外の人がすぐに入ってこれるような状況を作っていたっていうのもあったりします。あとはもう曲自体ですね。時代と共に古くならないように作っていた。それが功を奏した気もします。
―きくおさんのInstagramを見ると、2019年2月8日にYouTubeチャンネルの登録者数が10万人を突破したということを投稿されています。そこには「25%がジャパニーズで75%がノンジャパニーズ」と書いてあるので、2020年3月にバズが起こる前の数年間ですでに海外のリスナーを掴んでいたんじゃないかと思うんです。
きくお:なるほど。たしかにそうですね。アナリティクスのグラフを見ても、2012年から始めて、ちょっとずつ伸びてきてるみたいな感じです。
―きくおさんはPatreonという月額制のアーティスト支援プラットフォームも2019年に始められていますよね。ここでは英語で発信されています。
きくお:そうなんです。PatreonはボカロPとかじゃなくて、そもそもミュージシャンがほとんどやってない状態から始めました。pixivからFANBOXというサービスがリリースされたんで、英語圏の人はFANBOXじゃなくてPatreonだよなというので、2つ作ってとりあえずやってみました。
―Patreonはやってみてどうでしたか?
きくお:それはもう、いいことだらけですね。リターンもほとんど何もなく、更新もあまりせずに、寄付とか募金みたいなものだと思ってやってくださいみたいな感じでやっているので。ノーリスクローリターンみたいな感じです。
―支援者は国外の方ですか?
きくお:そうですね。入っていただいているのはほぼ100%が英語圏の方で、あとは少し中国の方がいるくらいです。初めて2、3日でかなり入っていただいて、そこからはずっとその時の感じが維持されてる感じです。
―これは、創作活動で生計を立てていきたい、けれど受注案件は肌に合わないという、きくおさんの志向や価値観にまさにフィットするサービスなのではないかと思います。
きくお:その通りです。だからもう本当にありがたい限りです。感謝ですね。

きくおのPatreonページ(https://kikuo.bandcamp.com/)
―これは僕の仮説なんですが、2020年や2021年は、コロナ禍でみんなが家にいる状況が世界中で生まれたことでTikTokの影響力が増して、TikTok発のバズが世界中のいろんなところで起こった時期だったと思うんですね。ただ、そこからすぐに忘れられたアーティストと、それをきっかけにファンを増やして根強く活動が広がったアーティストがいる。きくおさんの場合は確実に後者である。
きくお:そうですね。
―その差を分けたのが、BandcampやPatreonのようなアーティストとリスナーのコミュニティをつくるサービスにちゃんと拠点を作っていたことだと思うんです。きくおさんは2020年の段階でそれが整備されていた数少ないボカロPの一人だった。
きくお:なるほど。そうだと思います。それはかなりいい感じの洞察だと思いますね。何がいつどう当たるかっていうのは、本当にわからないんです。だから当たった時のためにキャッチする準備をしておく、いろんなところに種まきをしておくっていう。そのどれか一つがたまたまどうにかなってくれたみたいなことですね。体感としてもそんな感じです。
―もちろん音楽性の部分も大きいと思います。きくおさんの曲は、いい意味で聴き手の期待や予想とかを裏切るタイプである。いわゆるメインストリームでウケているものとは違う方向性でありつつ、多彩である。その魅力が一番大きいと思うんです。
きくお:ありがとうございます。
―ここまで戦略みたいな話ばかり聞いてきてしまったんですが、改めて、そういう音楽性のこだわりの由来を聞かせていただいてよろしいでしょうか。
きくお:能動的な方面と消去法の方面の2つの要因があって。消去法的な方というのは、できないことがすごく多いんですよ。楽器も弾けないし、楽譜も覚えられない。内向的すぎる性格なので、コミュニケーションも難しいところがあって、人に頼んだり一緒に作ったりするのもできない。そういう性格上の問題から自分一人だけで完結するDTMの制作スタイルに限定されちゃうんですよね。能動的な方というのは、そこで浅く広くいろんなものを組み合わせられるのがDTMの強みだと思うんですね。一つの楽器にとらわれず、アコースティックな楽器と電子音を組み合わせてみたり、たとえば1オクターブを7つの平均律にわけたり、微分音を使ったり、曲のイメージに合わせて遠いところを組み合わせることで自分にしか出せない個性を追求していこうというのはあります。とにかく音作りの面ではオリジナリティを強く持たせるにはどうしようということばかり考えてますね。
―今後の目標やビジョンとしてはどういうものがありますか?
きくお:曲作りしかできないし、それがやってて一番楽しいし、みんなそれを喜んでくれるし、田舎でゆっくりのんびりしながらいっぱい寝ていっぱい食べて、曲を作って趣味を楽しんで、行けるとこまで行けたらいいなっていうのを考えてます。あとはアメリカでライブしたいですね。そこには興味はあります。



















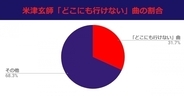


![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








