国立映画アーカイブでは、 企画上映「1980年代日本映画――試行と新生」を、 2月16日(火)より約2か月半にわたり開催する。 日本が経済大国となり、 消費社会が到来した1980年代。
映画にもさまざまな変化が訪れた。 1970年代に始まる大作化の流れが一層顕著になる一方、 若年観客向けのアイドル映画やアニメーションがヒットし、 新たな企業やプロダクションが映画作りに参加、 何よりも新しい才能が続々とデビューを飾った。 映画界のこうした構造変化は、 現在にまで影響を及ぼす重大なものだったと言えるだろう。 本企画は、 当館が近年開催している「現代日本の映画監督」シリーズや佐々木史朗、 黒澤満といった映画プロデューサーの特集をふまえ、 時代の新しい流れを示した作品や、 社会的に話題となった作品など計44本(42プログラム)によって、 1980年代の日本映画を回顧する試み。 バラエティに富んだ映画を通じて、 時代が浮かび上がってくるラインナップとなっている。 現代日本映画の起源であるこの時期の作品を、 是非チェックしよう。
アニメーション映画の新展開 1980年代は、 現在も続く劇場用アニメーション人気が定着するとともに、 作家性が強く打ち出されて新境地が拓かれた。 『じゃりン子チエ』(1981、 高畑勲)、 『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』(1984、 石黒昇・河森正治)、 『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988、 富野由悠季)、 『魔女の宅急便』(1989、 宮崎駿)などを35mmフィルムでご覧いただける。 名匠たちの意欲作 大手の映画会社でプログラムピクチャーを製作していた監督たちも、 時代の新たな展開に反応し、 インディペンデントな環境で斬新な作品を生み出していく 『ミスター・ミセス・ミス・ロンリー』(1980、 神代辰巳)、 『陽炎座』(1981、 鈴木清順)、 『怪異談 生きてゐる小平次』(1982、 中川信夫)、 『生きてるうちが花なのよ 死んだらそれまでよ党宣言』(1985、 森崎東)など、 熟練の監督たちの実験精神に満ちた作品をチェック。
編集部おすすめ
トピックス
ニュースランキング
-
1

驚愕の464工程、史上最高難易度のおりがみ本?! 『新世代 究極のおりがみ』発売!
-
2

三代目JSB今市隆二、HIRO・ATSUSHIの前で“ド緊張”したオーディションを回想「震えちゃって…」
-
3

Snow Man、「Summer Sonic Bangkok 2025」出演 大型音楽フェス初参戦
-
4

アークティック・モンキーズはどこへ向かう? No Buses近藤大彗らとバンドの現在地に迫る
-
5

シンガー・TOMOO、ファッションのテーマは「等身大のおめかし」グリーンカーペットの感想語る【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
-
6
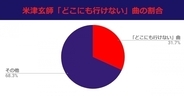
米津玄師の歌詞で「どこにも行けない」率は何%ぐらいなのか?
Amazonおすすめランキング PR
更新:2024-09-10 14:44
更新:2024-09-10 14:44
更新:2024-09-10 14:44
-
 イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン AIFENG ブルートゥース イヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリング 長時間再生 自動ペアリング 完全ぶるーとぅーす イヤフォン タッチコントロール Type-C充電 IPX7防水 片耳/両耳 小型/軽量 iPhone/Android適用 WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲーム (ブラック)2,299円 93%OFF 参考価格:33,999円
イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン AIFENG ブルートゥース イヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリング 長時間再生 自動ペアリング 完全ぶるーとぅーす イヤフォン タッチコントロール Type-C充電 IPX7防水 片耳/両耳 小型/軽量 iPhone/Android適用 WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲーム (ブラック)2,299円 93%OFF 参考価格:33,999円 -
 【 2024革新 骨伝導イヤホン 】イヤホン こつでんどう bluetooth 骨伝導 bluetooth5.3 マイク付き ブルートゥースイヤホン 耳掛け式 通話 軽量 IPX7 防水 オープンイヤーヘッドホン ワイヤレスイヤホン 耳を塞がない 急速充電 10時間連続使用可 骨伝導ヘッドセット 日本語ガイダンス スーポツ向き 物理ボタン スーポツ/ウェブ会議/通勤通学/ランニング 技適認証済み2,380円 68%OFF 参考価格:7,500円
【 2024革新 骨伝導イヤホン 】イヤホン こつでんどう bluetooth 骨伝導 bluetooth5.3 マイク付き ブルートゥースイヤホン 耳掛け式 通話 軽量 IPX7 防水 オープンイヤーヘッドホン ワイヤレスイヤホン 耳を塞がない 急速充電 10時間連続使用可 骨伝導ヘッドセット 日本語ガイダンス スーポツ向き 物理ボタン スーポツ/ウェブ会議/通勤通学/ランニング 技適認証済み2,380円 68%OFF 参考価格:7,500円 -
 イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン【2024限界突破・最先端Bluetooth5.4】YEAHYO オープンイヤー イヤホンブルートゥース イヤホン ワイヤレス 骨伝導イヤホンの進化 イヤーカフ イヤホン 耳を塞がないイヤホン 自動ペアリング 60時間使用可能 Type-C急速充電 Hi-Fi音質 音漏れ抑制 物理操作ボタン 超軽量設計 快適な装着感(ブラック)2,599円 93%OFF 参考価格:36,999円
イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン【2024限界突破・最先端Bluetooth5.4】YEAHYO オープンイヤー イヤホンブルートゥース イヤホン ワイヤレス 骨伝導イヤホンの進化 イヤーカフ イヤホン 耳を塞がないイヤホン 自動ペアリング 60時間使用可能 Type-C急速充電 Hi-Fi音質 音漏れ抑制 物理操作ボタン 超軽量設計 快適な装着感(ブラック)2,599円 93%OFF 参考価格:36,999円
更新:2024-09-10 14:44
-
 MP3プレーヤー Bluetooth5.1 音楽プレイヤー 32GB SDカード対応 ウォークマン 多機能 128GB拡張可能 スピーカー内蔵 映画鑑賞/写真閲覧/録音/FMラジオ/電子ブック/目覚時計/語学学習 ホワイト 日本語取扱説明書付き3,754円 25%OFF 参考価格:4,999円
MP3プレーヤー Bluetooth5.1 音楽プレイヤー 32GB SDカード対応 ウォークマン 多機能 128GB拡張可能 スピーカー内蔵 映画鑑賞/写真閲覧/録音/FMラジオ/電子ブック/目覚時計/語学学習 ホワイト 日本語取扱説明書付き3,754円 25%OFF 参考価格:4,999円 -
 MP3プレーヤー 32GB 最大128GBまで拡張可能 SDカード対応 HIFI音質 スピーカー搭載 音楽プレーヤー Bluetooth5.0 mp3プレーヤー 2.4インチ大画面 光るタッチボタン 多機能デジタルオーディオプレーヤー ストップウォッチ 録音 小型 軽量 FMラジオ/電子ブック/アラームなどの機能付き スポーツ/ランニング/言語学習などに適用 合金製 日本語取扱説明書付き4,180円
MP3プレーヤー 32GB 最大128GBまで拡張可能 SDカード対応 HIFI音質 スピーカー搭載 音楽プレーヤー Bluetooth5.0 mp3プレーヤー 2.4インチ大画面 光るタッチボタン 多機能デジタルオーディオプレーヤー ストップウォッチ 録音 小型 軽量 FMラジオ/電子ブック/アラームなどの機能付き スポーツ/ランニング/言語学習などに適用 合金製 日本語取扱説明書付き4,180円 -
 MP3プレーヤー Bluetooth5.1 音楽プレイヤー 32GB SDカード対応 128GB拡張可能 スピーカー内蔵 映画鑑賞/写真閲覧/録音/FMラジオ/電子ブック/目覚時計 ブラック4,233円 15%OFF 参考価格:4,999円
MP3プレーヤー Bluetooth5.1 音楽プレイヤー 32GB SDカード対応 128GB拡張可能 スピーカー内蔵 映画鑑賞/写真閲覧/録音/FMラジオ/電子ブック/目覚時計 ブラック4,233円 15%OFF 参考価格:4,999円
お買いものリンク PR















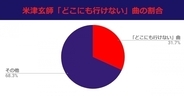


![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


