戦後の住宅難を背景に建てられた築70年以上の「門司港1950団地」(福岡県北九州市)が、今、国内外から注目を集めている。家賃は月1万円、条件は“入居者自身がDIYで部屋をつくること”。
観光地と生活の間にある、門司港という街の素顔
改札を抜けると、今回の案内人であり「渋沢プロジェクト」を主導する吉浦隆紀さんが出迎えてくれた。九州を拠点に空き家や団地の再活用に取り組んできた吉浦さんは、現在は築70年を超える「門司港1950団地」の再生に挑んでいる。

大正時代の姿に復元されたJR門司港駅。木造二階建てのクラシカルな駅舎は、左右対称の造りが特徴的だ(写真撮影/笠井鉄正)
「良かったら、散策がてら門司港の街を歩いてみませんか?」と吉浦さんに誘われ、団地へ向かう道のりを歩き始めた。

門司港レトロ(写真提供/吉浦さん)

門司港レトロ(写真提供/吉浦さん)
人通りの多い海辺の観光地から、山手へと足を進める。「この通りからあちらが『門司港レトロ』と呼ばれるエリア、こちらが住民の暮らすエリアです」と吉浦さん。港町の印象が強い門司港だが、実際は平地が少なく、坂を上がればすぐに住宅街が広がっている。にぎやかな観光地の空気から一変、のんびりとした佇まいの街並みが現れた。
立派なアーケードの商店街に足を踏み入れると、取材日は日曜だったが、人影はまばらだった。「地元の人は、日曜はしっかり休むので(笑)、平日はおじいちゃんやおばあちゃんでにぎやかなんですよ」と吉浦さん。とはいえ高齢の店主も多く、閉業する店舗も少なくない。


JR門司港駅から団地まで徒歩20分。街を歩くことで、知られざる門司港の“B面”に出合える(写真撮影/笠井鉄正)
想像以上の“空っぽ”状態にも関わらず、続々と寄せられた入居希望
緩やかな坂を上っていくと、鉄筋コンクリート造の団地が見えてきた。「畑田団地」改め「門司港1950団地」は、戦後間もない1951年、福岡県住宅供給公社の第1号として建設された建物。70年の使用期限が定められていたため、2021年に最後の入居者が退去し、その歴史に一度は幕を下ろした。

頑健な構造の門司港1950団地。旧耐震だが、階段室型団地タイプは壁式構造により、耐震性は強い傾向にあるという(写真撮影/笠井鉄正)
一度は解体を目されていたが、吉浦さんは入札に参加し、わずか90万円で落札する。土地だけなら数千万円の価値があるものの、解体費用が1億円近くかかるため、買い手がつかずにいたそうだ。「見学して15分で『これは残さなきゃ』と思いました」と吉浦さんは振り返る。
ただ、購入後に待っていたのは想定以上の“空っぽ”状態だった。配管は朽ち、電気は電柱から切断されていた。水道を引き直すだけで数百万円。通常なら再生を中止しても不思議ではない。

現在は無事に上下水道と電気が開通し、入居者専用のWi-Fiも完備されている(写真撮影/笠井鉄正)
条件はシンプルだ。家賃は月1万円、3年間の定期借家契約。入居者自身が部屋を解体し、自由につくり上げることができる。構造や外壁は壊せないが、キッチンなどの水回りや内装はすべて手を入れてよい。材料費はオーナー側が支給するため、初期費用も最小限で済む。
「渋沢プロジェクト」と名付けられたこの取り組みは、SNSでの発信が話題となり、YouTubeの人気チャンネル「ゆっくり不動産」で紹介されると、一気に全国から注目を集めた。入居希望は殺到し、A棟に続きB棟も含めた全34戸が満室に。部屋ごとに用途はさまざまで、住居として暮らす人もいれば、アトリエやカフェ、探偵事務所など、仕事や趣味の拠点とする人もいる。

今後インフラを整備予定というB棟は、蔦に覆われた佇まいにひと目惚れする人が多数(写真撮影/笠井鉄正)

海外からも問い合わせがあるという(写真撮影/笠井鉄正)
個性豊かな入居者たちが紡ぐ、それぞれの物語
門司港1950団地の魅力をもっとも雄弁に物語るのは、ここに暮らす、あるいは活動する人々だ。壁を塗り、床を剥ぎ、手探りで空間をつくり上げる過程は、単なる改修作業を超えて、その人自身の人生観を映し出すキャンバスのようにも見える。
団地の屋上では、小さなピクニックが開かれていた。

潮風が頬をくすぐる屋上は、入居者たちの憩いのスペース。高台にある団地からは門司港の街並みと関門海峡が一望できる(写真撮影/笠井鉄正)
まずは、児嶋さんに伴われて「book & cafe もじのすみか」を準備中のA棟23号室へ。古い団地の意匠を生かしつつ整えられた部屋には、本・本・本! 「もともとは留学予定で、自分の蔵書を置いておく場所を借りたいなと思ったのが応募のきっかけ。家族や友人が自由に出入りできる空間にしたいな、というところから、本と喫茶でのんびりできるお店を営みたいな、といつの間にか気持ちが変わっていました(笑)。この団地、雰囲気も居心地も、魅力的すぎるんですよね」

「昔のままの雰囲気をなるべく残したい」と話す児嶋さん。畳を張り替え、壁を塗り直した程度で、間取りや建具はそのまま使用予定という(写真撮影/笠井鉄正)

作業よりも読書が捗って困ります、と楽しげな児嶋さん。蔵書を寄付してくれる人もいるのだとか(写真撮影/笠井鉄正)
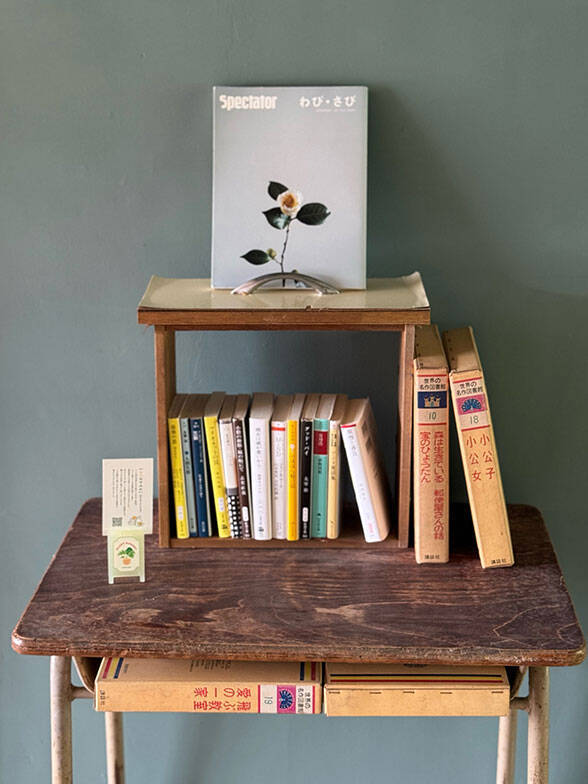
(写真提供/児嶋桜さん)
はじめて経験するDIYも苦にならないのは、友人である守田さんや、ともに準備を進める入居者たちの存在が大きいという。「みんな“クセつよ”だから楽しいですよ」。
A棟22号室でオープン予定の「atelier bald(アトリエ ボールド)」は、西洋占星術とハーブティーのお店。「お洋服のアトリエも兼ねてます。やりたいこと、何でも詰め込もう!と思って」と弾けるような笑顔を見せてくれた。落ち着いた雰囲気の23号室とは趣がガラリと変わり、床は剥き出しのモルタル、壁は白と鮮やかなピンクで塗り分けられている。入居者の個性でここまで印象が変わるものか、と改めて驚かされた。

「どこでもドアみたいで可愛いでしょ?」と笑う守田さん。サロペットに散るペンキがかっこいい(写真撮影/笠井鉄正)

「新しいことを始めようと思ったとき、家賃1万円というハードルの低さは魅力でした」と語る(写真撮影/笠井鉄正)
「古いものを大切に」思いを体現するカフェがオープン
すでに店舗運営をスタートさせた入居者もいる。長崎県で看護師として働く末満瑞穂さんが入居したのは、日当たりの良いA棟19号室。昨年9月から改修を始め、壁を塗るだけで数カ月を要したそうだ。「最初は塗っても塗っても剥がれてきて、本当に大変でした。でも吉浦さんが『とにかく何度も重ね塗りすること』とアドバイスしてくださって。
床は前の住人が重ねていたクッションフロアを剥ぎ、下地の木の床を再生。古い建具も残しながら、空間に命を吹き込んだ。2025年5月7日、自身の誕生日にカフェ「デイジー*ワールド」をオープンし、現在は諫早での仕事をしながら行き来し、月に数日だけ営業している。
「古いものを大切に、手を加えながら長く使っていきたい」という末満さんの思いを体現する同店には、かつてここで暮らしていた住人も足を運ぶという。こだわりの空間で穏やかに微笑む彼女は、間違いなく団地に新しい物語を刻み始めた入居者のひとりだ。

卵の殻からつくられた調湿・消臭効果のあるとされる塗料を使用するなど、素材にもこだわった末満さん。「吉浦さんと一緒に試行錯誤した工事も、良い思い出になりました」(写真撮影/笠井鉄正)

店内では、大切に手入れしてきたアンティークの家具やカトラリーがひっそりと来客を待つ(写真撮影/笠井鉄正)
不動産から教育へ。“自分の力で切り拓く”力が育まれる場所
門司港1950団地には、学生から現役の建築士、退職後のシニアまで、年齢も職業も異なる人々が集まっている。屋上のピクニックでは自然とノウハウがシェアされ、工具やアイデアを交換し合う光景が日常だ。
入居者自身が手を動かすことで、自然と技術や知識のシェアが生まれる。吉浦さんは、それを「建物を使った教育」と表現する。「義務教育では学べないことを、ここでは体験できるんです。

入居者の中には、プロの建築士も! 設計から施工まで自ら手がけているという。専門家の豊富なアイデアは、他の入居者にも良い刺激になっているようだ(写真撮影/笠井鉄正)
吉浦さんが見据える「渋沢プロジェクト」と空き家再生の未来
本格稼働から1年が経ち、門司港1950団地には少しずつだが確かな変化が生まれている。かつては空き部屋だった一室に人の声と灯りが戻り、団地全体にささやかな息吹が広がり始めた。
想像以上の手応えを感じているという吉浦さんに今後の展望を尋ねると「渋沢プロジェクトを含め、九州で空き家1万戸再生」という驚きの数字が返ってきた。「九州だけでも90万戸の空き家があります。その中の1万戸を再生することができれば、社会を変えるきっかけになるかもしれない。家として建てられた建物だからって、必ず住まなければならない決まりはないですよね? 児嶋さんのように蔵書を置いても良いし、自宅ではない場所にシアタールームを持ってもいい。もちろん、お店やアトリエとしての活用も考えられます」
その一環として、月3万円で九州中の空き家を利用できる“住まいのサブスク”構想も温めている。農作業の手伝いや地元企業との出合いを通じて、地域との関わりを深めながら自由に暮らす。人口減少時代にふさわしい“もうひとつの暮らし方”を提示しようとしているのだ。

入居者同士に加え、店舗を訪れる人々との縁もつながり始めた門司港1950団地(写真撮影/笠井鉄正)
また、吉浦さんは、この団地だけの再生だけでなく、記事のはじめに紹介したような団地への道のりそのものも新たな価値を持つと感じている。JR門司港駅から門司港1950団地に至る、観光地の華やかな表の顔から、商店街や旧市街といった街のB面を通り抜け、徒歩20分の間に出合える門司港という街の魅力。
「団地に人が訪れることで、途中にある商店街や古民家カフェに立ち寄る人も増える。街を知ってもらえれば滞在時間が延びて、いまは閑散としている場所にも再びにぎわいが生まれるはずです」。人口減少や空き家問題に直面する時代にあって、「住まいの再生」は「街の再生」へと広がりうる。古い建物を壊さずに活かすという発想は、環境にも、地域社会にも、そして入居者自身にもプラスをもたらす“三方良し”のモデルだ。

「僕は街に投資したい。門司港のようにポテンシャルを秘めた地域は、他にもいっぱいあるんです」と語る吉浦さん(写真撮影/笠井鉄正)
家賃1万円の団地は、多様な人を惹きつけ、街を動かし始めた。門司港1950団地は、かつての生活の記憶を抱えながら、次世代の暮らし方やライフスタイルを提案する場となりつつある。ここで育まれる新しいコミュニティと街のつながりが、門司港にさらなるにぎわいを生む日は、きっともうすぐそこだ。
●取材協力
・渋沢プロジェクト
・空き家暮らし





























![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
