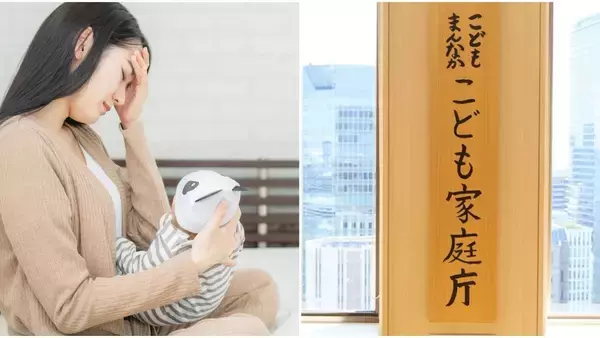
厚労省の『人口動態統計』によれば、2024年の出生数は過去最低の68万6061人で、前年から5.7%ダウン。一人の女性が生涯で出産する子どもの数を示す合計特殊出生率は1.15で、前年比0.05ポイント減となった。
「結婚・出産・育児は、富裕層だけの楽しみのように感じています」
都内在住で2歳の子どもを持つ女性・Aさん(30代後半)はいう。
「このご時世で、もうひとり出産しようとは思えません。私の周りには、独身を謳歌している人のほうが多いです。少子化は国としては問題かもしれませんが、家庭単位で考えると子どもがいなかったり、一人っ子であるほうが経済的にも精神的にも幸せだと思います。
私は、我が子を私立の小・中学校に行かせたいので、家計を考えると一人っ子で限界。年齢的にも、もうこれ以上はいいかな」
取材の中で最も多かったのは“経済面での不安”だ。昨今の生活必需品の値上げや住宅ローンの変動金利上昇を危惧する声もあった。
神奈川県在住で3歳と7歳の子どもを持つ女性・Nさん(40代)はこども家庭庁のお金の使い方に異論を唱える。
「ニュースで9億円を出産アドバイザーにかけるという政策を見ました。それよりも出産のたびに300万円、もしくは3人出産で1000万円などの現金を母親に配ってほしい。そのほうがよっぽど産む人は増えると思います」
こんな声もある。
「出産育児一時金が数年前に増額されたのはありがたかったですが、産んで終わりではなく、産んでからが子育ての本番。毎月1万円(3歳までは1万5000円)の児童手当ではなく、出産した女性には毎月10万円程度の子育て手当をもらいたい」
いっぽう、独身女性のなかには、将来にこんな不安を抱えている人もいる。
「結婚もしたいですし、子どももほしいです。でも、非正規で働いていますし収入が不安定で子どもは夢のまた夢。結婚・出産・育児は、富裕層だけの楽しみのように感じています」(都内在住の20代女性)
女性の雇用環境や収入については、東京大学大学院経済学研究科の教授で、『子育て支援の経済学』(日本評論社)などの著書がある山口慎太郎氏がこう指摘する。
「非正規従業員は、全労働者の約4割、女性に限っていえば5割を占めます。その人たちの不安要素を取り除いてあげる施策が必要です。待遇の底上げを進め、同じ仕事をしている正規・非正規従業員の格差もなくさなければいけません」
40歳で出産し、現在4歳になる子どもの母親である女性も、お金の問題を指摘する。
「娘が二十歳になったときに私は還暦を超えています。一人っ子だと、何かと心細いでしょうから本当はもう一人産みたい。でも、体力面での不安に加え、二人を大学まで行かせる教育費を考えるとなかなか踏み切れません」
前出の山口氏も国の教育費の支援が不足していることを指摘する。
「日本は、国内総生産(GDP)に占める公財政教育支出は3.7%と、経済協力開発機構(OECD)の平均4.9%を下回っており、教育支援は不足しているといえます。
教育費負担の軽減が出生率に与える効果は限定的ではあるものの、次世代の人材育成を通じ、より豊かで活力のある社会を築くことは子育てに希望が持てる社会につながるのでは」
仕事をあきらめたくないという気持ちも…
いっぽう、出生率アップに成功した国がある。
ハンガリーでは、2015年から新婚カップルへの税額控除を導入したのに加え、妻が妊娠すると妊娠91日目から給付金が出る。
さらに、4人出産した女性は所得税が生涯ゼロになるほか、30歳未満の子持ち既婚者の学費は無償、住宅助成金も潤沢だ。これにより、2010年から約10年で婚姻数は2倍近くに、1.25だった出生率は1.59ポイントまで改善した。
「日本では出産に適した年齢とされる20~30代の女性が減ってきているので、せめて出生率を上げるしかない。そのために、日本が取り組むべき点として、まずは、男性が家事・育児に積極的に参加することがあげられます。
ある国際データで、男性が家事・育児に参加する国ほど、出生率が高いことがわかっています。国内でも、父親が家事・育児に積極的な家庭ほど2人目が生まれやすい」(前出・山口氏)
いくら可愛い子どもでも、「ワンオペだからこれ以上は無理……」という母親は多いという。また、夫の会社に育休制度はあっても“取りづらい”人もいる。
「日本はほかの先進国と比較しても、育児休暇の制度自体は整ってきています。しかし、『実際には取りづらい』というのが最大の障壁だと思います。
そこで、企業のトップ、部下を持つ上層部には育休取得を奨励してほしい。育休を取りやすい雰囲気をつくることは、優秀な人材を惹きつける(企業の)魅力にもなる。幹部が意識的に育休を勧める企業が、もっと増えてほしい」(前出・山口氏)
現代の女性は働き方にも、苦慮している人もいる。3歳と5歳の子どもを育てながらIT関連企業に勤めるKさん(30代)はいう。
「子どもとの時間を大切にしたい一方で、仕事をあきらめたくないという気持ちがあります。今は、会社の理解があり、在宅勤務をメインでなんとか両立をしています」
女性にとって、出産をすることはキャリアをあきらめることにつながることもある。出産とキャリアを天秤にかけ、出産自体をあきらめた人や「あと一人ほしい」を踏みとどまった女性もいる。
前出の山口氏はいう。
「キャリアを積む上で大事な年齢と、子どもを産み育てるのに適した年齢が重なっている。今後、『キャリアを積んでから子どもをもうける』という認識を改める必要があるのでは。
男性ですが、大学院に通いながら同年代の女性と結婚し、20代半ばで第一子をもうけた教え子がいます。子どもを持ち、育てながらキャリアの重要な時期を迎えていく。
こうした生き方の広がりに、従来の企業の仕組みや社会制度が対応しきれていないのが現状です。ここから手探りで検証しながら、多様なライフコースを支える仕組みを社会全体に根付かせていくこと。それが、子どもを持ちたいと願う人が希望するタイミングで安心して家庭を築く環境づくりにつながり、結果として少子化対策に寄与するのだと思います」
日本は、女性が産み育てやすい社会をつくっていけるのだろうか。
取材・文/山田千穂 集英社オンライン編集部ニュース班



























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


