
自然豊かな環境に憧れて都市部から過疎地域に移住する人たち。だが日本の田舎での生活に詳しい花房尚作氏によると、移住した多く人々は生活が徐々に破綻し、田舎から去ってしまうことが多いという。
書籍『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ 過疎地域から考える日本の未来』より一部を抜粋・再構成し、過疎地域に住む人々の思考を解説する。
失敗する移住者たち
過疎地域の住民は排他性をそれほど持っていない。移住者の受け入れについて尋ねると、「あまりよそから人が来てほしくないです。でもよそから人が来るのは別に構わないです」と言う。そこで、「移住者はどういう人がよいですか」と質問すると、「地域愛のある人です。他は何も要らないです。でも犯罪者は来てほしくないです」と言う。ほぼ全員が同じように答える。
つまり、移住者を望んではいないが、移住したいのなら受け入れる。その代わり、地域の風土的個性には従ってほしいと考えている。
人口が多い都市部では気が合う友人や知人を自分で選べる。ところが、人口が少ない過疎地域では狭い範囲の中で、友人や知人がおのずと決まる。気が合わない者と付き合うのは誰しも難しい。
そこで、相手に気を合わせるのではなく、「地域の風土的個性に気を合わせる」という手法を取っている。
役場の職員採用についても同じだ。その選考基準は「深い郷土愛を持ち、地域に根差した人材」である。要するに、地域の現状に好感を持っていて引き続き保ちたい者になる。地域に不満を持っていて変化を望む者は選考から外れる。
じつは、移住者が地域に馴染むのは簡単だ。住民は暇を持て余しているので積極的に世話を焼いてくれる。農作物のお裾分けもあるし、野焼きの方法や地域の穴場も教えてくれる。ただし、地域の風土的個性に逆らう行為は許されない。
次のような失敗事例がある。ある夫婦が自然に囲まれた生活に憧れて過疎地域に移住した。移住先の決め手は支援金と就業先の斡旋だった。
「都会で悪いことをして逃げてきた」と身に覚えのない噂が
半年ほど過ぎた頃である。夫婦は定期的に要請される自治体活動が負担になっていた。その活動は参加、不参加にかかわらず作業費の徴収があった。徴収された作業費は飲み会に使われていた。
そこで「飲み会はやめませんか」と夫婦が提案したことで、住民から「決まりに従わないのは裏切りだ」「地域のつながりが壊れる」といった反発が起こった。
住民側からすれば、移住者を快く受け入れて面倒を見ている。地域の風土的個性に従うのが礼儀だ。その礼儀を反故にしたのだから反発を受ける。
当然ながら「税金泥棒ではないか」といった主張が正当性を持つ。そのうち「不法投棄をしている」「都会で悪いことをして逃げてきた」といった身に覚えのない噂が立つ。その夫婦は心身ともに疲れ果てて過疎地域を去った。
この他にも、住宅ローンを組んで家屋を購入した移住者がいる。その移住者から、「住民が自宅周辺をうろついて室内を覗き込み、毎日のように噂話をしているのが精神的に耐えられない」といった相談を受けたことがある。
住宅ローンは居住条件が付くので家屋の賃貸化が難しい。移住の際にはフットワークを軽くしておくことが肝心だ。
厄介事と息苦しさ
過疎地域には相互扶助の精神が根づいている。相互扶助の代表的な組織として自治会がある。地域によっては町内会・集落会・村落会・区会とも呼ぶ。主な活動内容は、道路清掃・草刈り・柵の修繕・冠婚葬祭・地域行事・ゴミの管理・防災管理・高齢者の見守り・児童の見守り・会費の集金・広報誌の配布等がある。
また、教育委員会では自然体験学習会や、モノづくり教室等を定期的に開催している。
その一方で、厄介事や息苦しさを生み出す要因にもなる。
まず、相互扶助は他者を監視する。たとえば、「あの人があれをしている」「この人がこれをした」と裏でコソコソと言い合う。「火のない所に煙は立たぬ」と言うが、過疎地域では火のない所に煙が立つ。
やってもいないことを「やっている」と言われることがよくある。
次に、相互扶助は関係性があいまいだ。仕切りたがりが偉そうにして場の雰囲気を悪くすることもあるし、場を取りまとめる者がいなくて困ることもある。
たとえば、草刈りを終えたあと、高齢者が「次も手伝うよ」と住民に伝えた。その住民は「来ても来なくてもよいよ」と返答した。まるで役に立っていないかのような返答に高齢者は激怒した。
「雨降って地固まる」と言うが、そう都合よく揉め事は収まらない。ぬかるんだ状態で放置するしかない。
移住者は転居の選択肢を持っているが、地元の住民はその選択肢を持っていない。住み慣れた地域で暮らす手段として、厄介事や息苦しさを受け入れている。誰しもが何かしらのわだかまりを持ちながら暮らしている。
それでも、地域内の揉め事は「顔を合わさない」という逃げ道がある。その逃げ道がないのが職場だ。職場での揉め事は相手を退職に追い込むまで続く。
よくあるのが、根拠のない指導や注意を繰り返して揉めるパターンだ。そのような職場のギスギスした状態は一見してわからない。どちらかの退職が決まって「またそうなったか」となる。過疎地域では定期的に似たような揉め事が起こる。
住民はこれまでの経験から揉め事が起こり易いことを知っている。そうならないよう普段から穏やかな言葉を選び、ゆるやかな口調で話すよう心掛けている。
たとえば、日本各地の方言の多くは語尾を装飾する。だに、だら、ずら、けん、だがや、け、にゃ、みゃあ、ちゃ、等だ。言葉尻を柔らかくすることで敵意がないことを相手に伝える。
揉め事が多い地域で暮らすための知恵と工夫である。揉めるのが嫌とかではなくて、揉めるものだと考えておくことが大切だ。
写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock
田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ 過疎地域から考える日本の未来
花房尚作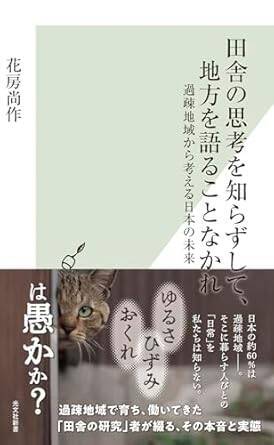






























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


