
少子高齢化が進む日本において、定年後も働き続ける人が増えている。定年後の人たちは、どのように働けば幸せを感じられるのだろうか?
定年後の幸せな働き方や時間の使い方、人間関係の再構築、そして老後の選択について『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』より一部抜粋・再構成してお届けする。
定年後の人たちの幸せな働き方とは
仕事に関しても、定年後は、時間の感覚が変わる。仕事に費やす時間については、いかに短時間で目的を達成するか――これが重要になる。一定の時間で、売り上げや利益などの数字を、どれだけ最大化できるか――それが勝負となる。
日本の企業では、やはり現在でも、長時間デスクに座っている人物が評価される傾向がある。しかし、政府が進めている「働き方改革」とも重なるが、定められた時間内で高水準の仕事をこなす「労働生産性」こそが重要なのだ。そして、この労働生産性を上げるためには、最大限に無駄を省くことがポイントとなる。
これを得意とするのが、定年後の人たちだろう。なにせ40年にも及ぶビジネスパーソンとしての経験がある。定年後の人たちは、ビジネスパーソン時代に何らかの組織やチームを率いてきた経験もある。当然、時間の使い方を考えた組織マネジメントもできるはずだ。
そして定年後の人たちは、現在は、役職を求めているわけではない。社会貢献も視野に入れて働くことができる。
かつて若いころは、時間をかけても、とにかくがむしゃらに働くことが結果につながると考えがちだった。
すなわち、余計なところにエネルギーを使わない、と言ってもいいだろう。こうしたことを実践しながら、若者やスタッフに「仕事術」を伝授していくのが、定年後の人たちの役目である。
2024年発表の総務省の統計では、65歳以上の労働者の75%以上が非正規で働いている。ポジティブに考えると、少子化で人手不足の日本には様々な仕事があり、隙間時間を使っておカネを稼ぐことができる、ということだ。
つまり若者よりも安定した生活基盤のある定年後の人たちは、自分の好きな時間に好きな仕事をチョイスすることができる。そしてそれが、人材育成や地域経済に貢献することになる。なかなか幸せな時間ではないだろうか。
プライベートな時間は優先的に確保
時間の使い方がうまい人……私が知っている人物のなかでは政治家に多かったように思う。実際、一流の政治家は、誰もが時間管理の達人だ。
総理大臣を務められた安倍晋三氏や森喜朗氏、そして、鈴木宗男氏もしかり。彼らは多くの人と会い、膨大な資料を短時間で読み、演説をこなし、かつ家族との時間も大切にしていた。
その時間術のコツは、前もってスケジュール帳にプライベートな予定を書き込んでおくこと。そのうえで仕事のスケジュールを組む。そうしないと仕事に忙殺され、いつまで経っても家族との時間を確保することができない。
たとえば夏休みの家族旅行……何ヵ月も前に宿や飛行機を手配してしまい、「確定」とする。どうしても休まなければならないように縛ってしまうのだ。
あたかも給料から天引きされる財形貯蓄のように、時間も先に確保しておく。そうすると家族との時間が生まれ、実はそれが、仕事へのエネルギーとなって返ってくる。
こうした時間の使い方は、定年後の人たちのほうが採用しやすいだろう。プライベートを優先して、余裕のある時間で仕事をする。仕事のなかで若者たちを指導し、社会貢献をする。なんと素晴らしい毎日だろう。
「選択と集中」で人間関係を再構築
そんな定年後の人たちの、仕事における人間関係についてはどうか?
人脈は広ければ広いに越したことはない──それはビジネスパーソンとして現役だったときの「法則」。しかし定年後に、この法則は当てはまらない。
定年後は、それまでに広げた人脈の「選択と集中」がテーマになる。人脈をある程度まで絞り込み、「これは」という人とだけ関係を深めていく。それには、深く付き合っていきたい人の基準を自分のなかで明確にしておく必要がある。
私の場合、40代にして、いわゆる「鈴木宗男事件」に連座して拘置所に入ったことがきっかけで、人間関係が大きく変わった。それまで親しかった人たちのほとんどが離れていったが、もちろん残った人もいた。
これによって、図らずも、人脈が絞り込まれることになった。結果的に、深く付き合っていく人の選択ができたことにもなる。
さらに人間関係においては、外務省という組織を離れて作家になると、付き合いたくない人からは逃げることが可能になった。もちろん、極端に人を選ぶと仕事が来なくなるが、心の底から嫌いだ、という人からは逃げられる。結果、さらに人脈の「選択と集中」が実現できた。
定年前であれば、ビジネスパーソンは、嫌な人とも付き合っていかなければならなかった。
しかし、定年後の仕事では、まったく状況が違う。
定年後の人たちが携わる仕事では、組織人になったとしても、ストレスの限界だと感じるようなことがあれば、迷わず離脱すべきだろう。自分の隙間時間を社会に還元し、ちょっとした収入を得るのが目的の仕事なのだから、すぐに判断を下すべきなのだ。
日本に住む定年後の人たちは、メンタルと体が元気であれば、非常に選択肢の多い老後を送れる。ゆえに定年後の仕事に執着する必要もない。
「仕事が楽しみなら人生は楽園だ。仕事が義務ならば人生は地獄だ」
これは『どん底』を書いたロシアの作家、マクシム・ゴーリキーの言葉だ。特に定年後の仕事は、楽しくなかったら、すぐに辞めるべきだ。
定年後に農業を始めるのは無理
近年、「定年退職したら田舎で農業をしながら自給自足に近い生活を送りたい」、そう考える人が多くなった。移住ブームもある。
都会生活を捨てて田舎暮らしをするのも一つの選択だが、それをつつがなく実践できるのは、おそらく体が丈夫な50代までだろう。定年後の人たちには、断言しよう、無理だ。
まず、60代から田舎暮らしをするとしたら、自分の地元に行くか、あるいは既に知己がいる場所など、何かしらの土地勘や人間関係がないと厳しい。
というのも、都市の生活に慣れ親しんだ人にとって、地方には、思いのほか閉鎖的な雰囲気が感じられるからだ。その結果、住み始めてからのちにコミュニティから弾き出されたりしてしまうと、都会に逆戻りすることになりかねない。
農業についても、既に経験があるなら別だが、定年後にイチからスタートさせるには無理がある。少なくとも30代から準備していく必要があるだろう。
いずれにせよ、60代からの田舎暮らしに関しては慎重にすべき、それが私の確信である。
文/佐藤優
『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』 (Hanada新書)
佐藤優 (著)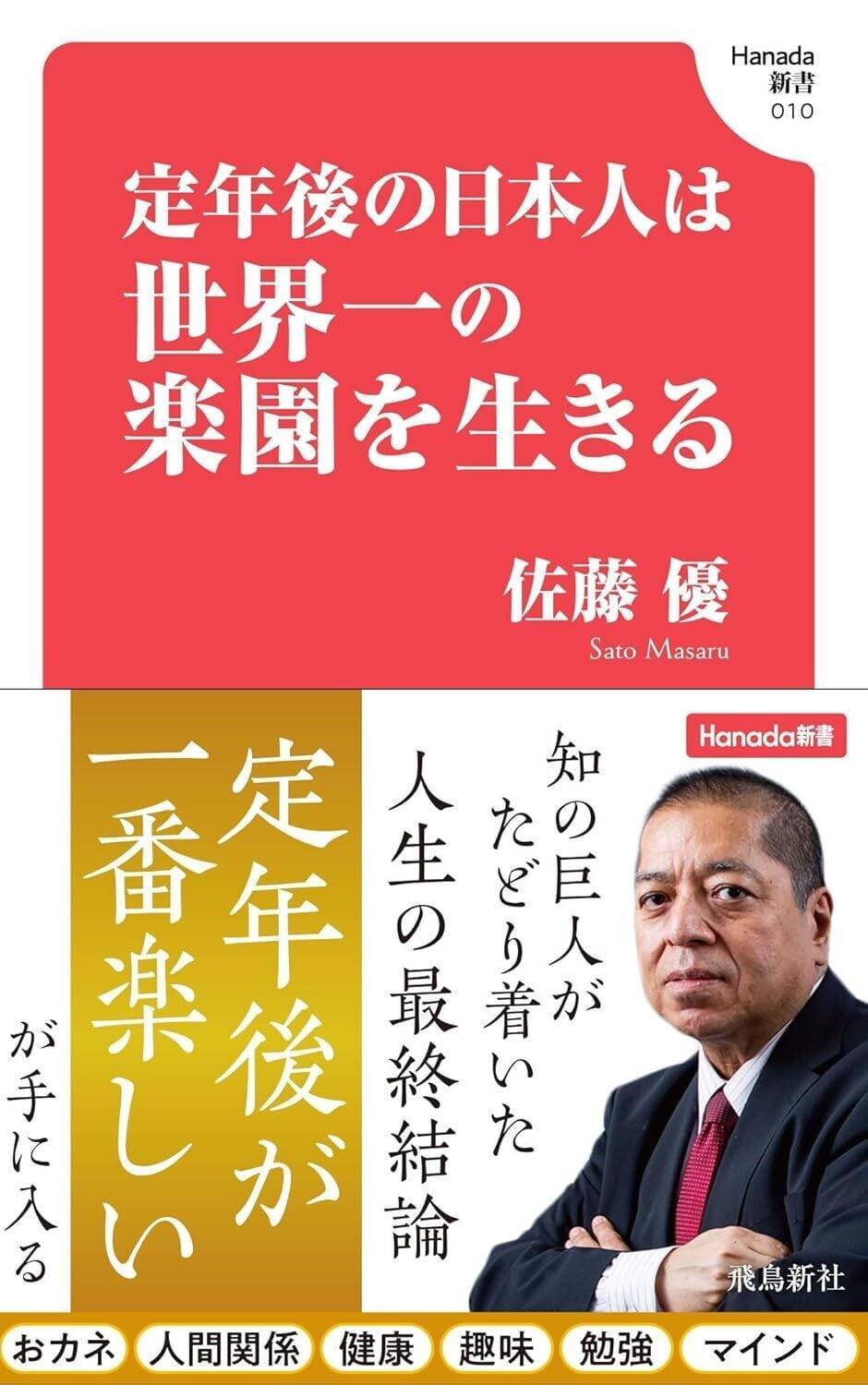
知の巨人が、たどり着いた人生の最終結論
佐藤優が「定年後に特化した知の技法」をはじめて完全伝授。
「定年後が人生で一番楽しい」が手に入る!
定年後に「遅すぎる」は一切ない!
人生は晩年こそが華である!
「還暦を迎えた人たちがどんな心構えを持ち現実的にどう対応すべきなのか?
人生の最終コーナーを回って自分のゴールを達成するためには、何が必要なのか?
嫌いな人たちにまで交友範囲を広げて、それを維持する必要はない。
残された人生の時間を、ストレスなく生きることに集中すべきなのだ。
本書は、私のこれまでの人生の集大成だと考えている――佐藤優」






























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


