
このところ連日のように被害が報じられ、クマに日本中が怯えている。この前代未聞ともいえる事態に、われわれができることとは––––。
クマの生態そのものが変化している可能性
野生動物と人間の間にあったはずの境界線が、静かに、しかし確実に溶解し始めている。
その兆候は、今や日本の至る所で見ることができる。北海道札幌市では、クマの出没が日常の風景になりつつある。10月、西区の宮丘公園で、帰宅途中の小学校低学年の女子児童が、わずか20メートルほどの距離でクマを目撃した。
公園や住宅街という、子供たちの生活空間そのものが、クマの徘徊ルートと重なっている。この事態を受け、付近の小中学校5校が臨時休校となった。もはや、クマの出没は遠い山の話ではなく、我々の生活を直接脅かす現実なのである。
さらに深刻なのは、クマの生態そのものが変化している可能性だ。岩手県北上市の温泉旅館「瀬美温泉」で起きた事件は、その不気味な兆候を感じさせる。
10月、露天風呂を清掃していた60歳の男性従業員が行方不明となり、後に旅館近くの山林で遺体となって発見された。遺体のそばには一頭のツキノワグマがおり、その場で駆除された。
驚くべきは、専門家による解剖の結果である。
「人間の肉の味」を覚えた個体
本来、ツキノワグマは植物食中心でおとなしい性質とされる。しかし、何らかの理由で「肉の味」、特に「人間の肉の味」を覚えた個体が現れ始めているのかもしれない。
これは、野生動物との関係における、根本的なルールの変更を意味する。従来の常識が通用しない、新たなフェーズに突入した可能性を示唆している。
舞台を世界自然遺産・知床に移せば、この問題がいかに根深く、人間側の行動に起因しているかがより鮮明になる。その雄大な自然は多くの観光客を魅了するが、その裏側でヒグマと人間の「適切な距離感」は崩壊しつつある。
8月、羅臼岳で男性がヒグマに襲われる事故が発生した。この事故は起こるべくして起きた悲劇だと言える。なぜなら、知床では以前から、一部の心ない観光客による無責任な行動が深刻な問題となっていたからである。
ヒグマに興味本位で近づき、写真を撮る。食べ物を与える
ヒグマに興味本位で近づき、写真を撮る。
それは、もはや餌付けではない。まわりまわってヒグマに死の宣告を下し、他の善良な人々に無差別の脅威をばらまく、許されざる行為だ。
このような愚か者たちにヒグマの脅威をわからせる必要がある。彼らの軽薄な好奇心と自己満足が、どれほど多くの命を危険に晒し、最終的にはヒグマ自身の命をも奪うことになるのか、その想像力の欠如は犯罪的ですらある。
この問題に対し、対策が試みられなかったわけではない。斜里町などは、2020年から3年間、知床五湖へ続く道で大規模なマイカー規制を実施した。代わりにガイドが同乗するシャトルバスを運行させるという、非常に理に適った取り組みであった。
初年度は多くの利用者を数え、成果を上げた。しかし、その試みは頓挫する。
短期的な経済性や利便性の前に、長期的な安全と自然保護という大義が屈したのである。このような場当たり的で継続性のない行政の姿勢は、批判されてしかるべきだ。
クマは一方的な悪者ではない
一方で、暗闇の中にも光はある。知床で活動する知床財団は、100年単位の視点で、ヒグマが豊かに暮らせる森作りという、地道で壮大な取り組みを続けている。
知床の森は、大正期からの開拓によって原生林が失われ、現在の森は針葉樹が多く、ヒグマのような大型哺乳類が暮らしやすい環境ではない。財団は植樹などを通して、かつての豊かな広葉樹林を取り戻そうとしている。
即効性は何もない。成果が見えるのは、今を生きる我々がこの世を去った後かもしれない。しかし、これこそが問題の根源に働きかける、誠実な態度と言えるだろう。その行動と理念は、ささやかではあるが、深く称賛されるべきである。
我々は、この複雑な現実をどう受け止めるべきだろうか。クマは一方的な悪者ではない。
白昼の街を恐怖のどん底に突き落としたロシアのヒグマ
森という巨大な食料庫を破壊され、住処を追われたクマが、人間の街という“コンビニエンスストア”に食料を求めてやってくるのは、ある意味で自然な摂理だ。
現在のクマ問題は、過去の我々の行動が生み出した、一種の因果応報なのである。人間が自然を意のままにできるという傲慢な考えは、ここで終わらせなければならない。
この野生動物との境界線が完全に破壊され、剥き出しの暴力として噴出した時、どのような惨劇が待っているのか。その答えを、我々はロシア極東の都市で見ることになる。
ロシア極東、カムチャツカ半島の都市ペトロパブロフスク・カムチャツキーで、2025年9月25日、一頭のヒグマが市街地に侵入し、住民を次々と襲うという戦慄の事件が起きた。このヒグマの行動は「暴走」と報じられるにふさわしい凶暴さで、白昼の街を恐怖のどん底に突き落とした。
最初の犠牲者は、市の中心部に近いスポーツフィールドで襲われた84歳の女性であった。幼稚園のすぐそばという、平和であるべき場所で起きた惨劇である。ヒグマは女性に襲いかかり、その頭皮を剥ぐという、およそ想像を絶する残虐な方法で致命傷を与えた。
女性は集中治療室へ緊急搬送されたが、地元保健省が「生命に適合しない傷」と発表した通り、その命を救うことはできなかった。野生動物が振るう暴力の、あまりに一方的で無慈悲な現実が、この老女の死によって突きつけられた。
「死んだぶり」でどうにかしたロシアの少年
ヒグマの暴走は止まらない。次に狙われたのは、オケアンスカヤ通りでスポーツセンターの近くにいた12歳の少年だ。ヒグマは少年に執拗に迫り、少年は必死に逃げた。
ヒグマは少年の背負っていたバックパックに襲いかかり、その衝撃で少年は転倒。こめかみと膝に傷を負った。しかし、この少年は極限の恐怖の中で驚くべき冷静さを見せる。
「死んだふり」をしたのである。痛みと恐怖に耐え、身じろぎもせず横たわる少年の上で、ヒグマは興味を失ったのか、やがてその場を立ち去った。少年は自らの知恵と勇気で九死に一生を得たが、その心身に刻まれた傷は計り知れない。
さらに、市内の駐車場では、一台の車に向かっていた男性がヒグマの標的となった。監視カメラの映像には、巨大なヒグマが猛然と男性に飛びかかる瞬間が記録されている。
男性はまさに紙一重で、近くにあったトヨタ・ハリアーの後部座席に飛び込み、ドアを閉めることに成功した。まさに「死を欺いた」奇跡的な脱出劇であった。
駆除という非情な決断を下す覚悟も必要
巨大な爪と牙で窓ガラスを割り、分厚い鉄板のボディをへこませ、無数の傷をつけた。車という文明の防壁がなければ、この男性もまた、ヒグマの暴力の前に無力であったことは疑いようがない。
一連の襲撃の後、この恐るべきヒグマは野生動物管理当局によって追跡され、射殺された。当局は、三件の襲撃すべてが同じ個体による犯行であると断定した。この事件は、人間社会の脆弱性と、野生動物が持つ根源的な力を、血腥い現実として示している。
「共存」という言葉は美しく響く。しかし、その言葉が持つ甘い響きに酔ってはいけない。現実の共存とは、血と痛みを伴う厳しい選択の連続である。それは、野生動物の世界と人間の世界との間に、明確で不可侵な境界線を再び引く作業を意味する。
そして、その境界線を越えてきた個体に対しては、時に駆除という非情な決断を下す覚悟も必要となる。
ロシアの事件で命を落とした老女、岩手で遺体となった従業員の死を無駄にしないために、我々日本人は思考を停止することなく、この困難な問題に向き合い続けなければならない。
野生動物への畏敬の念を取り戻し、長期的な視点で自然を再生させ、そして現実的な管理手法を確立する。その重い責任が、今、我々一人ひとりに問われている。
文/小倉健一




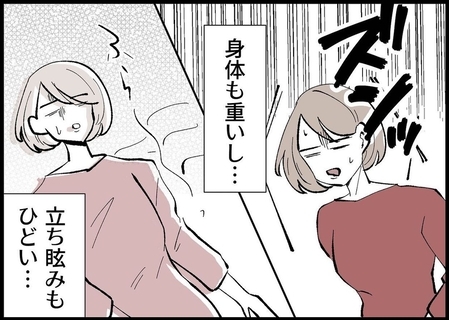




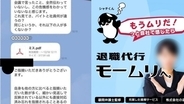














![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


