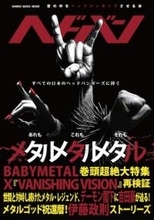「てつだうよ なんどもどんなようだって(手伝うよ 何度もどんな用だって)」
子どもの頃、響きの楽しさから無意識に呟き、母に「あ、そう。じゃ、タマネギ切っといて」などと用事を言いつけられてしまった経験が多々ある。
前から読んでも、後ろから読んでも同じになる「回文」。遠く鎌倉時代の歌人の作などもあるそうだが、私の場合は、幼少時に繰り返し読んだ、ある絵本との出合いがあまりに鮮烈だった。
その言葉の響き・不思議な世界が忘れられず、いまだに「しなもんぱんもれもんぱんもなし」とか「かるいきびんなこねこなんびきいるか(軽い機敏な仔猫何匹いるか)」とか、思わず呟いてしまうことがあるほど。
だが、遠い記憶で、絵本の正確なタイトルを忘れてしまっていたのだが、調べてみると、これはコピーライター土屋耕一さんの回文絵本『つつみがみつつ』(福音館書店・1975年刊行)のよう。
2003年に特製版が出たものの、現在は絶版のこの絵本。父母と息子の3人が家を「るすにする」ところから話は始まり、商店街で「ようかんかうよ」「ぞうかもかうぞ」などと買い物するが、雨が降ってきてしまい、「さがすやすがさ」→「とぼとぼと」歩き、新年のご挨拶に向かうストーリー仕立てになっている。
回文1つ1つの響きが楽しく、たざわしげるさんの絵が言いようのないおかしさで、大好きな1冊だった。
さらに、最近、ネットの古本屋で入手したのが、『土屋耕一回文集 軽い機敏な仔猫何匹いるか』(角川文庫)である。
コピーライターにして多趣味の粋人・土屋耕一さんが「キスが好き」「ダンディは遺伝だ」といったごく短いものから、数行にも渡る長文まで、長年の成果を紹介し、「回文の作り方」も巻末で伝授している。
その巧みさももちろんだが、回文の面白さを痛感するのは、単に「前から読んでも後ろから読んでも同じ」だけではなく、言葉と言葉を紡いでいくことによって、思いがけない言葉の出合いがあること。
文を考えるとき・喋るときは、普通は上から下につなげていくけれど、「回文」という言葉の組み立てによって、普段は無縁の言葉同士がひっつき、化学変化を起こし、時代や場所なども越え、思いがけない世界や物語性までも広がるということ。
たとえば、私が大好きな例をいくつかと、ひと言感想を添えてみたい。
・「黄ばんだ普段ばき」……唐突に白日のもとに晒されてしまった、「日常の風景」
・「うかつにも恩人を喪に使う」……遅刻の言い訳などで、つい恩師を死んだことにしちゃった? うかつにもほどがある。
・責任をとり ありありと恩に着せ……イイ人ぶって、かえって嫌なヤツだ
・おかしいと 鈍い警部に問いし顔……警部はたいてい愚鈍。名探偵モノでよくある設定。
・堅い帯いたく 肉体美老いたか……自分では若いと思っていても、老いは着実に忍び寄る
・堕落妻(だらくつま)が居(い)て 家庭が真っ暗だ……なんか、すみません。
自分の語彙も増やし、発想も広げてくれそうな「回文」遊び、やってみませんか。
(田幸和歌子)