最近、雑誌だけでなく書籍のタイトルでも散見される「ある傾向」に気づかないだろうか。
それは、「なぜ、……は……か?」という表現である。
そう言われてみると、たしかに毎号といっていいほど、この表現が使われている。10月11日発売の11・3号の表紙に見られた特集タイトルも、「悪口を言う人はなぜ、悪口を言うか?」だった。お笑い芸人であれば、「悪口を言う人は悪口を言う人だからでしょう」と単純につっこむかもしれないが、どこか日本語として違和感を覚える。
それは、「悪口をいうか」ではなく「悪口をいうのか」ではないか、流行りかもしれないが、肯定文の疑問形ならまだしも、「か」で終わる日本語の疑問文にどうして重ねて“?”を使うのか、といった細かな点だけではない。全体的に、こなれた日本語でないという印象を受けるだけでなく、表層的な思考を感じさせる。
かくいう筆者も同誌にタイトルをつけたことがあるが、このような表現を使うと、上司や先輩から「言葉を大切にしろ」「もっと考えろ」とひどく叱られ、再考を強いられたものである。
とはいえ、言葉は時代とともに変わる生き物であり、現在の読者が敏感に反応すれば、売れてなんぼの商業誌としては、第三者からこのような小言をいわれる筋合いはない。その意味では、プレジデント編集部の方々には「失礼」と一言添え、個人的見解としてお許しいただきたい。
ただ、筆者が心配しないではいられないのが、「なぜ、……は……か?」という論法に疑問を感じなくなってしまった現代日本人の思考であり、それを普及させるマスコミの社会的責任である。
「検索社会」といわれるほど、検索サイトに言葉を入力すれば答えが出てくる時代。コインを入れれば望みの商品が出てくる自動販売機と同じ仕掛けである。なんでもかんでも「フレームワーク」でまとめたがる思考、すべての社会現象が1+1=2となると信じ、法則で片づけようとする傾向は、まさに「なぜ、……は……か?」という表現に凝縮されている。出版社経営の利益最大化という観点からは否定できない戦略ではあるが、本来、出版社はなんのためにあるのかという企業の最大目的を考えれば疑問が残る。
出版社だけでなく、物事を単純化するのではなく洞察することを旨としてきた大学でも、「なぜ、……は……か?」という思考が一部で見られる。
1990年代以降、新設を中心に「実学」を標榜する大学が増えたのとは逆に、近年は「教養を重視する」というところが増えてきた。
●ビジネスに関する教養も実学の範疇
一方では、「実学を見直せ」というオピニオンも聞かれる(『実学教育改革論』(橘木俊詔/日本経済新聞出版社/2014年)。筆者は東京高等商業学校(後に東京商科大学=現・一橋大学)に続き明治期に教養、理論を重視した実学の府として設立された神戸高等商業学校(後に神戸商業大学、神戸経済大学=現・神戸大学)に関係していることもあり、橘木氏同様、職業を重視した戦前の高等教育と現在のドイツにおける教育体制には共感している。だが、教養か実学かという二者択一の議論に賛成しているわけではない。どちらかに偏重するのではなく、教養と実学の両方が重要である。
筆者も大学生を実際に教え、さらには高校にも足を運び出前講義を行った際、日本の高等教育におけるビジネス教育があまりにもお粗末であることを痛感する。このままでは、経済大国日本であり続けることがますます難しくなってくるのではないかと心配される。
去る8月、岡山県下の高校の校長、教頭をはじめ教師が約150人集まる研修会で「高校生に『現実』のシャワーを浴びせよう―『ビジネス・リベラルアーツ』のすすめ」と題した講演を行った。このようなテーマで講演してくれとの依頼があるくらいだから、ビジネス教育に関する関心が高まっていることは明らかだ。とはいえ、高校だけでなく大学でも、実際にどのような教育を行っていいのか手探りのような状況である。
高校はもちろんのこと、大学でもまだ少ないのが実務経験者。だからして、経済界を中心に「企業で経験を積んだ人を教員に招けばいい」という声が出てくる。それは良いことである。かく言う筆者も企業で経験を積んだ。マスコミという環境に恵まれ、一般の人では会えないような著名な経営者たちと対話することができた。さらに、働きながら学位(修士、博士)を取得し、現在、大学で教鞭をとっている。
●「実学重視」の落とし穴
しかし、「企業で経験を積んだ人」が教壇に立てば、薄っぺらではない理想的なビジネス教育ができるのだろうか。「実学教育」の名のもと、今、一部の大学(院)では、街場のセミナーのようなカリキュラムを導入する風潮が見られる。例えば、近年増えている「観光」「サービス」を冠にした学部、学科を中心に「ホスピタリティ教育」を謳い、マナーやおもてなしの講座をカリキュラムに取り入れている大学が少なくない。基本的な行儀さえままならない大学生が多い昨今の事情を鑑みれば、いたしかたないことかもしれないが、こうした内容がすなわちホスピタリティ・マネジメントであると誤解されていることを懸念する。
社会人が集まるビジネス・スクール(経営大学院=MBAコース)でさえ、時流に沿った講義が人気を呼ぶと考え、「企業で経験を積んだ人」が自身の経験や自画自賛型方法論を教えているところがある。その中には、学位を持たない部長クラスのサラリーマン・ウーマンが、修士以上の学位取得を目指す学生を教えている大学院が存在する。さらに驚いたことに、修士どころか学士だけの教員が、修士以上の論文審査に加わっている場合もある。「入学する時点では、そうした事実を知らなかった。大学院の先生なのだから、全員が博士(経営学か経済学)を持っているものだと思い込んでいた」という大学院生の声を聞いたことがある。ともあれ、大学院生は複雑な心境だろう。皮肉にも、そのような大学院はまちがいなく「実学重視」を謳っている。
今どき、大学教授(准教授以下も含む)になるには、学位(博士)を取得していることが必須条件である。公募などでは、ほとんどの大学が「博士を有していること」と募集要項に記してある。もし記していないとすれば、学位を持たない人が幅を利かせているめずらしい大学である。そのような大学では、学術的実績がなくても「有名だから」「若者に影響力がある」「(よくわからない表現ながら)発信力がある」といった点が評価され、博士をとっても就職で苦労している研究者(ポスドク)を尻目に、「えっ、なぜ」と思われる人が専任教員として採用されている。
しかし、MBAのような専門職大学院という課程では、博士を持っていなくても、ある分野のプロフェッショナルであれば迎えられる。当該大学院の教員欄を見てみると、一流大学の学部を出て大企業や官庁、コンサルタント会社などに勤め、海外の有名大学院へ留学した人が必ずいることに気づく。意外と彼らの中には、修士(海外大学院MBA)だけで博士を持っていない人が少なくない。博士の学位はなくても、「実学」と思われる理屈をわかりやすく教えてくれるから、高学歴・エリート信仰、フレームワーク思考の社会人学生の間では評価が高い傾向にある。アカデミックな作法に従わないと許さない「学術原理主義」の教授よりは、社会人学生との親和性が高いといえよう。
大学院、大学(学部)の別を問わず、受講生を対象に行う講義アンケートでは、「おもしろい講義」は「良い評価」が得られるかもしれないが、大学として本来の奥深い教育が行えたかという点においては疑問が残る。結果的に、大切なものを失っていないだろうか。決しておもしろくない講義を行えばよいといっているわけではなく、何気なく使われている「楽しい」という形容詞を深く考えなくてはならない。これは、前出の「なぜ、……は……か?」に対する反証である。
現在の大学生、はたまたその両親までも、「楽しい」=「エンターテインメント」としてとらえている。しかし、日本語の「楽しい」とはそのようなものではなく、多様な経験や学びを重ねたからこそわかる「大人の味」である。マナーやフレームワークを教えただけでは、この深い味がわかるようになるとは考えられない。
●ビジネス・リベラルアーツ
そうならないためにも、大学が行う理想的な経営教育とは何かという問いに立ち戻り、再検討する必要がある。そこで、筆者はビジネスと連動した「ビジネス・リベラルアーツ」を提唱する。日本の大学は戦後、アメリカのリベラルアーツカレッジをモデルにして、「一般教養」教育を展開してきた。かつてこのような講義を受けたOB・OGは、「教養」と聞けばすなわち大教室で講義される浮世離れした机上の空論と思うかもしれない。
そうではなく、ビジネス・リベラルアーツは「食い扶持」をつくる、リーダーシップを発揮する、起業・経営を行う上で役立つ知的バックグラウンドである。これまでのビジネスと遊離したと思われる「一般教養」とは一線を画す。それらの中には、経営学の基礎理論、経営史、そして最近の経営情報だけでなく、ほとんどの企業が最も重視する能力として挙げているコミュニケーション能力、松下幸之助が社員に求める資質として尊重した愛嬌、そして大阪商人のビジネス・ツールとしても使われた笑い(ユーモア)など、実務家が長年にわたり構築してきた実践的叡智も含む。
今、経済学だけでなく経営学も統計分析を駆使した合理的なサイエンスへ向かう傾向が顕著だ。さらに「ビッグデータ・ブーム」が拍車をかけている。しかし、合理的であると考え実行したことが、結果的に合理的ではない。泥水を飲んだ経験がある企業家の中には「理論は役立たない」と断言する人がいるのも、この事実に起因する。たしかに、理論を知らなくても金儲けはできる。ただし、理論も教養であると定義すれば、この主張は「教養などなくても一生を過ごせる」というロジックに似ている。では、教養なき人生は充実しているだろうか。ヨーロッパに古くから存在する「教養市民」の価値観からすれば、教養なき一生は非常にさびしい人生である。いや、教養があるがゆえに、実利的にも成功している人も少なくない。
●大学で今求められる人材とは
一方、学術一筋の研究者にも長所と短所がある。長所は、いうまでもなく学術に詳しいこと。一方、短所は学術が最高であり、それ以外の世間(既成の価値)を認めようとしない点である。すべての研究者がこのタイプであるとはいえないが、マジョリティを形成している。もちろん「少数有力説」もある。例えば、元一橋大学学長で、その後共立女子大学学長も務められた阿部謹也氏が上梓した『学問と「世間」』(岩波新書)では、生活=「世間」を学問の対象とすることを説いたオーストリアの哲学者フッサールに拠りながら、国民から遊離した大学の学問の現状を批判的に考察し、現場主義による学問の再編成を提唱している。同書には、次のようなくだりがある。
「研究者たちは誰に向かって論文や著書を書いているのだろうか。狭義には学会であろうが、そのほかにそれぞれの著者の『世間』がある。一般的な文章は『世間』に向けて書かれるのである。その『世間』は著者を理解し、その文章が公刊されるたびになんらかの反応をする集団である。それは読者であると同時に仲間であり、著者はその『世間』と暗黙の内に了解しあい、自分の行動のすべてについて『世間』の反応を期待している」
社会科学系リサーチ・ユニバーシティの代表格である一橋大学で学長を務めた研究者が、学究生活を極めた晩年、このように著しているのだ。いわゆる、研究よりも教育を標榜するサービス・カレッジで、旧来型の「学者という世間」のみを基準に教員を採用、審査し続けていることは浮世離れしているといえよう。現在の大学で求められるのは、経営学の分野で例えれば、経営学の学位(博士)を有し、なおかつ、経営者、ビジネスパーソンを理解し違和感なく交流できる人材だろう。それも専門バカではなく、幅広くビジネス・リベラルアーツを語れる「学術的雑談力」を備えた人が望ましい。
大学を取り巻く環境が激変しており、「大学」と名乗る教育機関も、一律の基準で定義できなくなってきた。競争戦略の観点からも、いかに差別化していけるかが大学の価値を左右するようになる。ビジネス・リベラルアーツも差別化を促す有力な武器となる。
(文=長田貴仁/神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー、岡山商科大学教授)













![医療機器販売の(株)ホクシンメディカル[兵庫]が再度の資金ショート](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FTsr%252Fa8%252FTsr_1198527%252FTsr_1198527_1.jpg,zoom=184x184,quality=100,type=jpg)
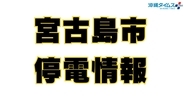











![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)


![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






