5日に『金曜ロードショー』(日本テレビ系/毎週金曜21時)にて放送される映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 ‐永遠と自動手記人形‐』(以下『外伝』)には、少女マンガの血が流れている。そう書いたら、おかしく思われるだろうか。
【写真】『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』場面写真(32点)
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は、兵器として育てられ、感情を喪失していた少女ヴァイオレット・エヴァーガーデンが、自動手記人形(ドール)と呼ばれる手紙の代筆業を通して、人間的な感情を獲得していく物語だ。
『外伝』は、エイミー・バートレットとテイラー・バートレット、引き離された2人の姉妹と彼女たちの心をつなぐヴァイオレットが描かれる。全寮制の学校に入れられ、自由を奪われたエイミーのもとに、主人公のヴァイオレットが教育係としてやってくることから始まる。一人称が「僕」であるエイミーは、最初はヴァイオレットに反発するも、自身の気持ちを受け止めてくれる彼女に想いを寄せていく。デビュタント(舞踏会)で立派にワルツを踊れるように指導するヴァイオレットは女学生たちに「騎士姫」と呼ばれ、半男装の出で立ちでエイミーの手を取りワルツを踊る。
全寮制の学校、騎士のような女性、一人称「僕」の女性、みすぼらしい生まれの少女が貴族へと貰い受けられる、花の名前を冠した登場人物…。本作には日本の少女マンガが描き続けてきたモチーフがたくさん登場する。
日本の少女マンガとは、何を描き続けてきたものだったか。それが今日も重要なものであるのはなぜか。そして、なぜ本作に少女マンガの要素が流れていることが大切なことなのだろうか。
それは、少女マンガが、女性たちの自由を願う気持ちに寄り添い続けたメディアだからだ。
■日本の少女マンガが描き続けてきたものとは
「少女マンガの神様」と呼ばれるマンガ家・萩尾望都は、イタリアで少女マンガの歴史について講演した際、手塚治虫の『リボンの騎士』から紹介を始めている。
『リボンの騎士』は、中世ヨーロッパの架空の国を舞台に、女の心と男の心を持って生まれたサファイア姫が、王位継承のために男として育てられるという物語だ。萩尾によれば、このマンガを読んだ当時の女の子たちは、「『もし自分も男の子だったら…』と思いながら、サファイアと一緒に冒険を楽しみました。この『もし男の子だったら』というテーマは、『リボンの騎士』以降、頻繁に日本の少女マンガの中で扱われます」(『私の少女マンガ講義』新潮文庫)と語っている。
講義は『リボンの騎士』にはじまり、『ベルサイユのばら』や『ポーの一族』を通り、『エースをねらえ!』や『キャンディ・キャンディ』、BLジャンルの台頭から『BANANA FISH』や『NANA』などを経由し、最後は、架空の江戸時代を舞台に男女逆転の世界を描いた『大奥』の紹介で終わる。
この講義で萩尾は、なぜ日本の少女マンガが「もし男の子だったら」というテーマを描き続けてきたのかについて明確に解答している。萩尾は、日本の少女マンガは時代ごとに「少女たちが夢見た美しいものや暮らし、生きかた、憧れを描いてきた」(『私の少女マンガ講義』新潮文庫)ものだと語る。少女マンガにおけるジェンダーの逆転や攪乱(かくらん)する物語は、女性ゆえの不自由さから解放されて、自由になりたいという女性たちの夢を反映しているのだ。
■不自由な「牢獄(学校)」で展開される束の間の自由
では、『外伝』はどのような点で少女マンガ的だと言えるだろうか。
本作は2つの物語で構成されている。前半はヴァイオレットとエイミーの物語で、後半はエイミーの妹テイラーがヴァイオレットを訪ねてくることから始まる。とりわけ、少女マンガ的なのは前半だ。
舞台は全寮制の女学校。
エイミーも、貴族の振る舞いを身に付けさせ、しかる場所に嫁がせるために不本意に入学させられた。それゆえ、学校は閉じられた牢獄のイメージで描かれる。
全寮制の学校は、少女マンガでは定番の舞台の1つだ。閉じられた箱庭の中で、不自由を強いられながら、友情や恋心が支えになる。少女マンガはそんなドラマを数多く紡ぎあげてきた。
この牢獄の学校において、ヴァイオレットはエイミーに、束の間の夢を見せる存在だ。依頼に応じてどこでも駆けつける自動手記人形であるヴァイオレットは様々な場所を移動できる。その自由がエイミーにはない。
エイミーの一人称が「僕」であるのも印象的だ。これは男のように自由に生きたいという少女マンガ的な願いにも通じるが、本作ではそれを逆手にとって、複雑な環境に囚われたエイミーの描写に利用する。
原作小説では、エイミーの出身地は貧しい娼婦街となっている。エイミーは、髪も短く少年のように振る舞っていたが、原作者の暁佳奈はその理由を「女が趣味でもなく男装をしているのならば理由はほぼ貞操を守るために限られるだろう」と書いている(KAエスマ文庫『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝』P93)。
彼女の一人称が「僕」なのも、おそらくその出自が関係しているのだろう。男の方が自由だからというより、女ではまともに生きられない環境だったから男装をしていたのだ。
そんなエイミーは、女学校で淑女の教育を受ける中で、「僕」ではなく「わたくし」という一人称を使わねばならなくなる。女として生きるのが困難な環境を生き抜くために身に付けた「僕」の一人称を、今度は女性の役割を押し付けられた挙句、捨てねばならない。
エイミーはある日突然、父と名乗る貴族に引き取られ、ほとんど選択の余地なく貴族の娘となることを強いられた。
だから、彼女に自由を見せられるのは異性ではなく、同性のヴァイオレットなのだ。「騎士姫」と呼ばれるヴァイオレットこそがエイミーに自由を見せる「王子様」として振る舞える。
デビュタントでヴァイオレットが着る衣装はそのことを強調する。パンツルックの男性用タキシードのような意匠が混じった服を身にまとい、エイミーをやさしくリードして華麗なワルツを踊るヴァイオレットは、『ベルサイユのばら』のオスカルを想起させる。
デビュタントが終わればヴァイオレットは学校を去り、束の間の夢として、前半の物語は幕を閉じる。学校の外門が、まるで牢屋の鉄格子のようにエイミーとヴァイオレットを分断している。だが、彼女がヴァイオレットに託した手紙だけは、その牢獄の外に出て、最愛の妹に届くのだ。
■新時代の希望を描く後半
『外伝』の後半は、一転して、解放的な雰囲気が漂う。
後半は、エイミーの妹テイラーとヴァイオレットの物語だ。自由のない生活を強いられるエイミーとは対照的に、テイラーは活発だ。
エイミーは職業を選ぶ自由はなく、どこにも行けない。
女性の不自由さを、少女マンガ的なモチーフを使い描いた前半とは対照的に、後半は新時代の希望が描かれる。
テーマは「仕事」だ。ここではテイラーの夢である郵便配達という仕事にスポットが当てられる。
少女マンガは歴史を重ね、派生ジャンルとしてより高い年齢層をターゲットにしたジャンルが生まれた。女性の社会進出の増加に合わせてマンガも同様にその描く範囲を広げていき、働く女性たちの気持ちに寄り添う作品も数多く生まれている。
後半には、ヴァイオレットの同期のドール、ルクリア・モールバラが登場する。彼女は結婚を控えていて、結婚後も仕事を続けることが明かされる。エイミーとテイラーの本筋のストーリーには直接かかわらないこのエピソードは、結婚だけが女のゴールではない時代がやってきたことを示している。
テイラーが自由を得たのは、エイミーが身を挺して残酷な運命を受け入れたからだ。まだ全ての女性に自由が訪れたわけではないが、昔よりも自由になっているとすれば、それはエイミーのように身を挺して戦ってくれた人がいたからだ。新時代に希望を託した先人の思いと、それを忘れないようにする後の世代。
「手紙」というのは伝達手段だ。アニメや映画、そして少女マンガも「媒介=メディア」だとすれば、何かと何かをつなぎ、伝達するものである。この映画は、前半と後半のエピソードによって、これまでの女性たちの苦しみと、これからの時代に託す希望をつないでいるのだ。
そして、その自由への願いは、日本の少女マンガが何十年もの間、ずっと寄り添い続けてきたものなのだ。(文:杉本穂高)
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-』は11月5日、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送。
























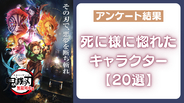







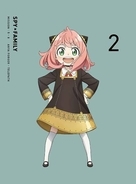

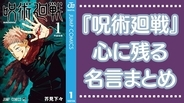


![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








