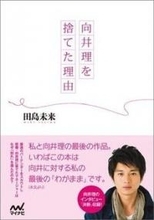伊藤昌哉『自民党戦国史』上・下(ちくま文庫)
元首相・大平正芳の側近という立場から、1970年代の自民党内の熾烈な権力闘争を描いたノンフィクション。私が読んだ朝日文庫版では上・中・下巻あった長編ながら、面白くて一気に読んでしまった。とにかく登場する政治家がみんなキャラが立っているのだ。大平とは性格的にはまるで正反対だったのに盟友関係にあった田中角栄と、大平・田中とは激しい対立を続けた福田赳夫と三木武夫という、いわゆる「三角大福」の4人が駆け引きを繰り返しながら、順番に政権を担当していたそんな時代。いずれも志半ばで政権を退かなければならなかったこともあり、最後に首相となった大平の在任中には、党分裂の危機にまで陥る。結果的にこの危機は大平自身の死をもって回避されるのだが……。
著者である伊藤は、大平が派閥の領袖から首相となり、在任中に亡くなるまで、ことあるごとに私的な立場から助言を与えてきた。だからといってイエスマンだったわけではない。たとえば、三木内閣の大蔵大臣だった大平が、ロッキード事件のさなか伊藤との会話中にしたある発言に対し、《あなたがそれをいえば、一発で政治生命を失ってしまいますよ》と忠告している。こうした優秀な側近がいたからこそ、大平は首相にまでなれたということもできるだろう。
ちなみに大平も伊藤も、元はといえば首相在任中の池田勇人のブレーンである。池田が推し進めた「所得倍増計画」もまた、彼らや大蔵官僚だった下村治といった優秀なブレーンのおかげで生まれ、実現できたものだった。
ジョン・ネイスン『ソニー ドリーム・キッズの伝説』(山崎淳・訳、文春文庫)
アメリカ人の日本研究者によるソニーの社史。徹底した取材にもとづき、同社の創業から発展の歩み、歴代の経営者たちの横顔を描き出す。私がとくに印象に残ったのは、3代目社長の大賀典雄がソニーに入るまでのくだりである。
大賀とソニーの関係は、彼がまだ東京藝大の声楽科の学生だった頃、ソニー(当時の社名は東京通信工業)のセールスマンから売り込まれたテープレコーダーを学校側に買うよう勧めるとともに、その技術的な欠陥をズバズバと指摘したことに始まる。その後、ソニーの創業者である井深大と盛田昭夫に気に入られ、同社と嘱託契約を結んだ大賀だが、当初の希望どおり声楽家の道を歩む。そんな彼を盛田昭夫は6年間かけてようやく口説き落として、正式な社員として迎え入れた。最後の口説き文句は《ソニーに入れば、いつの日か君はソニーの社長になれると思ってもらっていい》というものだったというから、すごい。
ちなみに本書が文庫化されたのは2002年のことだが、その翌年にはいわゆる「ソニー・ショック」があり、いまやソニーは往時ほどの勢いはなくなってしまっている。その根本の原因を探るためにも、これらの本にはたくさんのヒントが含まれているような気がするのだが。大賀典雄も今年80歳で亡くなったことだし、追悼の意味を込めても復刊をお願いしたい。
小林竜雄『向田邦子 最後の炎』(中公文庫)
テレビの「中の人」の話を読むのが好きだ。とりわけ、1960年代から80年代にかけての、テレビがお茶の間に君臨していた時代のテレビの人たちの本はけっこう熱心に読んできたつもりである。本書はそのなかでもとくに印象に残っている一冊。ぜひ同じ著書(自身も脚本家である)による『向田邦子 恋のすべて』とセットで読んでほしい。
この2冊は、脚本家で、のちに小説で直木賞も受賞した向田邦子(今月22日でちょうど没後30年を迎える)について、その後半生をたどり、作品に込められた意味などを読み解いたものだ。作品を分析するばかりでなく、向田の肉親や仕事をともにした人たちにも徹底的に取材して、その生と死に迫っておりじつにスリリングである。
それにしてもこういう本を読むたびつくづく思うのだが、テレビ、とくにドラマのつくり手の顔が昔ほど見えなくなっているような気がしてならない。おそらく、現場の裁量権がどんどん少なくなっているという事情もあるのだろう。ドラマでいえば、ディレクターや脚本家にキャストを選ぶ権利はほとんどないのではないか。向田は、じつは泉谷しげるが俳優デビューするきっかけをつくってもいるのだけれども、それは自分の作品でもないにもかかわらず、とある音楽番組で泉谷の姿を見て感じるものがあり知人であったスタッフに推薦したのだという。こんなことはおそらくいまではありえないのではないだろうか。
梅棹忠夫『裏がえしの自伝』(中公文庫)
今年3月から6月にかけて大阪の国立民俗学博物館で開かれた「ウメサオタダオ展」にあわせて文庫化されたもの。
《プレイというのはあそびである。車のハンドルにも「あそび」がある。つまり少々ハンドルをうごかしても、車輪のむきにはすぐにひびかないだけのゆとりがあるのである。いわば、目的に直結していないのがあそびである。目的合理性でつらぬいかれていないというのが、あそびの精髄なのである。
わたしは幼少のときから、自分の人生に目的をもつことをしなかった。(中略)どうせ人生には目的なんかないのである。
思えば、梅棹の仕事は一専門家の枠に収まらない、さまざまな分野を横断するものであった。仕事ではなくても関心を持って個人的に研究していたことも数多い。たとえば彼は若い頃から極地探検にあこがれ、仕事とはほぼ無関係に研鑽を積んだ結果、「アマチュア極地探検家」といえるほどにまでなったものの、実際に極地に足を踏み入れることはついにかなわかった。そんな梅棹が、自分のやりたかったこと、空想したことを代わりに実現してくれたと、高く評価するのが冒険家の植村直己である。
長尾三郎『マッキンリーに死す 植村直己の栄光と修羅』(講談社文庫)
というわけで、植村直己の評伝を一冊。本書には、植村が日本人初のエベレスト登頂の前夜、興奮のあまり思わずマスターベーションをしてしまったとか、犬ぞりによる北極圏単独行のさいには、人工衛星によって現在地を確認するというGPSの原型みたいな装置を使ったとか、面白い話が満載である。ただし私にはそういった冒険譚以上に、植村の日常生活に関する記述が印象に残った。行きつけの串カツ屋での公子夫人との出会いから結婚にいたるまでのくだりにしても(自身の著書にサインして贈呈するところなどカワイイ!)、北極単独行で多額の借金を抱え、その返済のためもともと人前で話すことが苦手にもかかわらず講演で全国を奔走したというくだりにしても、いちいち植村の不器用な性格が伝わってくるのだ。公子夫人の次の証言は、そうした性格ととともに、なぜ彼が集団による冒険ではなく「単独行」にこだわったのかという理由をも示している。
《植村はグズでノロマなところがあるんですね。
余談ながら、没後製作された映画『植村直己物語』は、公子夫人との関係を軸に植村の生涯を描いている。晩年、エベレストの冬季登頂や、犬ぞりによる南極大陸横断などに失敗するたびに、西田敏行演じる植村は情けない顔をして家に帰ってくるのだが、その姿にどうも既視感を抱いた。これって、『男はつらいよ』の寅さんと同じじゃ……? 寅さんが女にふられるたびに、妹の待つ柴又の団子屋に帰ってくるのに対し、植村は山や極地にふられるたびに、愛妻の待つ板橋の自宅に帰ってくる。この映画で公子夫人の役に、寅さんの妹・さくらを長年演じてきた倍賞千恵子が抜擢されたは当然だったといえるだろう。
なお、『マッキンリーに死す』もまた入手困難となっている。ついでにいえば、植村の著書も少し前なら文春文庫にほとんど入っていたのだが、いまでは一部をのぞいて品切れとなっているようだ。読みたい方は、古本屋や図書館で探してほしい。
ところで、今回の企画を受けていざ5冊選んでみたところ、梅棹忠夫の著書をのぞくとほとんどの本は、私が30歳になるかならないかという頃に読んだものだということに気がついた。
この企画はもともと、エキレビ!のライター陣が若い人に向けて夏にふさわしい文庫本を紹介しようというものだったはずだが、私の選書はむしろ、これまでそれなりに仕事を続けてきたものの現在曲がり角に立っている人にこそふさわしいものかもしれない。そんな人たちには、どうかこの暑い夏を乗り切ってほしい、と心よりお祈り申し上げるしだいである。おれも頑張る。(近藤正高)