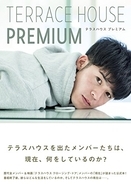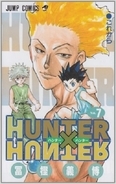寺山が先のエッセイを書いたのは高度成長期。この時代、ラーメンはハングリー精神の象徴であった。マンガ家の松本零士は上京当初の下宿生活の経験をもとに『男おいどん』という作品を発表、そこでは作者の分身たる主人公“おいどん”が近所の中華料理屋でラーメンライスを愛食するさまが描かれた。松本零士にとってラーメンは、貧乏な独身時代の記憶と分かちがたく結びついた食べ物だったのだ。
だが、いまラーメンはけっして安いものではなくなっている。速水健朗『ラーメンと愛国』によると、1990年代以降の不況下にあって外食産業では全体的に価格競争が進んだものの、ラーメン業界だけは例外だという。1990年に450円だったラーメン一杯の平均価格はそれ以降右肩上がりで上昇し、2007年には569円まで上がっている(総務省統計局「小売物価統計調査」)。価格だけではなく、かつて中国文化の装いに包まれていたラーメンのイメージ(ラーメン屋の意匠は雷紋や赤い暖簾が定番であり、『キン肉マン』でも中国代表の超人はラーメンマンだったし、インスタントラーメンのCMでも「中国四千年の味」というフレーズが流行った)は、いまや店員が作務衣風の服を着ていたりすっかり和風に変わった。戦後の日本でこれほどまでに社会的位置づけ、イメージが変化した料理も珍しいかもしれない。『ラーメンと愛国』はそんなラーメンの変化について、全編にわたって斬新な切り口で検証した好著だ。
本書では、屋台や店頭で供されるラーメンだけでなく、インスタントラーメンが誕生し普及する背景や経緯にもかなりのページが割かれている。そこでの主役は日清食品の創業者であり、1958年にチキンラーメンを世に送り出した安藤百福だ。安藤については、自宅の庭に建てた小屋でチキンラーメンを独自に開発したというエピソードもあいまって、無から有を生み出した発明家として注目されることが多い。しかし著者は、それとはまったく違った意味合いで安藤の再評価を試みている。
安藤百福は、チキンラーメンが発売されるや大ヒット商品となると、すぐに工場での生産を開始、それでも注文に対し生産が追いつかず、ついには全面的にオートメーション化をはかった大工場を建設して大量生産に乗り出す。安藤が取り入れたのは、20世紀初頭にアメリカの自動車メーカー・フォード社が生み出した大量生産システムの思想と技術だった。それは、日本のものづくりの源流にある職人の匠とはまるっきり正反対のものであった。
安藤はフォード式のシステムにより大量につくった商品を売りさばくため商社と組み全国の流通網を確立、さらには同時期に登場し各地に浸透していったスーパーマーケットを主要な足がかりとして販路の拡大を実現した。彼はまたチキンラーメンの宣伝のためまだ新興メディアであったテレビでCMを流している。余談ながらそれまで「支那そば」「中華そば」と呼ばれることの多かった麺料理が、「ラーメン」という名称に切り替わり一般に定着したのは、このチキンラーメンのCMの影響が大きかったという。
著者は上記のような安藤の仕事を振り返ったうえで、彼が《商品の“発明者”や新産業をゼロからつくった起業家》というよりもむしろ、《ラーメンを大量生産可能な“工業製品として発明し、安価な保存食品として世界に広めた》人物であったことを強調する。日本においてフォードの生んだものづくりの思想を実践し、もっとも成功を収めた人物こそ安藤であったというわけだ。
フォードの起こした生産技術の革命によりモノが量産化されることで、消費において人々が平等な社会がもたらされた。中流層が拡大、経済格差のきわめて少ない社会が形成された戦後の日本の高度成長も、こうしたフォードの思想の導入があってこそ実現したといっていいだろう。その一方で高度成長期の日本では、フォードの思想とは手段はまったく異なるものの同じく平等社会を理想としたマルクスの思想が若者たちの心をとらえた。共産革命をめざした彼らの政治運動は1960年代から70年代初めにかけて先鋭化をきわめる。1972年に長野県軽井沢の別荘へ連合赤軍のメンバーが立て籠もり、警察と銃撃戦を展開した事件(あさま山荘事件)は、そうした若者による一連の運動の終焉を象徴するものとなった。このとき、現場の警察官たちへ前年に日清食品から発売されたばかりだったカップヌードルが支給されたことはよく知られている。
本書はまた、連合赤軍の側も軽井沢に迷いこむ前、冬山での軍事キャンプ中にインスタントラーメンを食べていたという事実にも触れている。さらに《そこでの食生活に注目した栄養学者が、彼ら冬山のキャンプ生活でのインスタントラーメンを中心とした食事が、栄養バランスの偏りを生み、中でもカルシウム不足が精神的な不安定を引き起こし、連続リンチ殺人事件へと発展したと指摘していた》という話も紹介される。じつはこのくだりは、手前味噌で恐縮ながらわたしがかつてミニコミ誌に書いた原稿を参照したものだ。ネタ元として補足しておくと、この栄養学者というのは川島四郎で、その著書『まちがい栄養学』によると、メンバーたちはインスタントラーメンを麦と合わせて炊き、粥にして食べていたようである。
ところで、『ラーメンと愛国』というタイトルからわたしが真っ先に思い浮かべたのは、小熊英二の『〈民主〉と〈愛国〉』だ。同書はデモクラシーとナショナリズムという、現代のわたしたちからすれば相反するものと受け取られがちな概念が、戦後のある時期までは相反するどころか車の両輪のようなものとしてとらえられていたこと、さらに「民主」や「愛国」といった言葉の持つ意味も時代を追うごとに変質していったことを、戦後日本の思想家たちの膨大な言説を渉猟しながら検証したものだ。
上記のようなことを踏まえたうえで、ラーメンを民主主義のメタファーととらえながら本書を読んでみるというのも面白いかもしれない。たとえば、第1章では第二次大戦直後のアメリカの小麦戦略について書かれているが、前出の寺山修司や松本零士など小学生のときに敗戦を迎えた世代は、民主主義の洗礼をもろに受けると同時にアメリカから大量に輸入された小麦でつくったパンと脱脂粉乳の給食で育っている。この世代はやがて青年期にインスタントラーメンと遭遇することになるわけだが、安藤百福がこの商品化に着手した原点には、東洋独自の小麦食である麺食を盾としてアメリカのパン食推奨という食文化侵略に対抗しようという思惑があった。
あるいは第4章でとりあげられる田中角栄にとって民主主義とは、公共事業を通して中央から金を流すことで自党の支持層を拡大するという類いのものだった。田中がつくったシステムは、国内産業育成の原動力となる一方で、それぞれの土地に根ざした観光資源を軽視し日本全国どこへいっても画一的な風景が生まれることになった。本書ではその過程が、各地のご当地ラーメンの登場・進化の流れとパラレルであったことを指摘する。
さらに第5章では、近年、カルト的なファン(彼らは「ジロリアン」と呼ばれる)を増やしつつあるラーメンチェーン「ラーメン二郎」について、そこに通いつめるジロリアンたちが同チェーンに理念の体系みたいなものを見出し、そのなかから勝手にルールをつくり出してそれに則ったゲームを行なっていることに注目する。いわば彼らは「ラーメン二郎」というゲームを、ネットなどを介してコミュニケーションの材料としながら消費しているのだ。このようなコミュニケーションと結びついた消費活動は(AKB48の「選抜総選挙」などにも同様のことがいえそうだが)、民主主義の将来を示唆しているとも考えられるのではないか。
それにしても、こんなふうにラーメン=民主主義というふうに考えていくと、矢野顕子「ラーメンたべたい」の、“わたしはわたしのラーメンを責任をもって食べる”という意味の歌詞も何だか意味深長なものに思えてくる。最近では、「ラーメンポエム」ともいうべき手書きの広告コピーの掲示されたラーメン店も増えているようだが、やっぱりラーメンは他人にとやかく言われることなく、「ひとりでたべたい」ものである。