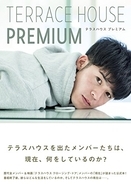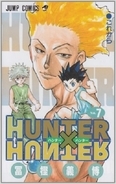《ぼくは、今「雑誌」を作ってるという意識はない。白い紙の束を全国に流通させることが、ぼくの仕事だ。黒いインクは、みんなに伝えたいことがある人、個人がやる仕事だ。ぼくの仕事は、一人→不特定多数につながる電話回線のとりつけだ》(「宝島」1980年5月号)
《一人→不特定多数につながる電話回線》という表現からは、やはりインターネットを連想してしまう。実際、「ポンプ」をいま読むと、誌面で自然発生的に読者たちが同じ話題で盛り上がる様子はネットの掲示板を彷彿とさせるし、巻末には前号以前に掲載された投稿に対する意見や感想がまとめられ、ブログにおけるトラックバックやツイッターのRTのような機能を果たしていた。
私は数年前、この「ポンプ」を、国会図書館で一日かかって創刊号から最終号まで閲覧したことがある。それは昔のサブカルチャー雑誌の投稿欄から、のちの著名人たちの無名時代の投稿を探し出すといういささか趣味の悪い企画のための作業で、その原稿は「ユリイカ」の雑誌特集(2005年8月号)に掲載された。
1979年から85年まで7年分のバックナンバーからは尾崎豊や直木賞作家の熊谷達也など意外な名前が見つかった。だが、「ポンプ」投稿者から生まれた最大のスターは何といっても、のちにマンガ家となる岡崎京子だろう。高校から短大時代にかけて同誌に投稿していた岡崎は当時より人気者で、読者のあいだでファンクラブが結成されたり、読者による「岡崎京子論」なんてものまで誌面に登場するほどだった。
ここ最近、映画「ヘルタースケルター」の公開と合わせて、原作者である岡崎に関する書籍があいついで刊行されている。ばるぼら著『岡崎京子の研究』もその一冊だ。さすが『教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書』をはじめ徹底した調査にもとづくデータベースづくりを得意とする著者だけあって、本書でもまた岡崎京子の仕事が微に入り細に入り網羅されている(それでもすべての仕事が網羅されているわけではないというのだが)。
このうち「岡崎京子の黎明期」と題する第1章では、前出の「ポンプ」に掲載された岡崎の文章やイラストなどが抜粋され、彼女のデビュー前夜の活動を浮き彫りにする。この章だけでもかなりの情報量なのだから、デビュー以降をとりあげた第2~5章にはさらにびっちりとデータが並ぶ。あとがきによれば、著者は4年前の夏に岡崎の完全な年譜をつくろうと思い立ち国会図書館に通いはじめたというから、たった一日こもって調べただけの私とはわけが違う。
本書には詳細な年譜・作品リストとあわせて、岡崎京子の作品あるいは彼女の活躍した時代背景、周辺のカルチャーなどについて架空の対談形式で解説されている。そこが本書のいまひとつの特色であり、おかげで初心者には入門編として、ファンにはより理解を深めるための手引きとして読むことができる。
本書全体を通して読んでみると、岡崎京子の作品も存在も独特のポジションにあったことがよくわかる。 そのデビューからして自販機本と呼ばれるエロ本だった。
1980年代末から1990年代前半にかけてはまさに彼女の全盛期であり、雑誌をはじめさまざまなメディアで岡崎の名前を目にした。このころにもなると岡崎はマンガ家という枠を超えて、時代のシンボルというかキーパーソンのような位置づけにあったように思う。本書に引用された雑誌の連載やコメントでの彼女の言葉は、いちいち示唆に富んでいて面白い。たとえば「朝日ジャーナル」での連載コラム「週刊オカザキジャーナル」の第23回(同6月21日号)では、《これからはもっと「おセンチ産業」が伸びるだろう、「泣かせてスッキリ」が重要な消費動向だと思う、が「一本抜く」射精産業みたいでヤだ》と未来をずばり予見していた。
個人的に高校に入学した直後(1992年)に休刊した「朝日ジャーナル」には間に合わなかったものの、「広告批評」での宗教人類学者・植島啓司とのFAXによる往復書簡や、パルコのフリーペーパー「GOMES」の巻頭コラム「虹の彼方に」はリアルタイムで愛読していた。これら連載は本書でもくわしくとりあげられていて、ああ、こんなこと書いていたっけと思い出すことも多々あった。このほか「月刊Asahi」「季刊都市」「思想の科学」などといったやや硬めの雑誌で連載を持っていたことも、マンガ家としてはちょっと異色といえる。
本書では岡崎京子のマンガを語るキーワードとして「編集」や「引用」という言葉が何度も登場する。たしかに岡崎の作品は、映画や音楽などほかのメディアから引用したさまざまなイメージの連なりでできていると言っても過言ではない。
岡崎京子は他ジャンルの作品からの影響を隠そうとしなかった。『東京ガールズブラボー』(1993年)に続々と登場する1980年代初頭の最先端カルチャーの固有名詞は、そのまま岡崎自身が10代のころに影響を受けたものだろう。彼女の愛読者たちも元ネタ探しを楽しみにしていたところがある。作品をより深く読むためにも、読者の関心は周辺カルチャーに広がった。そんな“風通しのよさ”が彼女の作品には一貫してあったように思う。たとえどれだけ陰鬱な作品であったとしても。
そんなふうにけっしてストレートに物語を展開しなかった岡崎だが、もし16年前にあの忌まわしい事故に遭わなければ、2000年代以降の「物語」回帰の時代――それこそ「泣かせてスッキリ」が重要な消費動向となった時代――にあってどんな作品を描いたのか、気になるところではある。
それにしても、どうして私はここまで岡崎京子と「時代」を執拗に結びつけてしまうのだろう。おそらく現在30代の私にとって、90年代前半の彼女の存在はそれほどまでに鮮烈だったのだ。とはいえ、あれから20年近くが経った。
蛇足ながら最後にもうひとつ。ネット上の各種アーカイブはここ数年で急速に増え、また利便性も高くなっている。私もそうだし、本書もまたその恩恵に浴していることは間違いない。しかし誰でも容易にアーカイブにアクセスできるからこそ、厖大なデータのなかから何を選び出し、何を読み取るかといったことにセンスがますます必要となってくるのではないか。本書からはそうしたセンスが強く感じられた。はばかりながら、本書を出すためばるぼら氏がかけた労力に対し、それに見合うだけの対価が支払われることを、同業者として願わずにはいられない。(近藤正高)