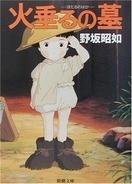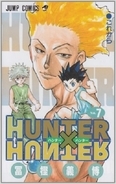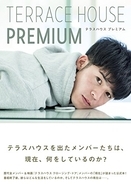ところが、その多くが失敗してしまった。
どうして日本では「成果主義」はうまくいかなかったのだろう?
『仕事と家族』の第3章を読んでいると、その一因がはっきりと示されていた。
おおづかみに紹介しよう。

日本の働き方と欧米の働き方
日本では就職する時点で「どのような職務につくのか」が決まっていないことが多い。
別の部署、別の職務に異動になったりする。
柔軟な配置転換が可能な「メンバーシップ型」の働き方だ。
日本の企業が「コミュニケーション力」を求める理由もここにある、と本書は指摘する。
職務がころころ変わるので職務能力ではなく、その場その場に応じた柔軟な対応が求められるのだ。
“職務内容の無限定性のために、チーム単位での仕事においては個人の責任の範囲が曖昧になり、長時間勤務を常態化させてしまう”。
このような日本的な働き方に対して、欧米は「ジョブ型」の働き方だ。
職務に対して賃金が決まる。
だから、欧米では、別の会社に転職しても職務が同じであればほぼ同一の賃金になる。
そして、欧米で成果主義が適応されるのは、管理職や専門職だ。
欧米型の働き方であれば、評価軸がクリアにできる。
なぜ「成果主義」は上手く機能しないのか?
日本ではどうか。
なにしろ会社内で、さまざまな職務に異動させられてしまうのだ。
職務給にするのは困難だ。
日本の能力主義は、職務ではなく“その人の潜在能力を評価する”ことになる。
だが「潜在能力」の評価が簡単にできるわけがない。
そうなると、実際に運用するときには年功制になってしまう。
年をとれば潜在能力がアップするという年功序列の考え方だ。
そのような働き方のなかで仕組みだけ成果主義にしても上手くいくはずがない。
ある意味で家族のように支え合う仕組みなのだから。
『仕事と家族』の第3章後半では、このような日本的な働き方と「男女雇用機会均等法」が生み出した「総合職は男性、一般職は女性」というねじれを考察している。
『仕事と家族』
『仕事と家族』は、全6章。
第1章 日本は今どこにいるか?
第2章 なぜ出生率は低下したのか?
第3章 女性の社会進出と「日本的な働き方」
第4章 お手本になる国はあるのか?
第5章 家族と格差のやっかいな関係
終章 社会的分断を超えて
「昔の女性に比べて今の女性のほうが仕事に身を入れているのだ」「女性が働くことが出生率の低下をもたらしている」「女性労働参加率と出生率が高いスウェーデンと同じようにすればいいのだ」「身につけたスキルを仕事で活かし続けたいと考える人が増えたから未婚化が進んだ」「日本人男性が欧米と比べて家事をしないのは労働時間が長いからやりたくでもできないのだ」といった主張が間違ってる、もしくは単純すぎることを、本書は次々と暴き出していく。
豊富なデータを使って、仕組みまで掘り下げて考察することによって、今後の「日本の仕事と家族」のあり方を考えるための土台となる一冊だ。
『仕事と家族』、ぜひ読んでほしい。
(米光一成)