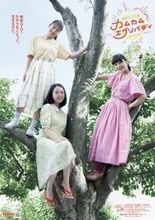雲田はるこ原作の漫画『昭和元禄落語心中』のほうでも動きがあり、最新刊の9巻が発売されたほか、それに続く10巻で物語が完結することが発表された。ファンにとってはいろいろ慌しい1週間だったのである。

ジャンボ鶴田の女装のようなもの
原作では第3巻の冒頭にあたる部分で、同期の相棒・有楽亭助六の企画で二つ目・前座だけが参加する鹿芝居を上演することになり、嫌々ながらも有楽亭菊比古(のちの八代目・八雲)も付き合わされる。しかし実際に舞台を踏んでみると、自分の一挙手一投足が観客の心を操っているという実感が湧きあがり、菊比古は初めて表現者としての快感を味わう。
そういう意味では重要な回だった。芸人の言葉に「キレイゴト」と「ヨゴレ」というものがあり、字義通りに芸の性質を指す。客を弄ったり、下がかったことを言ったりしないのがキレイゴトである。そのキレイゴトの菊比古が芸に開眼したのが芝居の舞台だった、というのが物語運びの妙味だ。
前回も書いたように鹿芝居は落語家の遊びとして人気があり、以前には頻繁に催された。ちょうど今、国立演芸場でも仲入り後に上演されているので関心がある方はどうぞ。
もっとも、あくまで余芸であるので菊比古のようなキレイゴトが拝めるかは保証の限りにあらず。鹿芝居について書かれたものも、素人役者ゆえのドタバタについて触れたものを多く見かける。
──私も昭和二十七年に、落語研究会のメンバーが神田立花で行なったのを見たことがある。演し物は『弁天小僧』。浜松屋店先の場の弁天小僧は故古今亭志ん生。なんだか海坊主か、ほうずきのお化けみたいで、あぐらをかいて、右の足先を左手で握って、グイと手前に引いたら、危く引っくり返りそうになったので、見ている方がびっくりした。
──稲瀬川勢揃いの場の方の弁天は故桂文楽(先代)。これは水もしたたるようないい若衆で、芝居もスムーズに進行していたが、赤星十三郎の柳家小さん(先代)が台詞を忘れて、赤い顔で、やたらに傘を上下して助けを求めていた。隣りは桂右女助(六代目三升家小勝。故人)の忠信利平だったと思うが、最初はちょっと耳許で台詞を教えていたが、直ぐに吹きだしてしまって、台詞は途絶え、赤星十三郎の傘の上下ばかりが一層激しくなったから、場内のあちらこちらで笑い声が起こり、賑やかな打ち出しになったのを覚えている。(山口)正二『聞書き五代目古今亭今輔』
知らざぁ言って聞かせやしょう
「寿限無」などと同様、NHKEテレの番組「にほんごであそぼ」で紹介されたことから、このフレーズもおなじみになった。菊比古の台詞はいいところで切れ場になっていたので、その後を書き出してみる。
知らざぁ言って聞かせやしょう。
河竹黙阿弥作、1862(文久2)年3月に江戸市村座で初演となった「青砥稿花彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)」のうち「浜松屋」である。女装の悪党・弁天小僧が南郷力丸(助六の演じた若党)を引き連れ騙りを仕掛ける場面で、この部分に白浪五人男の勢揃いだけを演じる場合は外題が「弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)」となる(上の引用にもある「弁天小僧」は通称)。劇中で頭巾の侍・玉島逸当として登場していたのが実は、弁天小僧たちの親玉・日本駄右衛門なのである。
落語の源流の1つは歌舞伎にあり
その「浜松屋」の場面で、玉島逸当や浜松屋の一同、それに弁天小僧と南郷力丸の面々が揃って観客のほうを向き、台詞を喋る場面があった。現実とは異なる芝居ゆえの演出で、本来ならば論争になっているのだから、一方向に視線が揃うわけがない。しかし舞台の上だから観客のほうを向くのが正しいのである。中央に居所を構えた主役を基本として上手や下手などに役者を振り分けるという構図自体に意味があり、観客はそれを脳内で変換しえ状況を再現するのである。他にも歌舞伎には所作やさまざまな約束事があり、それは落語にも移植されている。落語の演者が顔を左右に動かし、つまりカミシモを振って登場人物を描き分けるのは、舞台の空間感覚をそのまま高座へと凝縮した結果だ。
落語には芝居噺というジャンルもあり、歌舞伎の所作をなぞったような演出が行われる。落語立川流を脱退し今はフリーで活動している快楽亭ブラックは、公共電波では放送できないような内容の噺を十八番としていくつも持つ異能の落語家だが、大の歌舞伎ファンでもある(著書に『歌舞伎はこう見ろ!─椿説歌舞伎観劇談義』)。機会があればブラックの「七段目」をぜひ生でご覧いただきたい。
今回の噺
鹿芝居の場面が中心だったので、今回出てきた噺は一つだけ。夜更かしをして帰ってきた助六に菊比古が演じるように命じる「品川心中」だ。江戸では公認の遊廓は吉原だけだったが、四宿といい、東海道の品川、日光街道の千住、甲州街道の内藤新宿、中山道の板橋と、それぞれの街道の入口となる宿場が岡場所(半ば黙認された遊廓)として栄えた。そのうちの品川を舞台とする噺で、全盛期を過ぎて客足が衰えたために金の工面がつかなくなった女が、貸本屋の金蔵を相手に心中を仕掛けようとする。上下に分けて、上の部分だけが演じられることが多い噺である。
品川は東海道第一の宿場として風情を残すことに熱心な街だが、残念ながら当時の妓楼は建物がまったく現存していない。数々の見世の中でも、長州藩などの幕末の志士が出入りしていたことで有名になったのが土蔵相模である。それももちろん跡形もなく、現在は1階にファミリーマートの入ったビルになっている。「品川心中」の舞台となったのは白木屋という見世だが、このモデルに関しては諸説ある。落語家との散歩で落語の舞台を巡る楽しい本、長井好弘『噺家と歩く「江戸・東京」こだわり落語散歩ガイド』によれば、島崎楼説が有力だという。古今亭志ん輔と著者・長井の間のやりとりを引用したい。
「ところが師匠、この島崎楼が『品川心中』の舞台の白木屋ではないかという説もあるんです」
「えっ、なんでそうなるの?」
「欽ちゃんみたいだな。品川宿で、自家用の桟橋を持ってたのは、島崎楼だけだったみたいなんです」
なるほどね。
「東京かわら版」によれば、2月26日(金)、東京・新富町の銀座ブロッサム中央会館で開かれる「立川志らく独演会」において、品川を舞台にした噺2席「居残り左平次」とこの「品川心中」が演じられる予定とのこと。ことに「品川心中」は上下通しで聴ける機会である。もしまだ間に合うようなら、会場にお運びください。
(杉江松恋)
(おまけ)
私も新米落語プロデューサーというか、下足番として会を企画しています。よかったらこちらにも足をお運びください。

2/19(金)午後6時半(開演午後7時)「立川談慶独演会 談慶の意見だ」出演者:立川談慶、ゲスト:畠山健二(作家)

2/21(日)午前0時半(開演午前1時)「立川談四楼独演会 オールナイトで談四楼」出演者:立川談四楼、立川只四楼
2/23(火)午後2時半「立川さんちの喫茶★ゼンザ 立川流前座勉強会」出演者:立川志ら鈴、立川志ら門、立川らく葉、立川うおるたー、立川らくまん(予定)

2/24(水)午後6時半(開演午後7時)「台所鬼〆独演会 お腹一杯独演会」出演者:台所鬼〆