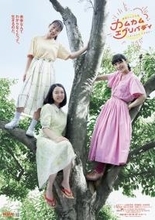スウェーデン・アカデミーが授賞を発表したのは、現地時間で10月13日午後1時(日本時間同日午後8時)。

ただし、13日夜のコンサートでもディランは、観客から大喝采で迎えられながらも、ノーベル賞については一切コメントすることなくすぐピアノ演奏に入ったという。さらにその後の報道では、発表から丸1日が経過した時点でもまだ、アカデミー側はディラン本人と直接連絡がとれていないとも伝えられる。おかげで「彼はノーベル賞を受け取りたくないのではないか」とまでささやかれ始めている。
これはあくまで憶測にすぎないが、ディランとしてみれば、ひょっとするとノーベル賞を受賞することで、平穏な生活を掻き乱されてはかなわないという思いがあるのかもしれない。1966年にバイク事故で重傷を負ったディランは、静養のためニューヨーク州のウッドストック近郊に新居を構えたものの、やがて不法侵入者があいつぎ、緊張しながらの生活を余儀なくされている。ちなみに、有名な1969年夏のウッドストック・フェスティバルは、実際にはウッドストックからかなり離れた農場で開かれたが、このときもディランは用心して、イギリスでのフェスティバル出演を口実にアメリカを離れた(中山康樹『ロックの歴史』講談社現代新書)。
ディランの影響から生まれた意味不明な歌詞
さて、ボブ・ディランは当然ながら日本のミュージシャンにも大きな影響を与えているわけだが、それは具体的にはどんなものなのか。せっかくなので、井上陽水を例に説明してみたい。
井上陽水は1973年、アルバム『氷の世界』をリリースした。アルバムレコードでは日本初となる100万枚の売り上げを達成した記念碑的な作品だ。
陽水は中学時代よりビートルズにあこがれ、ビートルズのようなかっこいい曲をつくろうと考え、そうしてきた。しかし、歌詞についてはどういうふうにすれば自分らしいものが書けるのか、まだその方法を完全につかんではいなかった。そこで陽水が参考にしたのがボブ・ディランだった。もちろんそれ以前から彼はディランを聴いてはいた。だがある日、シンガーソングライターの先輩である小室等の家に行ったとき、たまには真面目に聴いてみようと、歌詞カードを見ながら聴くことにしたのである。
このとき、陽水の心をとらえたのが、アルバム『Blonde on Blonde』(1966年)に収録された「Just Like a Woman(いかにも女らしく)」という曲だった。それを聴いて、陽水はほとんど一瞬のうちにすべてがわかったという。
原詩をそのまま書き写すとおそらく著作権的に差支えがあるだろうから、ここは片桐ユズルによる和訳を引用すると、それはこんな歌詞だった。
だれも苦しみを感じない
今夜こうして雨の中に立っていても
だれでもしっている
ベビーがあたらしい服をもらったことを
でもちかごろ そのリボンが
巻毛からおちてるじゃないの
いかにも女らしく取るじゃない、ほんとに
いかにも女らしく股をひろげるじゃないの、ほんとだよ
いかにも女らしく苦しむじゃないの
でも ちいさな女の子のようにもろいんだね
陽水はまず「だれも苦しみを感じない(Nobody feels any pain)」という、彼いわく《わけの分からないはいり方》にしびれたという。
そこで陽水が気づいたのは、「いかにも女らしく取るじゃない(She takes just like a woman)」にいたるまでの最初の6行は、何を言ってもいいんだということだった。
《とにかくそこまでの一行一行は、何かインパクトのある、Nobody feels any painとか何とかわけの分からないことをいっておけばよくて、むしろそこまでに意味のないことをいっておけばおくほど最後の四行が生きる。逆にいうと、あんまり最後の四行に関係のあることを前でいっちゃうと説明的になってつまらなくなっちゃう。それが分かって、そうか、こういうふうに書けばいいのかと思ったわけよ》
これにインスパイアされて陽水がつくったのが、アルバムの表題曲となる「氷の世界」だった。そこでは出だしから、窓の外にリンゴ売りなる謎の人物が現れたかと思えば、「誰かがふざけてリンゴ売りのまねをしている」とあっさり否定される。その後も意味不明な歌詞が続くものの、それも最後の「毎日、吹雪、吹雪 氷の世界」を生かすための前フリにすぎない。陽水に言わせれば《その言葉がありさえすれば、あとはもう窓の外でリンゴを売ろうがキュウリを売ろうが何でもいいんだと思ってたよ》。
何だか適当だが、それでいて陽水は、《詞の前半が適当であればあるほど、現代の寒々とした光景がよりいっそうあざやかに浮かび上がるのだという確信をもっていた》という。それも、ボブ・ディランの法則にしたがったものだった(ただし、陽水はこの時点で、ディランのいまひとつの特徴である、韻を踏んだ詩を完成させるまでにはいたらなかった)。
陽水は「氷の世界」を書き上げると、自信たっぷりに、当時彼を売り出すため尽力していたポリドール・レコードのディレクター多賀英典に見せた。
ノーベル賞発表前夜、陽水がディランをカバー
もともとディランは、日本ではその知名度ほどにはレコードは売れていなかったという。ラジオDJのピーター・バラカンはこれについて《歌詞の難しさや、きれいな歌い方を好む日本人にはいまひとつなじまない、あの歌い方そのものが主な原因でしょう》と書いている(『ラジオのこちら側で』岩波新書)。
ディランには、代表曲である「風に吹かれて(Blowin' in the Wind)」(1962年)や「ライク・ア・ローリング・ストーン(Like a Rolling Stone)」(1965年)などシンプルな歌詞で広く親しまれている曲がある一方で、前出の「Just Like a Woman」のように難解な歌も多い。『タランチュラ』という最初の著作(1966年)にしても、詩のような物語のような謎めいた、それでいて不思議な魅力のある48篇の散文をまとめたものだった。そこには、たとえばこんな文章が出てくる。
《エイブラハムここの明かりのなかへおいで……きみのボスはどうなのかね、言われたことをただやっているだけなんて言わないでくれ! きみの象形言語にぼくはつうじてはいないかもしれないけれどぼくは平和にやるのだ。(中略)ちょっとした情報と交換に、ぼくのファッツ・ドミノのレコードをきみにあげよう、hisとhersのタオルを何枚か、それにきみ専用のプライベート・セレクタリー……おいで》(ボブ・ディラン『タランチュラ』片岡義男訳、KADOKAWA)
ディランが日本のヒットチャートで健闘するようになったのは、1976年発表のアルバム。『欲望』あたりからのようだ。陽水はディランに学びつつ、彼に先んじて日本のマーケットで成功を収めたことになる。
そういえば、「氷の世界」には、「人を傷つけたくても、実際にはそれができないやさしさを胸に抱いている人は、いつかノーベル賞でももらうつもりで頑張っているのではないか」といった、これまた、わけのわかったようなわからない歌詞が出てきた。さしもの陽水も、まさかインスパイア元であるディランが、ノーベル賞に選ばれるとは夢にも思わなかったことだろう。
なお陽水は、ノーベル文学賞の発表前夜、渋谷Bunkamura オーチャードホールでコンサートを行なっている。このとき、ディランの思い出を語りながら、彼の「Knockin' on Heaven's Door(天国の扉)」のカバーも披露したという。これが翌日か翌々日なら、今回の授賞へのコメントもあったのだろうか。いや、食わせ者の陽水のことだから、案外まったく触れなかったかもしれないけれども。
(近藤正高)
参考→ノーベル文学賞受賞ボブ・ディランについて知りたいならばこの電書だ