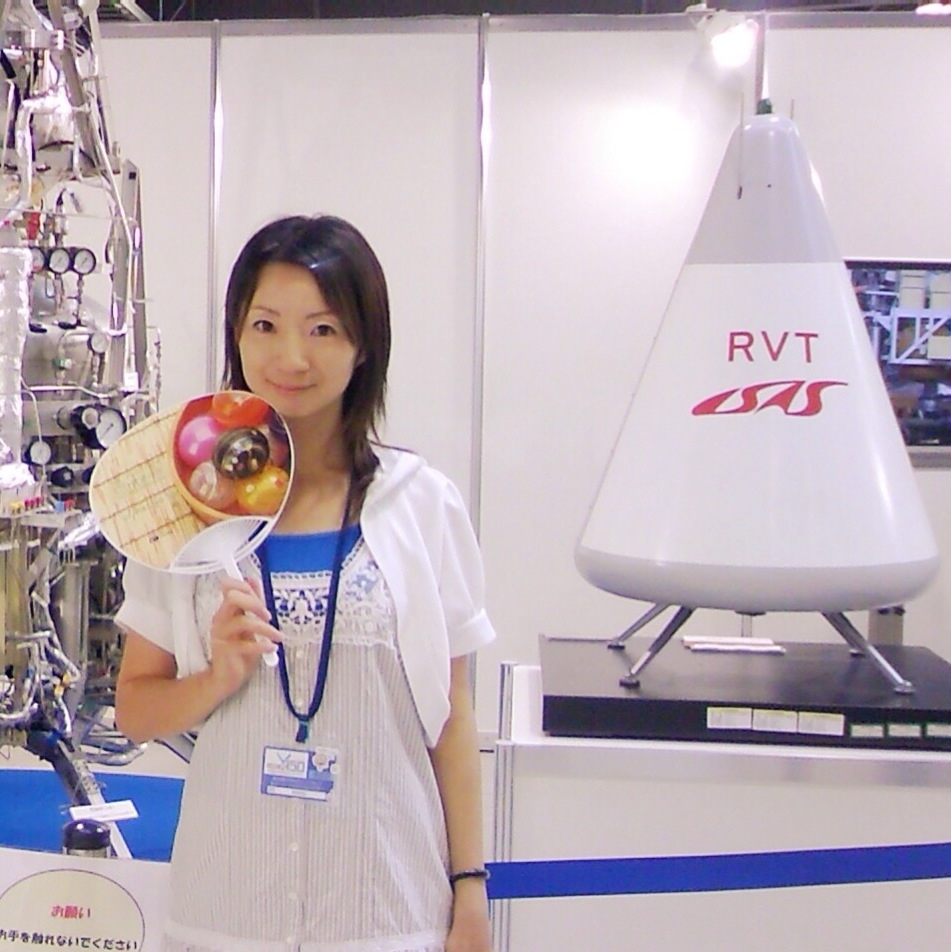店頭受取数は全国のファミリーマートで約2万件
ファミリーマートの店頭受取サービスは、店頭に設置されたFamiポートで「申込券(レシート)」を印刷してレジに持っていくと、店員さんから荷物が受け取れる。志水さんによると、全国のファミリーマートで店頭受け取りされる数は、1日当たり約2万件を上回るというから驚きだ。
全国にあるファミリーマートの中でも、郊外の駅前にある店舗はこのサービスの利用が多く、都心から1時間圏内の需要がもっとも高いという。朝注文して届いた商品を会社帰りに受け取るケースが多く、帰宅時間の20~23時がボリュームゾーン。朝7~8時の出勤時間に商品を受け取ったり、オフィス近くで昼休みに受け取る人も。

また使い方もさまざまだ。たとえば、家族に知られたくない趣味の商品やサプライズプレゼントなどは、店頭で受け取れば荷物を開けられてしまう心配がない。ネットショッピングで買ったものを、旅行や出張先のホテルの近くにあるファミリーマートで受け取る人もいるそうだ。
「このサービスのメリットは、お客様が誰かを特定せずに店頭で受け取れることです。我々はお客様のパーソナルデータを持っていません。そのため、不在がちな方や、宅配業者に自宅を知られたくない方にもお気軽にご利用いただけるサービスになっています」と志水さん。
そもそも店頭受取ってどんな仕組み?
注文した荷物がコンビニに配達されることはなんとなく理解出来るが、具体的にどのようなプロセスを経ているかはあまりイメージがつかない。志水さんによると、配送の仕組みは大きく2種類あるそうだ。
一つは配送業者が直接届ける形で、EC事業者の倉庫からファミリーマートの店頭までヤマト運輸や日本郵便が配送する方法。もう一つは自社の物流インフラを利用した形で、「お弁当などを運んでいる車両を使っています」と志水さんは語る。全国約53か所の拠点から日々200~300店舗に配送されているという。どちらの配送形態になるかはEC事業者との契約で異なり、どちらもデータのやり取りをして、EC事業者からユーザーに商品が店頭に到着したことを知らせる流れになっている。
ここで注目したいのは、自社物流を活用しているからこそできるサービスも展開していることだ。ファミリーマートの店舗から別の店舗へ荷物を送ることが出来る「はこBOON mini」は、到着まで通常の宅配より多少時間はかかるが、その分お得な料金を実現しているという。

ネットショッピングが普及し物流量が増えたこと、加えて再配達も多く発生していることから、昨今CO2排出量やドライバー不足が社会問題になっている。「問題を解決できるのは我々コンビニではないかと考えています」とは、2016年入社で同じくサービス担当の葛西さんの話。

自社のネットショッピングサイトで店頭受取サービスを2000年から開始し、2002年から他社サイトの取り扱いもスタートした。開始当初からはモデルが変わっているので一概に比較もできないが、近年取り扱う物流量も増加して1000倍になった。今後も伸び続ける見込みだという。
「様々な分野で急速にIT化が進んでいるが、物を届けるサービスは無くならない仕事だと思っています。このサービスも世の中から注目され、コンビニの役割もますます重要なものになってきています。利便性を高めてお客様にストレスなくご利用いただけるサービスをこれからも企画していきます」
(すがたもえ子)
【ファミマ・ドット・コム】