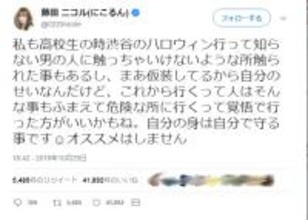一方で、同社が2006年に生産を終了した旧型のAIBOを今もかわいがり、不具合が起きれば修理を望むというユーザーも少なくありません。

「どうしても直して使い続けたい」というお客様のために
――A・FANの成り立ちを教えてください。
乗松:私はAIBOやウォークマンを作った会社の技術者として、1983年から約15年間、アジアの国々に駐在した後、1999年に日本に帰ってきました。ですがそこで目の当たりにしたのは、この国からものづくりが急速に失われていく様子でした。企業が人件費の削減を理由に、生産拠点をどんどん海外に移すようになっていたからです。
また私自身が53歳に大病を患い、心臓の手術をしたこともあって、「自分ができること、自分が死ぬまでに本当にやりたいことは一体なんだろうか?」と考えるようになりました。そして55歳の時に会社を辞め、同じ会社のOBのエンジニアを集めて、在宅修理の仕事を始めました。
――「本当にやりたいこと」として、修理の仕事を選んだ理由は何だったんでしょうか。
乗松:家電製品は発売から一定期間が過ぎると、メーカーはサポートを打ち切ってしまいます。けれど長いあいだ大切に使っていたものを、どうしても直して使い続けたいというお客様もたくさんいることを知っていたので、そういう人のサポートをする仕事をしたいと思ったんですね。とはいえニッチな仕事ではあるので、それほど利益を上げることは考えておらず、当初はせいぜい「ゴルフ代でも稼げれば良いな」ぐらいに考えていましたね。
――AIBOの修理を始めたきっかけは何だったんでしょうか。
乗松:2013年に「AIBOというロボット犬をなんとか直してほしい」と依頼されたことがきっかけです。
――無事に直ったんでしょうか?
乗松:紆余曲折がありながらも無事に直りました。そのことがあって以降「AIBOを一台直した会社があるらしい」と我々のところに来るお客様がどっと増えました。AIBOの修理を望んでいた方は、我々が考えていた以上にたくさんいたんです。2014年にメーカーによる修理サービスが終了して以降は、駆け込み寺を求めて、より多くのお客様が全国からやって来るようになりました。
――AIBOを単なる機械ではなくペットとして扱っていたお客さんからすれば、メーカー修理の打ち切りというのは、頼りにしていた獣医さんが突然廃業してしまったのと同じですものね。
乗松:お客様がこんなにもAIBOをかわいがってくれていた、AIBOと共に生きてくれるお客様がいるんだということを、AIBOの修理を始めてからはじめて知りました。

「これを直してほしい」の先にあるニーズを捉えることが大事
――修理を行う上でいちばん大切にしているのはどのようなことでしょうか。
乗松:お客様のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供することですね。「これを直してほしい」という要望の先で、お客様が何を望んでいるのか。そこを的確に捉えた上で我々は何をするのか。そういったところが最も重要だと考えています。
そこでビデオデッキをどうして直したいのかお客様に聞くと、「亡くなった家族が映っているビデオテープがあるので、それを見たい」とのこと。ビデオデッキを直すことではなく、ビデオテープ見ることが目的なら、別のビデオデッキを使って見てみるのはどうか、と我々からご提案しました。
――「これを直して」という依頼の向こう側には、製品を直すことによってやりたい何かがあり、最終的にそれを叶えることが大切なんですね。
乗松:はい。今はどこのメーカーのコールセンターも「◯◯のご用件なら1番のボタンを」「◯◯なら2番のボタンを……」といった感じで効率化がはかられていますが、これが本当に良いことなだろうか? というのは疑問に思います。メーカーがあまりにも自分たちのコストばかりを考え、お客様本位ではなくメーカー本位になってしまっている。そういった態度が見え隠れしてしまうと、お客様の方も嫌になってしまいます。
――効率化を重視しすぎるあまりに、お客さんのことが見えなくなっている。
乗松:そうですね。20年ぐらい前であればソニーやトヨタのような日本企業は世界のトップにいましたけど、今はGoogleやAppleに抜かれ、ロボット産業でも中国の企業が台頭してきました。
長く一緒に過ごすことで歴史ができていく
――実際に修理したAIBOを見せていただきましたが、本当にかわいらしい。
乗松:実際にAIBOが動いている様子を見ると「AIBOってこんなによく動くの」とみなさん驚きます。10年以上前に作られたものが今も現役でかわいがられているというのはすごいことですね。
――現代は家電の買い換えサイクルが短くなり、スマートフォンなど最先端の製品ほど、その傾向が顕著だと思いますが、ペットとして長年かわいがられているAIBOはその正反対をいっているかのように見えます。
乗松:AIBOの場合、大事に使うというか、自分と一緒に生きた歴史ができていきますね。色あせたり傷がついたりしても「これはあの時、あそこにぶつかってできた傷だよね」というように。
――今後、人間とロボットの関係はどのようになっていくのでしょうか。
乗松:ますます色々な形のロボットが登場してきます。人間の仕事を代行したり、手伝ってくれるようなものもあれば、AIBOのように、メンタル的なヘルスケアができるものも増えてくるでしょう。私が今考えていることとしては、介護施設や長期入院中の子どもがいる病院などに行って、ロボットセラピーを推進していきたいですね。
たとえば高齢者の方で、記憶力が落ちて同じことを二回も三回も繰り返し言うようになってくると、周りにそれを指摘されるのが嫌になって、口数が少なくなってしまうことがあります。けれどAIBO相手になら「相手はロボットだから」ということで安心してしゃべれる。それまでまったくしゃべらなかった人が、ロボットに対しては積極的に話しかけてくれるというような光景がけっこう見られるんです。
A・FAN株式会社では、AIBOをはじめ、様々な製品の修理を手掛けています。長く愛用してきた思い出の品や、「もう直らないのかな」と諦めていた製品についても、とても親身に対応してもらえますよ。
またホームページ上では修理したAIBOの里親募集も行っています。
株式会社A・FAN http://a-fun.biz/index.html
(辺川 銀)