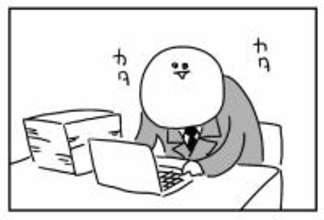不動産の運営・管理をワンストップで提供する不動産総合マネジメントサービスグループ・ザイマックスは3月5日、東京の同社本社で、モバイルワークオフィス「ちょくちょく…」を利用している企業5社との公開座談会を約100名が参加する中で開催した。
座談会トピックで注目を集めたのが、サテライトオフィスと在宅勤務の有効性の比較で、「サテライトオフィスと在宅、ぶっちゃけどっちが便利?」というテーマ。
結論から言えば双方のメリットを活用するのが、今後の賢い働き方のあり方と言えそうだ。
登壇者は、リクルートホールディングス、サントリーホールディングス、住友商事、日立ソリューションズ、富士通。それぞれの企業のノウハウを惜しみなく公開され、質問も活発に行われた。
在宅勤務のメリット
富士通 総務・リスクマネジメント本部 総務部の高柳望氏は、「在宅とサテライトオフィスでテレワークすることは、目的が違うと思います。育児や介護を行っている人だけではなく、書類整理などで集中して業務を行いたい時は、在宅の方が効率は良いという声が聞かれます」と在宅勤務のメリットを語る。

現状、テレワークでは在宅勤務制度が中心。ザイマックス不動産総合研究所の調査によると、2017年秋の時点で、「テレワークする場所や制度の整備」の設問では、26.2%の企業が「取り組んでいる」と回答している。
内容としては、「在宅勤務制度」(19.2%)が2017年春の調査から6.6ポイント、「専門事業者等が提供するレンタルオフィス、シェアオフィス等の利用」(6.7%)が同1.1ポイント伸びているほか、「自社が所有・賃借するサテライトオフィス等の設置」(5.4%)をしている企業も一定数みられ、働く場所の多様化・分散化が少しずつ進んでいる様子がうかがえた。
在宅勤務制度があればサテライトオフィスの利用は不要かと言えば、そういうことでもない。
実際に司会者が「在宅勤務制度があればサテライトオフィスは正直不要ではないか」という質問を出席者にしたところ、9割が、「必要である」と回答した。
出席者にアンケートを行ったところ、サテライトオフィスを利用している企業は約半分。大企業を中心としてサテライトオフィスの活用が進展しており、今後さらに採用を模索していきたいとの声もあった。
それではサテライトオフィスでの業務はどのような効果があるのか。
なぜサテライトオフィスが必要なのか
まず、サントリーホールディングスは、大阪に本社があり、東京の拠点は、港区台場。そこで、東京都心にアジト的なサテライトオフィスの活用をより進めるべきとの意見があるという。
同社は2006年にテレワーク制度を育児や介護を行う人などを対象に試行。当初100人くらいの利用者を想定していたが、利用者は数名に限られたこともあり、2010年から極力制約を設けない方向で本格運用を開始し、現在、約4,500人が利用している。同社ではオフィス以外で働くことが広がっているため、1日集中したいときにサテライトオフィスの活用を進めているケースが多い。

同社人事部課長の竹舛啓介氏
富士通は、2017年4月から全社員35,000人を対象に、出張先や移動中など場所にこだわらないフレキシブルな働き方を可能とするテレワーク勤務制度の導入を開始している。職場単位で導入を進め、現時点では約7割の職場が活用している。グループ全体で2017年度中に15拠点へと増える予定の社内サテライトオフィスも整備中。合計730席で月間利用者は重複を含め25,000人。また、「ちょくちょく…」も含めた外部サテライトオフィスも客先に行く営業などが活用している。
加えて、外部サテライトの活用について同社の高柳氏が「営業職から、自宅近辺よりは、お客様の間を飛び回る合間、もしくはお客様との打ち合わせ前後にすぐレポートを作成したいという声がった。また、在宅をしたいけれど、一人暮らしで環境が整っていないから、サテライトオフィスを使いたいという社員もいる」と述べ、サテライトオフィスのメリットも強調した。
同社は社内アンケートの回答結果も公表。
こうした効果の高いサテライトオフィスだが、セキュリティ面については「不安がない」という回答が7割である一方、離席した際、貴重品についてとられる不安があるという声もあった。
全体として社外サテライトオフィスの利用により、98%が生産性は上がったと回答しているとのこと。
リクルートホールディングスはリモートワークの実証実験を2015年に開始し、2016年1月に全従業員を対象とした上限日数のないリモートワークを導入開始。それに伴い同年4月から利用を開始したサテライトオフィスについて、同社働き方変革推進部 サテライトオフィスチームの馬立純一氏が説明した。現在、リクルートグループ全体の対象者7500人のうち、1500人がサテライトオフィスを活用しているとの実績があるという。一方、サテライトオフィスを一度も利用したことがない社員も少なくないため、今後さらに拡充したいと意欲を語った。なお、2016年10月からザイマックスと共同でキッズスペース付きのサテライトオフィスの実証実験も実施している。

一人あたりのサテライトオフィスの活用が格段に多い同社は、「8割以上がリピーターになる。営業職が4割利用し、お客様を回る合間に活用している。サテライトオフィスは拠点のように利用する。新宿、東京、横浜、大宮が多く利用されている。
在宅とサテライトの使い分けが巧みな企業も
日立ソリューションズ人事総務本部の小山真一氏は、自身が社内テレワーク利用No.1をめざすと意思表明。スケジュールを公開して、在宅とサテライトオフィスの活用などで、勤務している実情を明らかにした。小山氏は、「当社の働き方改革は、個人の幸せと企業の成長がリンクする形で進め、これを実現するためにテーマごとに施策を実施しています。その中で、テレワークは、真摯に徹底して推進します」と意欲を示した。

実際に担当者のスケジュールを見ると、在宅、サテライトオフィスでの業務を巧みに使い分けていた。
「もともとの在宅勤務制度は条件が厳しく、自宅限定で、コミュニケーションが少ない業務などに制限していた。使った方はたった2桁です。テレワーク制度は、いつでもどこでも使っていい、裁量労働勤務者、課長以上、育児・介護を抱えている総合職と幅を広げ、日立グループで社内サテライトオフィスの導入を進めたほか、外部サテライトオフィスも社員から利用したいという声があり、それに応えた」(同社・小山氏)
移動効率の向上・顧客接客機会の拡大を目的に、都内サテライトオフィスのロケーションとして40カ所が利用可能。営業・SEを中心に1,500人が「ちょくちょく…」の会員登録している。
各社の話を総合すると、営業やSEなど顧客の間を飛び回る職種についてサテライトオフィスは効果が大きい。打ち合わせ前後で書類をまとめ、それをすぐに提示できるなどの事例もあり、顧客対応もスピーディーになったという。
その一方、育児や介護を抱える社員や書類を集中して整理したいという場合は、在宅勤務の効果は大きい。
テレワークの運用はどうあるべきか
これからテレワークを実施する企業が続々と登場している。住友商事は今年秋に原則、全社員を対象とするテレワーク制度を導入すると発表した。事業領域が多岐に渡るため、全社一律の制度導入が難しいとされてきた総合商社でもテレワークの波が押し寄せていることをうかがわせた。

テレワークでの在宅勤務やサテライトオフィスでの業務は運用が重要になってくる。出席者からも、「サテライトオフィスにこもっている社員がいて困っていますが、どうすれば良いか」という質問があった。
これに対して、サントリーホールディングス人事部の竹舛啓介氏は、「ポイントは特定の人が利用する制度ではなく、誰でも使えるルールとすることが必要。そこで目標や時間管理を変えたこともなかった」と回答した。
日立ソリューションズでは、テレワークを導入する場合はSkypeを同時起動することをルール化し、テレワークのソリューションも自社で使い、マネジメントしている。
テレワークの導入により、同社の社員からは、「仕事と私生活の充実が両立するようになった」や「生産性や効率が向上した」との声が寄せられ、また、「会社に対する満足度も高まった」との思わぬ成果も。
短時間勤務制度を導入している75名のうち11名がテレワークを導入したことにより、働ける時間が長くなったという成果もあった。
それぞれのメリットを活かしさらなる生産性向上に
一方で日立ソリューションズの、サテライトオフィスだけではなく、社内の環境も充実して欲しいという声があった。
そこで、社内食堂を食事以外の時間帯にも有効利用するため、打ち合わせやオンライン会議などができる環境へと整備し、1日10人以上が利用している。同様に社内で集中できるように本社4Fの執務室に作業集中ブースを新設。
テレワークは各社とも生産性が向上するなどの利点があり、その手段として在宅勤務制度やサテライトオフィスがある。両方にもメリットがあり、在宅勤務制度とサテライトオフィスを上手に使い分けすることがさらに生産性をアップさせることになる。短時間労働者でも働ける時間が延び、会社満足度も高まるなどの効果も大きい。
在宅勤務からスタートしたテレワークだが今後、サテライトオフィスの拡大は中小企業も含めて大きな課題となって浮上してきた。さらに、日立ソリューションズが実践しているような社内空間の有効利用という視点もある。それぞれのメリットを活かしつつ、新しい働き方改革が今、日本企業で本格的に始動しようとしている。
(長井雄一朗)