【前編はこちら】渡辺正行が振り返る芸人への道「きっかけは落研、先輩・立川志の輔さんの落語を見て衝撃を受けた」
【写真】どの時代も第一線で活躍する、リーダーこと渡辺正行
──若手の頃ストリップ劇場である、「道頓堀劇場」にも出演していたそうですが、どういう経緯で出ることになったんですか?
渡辺 道頓堀劇場ではストリップの幕間に15分ぐらいコントをやる枠があったんですけど、専属の若手芸人が辞めて枠が空くことになって、「お笑いを本気でやる気があるんだったらやってみないか」とコント太平洋の市川太平さんに誘われたんです。1日4回ステージがあって、コントをやる他に事務所の電話番や劇場内の掃除、そこに専属でいた杉兵助先生の周りの世話などをして2500円くれたんです。ただし1年間、365日休みがなかったんです。
──ストリップ劇場に出ることに抵抗はなかったんですか?
渡辺 めっちゃ嫌でしたよ(笑)。前任者がどんなコントをやるのか下見に行ったら、黒い下着を着てSMをするみたいな酷いコントをやっていたんですよ。「こんな世界なんだ……」って引きましたね。でも当時劇団(「劇団テアトル・エコー」)にいても全然仕事はこなかったですし、とっかかりもなくて人前に立つことすらなかったんです。たとえストリップ劇場とはいえ、板の上でメシを食っている人になれるならやってみるかと。
──(コント赤信号の)小宮(孝泰)さんとラサール石井さんも賛成だったんですか?
渡辺 その頃はまだ3人でグループを組んでいるという感覚はなかったですから、こういう話があって、人生を左右することなので、自由意思で決めようと。
──ストリップ劇場のステージはいかがでしたか?
渡辺 最初は最悪でしたね。文化祭で大爆笑をとったネタをかけてみたら、面白いぐらいウケなかったんです。そもそもお客さんはストリップを見に来ているので、コントを見ようって意識がないんですよね。そしたら師匠の杉兵助先生が「頭で考えたネタはダメだ。スリッパで頭をはたいたり、プロレスをやってみたり、体を使ったコントをやるんだ」と言われて。
「え~! そんな浅草みたいなコント嫌なんだけど」と思っていたんですけど、先生がそれをやれって言うから、実際にスリッパで頭を叩いたらウケるんですよ。分かりやすいほうがいいんですよね。
──後に杉兵助師匠は『笑っていいとも! 』のレギュラーになるなどテレビでもブレイクしますが、ストリップ劇場でも爆笑をとっていたんですか?
渡辺 バケモノみたいな見た目でしたけど(笑)、舞台に立ったら確実に笑いをとるんですよね。どんなに僕らが頑張っても勝てなくて尊敬していました。いきなり先生はアドリブを入れるんですけど、そこへの対応力などは磨かれたと思います。でも基本的には、だらけにだらけたダメダメな修行時代でした(笑)。当時、ちょうど漫才ブームがきて、それを楽屋のテレビで見ていたんですよ。
「世の中は、こういう笑いが流行っているんだ。このブームに俺たちは乗れないな」って諦めかけていましたね。小宮と石井君はストリップ劇場を辞めたがっていたんですけど、僕はお客さんにウケ始めていたし、自分たちなんて所詮こんなものだからストリップ劇場のお笑い芸人でいいやって気持ちだったんです。そんな状況で漫才ブームがあって、2人は辞めるって言うから解散だねって話で。
──解散の話まで出ていたんですね!
渡辺 そんなときに、よく道頓堀劇場に遊びに来ていた「ゆーとぴあ」さんが、「単独リサイタルをやるから、お前たちも出ないか」って声をかけてくれたんです。だったら解散前に新ネタを1本作ろうって話になったんです。
僕はリーダーになりたかったから、「今だ!」と思って一晩で台本を書いて。次の日、2人に見せたら、「いいんじゃないの」ということでできたのが暴走族のネタだったんです。それで僕がリーダーになったんですけど、あのときに小宮がいい台本を書いていたら小宮がリーダーだったんです。これを我々の間では、「小宮の三日天下」と呼んでいます(笑)。
──暴走族のネタはどのようにできたのでしょうか?
渡辺 僕が刺激を受けていたのは、お笑い芸人ではなく、東京乾電池、つかこうへいさんの劇団、劇団東京ヴォードヴィルショーなど、笑いを前面に押し出している演劇の人たちでした。ああいうものをやりたいという気持ちがデカかったので、僕らの初期のネタはボケとツッコミがあまりないんですよ。あと漫才ブームを見て、この発想に勝てるにはどうすればいいのか、自分たちの力量はこれぐらいだから、どういうコントをやればいいのかなども研究しました。なぜ「暴走族」を持ってきたかというと、デカい声を出せる。
デカい声を出すと下手な演技が補えるし一生懸命やっているように見える。そこに大学生の偏差値ギャグみたいなものも入れ込める。他のグループはそういうことをやっていなかったので、そこで差別化できるだろうと。そういう計算をしてネタを作りました。
──意識的にお笑いを分析してネタを作っていたんですね。
渡辺 先ほど挙げた劇団の公演を観に行ったときは必ずメモを取って、こういうギャグの配列をしているんだと勉強しました。お笑い番組も、当時はビデオがないからテープレコーダーに録音して、「今の漫才・コントはこういう発想で、こんな人たちが売れている。こういうのが今の時代はウケるんだ」と分析して、それを自分の中に落とし込んでいって、自分たちの勝てそうなシチュエーションを台本にしていきました。
それを3人で練習して、さらに面白いものを入れ込む。そうじゃないと漫才ブームの中に入れなかったですし、みんなと違うことをしないといけないという意識も強かったです。
──後に「ラ・ママ」で若手芸人にアドバイスをしたり、「M―1グランプリ」の審査員を務めたりする礎が、その頃から築かれていたんですね。
渡辺 お笑いがどういうパターンで作られているか、他のお笑いコンビがどういう風にネタを作っているかなどを考える勉強になっていたかもしれないですね。
【後編はこちら】36年間若手コントライブを主催、渡辺正行が語る「爆笑問題、初舞台の衝撃」
















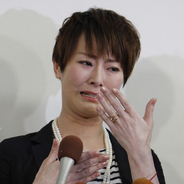











![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


