大相撲の四股名には
- 年寄名跡にあるものは名乗れない
- 「同音同字」「同音異字」の力士が他にいる場合は名乗れない
- 「止め名」は名乗れない
相撲の四股名に文字数の制限は特にない?では、最も長い四股名の力士って誰なの?
一方、四股名をどんなに短くしても「1文字以下」にはしようがないため、最も短い力士の四股名は1文字ということになります。
近年では「曙(あけぼの)」「勢(いきおい)」「輝(かがやき)」など、漢字1文字の力士の活躍が目立ってきています。
■1文字 曙 勢 など
漢字1文字の四股名で活躍した力士は、明治時代以降では明治~大正に活躍した「鳳(おおとり)」という横綱が最初でした。
その後も決して人数は多くないものの、漢字1文字の力士は何人か登場しました。最近では、ハワイ出身で初の横綱となった「曙」の活躍が、真っ先に思い浮かびます。
曙の手形(左)
また2019年現在も活躍中の「勢」が幕内に昇進した時には「四股名が漢字1文字の幕内力士は『曙』以来」ということで話題になりました。
その他、「輝(かがやき)」「彩(いろどり)」「魁(さきがけ)」なども注目されています。
輝は、十両に上がる前は本名の「達(たつ)」を四股名として名乗っていたため、初土俵からずっと1文字の四股名だったことになります。
2016年11月場所3日目には、「『勢』vs『輝』」という「漢字1文字対決」が実現しました。
幕内での漢字1文字の力士同士の対戦は、昭和以降ではこれが初めて、1833年(天保4年)10月場所初日の「『璞(あらたま)』vs『錦(にしき)』」の対戦以来、実に183年ぶりだったとのことです。
彼らの活躍の影響か、近年漢字1文字の四股名を名乗る力士が増えてきています。
ちこれから本場所で「漢字1文字対決」を見る機会が増えていくかも知れませんね。
■中にはこんなびっくり四股名も!
また過去には、漢字ではなくひらがな1文字の力士もいました。
それは昭和に活躍した「い」という力士で、読み方は「かながしら」でした。
「いろは歌」の最初に出てくる文字が「い」のため、そう読ませたと思われますが、大正時代には同じ「いろは歌」の最後につく「京」と書いて「かなどめ」と読ませる四股名の力士もいたというから、更に驚きです!
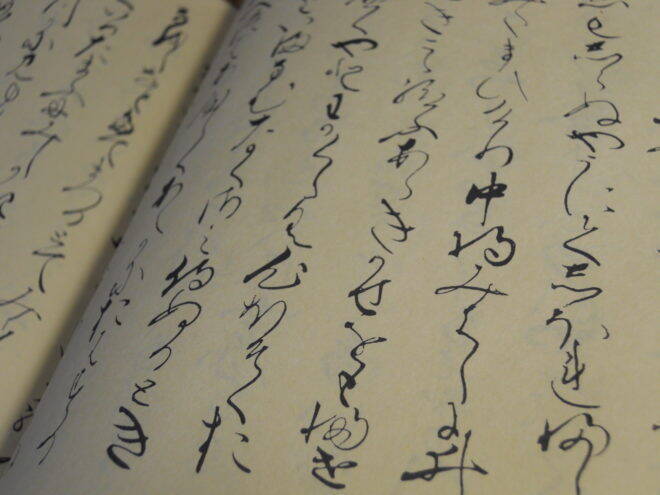
もし同じ時代に同じくらいの番付にいたら、「『い』vs『京』」の「いろは歌対決」が実現していたかもしれませんね。
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan






























![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



