2025年1月5日から放送予定のNHK大河ドラマ第64作『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の主人公である蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)。
彼は、江戸の地本問屋として出版界を牽引した人物です。
※あわせて読みたい記事:
2025年大河「べらぼう」主人公・蔦屋重三郎が出版界でライバルを駆逐していった決め手とは?
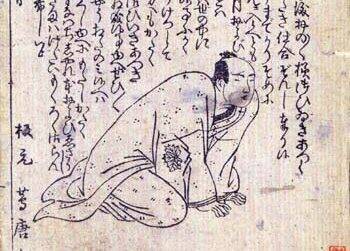
蔦屋重三郎(Wiipediaより)
重三郎が出版した「蔦屋版」の『吉原細見』(吉原のガイドブック)は、それまで業界を牛耳っていた「鱗形屋版」を圧倒していきました。
それにとどまらず、重三郎はさまざまなジャンルの本の出版に乗り出すことでも事業を拡大させていきます。彼には「次の一手」があったのです。
定期刊行物だった『吉原細見』と同じく、安定的な売り上げが見込めた本としては富本節の正本(音曲の詞章を記した本)・稽古本と往来物の出版が挙げられます。
この、富本節とはなんでしょうか。
■浄瑠璃の流行をキャッチする
三味線伴奏による語り物である浄瑠璃の世界では、この安永期に富本豊前太夫(2代目)という美声の人気太夫が登場したため、富本節の人気が大いに高まりました。
このため富本節を修得したいと考える人が増えて、富本節の正本や稽古本の需要が高まることになります。
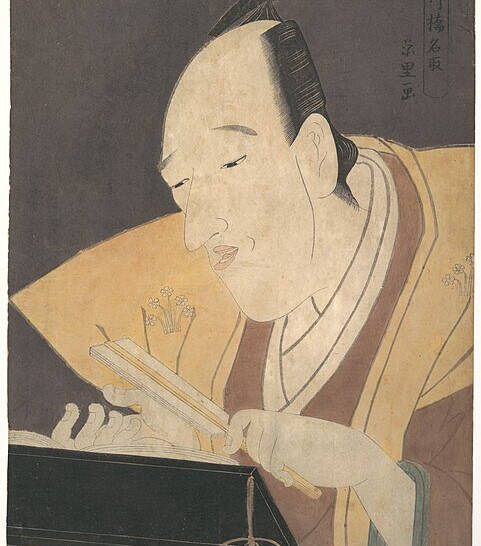
二代目富本豊前太夫(Wikipediaより)
世間の流行に敏感な重三郎はこれを見逃しませんでした。富本節の正本・稽古本の出版を手がけ、経営基盤の柱の一つとしたのです。
往来物とは手習いに使われた教科書のことで、庶民教育には不可欠な教本でした。
価格も安く設定されており、一冊あたりの利益は薄かったものの、長期にわたって摺りを重ねられるため安定した売り上げが見込める売れ筋商品だったのです。
安永9年(1780)から、重三郎は毎年のように往来物を出版し、富本節の正本・稽古本と同じく経営基盤の柱としていきます。
■ついに日本橋に進出
着々と経営基盤を強化した重三郎は、『吉原細見』 の出版の独占に成功した天明3年9月に、通油町(現在の東京都中央区日本橋大伝馬町)にあった地本問屋・丸屋小兵衛の店舗を買い取り本拠地とします。

大伝馬町の八雲神社
彼はここに耕書堂を開店し、吉原細見を販売していた五十間道の店は手代徳三郎に任せることにしたのです。
こうして、蔦屋は一介の書店・版元から地本問屋としての地位を得ることになりました。
ところで、移転した通油町は江戸経済を動かす豪商が集住する日本橋地域の町の一つでした。経済のみならず文化や情報の中心地であり、江戸の出版界を牛耳る書物問屋や地本問屋も数多く店を構えていたのです。
書物問屋の代表格である須原屋茂兵衛が通一丁目、地本問屋の鶴屋喜右衛門は重三郎と同じく通油町に店を構えていました。
そんな日本橋地域に進出できたことは、重三郎が名実ともに江戸の出版界のトップクラスに躍り出たことを意味していました。
吉原で書店を開店してからわずか十年で、彼は一流どころの書店版元の仲間入りを許されたのです。
この時、重三郎は三十八歳。時代はすでに十代将軍・家治の治世に入っていました。
なお、幼少期に両親の離別に接した重三郎ですが、通油町に転居したのを契機に両親を呼び寄せてもいます。
参考資料:『蔦屋重三郎とは何者なのか?』2023年12月号増刊、ABCアーク
画像:photoAC,Wikipedia
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan




























![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



