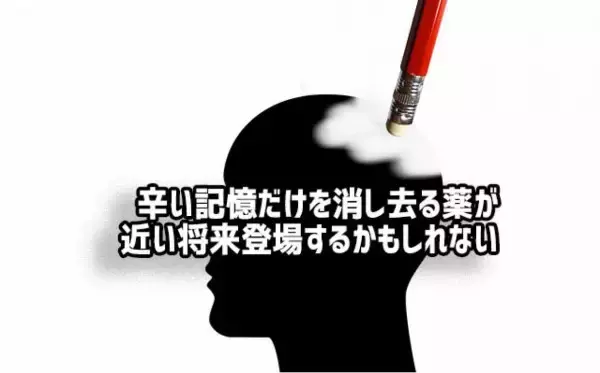
もしも過去の記憶を消せる忘れ薬があったら、何に使うだろうか?心に傷を残すようなトラウマとなっている記憶は、すぐにでも消したいものだ。
イギリスの研究者が、辛い記憶を忘れることができる”忘れ薬”の開発につながる発見を報告した。
そのタンパク質の関与を断ち切ってしまえば、これまで忘れ薬と有望視されていた薬の有効性が格段に上がるという。
忘れ薬として有望視されていたプロプラノロールの欠点を探せ じつは忘れ薬として有望視される薬がある。
それは高血圧などの治療に使われる「プロプラノロール」という薬だ。心臓の交感神経にあるβ受容体を遮断するので、心拍を抑えて血圧を下げる効果があるのだ。
この薬は、強い感情的な記憶の形成と関係がある脳のベータアドレナリン作動性受容体に作用することでも知られている。
受容体に結合するタンパク質が遮断されると、記憶の形成に必要なシナプスの変化が抑えられ、その影響で細かい記憶が保存されなくなる。
実際、2004年の実験で、トラウマ体験をした動物にプロプラノロールを投与すると、恐怖反応を示さなくなることが確認された。つまりトラウマの記憶を消す作用があったということだ。
こうして忘れ薬の候補となったプロプラノロールだが、その後の研究の結果はまちまちで、確実な記憶消去効果を発揮してくれなかった。
[画像を見る]
photo by iStock
特定のタンパク質をなくすことで忘れ薬の効果がアップ 今回、英ケンブリッジ大学のエイミー・ミルトン博士らは、プロプラノロールが効かない原因を探り、先日開催された『ECNP』の学会で発表している。
それによると、「シャンク(Shank)」と呼ばれるタンパク質があると、プロプラノロールで記憶を消そうとしてもその効果が打ち消されてしまうのだそうだ。
ミルトン博士らが行ったのは、ラット版のパブロフの犬(条件反射)のような実験だ。
クリック音を鳴らすと同時に、ラットに電気ショックを与える。すると、ラットはクリック音を耳にするだけで、反射的に恐怖反応を示すようになる。電気ショックのトラウマを思い出すからだ。
次に、クリック音を鳴らして、ラットがトラウマ的記憶を思い出した直後、プロプラノロールを投与する。
このときシャンク・タンパク質があるラットでは記憶が消えなかったという。一方、シャンク・タンパク質を劣化させてやると、きちんと記憶は抹消された。
今のところ、シャンク・タンパク質そのものが記憶を守っているのか、それとも別の記憶維持プロセスの副産物なのかは明らかになっていない。
それでもシャンク・タンパク質は、記憶消去が上手くいくかどうかを知る目印にはなるという。
[画像を見る]
photo by iStock
人間に適応できるようになるには更なる研究が必要 同じことを人間でもできるかというと、それはまた別の話だ。
ミルトン教授によれば、映画のように、自分にとって都合の悪い記憶だけを選んで消せるようにするのは難しいと考えている。
覚えておきたい記憶まで消し去られてしまうほど悲しいことはない。
それでも、これまで記憶消去の実験に使われてきたカタツムリではなく、ラットで研究ができているということは、人間への応用に前進しているとみなせるそうだ。
PTSDなど、深刻な心のトラウマの治療として、こうした研究を応用できればいいと、ミルトン教授は願っているという。
References:Scientists find protein which indicates wheth | EurekAlert! / UCLA biologists 'transfer' a memory | EurekAlert! / written by hiroching / edited by parumo
追記(2021/10/18)リンクを一部変更して再送します
『画像・動画、SNSが見れない場合はオリジナルサイト(カラパイア)をご覧ください。』
イギリスの研究者が、辛い記憶を忘れることができる”忘れ薬”の開発につながる発見を報告した。
薬で記憶を抹消できるかどうかは、あるタンパク質にかかっているという。
そのタンパク質の関与を断ち切ってしまえば、これまで忘れ薬と有望視されていた薬の有効性が格段に上がるという。
忘れ薬として有望視されていたプロプラノロールの欠点を探せ じつは忘れ薬として有望視される薬がある。
それは高血圧などの治療に使われる「プロプラノロール」という薬だ。心臓の交感神経にあるβ受容体を遮断するので、心拍を抑えて血圧を下げる効果があるのだ。
この薬は、強い感情的な記憶の形成と関係がある脳のベータアドレナリン作動性受容体に作用することでも知られている。
受容体に結合するタンパク質が遮断されると、記憶の形成に必要なシナプスの変化が抑えられ、その影響で細かい記憶が保存されなくなる。
実際、2004年の実験で、トラウマ体験をした動物にプロプラノロールを投与すると、恐怖反応を示さなくなることが確認された。つまりトラウマの記憶を消す作用があったということだ。
こうして忘れ薬の候補となったプロプラノロールだが、その後の研究の結果はまちまちで、確実な記憶消去効果を発揮してくれなかった。
[画像を見る]
photo by iStock
特定のタンパク質をなくすことで忘れ薬の効果がアップ 今回、英ケンブリッジ大学のエイミー・ミルトン博士らは、プロプラノロールが効かない原因を探り、先日開催された『ECNP』の学会で発表している。
それによると、「シャンク(Shank)」と呼ばれるタンパク質があると、プロプラノロールで記憶を消そうとしてもその効果が打ち消されてしまうのだそうだ。
ミルトン博士らが行ったのは、ラット版のパブロフの犬(条件反射)のような実験だ。
クリック音を鳴らすと同時に、ラットに電気ショックを与える。すると、ラットはクリック音を耳にするだけで、反射的に恐怖反応を示すようになる。電気ショックのトラウマを思い出すからだ。
次に、クリック音を鳴らして、ラットがトラウマ的記憶を思い出した直後、プロプラノロールを投与する。
このときシャンク・タンパク質があるラットでは記憶が消えなかったという。一方、シャンク・タンパク質を劣化させてやると、きちんと記憶は抹消された。
今のところ、シャンク・タンパク質そのものが記憶を守っているのか、それとも別の記憶維持プロセスの副産物なのかは明らかになっていない。
それでもシャンク・タンパク質は、記憶消去が上手くいくかどうかを知る目印にはなるという。
[画像を見る]
photo by iStock
人間に適応できるようになるには更なる研究が必要 同じことを人間でもできるかというと、それはまた別の話だ。
ミルトン教授によれば、映画のように、自分にとって都合の悪い記憶だけを選んで消せるようにするのは難しいと考えている。
覚えておきたい記憶まで消し去られてしまうほど悲しいことはない。
それでも、これまで記憶消去の実験に使われてきたカタツムリではなく、ラットで研究ができているということは、人間への応用に前進しているとみなせるそうだ。
PTSDなど、深刻な心のトラウマの治療として、こうした研究を応用できればいいと、ミルトン教授は願っているという。
References:Scientists find protein which indicates wheth | EurekAlert! / UCLA biologists 'transfer' a memory | EurekAlert! / written by hiroching / edited by parumo
追記(2021/10/18)リンクを一部変更して再送します
『画像・動画、SNSが見れない場合はオリジナルサイト(カラパイア)をご覧ください。』
編集部おすすめ





























