6月28日に全国公開され、瞬く間にその評判が広まっている劇場アニメ『ルックバック』。
マンガ『チェンソーマン』の躍進で一躍人気漫画家となった、藤本タツキ先生のマンガを原作とするこの映画。
上映時間はたった58分。キャスト陣にも、いわゆる人気声優と呼ばれる人はなし。それでもこのアニメ映画が、多くの人々の心をこんなにも捉えて離さない理由とは。
※本記事は映画のネタバレを含みます。
マンガを描く事が始まりで、すべてだった──二人の少女の青春譚
藤本タツキ先生による同名マンガを原作とする『ルックバック』。本作は元々、2021年にWeb媒体である『ジャンプ+』にて読み切り作品として掲載されたマンガです。
短編作でありながらも140ページ超という異例のボリューム。重ねて配信2日足らずで閲覧数は400万PVを突破し、『ジャンプ+』史上最多の閲覧数を残す読切作品となったことも、話題を集めました。同年には『このマンガがすごい!2022』オトコ編1位、『マンガ大賞2022』第2位に輝くなど、読切マンガとしては異例の実績を残しています。
劇場アニメ「ルックバック」公式サイトより
本作が描くのは、絵やマンガを描く事に心を奪われた二人の少女の物語です。同学年で一番絵が上手いのは自分、という自負を持っていた藤野。けれどある日、不登校の京本が自分よりずっと絵が上手いことを知り、彼女に負けまいと藤野は奮起して絵を練習するようになります。
その中で京本もまた、藤野の絵の美味さに憧れ、同い年の自分を“先生”と呼ぶほどに尊敬していると知る藤野。絵を描く事をきっかけに仲良くなった二人の少女は、そのまま共作でマンガの執筆に挑戦することに。十代の青春時代を、共に創作に費やしていく……そんなあらすじとなっています。
「最高の作品を作る」という並々ならぬ情熱が伝わる映画だった
本映画が話題となったポイントのひとつは、やはりマンガ原作の世界観を非常に大事に映像化していた点でしょう。一言でいえば、創作に携わるすべての人に向けた「創作讃歌」が主題となる本作。
作品のテーマ通り、マンガから映画へ媒体こそ変われど、かかわる多くの人が「最高の作品を作る」という強い思いの元に制作へ取り組んでいる。映画の節々からそんな作り手の情熱を感じる点が、大勢の注目を集めているのではないでしょうか。
紙媒体となるマンガは、当然原則として動きや躍動感に乏しい形式。ですが映画ではまるでマンガのコマ同士を繋ぐように、非常になめらかで丁寧なシーンカットが多数描かれています。映像化・実写化の際ファンが最も恐れる、原作から余計なセリフやシーンを足すことも一切なし。

原作は通常のマンガに比べ台詞が少なく、キャラクターの表情で心情や情景描写を巧みに表現しているのが大きな特徴。ですがその台詞のない無言の間の空気感も、きっちりと繊細に映像として描かれています。
一方で原作のマンガには、随所に藤本タツキ先生のバックボーンを思わせる様々なオマージュや小ネタも満載。
創作や“作品を作る”ことに対して、細部までリスペクトが込められた本作。重ねてそれが最も如実に表れているのは、やはり本作のエンドロールではないかと筆者は思います。
映画に携わったスタッフの名前がクレジットされるエンドロール。普通のアニメ映画では、作中でキャラクターを演じた声優さんの名前がまず最初に来ることが多いですよね。
ですがこの映画でエンドロールの一番最初に流れるのは、映画のコマをひたすら描き続けたアニメーションスタッフの名前です。大勢の人が愛を込めた作品として、しっかり最初から最後まで見逃せないものを作る。そんな意図を持って、エンドロールも作られているように感じました。
“あるある”で誰しもが身に覚えのある記憶を追体験できる
マンガや絵、音楽、文章、演劇、写真、映像、工作……。物や形こそ代われど、何かを創り出す人、あるいは創作で自分を表現する人。今はやっていないけど昔はやっていた、という人も含めれば、そんな「ものをつくる」ことに夢中になった経験のある人は世の中に大勢います。
『ルックバック』はそもそも、原作からなぜここまで大きな話題を呼んだのか。その理由は、すべての「ものをつくる」人の原体験や、「なぜものを作るのか?」という問いの本質を、とても鮮やかに描いているからにほかなりません。
見た目がかわいいわけでも、かっこいいわけでもない。
運動神経も悪くはないけど普通。勉強もまあできてそこそこ。
それでも絵が上手ければ、クラスのヒーローになれる。
お調子者として面白おかしく振舞えば、クラスの人気者になれる。
歌が上手だと、書いた読書感想文が賞を取ると、大勢から褒められる。
そうやって小学生の頃、幼い自尊心やプライドを形成した記憶がある人は、意外と多いことでしょう。
他の人にはない、自分だけの“得意”や“好き”。ですが成長し自分の世界が広がるにつれ、上には上がいると気付き、自分は大したことない凡人だと知る。そんな挫折はものづくりのみならず、スポーツや勉強の世界でも大勢が味わう感覚です。
そこで自分の“得意”や“好き”を、あっさり諦めた人ももちろんいるかもしれません。ですがそれ以上に、感じた悔しさを糧にして、上達や成長のためひたすら練習を積み重ね、自分の“好き”に情熱を傾けた人も多いはず。
藤野や京本と同じマンガではなくとも、あるいは当時夢中になったものが今はもう手元になくとも。その経験を知る人にとって彼女たちの姿はとても眩しく、同時に昔の自分を思い出して、どこか懐かしくもソワソワとした気持ちになることでしょう。
創作の持つ大きな力。それが刃物になることもある
重ねてこの『ルックバック』は何よりも「ものをつくる」こと、創作に向き合い続ける人の背中を押してくれる作品です。絵を描く、音楽を作る、文章を書く。
写真や映像を撮る、服をデザインする、ネタや脚本を書く。世間では特にエンターテイメントの分野で、作品を作る多くの人たちがいますよね。
創作を仕事にする人。今まさに創作を仕事にするべく奮闘している人。
あるいは別に仕事を持ちながら、それでも創作を辞められない人。
そんな人々の中には、「ものをつくる」喜びと地獄に直面した経験のある人も多いはず。もちろん今まさにライターとして、この記事を書く筆者自身も例外ではありません。
創作は楽しい。作品への評価はニアイコール自分への評価で、褒められると自分が認められた気がして嬉しい。けれど、100人に誉められるよりも1人に貶された方が強く印象に残ってしまう。
一方で“認められたい人”からの嬉しい言葉には、どんな高評価も貶しも吹き飛ぶ強い力がある。
劇中で小学生の藤野が感じた喜びや悲しみは、多くの「ものをつくる」人にとって非常に既視感のある感覚だと思います。
そんな人々は、創作に大きな力があることも知っています。なぜなら誰あろう自分自身が、創作に人生を変えられた人間の一人だから。自分の作るものが、人の人生を変える。それは非常に嬉しいことですが、それがかならずしも良い方向に向かうとは限りません。
時として自分の作るものは、誰かを不幸にする刃物になる。
創作は時に、人一人の人生を変える。しかし一方で基本的に、創作は直接的に人の命を救うわけでもなければ、生活になくてはならないインフラでもありません。創作は、エンタメは不要不急のもの。数年前まで世界中に蔓延した感染症の中では、そんな言葉が飛び交うこともありました。
元を辿れば「好きだから」という理由で、あるいは「自分が褒められるから」という、承認欲求を満たすために始めた創作。ですが時間が経つにつれ、そんな人々には好きだからこその苦しみや葛藤、そして創作を続けるがゆえの苦悩が積み重なっていきます。
好きだけど苦しい、好きだから辛い─それでも辞めないのはなぜ?
好きなのに苦しい。やりたいことだからこそ辛い。その板挟みの中で「好きなものを嫌いになる前に辞める」という判断は、客観的に見れば非常に賢明な判断です。ではなぜ、それでも作り続ける人たちがいるのか。その答えは、まさに映画で描かれた藤野と京本が過ごした時間のすべてに詰まっています。
言葉にしようとすると、とても難しいこの感覚。「好きだから続けてるんでしょ?」と尋ねられても、それを全肯定できない人もきっと多いでしょう。
好きか嫌いかと言われれば、確かに嫌いではない。筆者自身も“好き”というよりは、“向いている”という気持ちの方が大きいのが正直な本音です。その中で当然藤野の言う通り、イヤになることも面倒になることも、「自分はなんでこんなことをしてるんだ」とウンザリする瞬間も実際にたくさんあります。
しかし強いて言葉にするならば、喜びも嬉しさも恥ずかしさも、悲しさも悔しさも絶望も。普段の何気ないありふれた一瞬から、かけがえのない特別な感情まで。
自分の人生の多くの時間が、当たり前のように創作と共にあったから。なくなった所が想像できない。なくなったら、どうやって生きていけばいいかわからない。そんなところでしょうか。だからこそ、作中で描かれた“もしも”の未来でも、二人はそれぞれに絵を描く道を歩んでいました。
運命の出会いがなくとも、創作を手放すことはなかった藤野と京本。改めて考えるとそれは大きな希望で、そしてむしろそれこそが、「何があっても創作からは逃れられない」という最も恐ろしい、今作の提示する結末なのかもしれません。
原作マンガが話題になった時同様、多くの著名人やクリエイターからの絶賛の声も相次いでいる、劇場アニメ『ルックバック』。何かに情熱を燃やした経験がある人、特に創作に携わる人の胸を大きく打つ本作。「ものをつくる」人々が全身全霊を注いで作ったその物語が、これからもより大勢に広まっていくことを、創作に関わる人間の端くれとして願って止みません。
(執筆:曽我美なつめ)

































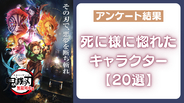

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








