事後諸葛亮(じごしょかつりょう)とは、事態がすべて手遅れになったあと、終わったあとに、さも状況を見越していたかのように「ああすればよかった、こうすればよかった」と訳知り顔で解説すること。
意味
事態がすべて手遅れになったあと、終わったあとに、さも状況を見越していたかのように「ああすればよかった、こうすればよかった」と訳知り顔で解説すること。いかにも知者であるとふるまう様を、三国志の名参謀、諸葛亮になぞらえている。
元ネタは中国の小説?
元は中国語圏のスラングで、1975年に中国で出版された『煤城怒火』という小説に出てくるのが最初だとされている。その後中国語圏で使用されてきたが、日本での認知度は低かった。日本注目が集まったのは2020年1月末。
ラジオ番組「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」で取り上げられると、その語感のよさからtwitterであっという間に共有されトレンド入りした。
SNSなど、意見を共有するツールが浸透したことにより、一般人でも事件事故に意見を述べることができるようになった。
だがしかし、ことが起こったあとに必要なのは、ああすればよかったという手遅れな意見ではなく、「これからどうするべきなのか」という建設的な意見である。
……と、頭でわかっていても、事後諸葛亮してしまうのが人の性なのかもしれない?




























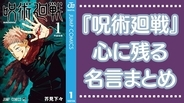
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








