レースにはHMキッズトン少佐の名義でエントリーされているが、実際に運転したのはおそらくロニー・ホアー大佐だろう。彼はフェラーリを英国に輸入するために、後にマラネッロ・コンセッショナリーズを立ち上げた人物だ。この活動は、ホーソーンの突然の死という運命に妨げられなければ、彼も自身のために進めていた計画だったという。
現在、このアウレリアはホーソーンが所有していた時代とほぼ同じ状態に保たれている。ちょっとした錆もきれいに取り払われ、スタンダードのエグゾーストはアバルト社製のものに取り替えられた。こうして眺めてみると、少々"ポンコツ気味"な時期があったことなど嘘のようだが、これまでの歴史がかき消されてしまったというわけでもない。あれから新たな経歴が加わってもいる。ジョン・カンディは2001年にレストアを完成させてから、このランチアで西ヨーロッパ中をゆうに約6万5000kmもドライブしたという。
目の前にあるシートのレザーも、ステアリングホイールも、マイク・ホーソーン本人が座り、握ったそのままの現物だ。カーペットは仕方なく交換したものの、ジョンはできるかぎりオリジナルの素材をよみがえらせようと尽力した。それでも、ウエストラインから下のボディの大半は、新しいパネルへの交換を余儀なくされたという。新しいパネルは手作業で造形され、突き合わせ溶接で接合した。
これはピニン・ファリーナでの手法に共通点の多い方式だ。バルクヘッド、エンジンベイ、トランクフロア、センタートンネルだけは、基本構造をオリジナルのままに保つことができたという。ボンネットとトランクリッドは、1970 年代後半に粗雑に作られたアルミニウム製のものを取り外し、スチールで新調されている。

ジョンは、完ぺきに平らな側面を創り上げるピニン・ファリーナの手法に心酔しており、このレストアでもその方法の再現に努めたという。「通常はドアスキンの縁がシェルの内側に巻き込まれがちですが、そうなると凸面が生じてしまいます。ピニン・ファリーナはそうした方法は取らずに、外側の平らなスキンを内側とともにカットした上で、溶接してからつなげています。
機構部分は細部まで入念にリビルドされた。事実上、ほぼすべての部分がリビルドされたといえるだろう。その中には、ツーリスト・トロフィー・ガレージが挑戦した試みの後始末も含まれていた。彼らは、全アルミニウム製のV6エンジン(バンク角90°、総排気量2451cc)から、ファクトリー出荷時の最高出力118bhpを上回る出力を引き出そうと試みていた。
シリンダーヘッドやインテークマニホールドなどのアルミニウム製部品は、研磨されすぎていたことで、加齢によって危険なレベルにまで薄くなり、さらにバルブガイドは磨耗によってゆるみ、バルブステムの支えが適切に効きにくい状態になっていたという。
この車は、細部まで気が利いている。ダッシュボードにはツーリスト・トロフィー・ガレージのセント・クリストファー・バッジが輝いている。
そしていよいよ、私自身が運転に挑むチャンスが巡ってきた。私は以前に、コラムシフトのセリエ3と、ナルディ社製シフトを備えたセリエ5のアウレリアを運転する機会に恵まれたが、どちらの際にも心の中に浮かんでいたのは「WPD10」だった。私にとって「WPD 10」はB20の決定版で、自分で運転できることは夢のようだ。1972年当時の雰囲気にひたる私に、「スピードメーターの反応はとても遅いよ」とジョンが教えてくれる。「70mphを指していたら、実際には90mphくらいは出ているはずだ」という。仮に計器が"7"を指していたら、実際には"10"(と少し)をかけた数字がスピード、"1000"をかけた数字がエンジン回転数といった具合だ。

長いシフトレバーは、フロアから突き出し、細身なセンタートンネルの右側へと伸びている。このシフトレバーはおだやかながらも的確に動かすのがコツで、古いシンクロメッシュの性能を補助する際によく使う、ダブルクラッチをしながら素早いシフトチェンジを試みるテクニックは通用しない。
あちこちに通常の車とは少々異なる方式をとったエンジニア達の設計に沿って、この車には、この車ならではの流儀がある。シンクロがない1速へのシフトダウンは、車が停止してからだ。
時には、直径がありえないほどに小さいクラッチから、ちょっとした振動も起こる。また、大きなドラムブレーキは、最初の設定では均等に作用しないこともあった。そうした些細な難点はありつつも、乗り回すのに支障はない。ほどなく、アウレリアはスムーズに調子が上がってきた。回転数の上昇とともに、エンジンからは少しばかりダーティーなビートが響きわたる。あらゆるアクションから、質の高い技術の冴えが伝わってくる。

カーブの走行も抜群の安定感だ。優れたグリップを提供してくれるド・ディオン式のリア・サスペンションのおかげで、先のモデルに採用されていたセミトレーリングアーム式に比べて、パワーが出ている状態でもより安定したアンダーステア傾向が実現されている。ランチアのオールドモデルのご多聞に漏れず、真剣に運転するほどに、鋭さや攻撃性も増してくる。S字カーブをこなして格別の満足感を得ながら、私は64歳を数えるこのマシンの有能さを実感した。そしてすぐさま、スピードメーターが示していた数字よりも30%近く速いスピードで、このカーブを走り抜けていたことに気づく。
私が初めて出会った時、この「WPD 10」は18歳で、とても草臥れた状態だった。現在、「WPD 10」はレストアから数えてさらに18年経ったところだが、今もなお完全な状態に保たれている。時代も異なれば、状態も異なる。いずれにしても、アウレリアを愛したことでも有名なマイク・ホーソーンが今の「WPD 10」を見たらどんなに喜ぶことか、目に浮かぶようではないか。

















![医療機器販売の(株)ホクシンメディカル[兵庫]が再度の資金ショート](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FTsr%252Fa8%252FTsr_1198527%252FTsr_1198527_1.jpg,zoom=184x184,quality=100,type=jpg)
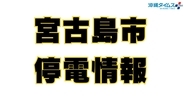











![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)


![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






