2000年の大統領就任以来、ロシアで実権を握り続けるプーチンとはどんな人物か。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんは「祖国復興の邪魔者は殺せばよいと思っている一方で、人情味を見せる場面もある」という。
■プーチンが忘れない「劣等民族」への転落
【黒井】プーチンは、エリツィンの後継者として出てきた時から、ロシア民族主義、愛国主義を語っています。当時、シロビキ(旧KGBなど治安・国防機関出身者)の仲間たちとやってきたこと、言ってきたことは、“共産主義ではない超大国=ソ連”の懐古主義です。
「強いロシアを再び!」ということで、トランプ風に言えばメイク・ロシア・グレート・アゲインです。民族主義というイデオロギー的なものより、もともと世界の超大国だった強い我が国を再び、という懐古意識が根底にあると見ています。
その原動力は、エリツィン時代の屈辱感だと思います。私がモスクワに住んでいたのは、ソ連末期のゴルバチョフ時代からエリツィン時代にかけての移行期の2年間なのですが、当時のロシア国民は自由を手にした解放感と同時に、ロシアが世界の破綻国家に堕ち、ロシア人が国際社会でまるで劣等な民族であるかのような扱いを受けた屈辱感を強く感じたと思います。
ソ連時代は、それは窮屈な監視社会ではありましたが、世界を“米帝”(アメリカ帝国主義)と分け合う世界のソ連でした。モスクワには世界中の共産国から留学生が集まっていました。それが、破綻国家となり、国民生活は破壊されました。欧州の白人世界で最も馬鹿にされる。ロシア国民そのものが、それこそ自虐ネタを日常的に口にするような時代でした。
そうしたなかで、プーチンと仲間たちは30代、40代を過ごしています。プーチンは、メイク・ロシア・グレート・アゲインの夢に向かって、本人たちは世直し意識で、国の立て直しをしていると、信じていると思います。やり方が、旧KGB仕込みの謀略まみれで、邪魔だと思ったら殺せばいい、としていることが大問題ですが。
【小泉】興味深い人物ですよね。出てきた時は、それほど彼に強い力はなかった。エリツィンに後継者として引っ張り上げられるのですが、モスクワの政界で大きな影響力は持っていませんでしたし、エリツィンには忠実な人物。エリツィンの取り巻きからはむしろ御(ぎょ)し易(やす)いと思われていましたよね。
■ヒトラーと同じ政治手法
【黒井】私は情報機関関係のニュースを追っていたので、プーチンがFSB(ロシア連邦保安庁)長官に引っ張り上げられた時くらいに初めて意識したのですが、当時のモスクワ政界では小物(こもの)でした。当時のモスクワ政界の中心はエリツィン派ですが、ほぼ全員が腐敗した汚職人脈でした。
他方、当時はSVR(対外情報庁)初代長官や外相、首相を歴任したエフゲニー・プリマコフの派閥がまだ力を持っていましたし、ユーリ・スクラートフ検事総長がエリツィンの汚職疑惑を追っていました。エリツィンは引退後の保身が最重要課題で、後継者候補となる首相ポストを頻繁にすげ替えますが、最後に無名だったプーチンを指名します。
しかし、プーチンはモスクワでFSB長官、首相、大統領代行と歴任する間に、着々と昔のKGB仲間を呼び寄せ、世直しの構想を練っています。
大統領になってすぐ、メディア王と呼ばれたオリガルヒ(寡占(かせん)資本家)のウラジーミル・グシンスキーを逮捕し、メディア支配に乗り出します。そして、オリガルヒとその背後にいる欧米西側主要国、それと強力なマフィアがいたチェチェン人を「敵だ!」と人々に提示して、愛国主義を煽動する。
政府内では治安機関系の組織からプリマコフ派を排除します。プロパガンダ宣伝、民族主義・愛国主義、敵認定の排撃煽動、治安機関強化と、ほとんどすべてがヒトラーの手法のコピーに見えます。
■コネがルールに優先するロシア社会
【小泉】プーチンは第1次政権時に相当に権力を固めましたね。石油王のミハイル・ホドルコフスキーに脱税の嫌疑をかけて会社を解体し、本人も投獄した。これでエリツィン政権期に権力を握ったオリガルヒたちを押さえつけたわけです。で、自分の権力に逆らわないオリガルヒたちには利権をごっそり与えて服従させました。
さらにプーチンの権力掌握で決定的だったのは、大統領の3選禁止の規定からメドベージェフに代行させた後に、大統領に再び戻ってきた2012年以降だと思います。誰もが「プーチン様には逆らえないよね」という空気は、あの時期から決定的だったかなと思います。
典型的なパトロン=クライアント関係ですね。
■現代に蘇ったロシア皇帝
【黒井】私が知っているゴルバチョフ末期からエリツィン時代は、それが突き抜けてましたが、そもそもソ連時代からそうですね。ヨーロッパよりちょっとアラブ世界と似ているかもしれません。
ロシアの今後を予測するということを考えた時に、主義主張のような建前の部分に加えて、権力内部の力関係の部分も重要です。それらを融合して予測する必要がありますが、そこが難しい。でも、特にこの十数年はどんどんプーチン重視になっていると思います。
【小泉】我々に見えるものがふたつあります。ひとつは国家としての建前があって、もうひとつはプーチンを中心とする裏事情。実際は両方あるのですが、だんだんプーチン個人の存在が圧倒的になってきたということでしょう。
【黒井】ニュース映像ですごく印象的だった場面があります。2014年にクリミアを勝手に併合した際のクレムリンでの集会です。プーチンが会場に降臨すると、ロシア政界の要人が全員、教祖を見るような目で一心不乱に拍手をして称(たた)えている。「ああ、彼は皇帝になったんだな」と、その光景はダイレクトに示していました。あれはちょっと異様でした。
【小泉】涙を流している人とかいましたね。
■暴君プーチンが犯した失敗
【黒井】マイダン革命後のクリミア奪取が、プーチンの皇帝化を決定的にしたと思います。振り返ると、マイダン革命自体はプーチンも想定外だったでしょうから、あの時はそこまでやる計画が最初からあったわけではないでしょう。
あの時は、とにかくロシア黒海艦隊の本拠であるセバストポリを守るという意識から策を講じたわけですが、米国が強硬に対応してこないのを予測して、強気の手を打ったら成功した。プーチンはそれまでもロシア国内や旧ソ連圏では強硬派でしたが、クリミア奪取の成功で、いっきに暴君化していったのかなという気がします。
【小泉】そうですね。プーチンはその延長で、ウクライナを手に入れたかったのでしょうね。
【黒井】プーチンのキャラクターの特徴をひと言で言うと、精神的マッチョ志向のナルシストだと思います。先ほど言ったように、原動力はメイク・ロシア・グレート・アゲインだと思うのですよね。それに加えて、ウクライナがロシアの一部だという思想は、もともとあったでしょう。
そんななか、国際的なパワーポリティクスの環境が変わり、西側がどんどん内向きになっていった。特に米国が、です。オバマと第1期目のトランプです。バイデンは国際社会への民主的な介入をやろうとしたのだけれど、アフガニスタン撤退時のドタバタを見れば、プーチンからするとたいして強敵でもない。
西側がもうそれほど怖くないなとなった時に、FSBが「ウクライナは簡単に落ちるだろう」という報告をプーチンに上げる。
■世にも珍しい“真面目”な権力者
【小泉】FSB報告書を提出したのが、FSB第5局長のセルゲイ・べセダです。FSBは本来は国内治安機関なのですが、旧ソ連は「国内」扱いでFSBも管轄しています。彼はその後、失脚したと言われていたのですが、ウクライナとの交渉の場にFSB顧問として出てきている。プーチンは、自分が任命した男を切るのは沽券に関わると考えているのでしょうね。
【黒井】ベセダの間違った報告を真に受けて自分が判断ミスをしたという論理は絶対に認めないです。なので、そもそものベセダの報告自体をなかったことにしたのでしょう。プーチンは、自ら公開の場に出てきて、自分の言葉で自分の決断の正しさを語る。その几帳面(きちょうめん)さは大きな特徴です。ソ連共産党の文化で育った原点みたいなものかと思います。
【小泉】変な方向の几帳面さは、ロシア人全体から感じますよね。
【黒井】そこはアラブにはないですね。アラブの独裁者もいちおう自己正当化を語りますが、雑ですし、誰も気にしません。「親分は好き勝手に決めて動くのが当然」「親分の考え? それは利益でしょ」くらいにみんな思っています。
【小泉】ただ、プーチンはけっこう、表向きには人情味があるようなことも言うのですね。ソ連時代の指導者にはなかったことです。2000年代のロシア人からすると、ソ連時代とは違うという印象になったでしょうね。
【黒井】褒めるわけではないのですが、プーチンは悪い意味で真面目です。自ら公の場に出てきて自分の言葉で話す。世界を見渡しても、人々を散々弾圧し、殺傷している権力者としては珍しいです。自分が出てきて、欺瞞と詭弁ではありますが、それなりに自分の選択、行動の辻褄(つじつま)を合わせようとします。
■プーチンとヒトラーの共通点
【小泉】本心っぽい面が垣間見えることもよくありますね。国民対話(編注:プーチン大統領が国民の質問に直接答えるイベント)も、8時間とかかけてカメラの前でやります。けっこうアドリブの質問もあって、プーチンもアドリブで対応しています。
【黒井】やっぱり悪い意味で、真面目で自分の言葉に責任を持つ。そういうところもヒトラーに似ていると思うのですよね。ヒトラーもきわめて悪い意味で、真面目ではありました。
でも、そういう性格ならなおのこと、自分で自分の非を認めませんから、戦争を自分からやめることは考えにくいです。ヒトラーもそうでしたが、そこが今回の“プーチンが始めた侵略戦争”が終わらない最大の原因だと思います。
【小泉】軍事的に見ても、ロシアは戦場では優位なんだけどウクライナという国を滅ぼせるような勝ち方はしていない。この点はそう変わらないでしょう。とすると、やはり双方の継戦能力が尽きて、より膠着の様相が強まるまで、なかなか戦闘は収束しないだろうという気がします。
変化を持たせられるとすれば政治の力ですが、トランプ政権はロシアに強力な制裁をかけてでも停戦を強要することを避けている。長期化の見通しがこの点からも予想されてしまうように思います。
----------
小泉 悠(こいずみ・ゆう)
東京大学先端科学技術研究センター准教授
1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー文芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』(ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)などがある。
----------
----------
黒井 文太郎(くろい・ぶんたろう)
軍事ジャーナリスト
1963年生まれ。横浜市立大学卒業。週刊誌編集者、フォトジャーナリスト(紛争地域専門)、『軍事研究』特約記者、『ワールド・インテリジェンス』編集長などを経て、軍事ジャーナリスト。専門は各国情報機関の最新動向、国際テロ(特にイスラム過激派)、日本の防衛・安全保障、中東情勢、北朝鮮情勢、その他の国際紛争、旧軍特務機関など。著書に『イスラム国の正体』(KKベストセラーズ)、『イスラムのテロリスト』『日本の情報機関』(以上、講談社)、『インテリジェンスの極意!』(宝島社)、『本当はすごかった大日本帝国の諜報機関』(扶桑社)他多数。近著に『プーチンの正体』(宝島社新書)がある。
----------
(東京大学先端科学技術研究センター准教授 小泉 悠、軍事ジャーナリスト 黒井 文太郎)
『国際情勢を読み解く技術』(宝島社)より、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。(第1回)
■プーチンが忘れない「劣等民族」への転落
【黒井】プーチンは、エリツィンの後継者として出てきた時から、ロシア民族主義、愛国主義を語っています。当時、シロビキ(旧KGBなど治安・国防機関出身者)の仲間たちとやってきたこと、言ってきたことは、“共産主義ではない超大国=ソ連”の懐古主義です。
「強いロシアを再び!」ということで、トランプ風に言えばメイク・ロシア・グレート・アゲインです。民族主義というイデオロギー的なものより、もともと世界の超大国だった強い我が国を再び、という懐古意識が根底にあると見ています。
その原動力は、エリツィン時代の屈辱感だと思います。私がモスクワに住んでいたのは、ソ連末期のゴルバチョフ時代からエリツィン時代にかけての移行期の2年間なのですが、当時のロシア国民は自由を手にした解放感と同時に、ロシアが世界の破綻国家に堕ち、ロシア人が国際社会でまるで劣等な民族であるかのような扱いを受けた屈辱感を強く感じたと思います。
ソ連時代は、それは窮屈な監視社会ではありましたが、世界を“米帝”(アメリカ帝国主義)と分け合う世界のソ連でした。モスクワには世界中の共産国から留学生が集まっていました。それが、破綻国家となり、国民生活は破壊されました。欧州の白人世界で最も馬鹿にされる。ロシア国民そのものが、それこそ自虐ネタを日常的に口にするような時代でした。
そうしたなかで、プーチンと仲間たちは30代、40代を過ごしています。プーチンは、メイク・ロシア・グレート・アゲインの夢に向かって、本人たちは世直し意識で、国の立て直しをしていると、信じていると思います。やり方が、旧KGB仕込みの謀略まみれで、邪魔だと思ったら殺せばいい、としていることが大問題ですが。
【小泉】興味深い人物ですよね。出てきた時は、それほど彼に強い力はなかった。エリツィンに後継者として引っ張り上げられるのですが、モスクワの政界で大きな影響力は持っていませんでしたし、エリツィンには忠実な人物。エリツィンの取り巻きからはむしろ御(ぎょ)し易(やす)いと思われていましたよね。
■ヒトラーと同じ政治手法
【黒井】私は情報機関関係のニュースを追っていたので、プーチンがFSB(ロシア連邦保安庁)長官に引っ張り上げられた時くらいに初めて意識したのですが、当時のモスクワ政界では小物(こもの)でした。当時のモスクワ政界の中心はエリツィン派ですが、ほぼ全員が腐敗した汚職人脈でした。
他方、当時はSVR(対外情報庁)初代長官や外相、首相を歴任したエフゲニー・プリマコフの派閥がまだ力を持っていましたし、ユーリ・スクラートフ検事総長がエリツィンの汚職疑惑を追っていました。エリツィンは引退後の保身が最重要課題で、後継者候補となる首相ポストを頻繁にすげ替えますが、最後に無名だったプーチンを指名します。
しかし、プーチンはモスクワでFSB長官、首相、大統領代行と歴任する間に、着々と昔のKGB仲間を呼び寄せ、世直しの構想を練っています。
大統領選の当日にはもうエリツィンからの電話を無視しています。
大統領になってすぐ、メディア王と呼ばれたオリガルヒ(寡占(かせん)資本家)のウラジーミル・グシンスキーを逮捕し、メディア支配に乗り出します。そして、オリガルヒとその背後にいる欧米西側主要国、それと強力なマフィアがいたチェチェン人を「敵だ!」と人々に提示して、愛国主義を煽動する。
政府内では治安機関系の組織からプリマコフ派を排除します。プロパガンダ宣伝、民族主義・愛国主義、敵認定の排撃煽動、治安機関強化と、ほとんどすべてがヒトラーの手法のコピーに見えます。
■コネがルールに優先するロシア社会
【小泉】プーチンは第1次政権時に相当に権力を固めましたね。石油王のミハイル・ホドルコフスキーに脱税の嫌疑をかけて会社を解体し、本人も投獄した。これでエリツィン政権期に権力を握ったオリガルヒたちを押さえつけたわけです。で、自分の権力に逆らわないオリガルヒたちには利権をごっそり与えて服従させました。
さらにプーチンの権力掌握で決定的だったのは、大統領の3選禁止の規定からメドベージェフに代行させた後に、大統領に再び戻ってきた2012年以降だと思います。誰もが「プーチン様には逆らえないよね」という空気は、あの時期から決定的だったかなと思います。
典型的なパトロン=クライアント関係ですね。
プーチンのパトロネージュを得られるかどうかですべてが決まっていく。縁故主義的ですが、もっともロシアは昔からそういう社会ではあります。コネで解決する。その巨大バージョンを、プーチンはやっているのかなと思うのですよね。ロシアではルールは絶対視されない。ルールより権力者の意向です。法に対するニヒリスティックな意識が強くあります。
■現代に蘇ったロシア皇帝
【黒井】私が知っているゴルバチョフ末期からエリツィン時代は、それが突き抜けてましたが、そもそもソ連時代からそうですね。ヨーロッパよりちょっとアラブ世界と似ているかもしれません。
ロシアの今後を予測するということを考えた時に、主義主張のような建前の部分に加えて、権力内部の力関係の部分も重要です。それらを融合して予測する必要がありますが、そこが難しい。でも、特にこの十数年はどんどんプーチン重視になっていると思います。
そういう意味では、予測がだんだんとしやすくなってはきています。
【小泉】我々に見えるものがふたつあります。ひとつは国家としての建前があって、もうひとつはプーチンを中心とする裏事情。実際は両方あるのですが、だんだんプーチン個人の存在が圧倒的になってきたということでしょう。
【黒井】ニュース映像ですごく印象的だった場面があります。2014年にクリミアを勝手に併合した際のクレムリンでの集会です。プーチンが会場に降臨すると、ロシア政界の要人が全員、教祖を見るような目で一心不乱に拍手をして称(たた)えている。「ああ、彼は皇帝になったんだな」と、その光景はダイレクトに示していました。あれはちょっと異様でした。
【小泉】涙を流している人とかいましたね。
■暴君プーチンが犯した失敗
【黒井】マイダン革命後のクリミア奪取が、プーチンの皇帝化を決定的にしたと思います。振り返ると、マイダン革命自体はプーチンも想定外だったでしょうから、あの時はそこまでやる計画が最初からあったわけではないでしょう。
あの時は、とにかくロシア黒海艦隊の本拠であるセバストポリを守るという意識から策を講じたわけですが、米国が強硬に対応してこないのを予測して、強気の手を打ったら成功した。プーチンはそれまでもロシア国内や旧ソ連圏では強硬派でしたが、クリミア奪取の成功で、いっきに暴君化していったのかなという気がします。
【小泉】そうですね。プーチンはその延長で、ウクライナを手に入れたかったのでしょうね。
【黒井】プーチンのキャラクターの特徴をひと言で言うと、精神的マッチョ志向のナルシストだと思います。先ほど言ったように、原動力はメイク・ロシア・グレート・アゲインだと思うのですよね。それに加えて、ウクライナがロシアの一部だという思想は、もともとあったでしょう。
そんななか、国際的なパワーポリティクスの環境が変わり、西側がどんどん内向きになっていった。特に米国が、です。オバマと第1期目のトランプです。バイデンは国際社会への民主的な介入をやろうとしたのだけれど、アフガニスタン撤退時のドタバタを見れば、プーチンからするとたいして強敵でもない。
西側がもうそれほど怖くないなとなった時に、FSBが「ウクライナは簡単に落ちるだろう」という報告をプーチンに上げる。
それで容易ならやってしまおうと判断したということだと思います。彼は自己正当化が最優先なので、失敗しても認めません。
■世にも珍しい“真面目”な権力者
【小泉】FSB報告書を提出したのが、FSB第5局長のセルゲイ・べセダです。FSBは本来は国内治安機関なのですが、旧ソ連は「国内」扱いでFSBも管轄しています。彼はその後、失脚したと言われていたのですが、ウクライナとの交渉の場にFSB顧問として出てきている。プーチンは、自分が任命した男を切るのは沽券に関わると考えているのでしょうね。
【黒井】ベセダの間違った報告を真に受けて自分が判断ミスをしたという論理は絶対に認めないです。なので、そもそものベセダの報告自体をなかったことにしたのでしょう。プーチンは、自ら公開の場に出てきて、自分の言葉で自分の決断の正しさを語る。その几帳面(きちょうめん)さは大きな特徴です。ソ連共産党の文化で育った原点みたいなものかと思います。
【小泉】変な方向の几帳面さは、ロシア人全体から感じますよね。
【黒井】そこはアラブにはないですね。アラブの独裁者もいちおう自己正当化を語りますが、雑ですし、誰も気にしません。「親分は好き勝手に決めて動くのが当然」「親分の考え? それは利益でしょ」くらいにみんな思っています。
【小泉】ただ、プーチンはけっこう、表向きには人情味があるようなことも言うのですね。ソ連時代の指導者にはなかったことです。2000年代のロシア人からすると、ソ連時代とは違うという印象になったでしょうね。
【黒井】褒めるわけではないのですが、プーチンは悪い意味で真面目です。自ら公の場に出てきて自分の言葉で話す。世界を見渡しても、人々を散々弾圧し、殺傷している権力者としては珍しいです。自分が出てきて、欺瞞と詭弁ではありますが、それなりに自分の選択、行動の辻褄(つじつま)を合わせようとします。
■プーチンとヒトラーの共通点
【小泉】本心っぽい面が垣間見えることもよくありますね。国民対話(編注:プーチン大統領が国民の質問に直接答えるイベント)も、8時間とかかけてカメラの前でやります。けっこうアドリブの質問もあって、プーチンもアドリブで対応しています。
【黒井】やっぱり悪い意味で、真面目で自分の言葉に責任を持つ。そういうところもヒトラーに似ていると思うのですよね。ヒトラーもきわめて悪い意味で、真面目ではありました。
でも、そういう性格ならなおのこと、自分で自分の非を認めませんから、戦争を自分からやめることは考えにくいです。ヒトラーもそうでしたが、そこが今回の“プーチンが始めた侵略戦争”が終わらない最大の原因だと思います。
【小泉】軍事的に見ても、ロシアは戦場では優位なんだけどウクライナという国を滅ぼせるような勝ち方はしていない。この点はそう変わらないでしょう。とすると、やはり双方の継戦能力が尽きて、より膠着の様相が強まるまで、なかなか戦闘は収束しないだろうという気がします。
変化を持たせられるとすれば政治の力ですが、トランプ政権はロシアに強力な制裁をかけてでも停戦を強要することを避けている。長期化の見通しがこの点からも予想されてしまうように思います。
----------
小泉 悠(こいずみ・ゆう)
東京大学先端科学技術研究センター准教授
1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー文芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』(ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)などがある。
----------
----------
黒井 文太郎(くろい・ぶんたろう)
軍事ジャーナリスト
1963年生まれ。横浜市立大学卒業。週刊誌編集者、フォトジャーナリスト(紛争地域専門)、『軍事研究』特約記者、『ワールド・インテリジェンス』編集長などを経て、軍事ジャーナリスト。専門は各国情報機関の最新動向、国際テロ(特にイスラム過激派)、日本の防衛・安全保障、中東情勢、北朝鮮情勢、その他の国際紛争、旧軍特務機関など。著書に『イスラム国の正体』(KKベストセラーズ)、『イスラムのテロリスト』『日本の情報機関』(以上、講談社)、『インテリジェンスの極意!』(宝島社)、『本当はすごかった大日本帝国の諜報機関』(扶桑社)他多数。近著に『プーチンの正体』(宝島社新書)がある。
----------
(東京大学先端科学技術研究センター准教授 小泉 悠、軍事ジャーナリスト 黒井 文太郎)
編集部おすすめ












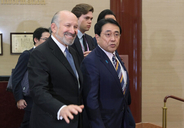


![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
