※本稿は、三宅香帆『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
■物語には“普遍的な要素”がある
話を普遍的なテーマとして語る技術である「不易」。
結局、古典こそが、強い。物語を読んでいるとしみじみそう思います。誰もが好きな普遍的な展開こそが、繰り返されているのです。
古典的なテーマを知れば知るほど、物語を読むことは面白くなる。
そしてどんな世代の人とも、話しやすくなる。
「あ、今この話をしているな」と、話の系譜が理解できるようになるから。
系譜が理解できるようになれば、一流の鑑賞者になったも同然ではないでしょうか。
ここでは「不易」の例を2つ紹介しましょう。
■『推し、燃ゆ』中心に展開する推しブームの話
最近、「推し」という言葉の功罪が語られるようになった。「推し」ブームも何周かまわった、といいましょうか。
なぜこの頃、「推し」はマイナスに語られがちなのか。そもそも「推し」とはポジティブなものではないのか。ここでは「推し」ブームの変遷を、出版物の言説から見るという試みに独断と偏見に基づき挑んでみる。
①「推しメン」の誕生(2011年頃)
「推しメン」がユーキャン新語・流行語大賞の候補語に選出されたのは2011年、今から10年以上も前のことだ。
この言葉ができた当時、世は空前のAKB48ブーム。つまり「推しメン」といえば、「多数のアイドルのなかで、自分が今いちばん『推したい』メンバーはこの子」という、選択肢が複数あることを前提とした語彙だった。
AKB48グループの特徴は、従来存在しなかった大人数のアイドルグループであること。たくさんいるアイドルたちを前にして、どの子を応援しようかな? どの子を応援していることを自らのアイデンティティにしようかな? と、アイドルを「選ぶ」行為こそが「推しメン」という言葉に込められていた。それはAKB48を人気にした「総選挙」という仕組みと繋がる。
批評家の宇野常寛は、当時のAKB48の在り方を「市場の暴走を肯定する装置」と捉えた(『原子爆弾とジョーカーなき世界』、メディアファクトリー、2013年)。
つまり「推しメン」とは、店頭に並ぶ商品から選び買うように、応援するアイドルを選択する行為を肯定する語彙だった。しかし後述するように、この「肯定」のムードは、長くは続かなかったのだ。
■「推し」と「オタク」の切っても切れない関係
②「オタク」の蜜月(2012~2019年頃)
2010年代のカルチャーシーンの特徴をひとことで表現するならば、「オタク」という言葉のメジャー化、に集約される。
2017年に話題になった『浪費図鑑 悪友たちのないしょ話』(劇団雌猫、小学館)は、さまざまなジャンルのオタクの女性たちによるエッセイを収録する。
この本のキャッチコピーは「これは『浪費』ではなく、『愛』です」。本書は「オタク」という語彙を「推しメンに多額のお金を遣う存在」と定義し、「労働を頑張りながら、稼いだお金を趣味に充てる女性」の生態を描き出す。
実際、本書に収録されている女性たちは、従来「オタク」として連想される男性や、コミュニケーション能力の低い存在としては描かれない。むしろ都会でしっかり働き、自立した女性として生きている様子が強調されているのだ。
しかし、この本のキャッチコピーでまだひとことも「推し」という言葉が使われていない。当時はまだ「オタク」という語彙こそが「推し」文化を代表する概念だった。
■コロナ禍で「推し」が普及
③「推し」ブームのメジャー化(2020~2022年)
そしてやってきたのが、コロナ禍である。私たちはステイホームを強いられ、従来のように飲み会などで他人と会いづらくなった。
メディアはその閉塞感を破るかのように、ひとりでできる趣味として「推し活」を流行させる。余暇はコミュニケーションではなく、趣味で埋めよう、と。
宇佐見りんの『推し、燃ゆ』(河出書房新社、2020年)は芥川賞を受賞した。若き女性作家の「推し」小説が評価され、売れたことで、「推しって、流行ってるんだね!」という印象を持った人もいるかもしれない。
一方で、この小説の面白いところは、あるアイドルを応援する少女の物語でありながら、彼女がセルフネグレクト状態に陥っている点である。
つまり『浪費図鑑』にあったような「稼いで、自立して、趣味にお金を遣うことのポジティブさを強調する」のではなく、本作は「推しを応援しながらも、自分自身を支えることができない内面の吐露」を主題とする。推しは、ただポジティブな言説では、もはやなくなっているのだった。
■「推しブーム」の揺り戻し
④「推し」がしんどい期(2023年~?)
カルチャー雑誌『ダ・ヴィンチ』2023年2月号の特集は「推しがしんどい~推しがいないのもしんどい~」。とうとう、「推しのマイナス面」が堂々と語られる時代になったのである。
そもそもコロナ禍の閉塞感を打ち破るものとして「推し活」が流行していたのを見ると、コロナ禍の緊張感がひと段落し、むしろ円安や増税に圧迫される社会に皆が目を向け始めたことで、「推しがしんどい」という空気が出てきたのかもしれない。
「推し」とは、AKB48を見るまでもなく、「多数の選択肢がある市場のなかで好きな存在を選ぶ行為」だ。市場が荒れやすい時期に、「推し」にも動揺が走りやすいのは当然である。
同じく2023年に刊行された『「推し」の文化論 BTSから世界とつながる』(鳥羽和久、晶文社)は、現代の「推し活」が資本主義に乗っかりつつ、資本主義に抵抗する葛藤を見せていることを明らかにする。
私たちの社会の景気と「推し」は相関する。
(2023年7月時点の原稿をもとに改稿)
■村上春樹作品の「普遍性」と話の広げ方
次は、「村上春樹」という“不確かな壁”について語ってみたい。
そう、村上春樹は壁である。どういう意味かといえば、村上春樹くらい、現代の作家にとって超えられない壁はないだろう……と『街とその不確かな壁』を読んで思ったのだった。
もちろん後続の作家にとっては、大江健三郎も田辺聖子も石原慎太郎も村上龍も偉大すぎて、決して「超えられそう感」のある壁ではない。戦後、日本の勢いがあった時代の小説家はそっくりその日本の勢いを小説に閉じ込めている。
現代の作家の、どれだけ衰退する日本のムードを背負っているんだ、私だって勢いのある時代に生まれたかったぞ、という恨み節がそこかしこから聞こえてきそうである。
だがそういう話とは別に、『街とその不確かな壁』は、村上春樹文学の「継承者」の問題を浮き彫りにしている。
というのも本書には“イエロー・サブマリンの少年”というキャラクターが出てくるのだが、彼が主人公のある仕事を引き継いでくれる場面が描かれるのだ。
主人公が著者自身のことを指すのだとすれば、少年は、村上春樹の子供――といっても血のつながった子供ではなく「自分の仕事を継承してくれる存在」――を暗示しているのではないだろうか。
つまり本作には、村上春樹自身による「誰が自分の仕事を継承してくれるのだろう?」という問いが書き込まれている。
■村上春樹の後継者は誰か
とはいえ、これって考えれば考えるほど難しい問題だ。
そして仲間としての村上軍団も作らないまま、自分は個であることをいつも主張していた。
私は彼の小説が好きですべて読んでいるのだが、日本の小説家で「おお、この人の書くものは村上春樹のDNAが入っているぞ」と思ったことは、ほとんどない。もちろん影響を公言している作家はたくさんいるが、だがしかしその作家の書くものが村上春樹的かというとそうでもないのだった。
村上春樹自身も小説の中で首をひねっていた「で、僕の問題意識を引き継いでくれる人って、誰かいるんでしょうか……?」問題に、私が候補を提示してみることにする。
① 新海誠(映画監督)
どうでしょうか、いけると思いませんか。
そもそも村上作品の大きな特徴は「たったひとりの愛するきみ/あなたを救う」ことが物語の目的に置かれているところだ。新海監督の映画はかなり近い主題を描いており、それでいて女性との関係性(性的描写は含まないところなど)はモダナイズされている。
私は『街とその不確かな壁』と通じ合う初期作『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を新海監督がアニメ化してくれないかな~とずっと密かに妄想している。すごく合うと思いませんか?
■村上春樹の話は文壇の外まで広げられる
② 常田大希(King Gnu/ミュージシャン)
歌手⁉ と思われるかもしれませんが、いや私は大まじめにKing Gnuはいま最も「村上春樹的文体」を大衆に届けている作家だと主張したいですね。
みなさん、『白日』は有名だから聴いたことがあるかもしれませんが、しっかり歌詞を読んでください。
小説で村上春樹の後継者を見つけづらいのは、あの軽やかでありながら不安定な「僕」文体を綴ることがかなり難しいからではないか。そういう意味で、同じような「僕」語りを作り出すのは、むしろ歌のほうが今は得意なように感じるのだ。
■村上春樹作品の「普遍性」
③ 池辺葵(漫画家)
突然の、女性漫画家。『プリンセスメゾン』『繕い裁つ人』などの人気漫画の作者であり、現在は『ブランチライン』を連載中である。
彼女が担うのは、村上春樹作品に特徴的な「ひとりで淡々と文化的な仕事をしていくぞ」という決意である。池辺葵の作品はいつも「女性が仕事と文化を通して生きる様子」を描く。その筆致は淡々としているが、裏側には並々ならぬ頑固さが宿る。
それはまるで村上春樹の主人公がひとりでパスタを茹で、仕事をまっとうする描写そのものなのだ。
……というわけで「きみを救う物語」は新海誠に、「『僕』語り文体」は常田大希に、「文化的ライフスタイル」は池辺葵に、それぞれ継承していただくのはいかがでしょうか。
と私なりの候補を出したところで、やっぱり村上春樹の偉大さって「物語構造」「文体」「生活」そのすべてにおいて新しかったところにあるのだと再確認。
“イエロー・サブマリンの少年”の荷はけっこう重いよなあ、みんなで仕事は分担しようよ、働き方改革だよ、と言いたくなってしまった。
(2023年6月時点の原稿をもとに改稿)
----------
三宅 香帆(みやけ・かほ)
書評家・文筆家
1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了。著書に『人生を狂わす名著50』(ライツ社)、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)、『副作用あります⁉ 人生おたすけ処方本』(幻冬舎)などがある。
----------
(書評家・文筆家 三宅 香帆)





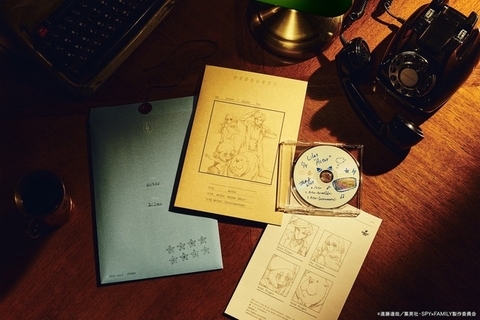







![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
