秋になると「気分が沈む」「やる気が出ない」「眠りが浅い」と感じる人が増えている。検査では異常がなくても、心と体のバランスが崩れているケースが少なくない。
■セロトニン不足が心身の不調を招く
厚労省「精神保健医療福祉の現状等について」の「令和5年(2023年)患者調査」によれば、日本の五大疾病(糖尿病、がん、心疾患、脳卒中、精神疾患)の中で最も患者数が多いのは精神疾患で、約603万人にのぼります。平成29年(2017年)の約419万人から大幅に増加し、ストレス社会の進行とともに「心の不調」が社会全体に広がっている現状が浮き彫りになっています。
心の不調を理解するうえで欠かせないのが「脳腸相関」という考え方です。腸は“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンをつくる工場。セロトニンは気分の安定や睡眠の質を左右する大切な物質です。腸の働きが落ちるとセロトニンの産生が減り、不眠・倦怠感・気分の落ち込みといった症状が現れやすくなります。つまり、秋のメンタル不調の本質は「気持ちの問題」ではなく、腸の不調から生じるセロトニン不足にあるのです。
秋は気温差が大きく、自律神経がもっとも疲れやすい季節です。その影響を最も受けやすいのが腸。私の外来でも、「なんとなく元気が出ない」と来院される方の多くが、腸の冷えや乱れを抱えています。
腸の温度が下がると、消化吸収力とセロトニン産生はともに低下します。逆に、温かい汁物や発酵食品を取り入れると腸が動き出し、自然と気分も上向くのです。心と体は常に連動しています。心の疲れを癒すためにこそ、まず「腸を温め回復させること」から始めてほしい――これが、私が秋の外来で最も伝えたいメッセージです。
■心をメンテナンスする旬の食材
腸を整えるには、毎日の食事が最大の治療になります。その手がかりは、意外にもスーパーの魚売り場にあります。
とくに秋におすすめなのが「戻りガツオ」。夏に北上して脂が抜けたカツオが、秋になると南下しながら身に栄養を蓄えて戻ってきます。赤身の旨みに脂がのった旬の味わい。まるで、夏に消耗した体を立て直すために“自然が戻してくれる魚”のようです。
戻りガツオには、セロトニンの材料となるアミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれています。加えて、それをセロトニンへ変換するビタミンB6、そして脳への酸素供給を助ける鉄分も多く含まれ、気分の安定や集中力の維持に役立ちます。
調理のコツは薬味との組み合わせ。ショウガやニンニク、青じそには血流を促し、腸を温める作用があり、ポン酢を合わせれば酸味が唾液を誘発して消化を助けます。私は患者さんに、「カツオのたたきにショウガと玉ねぎを添えて」とすすめています。火を使わず、スーパーで買える一皿が、そのまま“メンタルケアの食事療法”になるのです。
旬の一切れが、重たい気分を軽くする。私は診療を通して、食事が心に与える力を伝えています。
■世界の潮流は“全体を診る”
いま世界の医療現場では、「体の声」を多角的にとらえ、データと人の知恵の両輪で診る医療が進化しています。臓器ごとの専門を越え、複数の診療科や専門職が連携して患者を支える“チーム医療”が主流となりつつあります。
AIをはじめとする新しい技術を活かしながら、心と体を一つのシステムとして理解する――そんな「全体を診る」姿勢が、いまや世界共通の医療の潮流です。
私が所属する順天堂医院総合診療科も、まさに同じ理念。腸や自律神経の乱れを心の症状から切り離さず、必要に応じて専門医と連携し、患者さんの全体像を見ながら治療の道筋を立てていく。
たとえば「秋バテ気分」だと思っていた方が、実は腸の不調による軽いうつ状態であることも少なくありません。総合診療という入り口を持つことで、早期発見・早期改善につながるのです。
こうした“全体を診る視点”は、病院の中だけでなく、家庭の食卓にも通じます。医療の根底にあるのは、「一部を治す」ではなく「全体を診る」という発想。心と体を一緒に支える栄養をとることも、その一環です。
その意味で、秋が旬の戻りガツオは象徴的な存在。トリプトファン、ビタミンB6、鉄分――脳と腸のバランスを取り戻す要素を兼ね備え、まさに“全身の調和を実現する食材”です。
■医師自身の実践──“腸を整える”という習慣
私自身も、この“全体のバランス”という考え方を、食生活に取り入れています。診療・研究・子育てに追われる日々の中でも、「腸を整える食べ方」が心身の軸を支えています。
朝はお味噌汁や果物で腸を目覚めさせ、昼は軽めに、夜は温かい汁物や魚を取り入れる。季節のリズムに合わせて食を調えるだけで、心と体の歯車が噛み合うのを実感します。
五感で季節を味わうことも心がけています。
帰宅後の夜、私がよく作るのは、シンプルな料理です。野菜は野菜そのものに塩やゴマとオリーブオイル、醤油ゴマや塩昆布も活用します。これからの季節には、豚汁など「具だくさんの味噌汁」。根菜、豆腐、わかめを入れ、仕上げにすりゴマをひと振り。湯気と香りが立ち上る瞬間、体の奥から副交感神経が働きはじめます。
こうした習慣を続けていると、朝の目覚めが軽くなり、感情の波も穏やかになります。私は患者さんにいつも伝えます。「完璧を目指さなくていい。一切れの戻りガツオ、一杯の豚汁、その小さな積み重ねが、心を安定させる最大の治療です」と。
■日常に取り入れやすい“メンタル強化食材”──まごわやさしいこ
心と体の全体適正には、特別な食材や高価なサプリより、「続けられる日常の食事」が何より大切です。
関口さんが提唱する合言葉は、「ま・ご・わ・や・さ・し・い・こ」。ま=豆、ご=ゴマ、わ=わかめ(海藻)、や=野菜・果物、さ=魚、し=しいたけ(きのこ)、い=いも、こ=酵素(発酵食品)。このリズムのよいフレーズの中に、鉄・たんぱく質・ビタミンをバランスよくとる知恵が詰まっています。
関口さんから触発された私のメンタル強化食材を抜粋して、以下解説します。
1.旬の食材
旬の食材は美味しく、栄養も豊富。秋はきのこやさつまいもが代表ですが、戻りガツオはこの季節ならではの心強い一皿です。
2.果物(や=野菜、果物)
バナナとキウイがおすすめ。どちらもセロトニンの材料トリプトファンを含み、キウイはビタミンCでストレスに強い体をつくります。
3.魚(さ=魚)
魚は脳と心を支える栄養の宝庫。サンマやサバ、イワシなど青魚に含まれるEPA・DHAは神経細胞を守り、不安やイライラを和らげます。一方、カツオは刺身やたたきで手軽に食べられ、赤身魚ならではの力で“心の栄養”を補います。
4.発酵食品(味噌・納豆・ヨーグルト)(こ=酵素(発酵食品)
味噌汁、納豆、ヨーグルトなどの発酵食品は腸内環境を整え、セロトニン合成を助けます。少しでも毎日続けることが大切です。
5.豚肉
豚肉はビタミンB1と鉄を含み、脳のエネルギー代謝を助け、倦怠感や集中力低下を防ぎます。豚汁や生姜焼きなど、身近な料理で“心を整える栄養源”になります。
■今日の一切れが、明日の元気を支える
私たちの体は、食べたものでできています。だからこそ、「今日の一切れ」を大切にしてほしい。一切れの戻りガツオが、体の奥で血となり、心を穏やかにし、明日の元気をつくります。
秋は、心身が静かに回復へ向かう季節。自然が冬支度を整えるように、私たちの体も“整える季節”に入ります。焦らず、比べず、できることから。それが、秋のメンタル不調を乗り越えるいちばんの近道です。
そして何より大切なのは、こうした食べ方を「未来への投資」ととらえることです。資産形成と同じように、健康形成もアップダウンを繰り返しながら、積み重ねるほどに右肩上がりを描いていきます。毎日の小さな積み重ねが、明日のあなたを支えるのです。
心と体は決して切り離せない。腸を温め、血を巡らせ、感情を整える――それらはすべて“生きる力”を養う営みです。医療もまた、その延長線上にあります。治すだけでなく、育てる。診るだけでなく、支える。
食べるという行為の中に、人が自らの健康を取り戻す智慧がある。今日の一切れを味わうことは、明日のいのちを育てること。その静かな実践こそ、真に豊かな長寿への第一歩なのです。この秋、ぜひ戻りガツオをひと切れでも召し上がってください。
----------
齋田 瑞恵(さいた・みずえ)
順天堂大学医学部准教授
順天堂大学医学部(東京都文京区)総合診療科学講座准教授。順天堂医院総合診療科医局長。公益財団法人 星 総合病院(福島県郡山市)総合診療科。総合診療専門医、日本総合健診医学会・日本人間ドック学会人間ドック健診専門医、日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア指導医、日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医、日本東洋医学会会員、日本母性内科学会会員、日本病院総合診療医学会評議員、日本抗加齢医学会評議員。1男2女の子育てとイタリア在住経験を活かした女医ならではの総合診療に定評。外来は予約制。西洋と東洋医学の融合したコロナ後遺症外来、予防接種の啓発、生活習慣改善などを通じ「幸せなおじいちゃん、おばあちゃんになろう」をスローガンとする。総合診療専門医の育成にも注力。テレビ東京「主治医が見つかる診療所」、ビジネス誌『プレジデント』、『ウエッジ』などメディアでも活躍中。
----------
----------
高橋 誠(たかはし・まこと)
医療・健康コミュニケーター 病院広報コンサルタント
1963年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。ミズノスポーツ広報宣伝部、リクルート宣伝企画部、米国西海岸最大の製函会社でのパッケージ・デザイン営業・マーケティング(LA12年)、ゴルフ場経営(山梨2年)、学校法人慈恵大学広報推進室長(東京16年)を経て、2020年より現職。日米複数法人通算40年の広報宣伝業務を通じ、メディア・医療関係者と幅広い交流網を構築。現職にてメディアと医師をつなぐ。プレジデントオンライン「ドクターに聞く“健康長寿の秘訣”」、月刊美楽「幸せなおじいちゃん、おばあちゃんになろう」、月刊源喜通信「食と健康」で医療・健康コラムを連載中。主な出版プロデュースは『世界一の心臓血管外科医が教える 善玉血液のつくり方』(2025年、渡邊剛著、坂本昌也監修、あさ出版)、『心を安定させる方法』(2024年、渡邊剛著、アスコム)、『人は背中から老いていく 丸まった背中の改善が、「動ける体」のはじまり』(2025年、野尻英俊著、岡田あやこ体操監修)。趣味はゴルフ、ワイン(日本ソムリエ協会ワインエキスパート#58)。
----------
(順天堂大学医学部准教授 齋田 瑞恵、医療・健康コミュニケーター 病院広報コンサルタント 高橋 誠)
順天堂大学の齋田瑞恵准教授は「寒暖差による自律神経の乱れを甘く見ないほうがいい。特に腸の不調は心身の不調につながるので注意が必要だ」という――。(取材・文/医療・健康コミュニケーター 高橋誠)
■セロトニン不足が心身の不調を招く
厚労省「精神保健医療福祉の現状等について」の「令和5年(2023年)患者調査」によれば、日本の五大疾病(糖尿病、がん、心疾患、脳卒中、精神疾患)の中で最も患者数が多いのは精神疾患で、約603万人にのぼります。平成29年(2017年)の約419万人から大幅に増加し、ストレス社会の進行とともに「心の不調」が社会全体に広がっている現状が浮き彫りになっています。
心の不調を理解するうえで欠かせないのが「脳腸相関」という考え方です。腸は“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンをつくる工場。セロトニンは気分の安定や睡眠の質を左右する大切な物質です。腸の働きが落ちるとセロトニンの産生が減り、不眠・倦怠感・気分の落ち込みといった症状が現れやすくなります。つまり、秋のメンタル不調の本質は「気持ちの問題」ではなく、腸の不調から生じるセロトニン不足にあるのです。
秋は気温差が大きく、自律神経がもっとも疲れやすい季節です。その影響を最も受けやすいのが腸。私の外来でも、「なんとなく元気が出ない」と来院される方の多くが、腸の冷えや乱れを抱えています。
腸の温度が下がると、消化吸収力とセロトニン産生はともに低下します。逆に、温かい汁物や発酵食品を取り入れると腸が動き出し、自然と気分も上向くのです。心と体は常に連動しています。心の疲れを癒すためにこそ、まず「腸を温め回復させること」から始めてほしい――これが、私が秋の外来で最も伝えたいメッセージです。
■心をメンテナンスする旬の食材
腸を整えるには、毎日の食事が最大の治療になります。その手がかりは、意外にもスーパーの魚売り場にあります。
とくに秋におすすめなのが「戻りガツオ」。夏に北上して脂が抜けたカツオが、秋になると南下しながら身に栄養を蓄えて戻ってきます。赤身の旨みに脂がのった旬の味わい。まるで、夏に消耗した体を立て直すために“自然が戻してくれる魚”のようです。
戻りガツオには、セロトニンの材料となるアミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれています。加えて、それをセロトニンへ変換するビタミンB6、そして脳への酸素供給を助ける鉄分も多く含まれ、気分の安定や集中力の維持に役立ちます。
つまり、「材料」と「働き手」を同時に摂れる、“心を元気にする魚”なのです。
調理のコツは薬味との組み合わせ。ショウガやニンニク、青じそには血流を促し、腸を温める作用があり、ポン酢を合わせれば酸味が唾液を誘発して消化を助けます。私は患者さんに、「カツオのたたきにショウガと玉ねぎを添えて」とすすめています。火を使わず、スーパーで買える一皿が、そのまま“メンタルケアの食事療法”になるのです。
旬の一切れが、重たい気分を軽くする。私は診療を通して、食事が心に与える力を伝えています。
■世界の潮流は“全体を診る”
いま世界の医療現場では、「体の声」を多角的にとらえ、データと人の知恵の両輪で診る医療が進化しています。臓器ごとの専門を越え、複数の診療科や専門職が連携して患者を支える“チーム医療”が主流となりつつあります。
AIをはじめとする新しい技術を活かしながら、心と体を一つのシステムとして理解する――そんな「全体を診る」姿勢が、いまや世界共通の医療の潮流です。
私が所属する順天堂医院総合診療科も、まさに同じ理念。腸や自律神経の乱れを心の症状から切り離さず、必要に応じて専門医と連携し、患者さんの全体像を見ながら治療の道筋を立てていく。
たとえば「秋バテ気分」だと思っていた方が、実は腸の不調による軽いうつ状態であることも少なくありません。総合診療という入り口を持つことで、早期発見・早期改善につながるのです。
こうした“全体を診る視点”は、病院の中だけでなく、家庭の食卓にも通じます。医療の根底にあるのは、「一部を治す」ではなく「全体を診る」という発想。心と体を一緒に支える栄養をとることも、その一環です。
その意味で、秋が旬の戻りガツオは象徴的な存在。トリプトファン、ビタミンB6、鉄分――脳と腸のバランスを取り戻す要素を兼ね備え、まさに“全身の調和を実現する食材”です。
■医師自身の実践──“腸を整える”という習慣
私自身も、この“全体のバランス”という考え方を、食生活に取り入れています。診療・研究・子育てに追われる日々の中でも、「腸を整える食べ方」が心身の軸を支えています。
朝はお味噌汁や果物で腸を目覚めさせ、昼は軽めに、夜は温かい汁物や魚を取り入れる。季節のリズムに合わせて食を調えるだけで、心と体の歯車が噛み合うのを実感します。
五感で季節を味わうことも心がけています。
戻りガツオの鮮やかな赤や、さつまいもの香りは、見る・嗅ぐという感覚を通じて心を明るくします。食事は栄養を摂る行為であると同時に、感情を整える時間でもあるので、こどもたちのお弁当も色を意識するようにしています。
帰宅後の夜、私がよく作るのは、シンプルな料理です。野菜は野菜そのものに塩やゴマとオリーブオイル、醤油ゴマや塩昆布も活用します。これからの季節には、豚汁など「具だくさんの味噌汁」。根菜、豆腐、わかめを入れ、仕上げにすりゴマをひと振り。湯気と香りが立ち上る瞬間、体の奥から副交感神経が働きはじめます。
こうした習慣を続けていると、朝の目覚めが軽くなり、感情の波も穏やかになります。私は患者さんにいつも伝えます。「完璧を目指さなくていい。一切れの戻りガツオ、一杯の豚汁、その小さな積み重ねが、心を安定させる最大の治療です」と。
■日常に取り入れやすい“メンタル強化食材”──まごわやさしいこ
心と体の全体適正には、特別な食材や高価なサプリより、「続けられる日常の食事」が何より大切です。
その考えを具体的に教えてくれるのが、第1回でもご紹介した管理栄養士・関口絢子さんの新刊『食が細くなってきたら! 少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』(アスコム)です。
関口さんが提唱する合言葉は、「ま・ご・わ・や・さ・し・い・こ」。ま=豆、ご=ゴマ、わ=わかめ(海藻)、や=野菜・果物、さ=魚、し=しいたけ(きのこ)、い=いも、こ=酵素(発酵食品)。このリズムのよいフレーズの中に、鉄・たんぱく質・ビタミンをバランスよくとる知恵が詰まっています。
関口さんから触発された私のメンタル強化食材を抜粋して、以下解説します。
1.旬の食材
旬の食材は美味しく、栄養も豊富。秋はきのこやさつまいもが代表ですが、戻りガツオはこの季節ならではの心強い一皿です。
2.果物(や=野菜、果物)
バナナとキウイがおすすめ。どちらもセロトニンの材料トリプトファンを含み、キウイはビタミンCでストレスに強い体をつくります。
3.魚(さ=魚)
魚は脳と心を支える栄養の宝庫。サンマやサバ、イワシなど青魚に含まれるEPA・DHAは神経細胞を守り、不安やイライラを和らげます。一方、カツオは刺身やたたきで手軽に食べられ、赤身魚ならではの力で“心の栄養”を補います。
青魚と赤身魚を組み合わせれば、秋のメンタル不調に強い食卓が完成します。
4.発酵食品(味噌・納豆・ヨーグルト)(こ=酵素(発酵食品)
味噌汁、納豆、ヨーグルトなどの発酵食品は腸内環境を整え、セロトニン合成を助けます。少しでも毎日続けることが大切です。
5.豚肉
豚肉はビタミンB1と鉄を含み、脳のエネルギー代謝を助け、倦怠感や集中力低下を防ぎます。豚汁や生姜焼きなど、身近な料理で“心を整える栄養源”になります。
■今日の一切れが、明日の元気を支える
私たちの体は、食べたものでできています。だからこそ、「今日の一切れ」を大切にしてほしい。一切れの戻りガツオが、体の奥で血となり、心を穏やかにし、明日の元気をつくります。
秋は、心身が静かに回復へ向かう季節。自然が冬支度を整えるように、私たちの体も“整える季節”に入ります。焦らず、比べず、できることから。それが、秋のメンタル不調を乗り越えるいちばんの近道です。
そして何より大切なのは、こうした食べ方を「未来への投資」ととらえることです。資産形成と同じように、健康形成もアップダウンを繰り返しながら、積み重ねるほどに右肩上がりを描いていきます。毎日の小さな積み重ねが、明日のあなたを支えるのです。
心と体は決して切り離せない。腸を温め、血を巡らせ、感情を整える――それらはすべて“生きる力”を養う営みです。医療もまた、その延長線上にあります。治すだけでなく、育てる。診るだけでなく、支える。
食べるという行為の中に、人が自らの健康を取り戻す智慧がある。今日の一切れを味わうことは、明日のいのちを育てること。その静かな実践こそ、真に豊かな長寿への第一歩なのです。この秋、ぜひ戻りガツオをひと切れでも召し上がってください。
----------
齋田 瑞恵(さいた・みずえ)
順天堂大学医学部准教授
順天堂大学医学部(東京都文京区)総合診療科学講座准教授。順天堂医院総合診療科医局長。公益財団法人 星 総合病院(福島県郡山市)総合診療科。総合診療専門医、日本総合健診医学会・日本人間ドック学会人間ドック健診専門医、日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア指導医、日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医、日本東洋医学会会員、日本母性内科学会会員、日本病院総合診療医学会評議員、日本抗加齢医学会評議員。1男2女の子育てとイタリア在住経験を活かした女医ならではの総合診療に定評。外来は予約制。西洋と東洋医学の融合したコロナ後遺症外来、予防接種の啓発、生活習慣改善などを通じ「幸せなおじいちゃん、おばあちゃんになろう」をスローガンとする。総合診療専門医の育成にも注力。テレビ東京「主治医が見つかる診療所」、ビジネス誌『プレジデント』、『ウエッジ』などメディアでも活躍中。
----------
----------
高橋 誠(たかはし・まこと)
医療・健康コミュニケーター 病院広報コンサルタント
1963年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。ミズノスポーツ広報宣伝部、リクルート宣伝企画部、米国西海岸最大の製函会社でのパッケージ・デザイン営業・マーケティング(LA12年)、ゴルフ場経営(山梨2年)、学校法人慈恵大学広報推進室長(東京16年)を経て、2020年より現職。日米複数法人通算40年の広報宣伝業務を通じ、メディア・医療関係者と幅広い交流網を構築。現職にてメディアと医師をつなぐ。プレジデントオンライン「ドクターに聞く“健康長寿の秘訣”」、月刊美楽「幸せなおじいちゃん、おばあちゃんになろう」、月刊源喜通信「食と健康」で医療・健康コラムを連載中。主な出版プロデュースは『世界一の心臓血管外科医が教える 善玉血液のつくり方』(2025年、渡邊剛著、坂本昌也監修、あさ出版)、『心を安定させる方法』(2024年、渡邊剛著、アスコム)、『人は背中から老いていく 丸まった背中の改善が、「動ける体」のはじまり』(2025年、野尻英俊著、岡田あやこ体操監修)。趣味はゴルフ、ワイン(日本ソムリエ協会ワインエキスパート#58)。
----------
(順天堂大学医学部准教授 齋田 瑞恵、医療・健康コミュニケーター 病院広報コンサルタント 高橋 誠)
編集部おすすめ











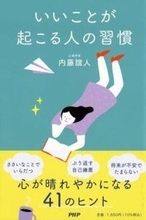


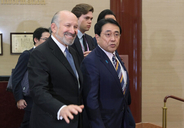


![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
