※本稿は、山下明子『食べる瞑想』(三笠書房)の一部を再編集したものです。
■食欲をコントロールする「ひと呼吸」
本稿では現代人が陥りがちな「食べすぎ」問題について、「食べる瞑想」が大変に効果的であることを解説していきたいと思います。
「今、息を吸っている」
「今、息を吐いている」
このように、一つひとつの呼吸に対して気づくこと。これが呼吸瞑想です。
呼吸瞑想は「フォーカス・アテンション瞑想」と呼ばれる種類の一つです。フォーカス・アテンション瞑想とは、その名の通り、一つの対象に意識を集中し続ける瞑想のこと。呼吸瞑想の場合は、自分の「呼吸」がその対象となります。
呼吸瞑想をすることで「今、自分の意識がどこにあるのか」に気づけるようになり、背外側前頭前野(DLPFC)の働きが高まります。背外側前頭前野は、集中力や注意力、問題解決力や自己コントロール力を司っている部位でしたよね。
つまり、呼吸瞑想を習慣にすることで、目の前にあるものに飛びついてしまうような衝動的な行動を抑え、少し先の未来の自分を見据えた食選択ができるようになるのです。早速、実践してみましょう。
■鼻腔を通り抜ける空気の流れを感じる
Work 基本の呼吸瞑想
座って軽く目を閉じます。
息を吸いながら、鼻腔(びくう)を通り抜ける空気の流れを感じます。
息を吐きながら、鼻腔を通り抜ける空気の流れを感じます。
息を吸いながら、幸せを感じます
(幸せが感じられなくても、感じようとしてみてください)。
息を吐きながら、体の力が抜けてリラックスするのを感じます。
ここまでを繰り返します。
事前にやりたい時間だけタイマーをかけておいてもいいでしょう。
■呼吸瞑想は「食べすぎ」を防ぐ
呼吸瞑想をしていると、次第に呼吸のスピードが落ち、ゆったりと安定した呼吸に変化していきます。そして、自律神経が整います。
自律神経には活動時に優位になる「戦闘モード」の交感神経と、休息時に優位になる「休息モード」の副交感神経がありますが、忙しいスケジュールや絶え間ない騒音、膨大な情報の波の中で生きる現代の私たちは、知らず知らずのうちに緊張が高まり、交感神経が働きすぎる傾向にあります。
この交感神経が優位な状態が続くと、自然と食欲が増進し、過食が起こりやすくなってしまいます。つまり、現代人は「食べすぎ」の傾向にあるわけです。
だからこそ、呼吸瞑想を習慣にすることは非常におすすめです。
呼吸瞑想によって自律神経を整え、副交感神経が優位になることで、ダイエット中にイライラして暴食してしまったり、満腹なのについ間食してしまったりして後悔する、なんてことを上手に避けられるようになります。
さらに、自律神経が整うと、胃腸の働きも自然とよくなります。その結果、食事そのものをより美味しく、心ゆくまで楽しめるようになるのです。
■呼吸瞑想のコツは「がんばらない」
そうは言っても、呼吸瞑想は数回試しただけで劇的な変化が起こるものではありません。毎日繰り返し行い、日々の習慣にすることによってはじめて、徐々にその効果を実感できるようになります。
「よし! 今日から毎日がんばるぞ!」
今、こう思った人は、ちょっとお待ちください。
呼吸瞑想は意気込みすぎたり、明確な目標を設定したりすると、かえってうまくいかなくなります。これは、医師としての長年の経験から断言できます。
くれぐれも、がんばらないでください。
「とりあえず、ちょっとやってみよう」くらいのつもりで実践してみましょう。
より深く集中して呼吸瞑想を行いたいときは、静かに座れる時間と場所を確保してください。
■おすすめは「食事前にひと呼吸」
呼吸瞑想を5~20分行うことで、脳からα(アルファ)2波が出現し、心身ともに深いリラックス状態になることがわかっています。
さらに、このα2波によって脳の状態が整えられると、その後の時間にもいい影響が及びます。例えば、朝起きた直後に行えば心穏やかな日中を過ごすことができ、夜寝る前に行えばぐっすり安心して眠ることができるのです。
朝や夜に時間を作るのが難しい人や、続けられる自信がない人は、一日たったひと呼吸でも実践する工夫をしてみましょう。ひと呼吸なら10秒程度で終わります。
例えば、パソコンが起動するまでの時間や歯磨きの前、入浴時など、日々のルーティーンの中に「ひと呼吸」だけでも取り入れてみてください。
特に、食べすぎで悩んでいる人や、食事中に考え事をしたり、ついスマホを触ってしまったりする人におすすめなのは、食事の直前に呼吸瞑想を行うことです。
先ほどもお伝えしたように、交感神経が活発な状態で食事をすると、胃腸の働きが悪くなるうえに、早食いになってしまいます。すると胃腸に負担がかかってしまいますし、満腹になる前に適量以上を食べてしまい、カロリーオーバーになる恐れもあります。
「食事前には、少し呼吸を整える」
がんばろうと意気込む必要はありませんが、食べすぎの傾向にある人は、このことだけでも頭の片隅に入れてみてください。
■「食欲ジャック」を解き明かす方法
ついつい間食や夜食に手が伸びてしまうこと、ありますよね。
毎日不定期に間食をしている人は「どんなときに食べたくなるのか」「どんなきっかけが自分を突き動かしているのか」を一度振り返ってみることが大切です。
さて、あなたは次の五つのような状況で、必要以上にお菓子を食べてしまった経験はありませんか?
●動画やテレビを見ながら、スナック菓子を食べていた
●周りの人につられて、目の前のおやつに手を出した
●怒りがおさまらず、お菓子をいくつも食べた
●仕事をしながら、お菓子で小腹を満たした
●勉強をしながら、机の上に置いていたお菓子を食べた
もし心当たりがあるなら、そのときのことを思い出してみて、続けて次の質問にも答えてみてください。
そのとき食べたお菓子は、どんな味でしたか?
どうでしょうか。
食べたはずのお菓子の味が、うまく思い出せないのではないでしょうか。
味をしっかりと感じ取れていないのであれば、それは「食べる瞑想」の観点からすると、あまりよくありません。意識せずに口に入れているということは、本当に体が欲して食べているわけではないからです。
■「甘いものを爆食い」を止める自分への問い
間食をしたくなるきっかけの多くは「突発的な感情」や「無意識の習慣」です。感情の波や周囲の行動に影響されて食行動が始まるとき、私たちは「食べている」という自覚すらないこともあります。
もし最近、間食しすぎていると感じたら「そもそも、なぜ食べたくなったのか」について深く考えてみましょう。次のように自分自身に問いかけていくと、思わぬ本心に出会えることがあります。
自問自答の例
いつ、どこで、つい食べてしまったのですか?
→食後に自宅で間食をしてしまった
何を、どのくらいの量食べましたか?
→クッキーを7枚食べた
食べたその日、どんな出来事がありましたか?
→頼まれていた仕事がうまくいかなかった
食べるとき、どんな感情がありましたか?
→甘いもので気分を上げたかった
このような食行動の振り返りを行う習慣をつけると、次に同じような行動をしそうになったときに「どうして食べたくなったのか?」という問いが自然と頭に浮かぶようになります。
先の例では、「仕事がうまくいかなかったこと」が間食の引き金になっていることがわかります。つまり、また間食をしてしまいそうなときに「仕事のストレスを間食で打ち消そうとしているだけだ」と自身で認識できるようになるのです。
このような自問自答によって、自分の食行動を俯瞰的な視点で捉えることができたら、最後に次の問いを自分に投げかけてみてください。
「それは一時的な快楽か? それとも本当の幸福か?」
人の脳は、甘いものや美味しいものを食べると快楽を感じるようにできています。そのため、快楽でストレスを打ち消そうとするのは自然なことです。
だからこそ、食欲にジャックされている自分自身にいち早く気づき、その衝動に振り回されない工夫をしましょう。
Work 食欲の理由を明らかにする
この二、三日で、無自覚な食事をしましたか?
心当たりがある人は、次の質問に答えてみましょう。
質問 1
いつ、どこで、つい食べてしまったのですか?
質問 2
何を、どのくらいの量食べましたか?
質問 3
食べたその日、どんな出来事がありましたか?
質問 4
食べるとき、どんな感情がありましたか?
質問 5
食べた後、どんな気持ちになりましたか?
質問 6
それは一時的な快楽でしたか? 本当の幸福でしたか?
----------
山下 明子(やました・あきこ)
医学博士
佐賀県生まれ。医療法人社団如水会今村病院副院長。脳神経内科医として6万人もの生活習慣病患者を診察し、「健康づくりを指導する専門家」として多くの信頼を集める。薬ばかりに頼るのではなく、一人ひとりが主体的に健康になれるよう、Well-being、マインドフルネス、栄養、運動、睡眠、脱依存、習慣化を組み合わせた多角的なアプローチを提唱。日本人間ドック学会専門医、日本抗加齢医学会専門医など、専門資格も多数。
----------
(医学博士 山下 明子)




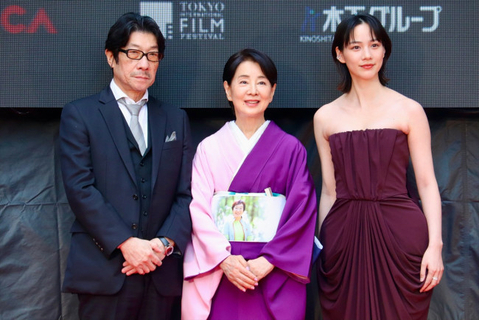
















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
