※本稿は、ローラ・L・カーステンセン(著)、米田隆(監修)、二木夢子(訳)『スタンフォード式 よりよき人生の科学』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
■貯蓄ができないのは脳のせい
もし借金を抱えていたり、わずかな貯金をつくれていなかったりで、老後が心配だとしても、それはあなただけのせいではない。これも脳のせいだ。認知科学の成果ははっきりしている。将来に向けて貯蓄できない理由は、実際に歳をとった自分を想像するのが難しいからだ。たとえ貯蓄していたとしても、たいてい金額が不足している。
一般的に、将来の自分を現在の自分より禁欲的で、少ないお金で生きられるとイメージするからだ。夫婦は、配偶者が亡くなったあとに必要なお金をかなり低く見積もりがちだ。生き残ったほうはあまりぜいたくをしないだろう、と考えてしまう(パートナーがいないとすっかり落ち込んでしまうと考えるらしい)。これまでの半分の金額しかいらないと思いがちだが、たとえ1人で暮らし、1人で車に乗るとしても、住宅ローンや車のローンは半額にならない。
若いころにお金に苦労していた人でさえ、引退後の収入はさらに低いのに、それで十分に心地よく過ごせると考えてしまう。結局のところ、お年寄りにそんなにお金がいるだろうか、と思ってしまう。
老後に必要な最低限の収入を計算してみてほしいと尋ねると、たいてい、かなりつつましい金額が返ってくる。本当に80歳になってその金額で生きていけるのかと聞くと、なんとかやりくりするよ、という答えが返ってくる。では、その金額でいま生活できるのか、と確認すると、「とんでもない」と言う。論理的には意味が通っていない。でも、認識のうえでは、私たちはいつもこうしているのだ。
■人間は“将来を過小評価する”癖がある
人々は一般的に、現在の価値を過大評価し、将来の価値を過小評価する。この想像力の欠如を、社会科学の用語で「遅延価値割引」という。お金に関する意思決定において、非常によく見られる現象だ。何人もの人に、今日10ドル欲しいか、来週12ドル欲しいかと尋ねてみると、お金が少なくなるにもかかわらず、すぐに10ドルもらうほうを選ぶ人が多い。
「つかまえた1羽の鳥は、藪のなかにいる2羽の価値がある」ということわざが思い浮かぶ。
このように明らかに不利な取引に陥ってしまうのは、なぜだろうか? たいていの方針を決定する際に、私たちは現在の自分に報い、痛みを先延ばしして将来の自分に負わせる傾向がある。いまケーキを一切れ食べてダイエットを来年に延ばしたり、いまたばこを吸って禁煙を後日に延ばしたりするのと同じように、いまお金を使って後日ツケを払う。いまぜいたくな生活をして、将来の自分に少ないお金でやりくりさせるのだ。
■「45年後の自分のイメージ」を見てもらう実験
現在の自分と未来の自分との溝が心理学的に深く埋め込まれているのだとしたら、この溝を埋めるために何かできることはあるだろうか。
スタンフォード大学の元大学院生で、心理学の研究を私と共同で行い、現在はニューヨーク大学で准教授としてマーケティングを教えているハル・ハーシュフィールドは、何か方法があるのではないかと考えている。ハーシュフィールドは最近、スタンフォード大学でコミュニケーション学の教授を務めるジェレミー・ベイレンソンと共同で、仮想現実(バーチャルリアリティ)を活用して未来の自分自身への理解を改善する研究を始めた。
まず、若いボランティア被験者の同意を得て、3Dアニメーションで各被験者のアバター(コンピューター上に再現した自分の分身)を制作した。次に、被験者にVRヘルメットを被ってもらい、コンピューターによって生成された「鏡」をのぞき込んでもらった。
ここからがおもしろい。対照群の人々[実験の効果を比較するための基準となる人々]には、実年齢に合わせた自分そっくりのアバターが見えたのに対して、残りの人々は鏡に映る「45年後の自分」を見ることになるのだ。
■“自分の老け顔”を見せたら、貯蓄の意欲が増した
彼らのアバターは電子処理によって老け顔になっている。髪は白くなり、頬は垂れ下がっていて、目の下のたるみには触れないほうがいいが、それでも自分だというのはわかる。
それからハーシュフィールドは被験者に、鏡のなかのバーチャルな自分とのつながりを感じるような一連の作業をさせた。もやのかかったイメージではなく、間近で「未来の自分」を見たことで、被験者たちはこの新たな自己イメージと感情的なつながりを感じるようになった。現実のものではなくても、歳をとった自分自身を文字どおり可視化してつながりを感じると、将来への備えが変化することが、研究によって示唆された。
実験の最後に、被験者は思いがけず手に入った1000ドルの使い道をどう割り振るかを尋ねられた。興味深いことに、鏡で未来の自分を見た被験者のほうが、退職後にとっておく金額が大幅に多かった。ハーシュフィールドは、未来の自分を他人として見なくなり、感情的なつながりが形成されるようになると、人々は貯蓄を始める、と考えている。
ただし、私たちには多数派に従う傾向もあり、そのことも貯蓄をしない方向に作用する。
■政府が“悪いお手本”になっている
さらに悪いことに、連邦政府もたいしてよい見本になっていない。保守派の人たちは長年、政府は一般家庭と同じように予算を扱い、手持ちのお金だけを使うべきだと主張してきた。
ところが、いまや家庭のほうが政府のようなお金の使い方をしている。国のように大量の借金を抱えているのだ。何かを買えなければカードを出せばいい。限度額に達したらもう1枚カードをつくればいい、というわけだ。
いつの日か支払い期限が来ることを気にもとめず、いますぐに買えないものをどんどんカードで買っている(ある「賢い」友人が、ようやく家族ぐるみでクレジットカードの使い方をコントロールできるようになったと教えてくれた。欲しいものが買えないときだけ使うことにしたのだそうだ)。
たいていのクレジットカード会社は高い金利を設定している。そのため、カードの利用者は長い目で見ると損をしていて、来週12ドルをもらう代わりに今週10ドルを使うようになっている。
■「確定拠出年金」は老後の貯蓄に活用できる
2008年から2009年の大不況では、年金の積み立て口座から前倒しで引き出して住宅ローンを支払う羽目になり、老後の貯えが減ってしまう人が出た。このような人は、年金生活に入ったあと、予想外の出費をしたり、高齢者によく必要になる人手(側溝の葉っぱの掃除、私道の雪かきなど)を雇ったりする余裕が少なくなる。そして、特別なお祝いや旅行といった、必須ではないが喜びをもたらしてくれる費用を節約しなければならなくなる可能性も高い。
ただし、ほとんどの国民は、貯蓄の機会がないわけではない。
多くの雇用主は、フルタイムの従業員にとても気前のよい制度を用意している。雇用主が課税猶予型の401k(確定拠出年金)を給与からの天引きで積み立ててくれるので、習慣の1つとして楽々貯められる(編集部注:日本でも導入している企業は多い 厚生労働省「確定拠出年金制度」)。
それだけでなく、従業員の拠出額に対して一定の割合を上乗せしてくれる場合もある。とても有利な制度にもかかわらず、資格があるのに加入しない従業員が多い。
■“断らないかぎり加入”は巧みである
経済学者は一見すると非論理的なこの行動に困惑するが、これもまた、人間がもつ現状維持へのバイアスの1つの例にすぎない。『NUDGE 実践 行動経済学 完全版』(日経BP)の著者であるリチャード・セイラーとキャス・サンスティーンは、従業員が自発的に401k制度に登録し、給与に対する拠出割合やファンドの銘柄などのやや面倒な判断を行わなければならないところに問題があると指摘する。言い換えると、制度への登録によって、現状維持を超えた行動を選ぶ必要があるということだ。
しかし、セイラーとサンスティーンによると、会社が自動的に従業員を登録し、利用を辞退する場合に従業員が手続きをする制度にすれば、参加率は飛躍的に上昇するという。心理学者は、デフォルト値(初期値・既定値)には基準に関するメッセージが含まれる、という言い方をする。
つまり、会社から「みなさんが断らないかぎりこの制度に加入してもらいます」と伝えるようにすれば、老後に備えた貯蓄はほとんどの人がやっている適切な選択だという考え方が伝わる。しかし、従業員の側に加入する負担をかけると、貯蓄が必ずしもやらなくてもいい行動、あるいは特別な行動である、という基準が伝わってしまう。
■“手取りを変えない仕組み”を導入する企業もある
さらに、プロセスをルーティン化し、お金をとっておく判断を何度も従業員にやらせないようにすれば、貯蓄のせいでお金を「失った」という感覚にともなう痛みも多少は消えるだろう。
一部の職場では、「セーブ・モア・トゥモロー(明日はもっと貯めよう)」という制度を提供している。この制度に合意すると、昇給のたびに退職金の積み立てが増え、手取りの給与は比較的同じ水準にとどまる。同僚よりもたくさん貯められるだけではなく、お金を「失った」感覚を味わわなくてすむ。
つまるところ、アメリカ文化がいま直面している問題は、貯蓄の優先順位を下げ、明日が来ないかのような消費をするよう、人々に教えてしまったことだ。実際には、どの世代よりも長い「明日」が来るにもかかわらず、である。社会保障制度があるので引退後は悠々自適で安定した生活を送れる、と国民に約束してしまったが、社会保障制度は実際には最低限のサポートしかしてくれない。
■“金欠で働かざるを得ない老後”はつらい
退職を控えるベビーブーマー世代の資金繰りが苦しいのは、貯金しそびれたから、企業年金がほとんどなくなったから、といった理由だけではない。クレジットカードなどの消費者債務がまだ続いていたり、住宅バブルのときに借金したローンがまだ返せていなかったりするからだ。2008年の経済危機では、貯蓄をしていた人すら金銭的問題に直面した。株価が下がり、多くの人の退職貯蓄が目減りしてしまったからだ。
私たちは、お金について不安を感じる退職者の世代を抱えるリスクがある。政府も国民と同じぐらい熱心に借金生活に入っている状況では、なおさら問題だ。
私は一貫して、体が健康な人はもっと長く働けるし、働くべきだと提唱してきた。彼らが仕事を刺激的でやりがいのあるものだと感じるだろうと期待してのことだ。しかし、お金がないために高齢まで長く働かざるをえない未来は、じつに暗い。
(参考文献)
・人々は貯蓄を始める:Ersner-Hershfield, H., Goldstein, D., Sharpe, W. F., Fox, J., Yeykelis,L., Carstensen, L. L., & Bailenson, J. N. (in press). Increasing saving behavior through age-progressed renderings of the future self. Journal of Marketing Research.
----------
ローラ・L・カーステンセン
スタンフォード大学心理学部教授
カリフォルニア州ロス・アルトス・ヒルズ在住。スタンフォード大学フェアリー・S・ディキンソン・ジュニア記念講座公共政策学教授や、同大学長寿研究所の設立者で所長も務める。カーステンセン博士の研究は20年以上にわたってアメリカ国立老化研究所から支援を受けている。グッゲンハイム・フェロー、アメリカ国立衛生研究所(NIH)メリット賞受賞者、マッカーサー財団高齢化社会ネットワーク会員でもある。
----------
(スタンフォード大学心理学部教授 ローラ・L・カーステンセン)













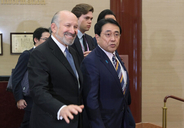


![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
