※本稿は、太田省一『とんねるずvs村西とおる』(双葉社)の一部を再編集したものです。
■独特な話術を手に入れるまで
村西とおるの本名は草野博美。1948年、福島県いわき市に生まれた。いわゆる団塊の世代、テリー伊藤と同じ世代になる。
父親は国鉄(現・JR)や常磐炭鉱で働いていたが、村西が生まれた頃にはすでに辞めて自営業を始めていた。だがそれもこうもり傘の修理をする行商のような仕事で、一家の生活はずっと貧しく苦しかった。村西も小学校から高校まで新聞配達などアルバイトをしていた(村西とおる『ナイスですね』、46‐48頁、54頁)。
中学を卒業後、福島県立勿来工業高校機械科に入学。だが学校の勉強をいくら懸命にやっても将来はたかが知れていると思い、まったくしなくなった。その代わり、小説などを手当たり次第に読みふけり、人生についてひたすら考えた。そして、「日本で有数の人間になりたい」「おれと会って三分話をしたら向こう三年絶対忘れられない人間になってやろう」と強く念じるようになった。
この言葉からは、ベビーブームのなか同世代人口が圧倒的に多かった団塊の世代ならではの競争意識の高さが伝わってくる。競争を勝ち抜くうえで村西とおるにとって最大の武器になった話術を磨く原点もまた、そこにあったと言えるだろう。
■英語の百科事典の販売で全国トップに
1967年、高校卒業とともに上京。池袋にある「どんぞこ」というスナックでバーテンになった。「日本で有数の人間」になるため一攫千金を狙う一方で、学歴も資格もない村西青年にとって考えられる選択肢がそれだったのである。
スナックと言っても「どんぞこ」は当時の老舗。地下から2階まであるつくりで、バンドなども入っているような大型店舗だった。ただ店員のほとんどは入れ墨が入っているような男たち。そこで村西は3年ほど働き、埼玉・川口にある系列のパブに支配人として赴任する。その頃、最初の結婚もした(同書、71‐72頁)。
だが夜の水商売の過酷さもあり、村西は22歳の頃に転職する。
しかし、ここで村西は驚くべき才覚を発揮する。当時、その会社には全国に6000人ものセールスマンがいて、契約数コンテストがおこなわれていた。村西が入社時は10週あるうちのすでに6週目の段階。ところが、村西は残りの4週だけでいきなり全国トップになったのである。(同書、74‐75頁。本橋信宏『全裸監督』、77頁)。
■悪魔的なセールストーク
村西とおるは、自らを「論理の天才」と豪語する。相手が「高い」「二、三日考える」「いますぐ決められない」「必要性を感じない」など難色を示す。セールスにはよくあることだ。
そんなときのために村西が身につけ、駆使したのが「応酬話法」である。
相手が「高い」と言えば、「お客さま、高いとか安いとかは比較の問題でございます」と即答し、その場にあるものなどを適当に使って例を持ち出す。たとえば、訪問先にたまたまあった電話を使ってこんな話をする。この電話が100万円するとする。それだけ聞けば確かに「高い」となる。だが高度情報化社会になった日本において、電話は必需品。「電話1本遅れたために1億2億のビジネスが吹き飛ぶことだってあるんでございます」と言い放つ。そして、この英語のソノシート付きのエンサイクロペディアが果たして高いのか、いや決してそうではないという流れに持っていく。村西はこうした臨機応変な話法のパターンを何十も持っていて、それを駆使した(同書、75‐76頁)。
■うっかりヤクザに声をかけてしまい…
あるときなど、街頭キャンペーンでうっかりヤクザに声をかけてしまった。
このように表面的には“馬鹿丁寧”とも言える慇懃な口調でありながら、実はしたたかなセールストークこそが、後に村西がAVのなかで駆使した「村西節」の土台であった。需要など本来なかったところに需要を作り出してしまうわけである。AV女優にも言葉の洪水を浴びせ、事前に想像していなかったような大胆なことまでさせてしまう。詐欺師的と言ってもよい。
こうして商才を発揮し始めた村西は、その後もさまざまな商売に手を出す。30歳手前のとき、喫茶店に置かれた当時流行のテレビゲームの台を扱って大儲けするなどもした(同書、84‐85頁)。
そんな頃出会ったのが、ビニ本である。「ビニ本」とは、一般的なヌードグラビアよりも過激な写真を載せた、いわゆるエロ本の一種。ただ陰毛と性器は見せず、その部分は黒塗りにされている。立ち読み防止のためにビニールで包装されていたことからこの名がついた。
■金銭へのどぎつい執着
ある日、新宿歌舞伎町にあるアダルトショップに何気なく入った村西はビニ本を発見する。ひとりの男性として性的に興奮(オキシドールで買ったビニ本の黒塗り部分を消そうとした)すると同時に、「これはひとつ商売しなきゃいけない」と奮い立った。
そして1980年、北海道でビニ本専門店「北大神田書店」(「北大」は北海道大学、「神田」は日本一の書店街である東京の神田からとった)を開店。たちまち店舗は全国に拡大し、全国最大のビニ本販売チェーンへと成長する。ビニ本は、卸価格400円を1800円で販売するような代物。利益も莫大なものになっていった(同書、115‐116頁。前掲『ナイスですね』、92頁)。
村西とおるは、なぜビニ本にそれほど惹かれたのか。
むろん、濡れ手に粟のような金儲けの手段として魅力的だったということがあるだろう。幼い頃から少年時代にかけて満足に食事もできないほど貧困に苦しんだ村西にとって、お金を稼ぐことは人一倍重要なことだった。
■「消費というものは善である」
さらに性についても村西は貪欲だった。初体験は中学2年のとき。その後上京してスナック勤めの頃は、1週間で何人の女性と関係を持てるか店員同士で競争していた。自慰行為も一晩に6回から7回はしょっちゅうだったと回想する。村西にとって「勃起は健康のバロメーター」で、それを確かめるためにいじってみるのだ(同書、61頁および71頁)。
ここから読み取れるのは、村西とおるにとって金銭欲と性欲は無限ということである。双方ともに、限界はあってないようなものというのがある。欲望に制限を設けてはならないし、その必要もない。
百科事典のセールスマンだった頃、村西は上司から「消費というものは善である」という教えをたたき込まれた。「あの人がいて今の自分がいると思っている」と村西は感謝する(同書、77頁)。
消費が浪費や散財ではなく快楽を引き起こすものであるのを顧客に想像させることで、欲望を抱くことそのものを善と認識させる。そのためには、売る側の村西自身もまた「消費=善」であることを誰よりも本気で信じる人間でなければならない。
お金は稼げば稼ぐほどよい。そのためには、お金をため込むのではなく、どんどん使わなければならない。そして性欲もまた同様だ。いくら消費しても次から次へと沸き起こってくるものであり、より新しく深い快楽を求める。それが性欲である。一般論としては常識外れかもしれないが、村西にとってはその状態こそが「健康」なのだ。
■いつも3000万円を持ち歩いていた
ビニ本の内容も、ますますエスカレートしていった。単なるヌードではなく、性器が映っているかいないかぎりぎりの過激な写真が当たり前になった。そこまでくれば、無修正への一線を越えるのは時間の問題だ。1万円以上で売られ、ビニ本よりさらに利ザヤも大きい「裏本」の販売に村西が手を伸ばしたのは、ある意味必然だった。そうなってしまえば、警察が動くのは避けられない。村西本人は免れたが、25店舗が一斉に摘発され店長たちが逮捕されたことも。テレビのニュースにもなった(同書、93‐94頁)。
販売だけに飽き足らず、自ら裏本製作にも乗り出した。印刷工場を買収してフル稼働させる。実際裏本は売れに売れ、3日に1回、その都度1000万円ずつが口座に振り込まれた。いつもアタッシュケースに3000万円のキャッシュを持ち歩いていたという(同書、96頁)。「消費は善である」というモットーに従い、その分使いもした。一晩に200万円くらい使う。社員50人を連れて台湾旅行にも行って豪遊の限りをつくした(同書、112‐113頁)。
ビニ本や裏本以外の商売にも手を伸ばした。その頃流行していた写真週刊誌を創刊するなど出版業に取り組んだり、芸能人の出演するイメージビデオを制作したり。アメリカのポルノ女優を日本に呼んでアダルトビデオの撮影もした。
これが、村西の撮った初AVだった。だが、事業はうまくいかなくなっていた。そして今度は村西自身がとうとう猥褻物販売容疑で逮捕。1984年のことである。北大神田書店グループも解散になった。
----------
太田 省一(おおた・しょういち)
社会学者
1960年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。テレビと戦後日本、お笑い、アイドルなど、メディアと社会・文化の関係をテーマに執筆活動を展開。著書に『社会は笑う』『ニッポン男性アイドル史』(以上、青弓社ライブラリー)、『紅白歌合戦と日本人』(筑摩選書)、『SMAPと平成ニッポン』(光文社新書)、『芸人最強社会ニッポン』(朝日新書)、『攻めてるテレ東、愛されるテレ東』(東京大学出版会)、『すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった』(ちくま新書)、『21世紀 テレ東番組 ベスト100』(星海社新書)などがある。
----------
(社会学者 太田 省一)
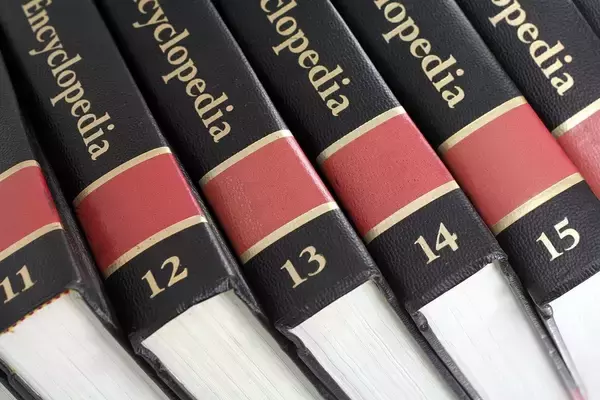














![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
