※本稿は、矢野耕平『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』(祥伝社新書)の一部を再編集したものです。
■「アウトソーシング」を好んで口にする親
【ネオ・ネグレクト〈名〉 衣食住に満ち足りた生活をしていても、親がわが子を直視することを忌避したり、わが子に興味関心を抱けなかったりする状態のこと。[――の行為に及ぶ]】
「いままで多くの親の相談に乗ってきたけれど、『アウトソーシング』をすぐ口にする親は一様に良くない傾向が見られるよね」
あるとき知り合いの同業者と談笑していたときに、こんなことを言われた。「アウトソーシング」とは、直訳すると「外部委託」「外注化」である。
ただ、そのことばを耳にした当初、わたしは正直ピンとこなかった。わたしは中学受験専門塾を経営しているが、そもそも塾というのは、「ご家庭の手ですべて解決できない」からこそ、わが子の中学受験勉強をアウトソーシングする場ではないのか。そう感じたからだ。
けれども、彼の発言内容をじっくりと考えてみたところ、その真意がわかってきた。彼が口にした「アウトソーシング」とは、すなわち「丸投げ」を意味していたのである。
さて、わたしが日々従事している中学受験の世界に見られるネオ・ネグレクトについて言及したい。
ここ1~2年は幾分落ち着いたが、首都圏を中心に中学受験(主に私立中高一貫校の受験を指している)を志す子どもたちの数が増加していて、たとえば、数年前には中学受験を題材にしたテレビドラマが放映されたし、中学受験の塾講師を主人公に子どもたちの受験模様を描いた漫画がヒットした。
中学受験がブームと形容しても差し支えないくらいに、大きな盛り上がりを見せていたのである。
では、このような親は問題であると断罪すべきなのだろうか。
そうとは限らない。なぜなら、わが子の中学受験に言い知れぬ不安や焦りを抱いてしまうということは、換言すれば、わが子に目が向いている証拠だからだ。自身の過熱ぶりに気づいたら、それを都度冷ましてやればよいだけである。そのために、わが子の中学受験を「アウトソーシング」している進学塾の講師に相談に乗ってもらうのは有効である。
一方、わが子の中学受験をきっかけに親が子に暴力を振るったり、家族関係が崩壊したり……などという事例がメディアの記事などでセンセーショナルに取り上げられることがある。もしそれが事実であれば、もちろん言語道断である。こうなってしまうと、もはや教育虐待に該当すると断じてよい。
■進学塾で感じたネオ・ネグレクト
わたしが中学受験に関わる親と接していて困るのは、わが子を直視していない親、「アウトソーシング」が「丸投げ」と同義になってしまっている親への対応だ。つまり、ネオ・ネグレクトに手を染めてしまっている状態の親に対して、どう導いていくべきか苦慮してしまうのである。
わが子の受験校についての親と塾との話し合いの場で、「わたし、考えるのが面倒くさいから、先生が全部決めてくださいよ」と言い放った母親は、まさにこのケースに相当するといえるだろう。
わたしの経営する中学受験塾に子を通わせる保護者の事例は紹介できないが、わたしの塾に問い合わせてきた親(実際に通ってはいないご家庭)について、わたしの見聞きした事例を4つほど紹介したい。
一つ目はこんな話だ。
わたしの塾(スタジオキャンパス自由が丘校・三田校)の特色の一つとして「自習室」を完備していることが挙げられる。塾の授業のない日であっても、月曜日~土曜日に常時開放し、そこで自学自習ができるようにしている。近年、共働きのご家庭が急増していて、親がわが子の学習に付き添いたくても、それが叶わない……それならば、わが子が塾の自習室を活用してもらい、質問があればその都度チューターや講師で対応しようと考えたのである。また、親子の距離が近すぎると、親がわが子の学習面にタッチしようとすることで、軋轢が生じてしまうケースがよく見られる。「自習室」はこういう事態を回避するための仕掛けでもある。
比較的最近の話だが、わたしの塾に問い合わせてきた親がいた。どうしてこの塾が気になったのかという点を尋ねると、「自習室がある塾だから……」と繰り返すばかり。塾の教材やカリキュラム、授業日程などの質問はまったくしてこない。その親と話しているうちに気づいたのは、子の家庭学習を塾に託したい、換言すれば、丸投げしたい……それによって、親としてその負担をなくしたいという要望が先行していることだ。乱暴に言えば、わが子の今後の成績がどうなるのかは大した問題ではない。
二つ目の事例を紹介しよう。
■なぜか「自習室ありの塾」「寮制の私立中高」に固執
あるタワマン密集エリアの小学校の校門外では、学校帰りを待ち受ける民間学童施設をはじめとした、さまざまな教育機関がマイクロバスやバンを待機させることがある。それらに乗り込む子どもたちはまさに「分刻み」のスケジュールで日ごと数多くの習い事が入っている。
そういう習い事の一つとして進学塾を選定する親がとみに増えてきたように感じるのだ。そして、かつては決して耳にしなかったこんな「要望」が、問い合わせてきた親から発せられることが多くなってきた。
「わが子には複数の進学塾を掛け持ちさせようと思っています」
わたしは即座に否定する。子どもたちが塾の授業がない日は、彼ら彼女らが宿題に取り組むという前提で、こちらもカリキュラムを構築しているのだ。別の塾を掛け持ちしたら、日々の学習が途端に回らなくなるのは当然だし、それによって子どもが勉強そのものを苦痛に感じてしまうようになるのは間違いない。
ただ、その手の親にこういう理屈を丁寧に説明しても、「じゃあ、ほかの塾を当たります」とすぐに電話を切られてしまうのが関の山だ。この点、先ほどの「自習室」を連呼する親とよく似た動機が感じられる。
とにかくわが子に自宅外で日々過ごしてほしいのである。
三つ目は、問い合わせをしてきた親、中でも小学校高学年の児童の親と面談すると、「現時点でのわが子の志望校」を表明される場合がままある。そんなときに、寮制度の設けられている地方の私立中高一貫校ばかりを志望するというケースに遭遇することが最近増えてきたのである。
全国には数多くの全寮制、あるいは一部寮制を導入している私立中高一貫校がある。たとえば、特定のスポーツのスキルを強化するために、いわゆる「強豪校」で寮生活を送るような子どもたちの話は聞いたことがあるだろう。
しかし、そういう特殊なケース以外にも、あえて親元からわが子を離し、中高生活を寮で過ごす子どもたちも大勢いる。
その子のタイプにもよるけれど、わたしは寮生活で心身共にたくましく成長を遂げた自塾の卒業生たちをこれまで何人も見てきているので、寮制について否定的な立場ではまったくない。
しかしながら、話を戻すと、わが子に何のビジョンも描かず、「中高は寮で過ごしてほしい」と口にするタイプの親がなぜかこの数年で急増しているように思えてならない。誤解を恐れず申し上げると、「わが子が邪魔である」という親の思いが透けて見えるような場面に出くわすことがよくあるのだ。
そういう面談対応をするたびに、ああ、この親は平生ネオ・ネグレクト行為をわが子にしているのだろうなと感じさせられる。
■「習い事」を詰め込み、仕事に専心できる時間を捻出する親
そういえば、ずいぶん前にこんなことがあった。このエピソードを四つ目の事例として紹介したい。
わたしは知人経由で、ある男性の「子育て」相談に応じたことがある。わたしは「子育て」の専門家ではなく、中学受験塾の講師だと最初は遠慮したのだが、どうしても話を聞いてほしいという。
夫婦共働きの家庭で、何かと忙しいという事情があったため、わが子は幼いときから保育園に預けるだけでなく、それ以外の時間帯にも「習い事」を詰め込むことで、仕事に専心できる時間を捻出していたらしい。
結果として、その男性はわが子とあまり触れ合わぬまま時間が経ってしまい、小学生になる子とどう接すればよいのかが皆目わからないし、何より子どもの本心が理解できないらしい。
このように、小学生になったわが子との意思疎通に苦慮するという経験が、それまでの親としての在り方を反省させられるきっかけになったのだろう。
わたしはそのときに上手く返答できたかどうかは覚えてはいないが、親としての自分の姿を客観視できているため、きっとその後の親子関係に改善が見られたに違いないと思っている。
----------
矢野 耕平(やの・こうへい)
中学受験専門塾スタジオキャンパス代表
1973年生まれ。大手進学塾で十数年勤めた後にスタジオキャンパスを設立。東京・自由が丘と三田に校舎を展開。
----------
(中学受験専門塾スタジオキャンパス代表 矢野 耕平)




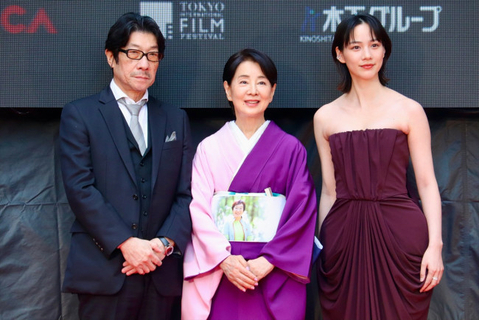
















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
