■阪神100年の分岐点は荒地にあった
どんな経営者も、経営判断という名の“賭け”に踏み切る瞬間がある――「鉄道」「百貨店」「プロ野球・阪神タイガースの経営」などを手掛ける阪神電気鉄道(以下:阪神電鉄)は、100年以上前に、「廃川と三角州、一帯の荒地を巨額買収」という賭けに出た。
川の跡地だけに土地は細長く、荒涼とした一帯は、見るからに用途がない。そんな土地を「410万円」(現在の20億~30億円)で買収した阪神電鉄の経営判断は、かなり疑問視されていたという。
しかしこの“賭け”が、グループの次の100年を決めた。荒地は住宅街に変貌を遂げ、甲子園球場や阪神タイガースもここから生まれた。生じた利益によって、阪神電鉄は単なる鉄道会社から「デべロッパー」「スポーツビジネス」へとビジネスの領域を広げることができたのだ。
2025年、阪神タイガースはセ・リーグ優勝を果たし、藤川球児監督は胴上げで甲子園球場のグラウンドを宙に舞った。今から100年前にさかのぼり、阪神電鉄の原点がギュッと詰まった「甲子園」の歴史を振り返りつつ、甲子園が阪神電鉄にもたらす「100年続くシナジー(相乗)効果」をたどる。
■こうして三角州は甲子園に変わった
まず、一帯の開発が始まる前の1909年と、甲子園の街がおおむね形成された1947年頃との違いを、地図で比較してみよう(図表1)。
※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像をすべて閲覧できない場合があります。その際はPRESIDENT Online内でご確認ください。
1909年の時点では、いまの阪神本線・武庫川橋梁の2kmほど上流から、武庫川本流と「枝川」が分流し、その下流で「申川(さるかわ)」が分岐。2本の分流に挟まれた三角州には小さな集落があるのみで、地図に「田畑」などの記号もほとんどない。
1905(明治38)年に開業した阪神本線は、もっとも川幅が広い枝川・申川の分岐地点あたりをまたぎ越している。のちに設置される「甲子園駅」は、この時点で影も形もない。
続いて、甲子園開発が進んだ1947年の地図を見てみよう。枝川はそのままのルートで道路(甲子園筋)に転用され、路上には路面電車(甲子園線)も見える。一帯は規則正しく道路が張り巡らされ、いまの「甲子園六番町」「甲子園浦風町」「浜甲子園」あたりは、かなり宅地化が進んでいるようだ。
そして、枝川・申川の分流で広くなっている河道や三角州は、阪神本線・甲子園駅や駅前広場、甲子園球場へと転用されている。地図上で見る限り、街としての甲子園開発は、地形を巧みに活かしたものといえそうだ。
■「阪神さんはどないするおつもりや?」
もともとすべての土地は「廃川と三角州、一帯の荒地」だ。
阪神電鉄はなぜ、川や荒地から鉄道・スポーツなど多分野にわたる「100年続くシナジー効果」を生み出すことができたのか。まずは「甲子園球場」「甲子園の街」の秘密を解き明かしていこう。
数々の開発計画のなかで、1924年3月に着工、8月に完成という突貫工事で先んじて建設されたのが「甲子園大運動場」(現在の甲子園球場)だ。「東洋一の球場」とも呼ばれたグラウンドは、1934年に来日したニューヨーク・ヤンキースが1試合15点を獲ったにもかかわらず、主砲のベーブ・ルースを含めて誰もホームランを打てなかったというほどに広い。
なぜ阪神電鉄は、すべてにおいて広大な球場を建設したのか? 阪神電鉄はもともとスポーツ施設の建設を計画していたものの、ここに「全国中等学校優勝野球大会」(いわゆる「夏の甲子園」)の開催地となることが、早期に決まっていたことが大きい。
■「満員に10年かかる」を4日で達成
中学野球(いまでいう高校野球)はこのころに人気が沸騰し、1923年に鳴尾球場で開催された夏大会では「超満員の観客がグラウンドになだれ込む」という事態が発生。数千人収容の仮設スタンドでは雑踏事故が起きかねないと危惧した大会主催者(大阪朝日新聞)から、阪神電鉄に「本格的な野球場の早期建設要請」があった。
ここで阪神電鉄側は建設の優先順位を上げ、翌1924年の夏大会までに、どうにか開業を間に合わせた。建設当初は「座席数5万、収容能力8万人」という球場を満員にするのに「10年はかかる」とされていた前評判を覆し、なんと開幕4日で満員御礼を記録。阪神電鉄は各駅に「球場は満員。来場をお控えください」と慌てて張り紙を出させたという。
1935年に「阪神タイガース」の前身球団(大阪野球倶楽部・大阪タイガース)結成でプロ野球に参入することができたのも、広大な甲子園球場があったからこそ。もちろん試合ごとに阪神電車は満員・満杯となり、鉄道部門には莫大な運賃収入がもたらされる。なおかつ系列の阪神百貨店も、タイガースが勝てば勝つほどに、公式グッズや応援商品が売れ、2025年9月の優勝セールでは月間売り上げが「前年比34%」もアップしたという。
さらに、阪神タイガースを含むスポーツビジネスは、2024年度で見ても「営業収益は年間500億円、営業利益は101億円」と、恐ろしいまでの好業績をたたき出している。甲子園球場を起点に生み出された利益は、運輸・スポーツなど阪神電鉄グループ全体に「100年続くシナジー効果」として、シャワーのように降り注ぎ続けているのだ。
■天気さえも味方につけた球場建設
そんな甲子園球場は、建設段階で「廃川」「三角州」という地の利を存分に活かしたようだ。各種資料や新聞記事などから「5カ月で巨大球場を建設できた」理由と秘話を探していこう。
まず、枝川は通常の川でなく「天井川」(川に土砂がたまりすぎて、地面より水面が高くなった川)であったため、コンクリートに必要な砂や砂利は普通の川より多量に存在した。土手の土も外野グラウンドに転用できるなど、建設資材をきわめて近場で調達できる環境だったことが大きいだろう。
また三角州だった一帯は人家がなく、建設を請け負った大林組は、夜間照明の電気を阪神電車から融通してもらったうえで、フル稼働で槌音を響かせて工事を続けることができた。ここに、3月~8月の工事期間中のうち、雨天は12日間のみという驚異的な空梅雨が球場建設を味方した。
甲子園球場のスピード開業は「川と三角州」という好条件に、天運が味方した結果と言えるだろう。
そして、「甲子園球場の驚異的な水ハケの良さは、砂地の多い三角州に建設したから」と、関西ではよく言われている。本当なのか?
阪神電鉄の方いわく「あまり関係がない」という。甲子園球場は必要に応じてグラウンド掘り起こしを行っており、この作業の出来で水ハケが違ってくるため、「阪神園芸(系列のグラウンド管理会社)の作業の出来次第」と考えられるとのこと。つまり、水ハケに関する「三角州のおかげ」という俗説よりも、「阪神園芸のおかげ」のようだ。
■住んでくれたら、電車賃1年無料
廃川と三角州の開発で、もうひとつ忘れてはならないのが「宅地開発」だ。球場がある「甲子園町」を中心に、「甲子園一番町~九番町」や「甲子園浜田町」「浜甲子園」などの街区があり、2km範囲内に7万人ほどの人々が居住している。荒地はどう転用され、規則正しく閑静な住宅街に変化を遂げたのだろうか。その過程を見てみると……
まず、小高い丘状の天井川を切り崩し、平たくなった川の跡地の上に、土や石を搬出する貨物線が敷かれた。周囲を住宅街に転換しつつ、貨物線は幹線道路「甲子園筋」として整備され、中央部には路面電車「甲子園線」として、1928(昭和3)年までに順次開通していった。いわば「川→貨物線→道路と路面電車」に変わっていった訳だ。
路面電車があれば、駅が遠くてもやすやすと甲子園駅までアクセスできる。さらに、阪神電鉄は住宅の購入者に「大阪方面・神戸方面に通勤される方、どちらかの方向の阪神電車が1年間無料」という特典を付けたため、駅から遠い街区まで、あっという間に分譲住宅で埋め尽くされた。
■阪神が夢見た「もうひとつの甲子園」
惜しまれるのは、開発構想が未完成に終わったこと。甲子園開発を取り仕切っていた三崎省三取締役は、宅地や野球場だけでなく、スポーツ施設や別荘地までセットで整備される予定であったという。さらに水族館・動物園もあり、阪神本線の南側は一大レジャータウンとなるはずであった。
戦争で多くの施設が縮小・閉鎖を余儀なくされたものの、もし実現していれば、甲子園球場の一帯は野球場・エンタメが融合した「ボールパーク」に発展していたかもしれない。さらに、浜甲子園の国際庭球場を舞台に、「開催中はロンドンに4億ポンド(日本円換算で約800億円)の経済効果」とも言われる「ウィンブルドン選手権」クラスのテニス大会を誘致してみたり……戦争への突入・戦後の接収に阻まれたものの、「もし実現していれば!」「戦後も施設があれば!」な妄想は尽きない。
それでも、宅地分譲は住宅販売の利益や開発のノウハウを阪神電鉄に与え、通勤客の運賃収入で阪神電鉄は潤った。これもまた、甲子園開発が生み出した「100年続くシナジー効果」と言えるだろう。
■阪急に追い詰められた阪神の決断
甲子園一帯での球場・住宅開発は、阪神電鉄グループ全体に莫大なシナジー効果をもたらした。しかし、川と三角州は普通売りに出されるようなものでもなく、「なぜ、どこから買ったのか」……答えを探りつつ、経緯をたどってみよう。
のちに売りに出される枝川は、先に述べた「天井川」であり、武庫川の本流が増水して流れ込むと、巻き添えで一帯を水浸しにしていた。あまりに危険な状態を兵庫県が見過ごすわけがなく、武庫川本流を大幅に拡張して増水時の水を逃がし、枝川・申川を「廃川」とする改修構想が立てられた。
同時期に兵庫県を悩ませたのが「トラック・自家用車が通れる道路の整備」だ。
そこで兵庫県が捻りだしたのは「廃川を高額で売却、両事業の資金に充てる」という、一挙両得な折衷案であった。
一方で、購入に名乗りを上げた阪神電鉄は、自社路線と並行する「阪急神戸本線」が1920年に開業したことで、宅地開発できそうだったエリアは阪急に圧され、制約されてしまった。沿線で広大な未用途地はこの一帯しかなく、河川改修工事の費用込み410万円(現在の20億~30億円)を投資してでも、鉄道の利用者増につなげる開発を行う必要があったのだ。
■100年前の決断が今も阪神を支えている
結果として、「廃川と三角州、荒地の巨額買収」“賭け”(経営判断)は成功を収め、100年続くシナジー効果を阪神電鉄にもたらした。また阪急電鉄にとっては「中学野球の豊中球場誘致」「プロ球団『宝塚運動協会』設立」などで先に目をつけていた「野球ビジネス」を攫(さら)われる事態でもあり、ライバルの鼻を明かすといった意味合いも、多少はあったと思われる……数十年後の「村上ファンド騒動」がきっかけで、阪神・阪急の経営統合が実現するなど、当時は誰も思いつかなかったであろう。
ただ、いまの阪神電鉄や阪急阪神東宝グループ経営陣も、しっかりと経営努力を行っている。阪神タイガースも野村克也氏・星野仙一氏といった外部指導者の招聘(しょうへい)で常勝へのDNAをチームに注入し、球場も絶え間ないリニューアルや「甲子園歴史館」開設、動物園跡地への「ららぽーと」誘致など、地域全体の集客をはかってきた。
阪神電鉄は、甲子園を起点とした「100年続くシナジー効果」に続く、次の50年・100年を見据えて体制を整えつつある。2025年のプロ野球・日本シリーズでの熱戦を観戦しつつ、中継に映る甲子園球場から「廃川と三角州」の歴史、100年前に一世一代の“賭け”に出た阪神電鉄・経営陣の心意気を、少しだけ思い起こしたい。
----------
宮武 和多哉(みやたけ・わたや)
フリーライター
大阪・横浜・四国の3拠点で活動するライター。執筆範囲は外食・流通企業から交通問題まで、元・中小企業の会社役員の目線で掘り下げていく。各種インタビュー記事も多数執筆。プライベートでは8人家族で介護・育児問題などと対峙中。
----------
(フリーライター 宮武 和多哉)




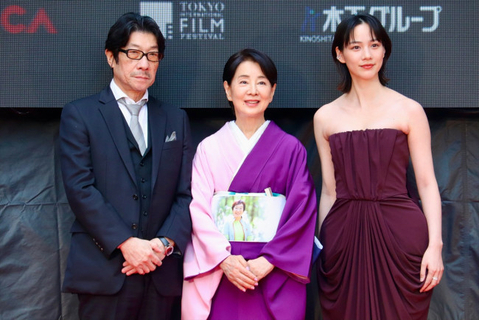













![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
