■高止まりする新米の価格は適正か
新米の時期になっても米価は高いままです。こうして価格が高止まりしている理由は、何なのでしょうか。さまざまな角度から検証していきましょう。
生産側から見ると、2023年から今年にかけての猛暑・干ばつ、台風などの局所的被害によって、一部のコメの品質(等級)や収量が想定を下回りました。そのため、供給がショートし、需要を下回ったことが価格の高止まりにつながったのです。
流通に目を向けると、買い取りを巡る業者間競争が価格を押し上げ、小売価格を跳ね上げています。また、玄米から白米にする「精米工程」でのタイムラグや流通上の偏在があり、店頭の在庫と現場需給がすぐに均衡しないというボトルネックもあります。
消費側から見ると、まず外食需要やインバウンド需要の増加、加工用(パックごはん等)や輸出の増加が見られ、米の需要が想定を上回りました。
そのうえメディア報道やSNSでの「品薄」情報が業者や消費者の心理を煽り、買い占めやまとめ買いが発生した時期もありました。こうした“需要の先食い”が価格を押し上げる一因となったのは間違いありません。
■「悪の組織」のようにいわれるJA
このように米価高騰は様々な要因が絡み合っているため、何をもって「適正価格」とするかはとても難しいことです。
まして農業資材や機械の価格も高騰している今、生産者としては経営持続可能な価格が維持されることを期待します。確かに一昨年までの米価は安すぎました。一方、消費者としては物価高騰の中で少しでも安い価格を求めるでしょう。どちらも当然です。ただし、現在の値上がりの中には適正値への「回復」の部分と、それを超過する「異常」な部分があると考えなければなりません。
前述の内容を考えれば「コメが高いのは○○のせいだ」と安易に決めつけることはできないはずなのですが、しばしばその槍玉に挙げられる組織があります。それが有名なJAです。「JAが生産者と流通業者の間に入って暴利を貪っている」という「JA中抜き論」はSNSで瞬く間に拡散され、広く誤解を招くこととなりました。
他にも「JAがコメを出し渋って値段を吊り上げている」とか「JAが海外にコメを売り飛ばしている」など根も歯もないデマが蔓延する事態に。これら事実に基づかない誤情報は、米価高騰に際してさらに消費者の不安を煽ったに違いありません。
■JAは協同組合かつ地域のインフラ
そもそも、JAとはどのような組織なのでしょうか。
JAは全国に496あり、それぞれのトップである組合長は原則として地域の農家が担います。農家にとっては、農業資材を購入したり、農産物の販売を委託したりする経済活動の共同体であると同時に、農業の技術指導や栽培計画等を担う経営支援組織でもあります。たまに「民営化しろ」などといわれますが、もともと公営ではありませんから的外れです。
また、一般の人にとってどのような組織なのかというと、「地域の複合的な経済・社会組織」といえます。地元のJAが経営するスーパーや直売所は、総じて品質管理が徹底されていて、地域農産物の供給(地産地消)、消費者の食の安全に寄与しています。その他、「JAバンク」「JA共済」といった金融・共済分野、ガソリンスタンドや葬儀場などもあり、特に地方では地域社会のインフラとして重要な役割を担っていることも少なくありません。少子高齢化や過疎化もあり規模の縮小を余儀なくされる場合もありますが、JAなしには生活自体が成り立たない地域があるのも事実です。
■米の流通におけるJAの役割
さて、日本のコメに関しても、JAはとても大きな役割を持っています。JAの米の取り扱いは、全国の取引先で通年販売を行うために、その多くが「委託販売・共同計算」の方式を取っています。
委託販売とは、JAが農家に代わって農作物の価格交渉から販売、納品、代金回収までの販売業務を行い、得られた代金を委託者に支払う仕組みです。総じて安定・効率・信頼を重視するのがJAを介したコメの流通といえるでしょう。これは労働力を確保することが難しい小規模農家、中規模農家にとっては特に重要な機能です。
また、共同計算とは、生産者から販売委託されたコメについて、時期によって変わる価格や経費を一旦保持した上で、全体のコメの集荷数量で割って計算することで収益を公平に分配し、生産者間の手取り額を平準化する仕組みです。
集荷時点で前払い金である「概算金」を支払い、販売・経費支払いが完了した後に最終精算である「本清算」を行います。すべての米の販売が完了しないと全体の価格や経費が確定しないため最終精算までには時間がかかりますが、変動する価格や経費を一旦保持するので、農家に公平に収益を分配できる点は相互扶助を是とする農業協同組合らしい制度といえるでしょう。
■JAは解体すべき組織なのか
流通の多様化に伴いJAのシェアも縮小傾向にはあるものの、その存在意義は依然として大きいことがわかります。しかし、昨今の米価高騰を皮切りにしばしばJAに対するバッシングが起きていて、「JA解体論」を叫ぶ人たちが現れるようになっています。
その内容はさまざまですが、特に大きな話題のひとつとなったのが「共同計算」に対する誤解です。ある米農家がJAに委託した米の「概算金」が539万円、「本精算」が140万円で合計679万円、そこから72万円の諸経費を差し引いて合計607万円の利益を出したという事例がありました。
ところが、どういうわけか概算金の539万円を話から除外し、JAが140万円のうち72万も中抜き」したという誤情報が拡散されました。72万円の諸経費は、JA職員の人件費、運送費、管理費などが含まれています。
■もちろん時代に合わせた改革は必要
JAは今、時代の潮流に合わせての改革を迫られています。販売経路の多様化が進み、大規模農家が自力で販売できるようになったことによってJAのシェアが減少する中で、どの様に存在していくのかが課題です。
しかし、決して「解体」が必要な組織ではありません。それはJAの共同組合としての在り方を鑑みれば自明のことですが、農家人口が減り、農業に関わる人が減った現代では理解されにくくなり、結果的に誤情報が拡散される事態となっています。
この問題の難しいのは誤情報の出所が「農家」だという点です。すべての農家が、JAを正しく理解しているとは限りません。農家とJAは、よく「搾取される側」と「搾取する側」とされていますが、それは適切な理解ではありません。
JAを本当に必要としている農家もいれば、その存在を疎ましく思う農家もいます。例えばJAに農産物を出荷する時には、その品質を担保するために決められた「規格」を守らなければなりません。しかし規格外品を受け取らないJAに対して、不満をこぼす農家もいます。そうして、SNS等で「もったいない」と声を上げれば、規格の必要性など置き去りにしたまま、一部の消費者が同調してJAを批判してしまうことになるのです。
■悪者をつくれば溜飲が下がるが
米の価格が高いのも、供給量が安定しないのも全てJAのせいだとして、溜飲を下げるのは簡単です。しかし、この問題はそんなに単純なものではありません。
コメの安定供給には、JA、政府、生産者、流通業者、消費者が正しい知識を持つことが重要だと私は考えます。米の安定的な価格と量の供給は、単に「作る・運ぶ・売る」だけの問題ではなく、「需給・価格・信頼・文化・政策」がすべて絡み合う複雑なシステムだからです。
例えば、政府が産地や生産者についてよく理解しなければ、政策が現場にフィットせず、さまざまな問題が解消されません。生産者が、市場構造や消費トレンドについて理解不足だと、過剰作付けや販路選択のミスマッチが起こりかねません。消費者が、米の価格構造や産地の労力を知らず「高い」と抗議すれば、むしろ生産基盤が弱体化してしまうことにもつながりかねません。
コメをはじめとする農産物の安定供給は、誰か一人の努力では成り立たず、関係者全員が視野を共有することで初めて成り立つのです。その意味で「互いに理解を深める」ことが、日本の農業従事者と消費者をつなぐキーワードとなると思います。
----------
SITO.(シト)
農家、農業ライター
1993年、愛知県生まれ。キャベツとタマネギを栽培する露地野菜農家で、農業ライター。
----------
(農家、農業ライター SITO.)





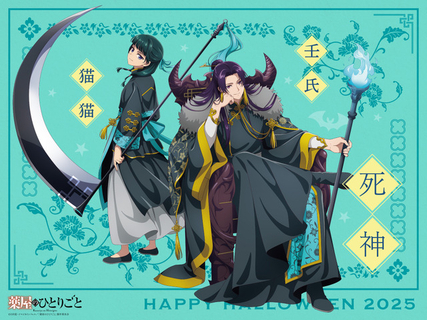









![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
