4月初旬、コロナ禍により苦境にあえぐ音楽業界、音楽関係者のために自己資金2000万円を寄付するプロジェクト『White Teeth Donation』を発表し、話題となった対馬芳昭さん。Ovall、mabanua、kan sanoら気鋭のアーティストが所属する〈origami PRODUCTIONS〉のCEOだ。
Interview:対馬 芳昭(origami PRODUCTIONS CEO)
━━noteに書かれた内容を読んで、感銘を受けました。動機はすごくよく分かっているつもりでいますが、どんな覚悟で寄付を決めたのか振り返ってお聞かせください。 ドネーションの前に、『origami Home Sessions』を立ち上げました。6人の所属アーティスト楽曲のデータを無償で公開し、それを使ってミュージシャンが楽曲を販売するというプロジェクトです。そこから始まったんですが、あの頃はとにかくライブができないということだけが世の中に広まった時期ですよね。例えば他の業種は問題なく営業していて、ソーシャルディスタンスの指示もなく混み合っていた。でも、ライブハウスはクラスターが発生したので、とにかくどこよりも先に営業できなくなってしまったんですね。 音楽関係者って昔から悪の対象にされがちなので、慣れっこではあったんですけど、ライブがなくなるとお金が回らない。収入がゼロになってしまう。おそらく、ライブハウスとかが日本で一番自粛が長いと思うんですよ。
━━それで私財を投じられたわけですけど、反響はどうでしたか? 良かったのが久しぶりに話す人たちの、安否確認というか、近況を話し合うきっかけになった。ほとんどの人がSNSを通して、僕の活動をすでに知ってくれていて。「もちろん見ているよ」という感じで、すぐに話が発展していったり、しばらく会ってない人に例えば子供が生まれていたり、逆にねぎらってもらった。お金の面で助けている実感はありますけど、それ以上に繋がりの再確認に僕が勇気づけられました。 ━━ドネーションが始まって1か月ほど経ちました。社会をめぐる状況もかなり変化してきていると思うんですが、一か月を振り返っていただくとしたら? 最初ははっきりとした情報がないので、とにかく音楽業界が的にされているというような感覚がありましたね。命を優先するために自粛しているのに、保証を求めると叩く人もいて。別に悪い事をしているわけじゃないのに、なんでこうなるんだろう、と。でもそのうち強烈に応援してくれている人も出てきて、敵ばかりじゃなく、2つに分かれるんだなと思った。
Ovall - origami SAI 2019
━━僕から見ると、対馬さんは音楽業界の「ファーストペンギン」のような感じで。対馬さんのスピーディーな行動もひとつの契機になって、いろんな人たちがトライ&エラーをし始めた。結果、音楽業界に勇気を与えたり、行動を変えたように見えました。 本当にそうだとしたら、すごくうれしい話ですね。
#OrigamiHomeSessions ( origami PRODUCTIONS )
━━例えば対馬さんが、これからのライブ業界がどうなっていくかとか、最悪なケースとかもあったら教えていただきたいです。 最悪なケースは、「ライブは無観客でやるもの」というのが常態化することですよね。それはアーティストにとって、リアクションや熱を感じられないという意味で最悪なケースだと思う。もちろんその中でも、ネット上でマネタイズしていく、課金のようなことは考えていかなきゃいけないと思うんですけど。でも、僕は個人的にはそこは楽観視しているところはあって。歴史上、いろんな病気が蔓延した中で、もう一生、人と近づけないなんてことは絶対ないと信じている。まあもちろん、1年は無理とかはあるかもしれないですけど。なので、ライブで大声を出すという社会はまた訪れると確信しているというか、そう信じたい。 ━━じゃあある意味そこまできちんと繋いでいくことが大事ですね。 そう。だから選択肢が1個増えたんだと思えばいい。例えば、レコードがあって、CDがあって、配信があって、Spotifyがあって、でも今レコードブームみたいに再熱したり、カセットテープとかもそうですけど、選択肢は増えているじゃないですか。例えばコロナの前から、<Coachella>に行ってみたいなと思いつつも、家で観れるみたいな進化もあったじゃないですか。ライブの会場が1000人で、東京の人しか来られないとして、地方の人も500円払えばそのライブが観れるとなれば、レコード会社からすると、キャパシティに依存しないライブができる。今までだったらソールドアウトの上がなかったけど、上が出てくるというか。会場は1.000人だけど、ネット上で10,000人が観たら、11,000人なわけで。そういう意味で、今までライブ配信はフリーで観るのが当たり前だったのが、お金を払うというカルチャーになってくれば、それはすごいチャンスだと思うんですね。━━さらにライブでリアルに観るってことが貴重な価値になりますね。もう、解禁された時の喜びってたぶん相当なものになると思うし、演奏家も含めてみんな涙するんじゃないかな。観る側もやっと生で観れるみたいなことを感じて、人類史においてこの感覚を共有するって中々ないと思うんですね。だから、当たり前だと思っていたものが、より貴重になっていくし、ビジネスとしてもより大きくなっていく。僕は完全にそっちのポジティブな面を信じています。 ━━(<FUJI ROCK FESTIVAL>の開催地となる新潟・)苗場にいく前に泣いちゃうみたいな。<FUJI ROCK FESTIVAL>のライブ配信も課金してもいいかもしれないですよね。 そうですね。この感じだったら、もうお金をとっても誰も怒らないかもしれない。 ━━ceroが3月に開催予定だったライブをオンライン配信にして、集客でいうと通常の10倍くらい集めたことになるので、おそらく収益的にも成功したんじゃないかと思います。なのでトライアンドエラーを繰り返して、収益的にもフィードバックできるようになってくると面白いですよね。 僕はもう完全にそっちを期待していますね。音楽関係者の気持ちがそっちにいかないと、これはやばいっていう雰囲気になっちゃうと、みんな奪い合いが始まってしまう気がするので。そういう意味で、僕が自分のお金を前に置いたのは、大丈夫だよっていうことなんですよね。絶対に大丈夫だって。これだけ優秀な人たちが、ミュージシャンも含めてたくさんいるわけで。気持ちが萎えたり、怖気づいたりした瞬間に終わる気がしたので、絶対に大丈夫だとしか僕は思っていないから行動に出たというのもある。
Kan Sano - origami SAI 2019
━━これからの活動で、対馬さんがこれから考えていることがあれば教えてください。 個人的にはあまり未来のことは考えてはいなくて、というより主義として考えないようにしているんです。あまり大きい絵を描いてしまうと、目の前のことに対応できなくなってしまうんですよね。だから、まず今のことだと思っています。ただ、助けてくれって声をあげてくれるのはいいんですけど、みんなドネーション疲れしている気がしています。音源をタダで渡して、売上をライブハウスへって言っているミュージシャンも、自分たちもキツいみたいな状況もあって。お客さんもこんなにいろんなところから助けてくれって言われても限界あるよって感じになっているじゃないですか。だから今やりたいと思っているのは、新たなコンセプトのチャリティーアルバムの制作です。ちゃんと参加してくれた人たちも対価がもらえる。ミュージシャンもアーティストも、スタッフ、例えばエンジニアさんとか、デザイナーさんとかも、その対価をちゃんと分けるっていう。ミュージシャンは普通印税方式なので、めちゃくちゃ売れたらその分貰えるみたいな仕組みだけど、今回は「バイアウト」という一定額で分配する仕組みにする。売上げが一定額を超えたらフリーの方々やライブハウスとか、それこそ飲食店とかも含めていいのかもしれないですけど損失があった人達に、どんどん分配していく。もちろんお客さんも寄付しているという感覚ではなくて、欲しいと思える作品を作る。それならある種全員ハッピーなんじゃないかなと思っています。施す側と施される側という図式にするのはすごくいいことなんですけど、おそらくもういっぱいいっぱいな感じなので。次に進んでいくためには、作った側もちゃんともらえるハッピーな形の作品を今作りたいなと思っていますね。━━とても面白いですね。あと、これはいろんなところで言っているんですけど、2000万円寄付するうちの残りの半分はいわゆるサッカーでいったらJリーグとか、ワールドカップとか、そういう「切磋琢磨できる大会」みたいなものをやりたい。音楽に関してはもちろんレコード大賞とか、紅白とかあるんですけど、僕が寄付している人間は一生関わらない可能性もあるので。海外だと、映画業界とブロードウェイとテレビでさえコミュニティが違う。でも日本だと、音楽も映画も全て芸能界っていう感じじゃないですか。僕らはもともと芸能界には入れない側なので、そっちには迷惑かけない形で、「音楽界」みたいなものを作って、お互いに共存していく。でないと、テレビに出ないと活躍できないっていう風に、活躍できるミュージシャンが限られてしまうので、そういったことは今後やっていきたいなと思っています。 ━━最後に、これは賛否両論ですが、ドイツでは文化省の大臣が「文化というのは守らなけばいけない」というのを公言して、実際に芸術家やアーティストに支援を出したと思うんですけど、日本はカルチャーというものに対する考え方やフィロソフィーが足りないなって僕は思ったんです。 全く同感です。例えば電化製品とか他の産業とかって、文化の影響って大きいと思っている。例えばYMOが世界に出て行ったときって、例えばソニーのウォークマンとか、車もそうですけど、イケてるみたいなものが一括りに考えられていましたよね。例えば韓国のサムソンなりヒュンダイなりが世界に出て行ったときも、韓国の音楽も同時に出ていってるんです。だから、若い人にとっては音楽とかファッションとか、それがクールなら、電化製品とか車とかも全部クールになっていく。だから、本当の意味でのクールジャパンみたいなものを作ろうとしたら、そういうことをやるべきなんですよね。もっと王道なものでいいものを作っていく。そうすれば文化が大事だということに気が付くはず。音楽関係者も、もっといいものにお金をかけていくことをしなきゃいけないと思っている。Text by nakohji koshiro
『White Teeth Donation』について『White Teeth Donation』活動報告ハッシュタグ #origamiHomeSessions
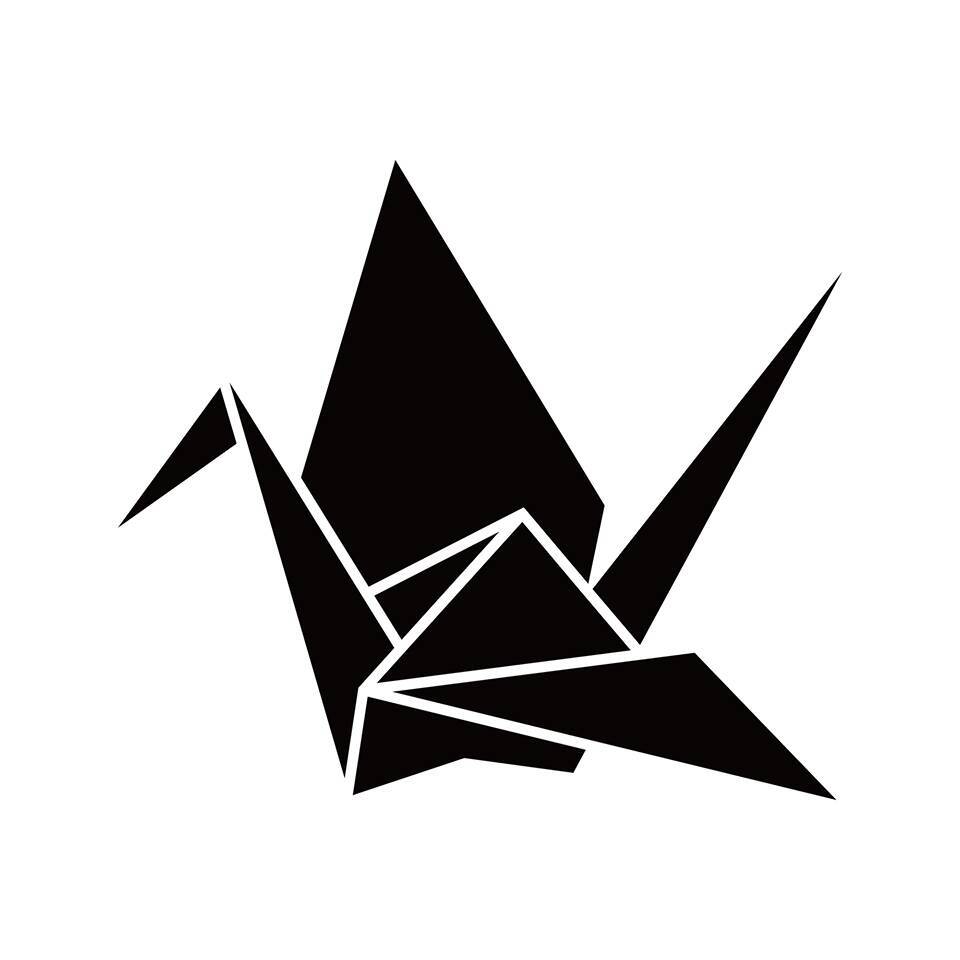
origami PRODUCTIONS1枚の紙でなんでもできるオリガミのように、楽器1つでどんな音でも奏でることができるミュージシャンが集うクリエイターチーム、レーベル。Ovall、Kan Sano、Michael Kaneko、Hiro-a-key、Shingo Suzuki、関口シンゴ、mabanua、Nenashiが所属。2007年に東京で産声をあげ、常に“音の鳴る方へ”と歩み続け、今に至る。渋谷のアンダーグラウンドで盛り上がっていたジャズ、ソウル、ヒップホップを軸としたジャムセッションムーブメントを世界中の音楽ファンに届けるべくスタートしたが、現在はより自由な表現を追い求め、ジャンルレスでボーダレスなスタイルで活動の幅を広げている。所属アーティストは国内外での大型フェスの常連であると同時に、映画・ドラマ・アニメやCM音楽の制作、また世界中のアーティストをプロデュース、リミックス、演奏などでサポートしている。 HP |Twitter|Instagram|Facebook|YouTube|Apple Music|Spotify
INFORMATION

origami Home Sessions
レーベルに所属するShingo Suzuki、mabanua、Kan Sano、関口シンゴ、Michael Kanekoはインストトラック、Hiro-a-keyはシンガーとしてアカペラ音源をネットにアップ。それらのインストトラック/アカペラは、ファンの方ももちろん視聴可能で、そのままの楽曲を楽しむことも可。アーティストの方々は、これら楽曲のパラデータ、ステムデータもダウンロードすることができる。そのまま使う、構成を変える、サンプリングするなどして、ラップや歌を乗せたり、楽器を足すなどコラボはアイデア次第だ。その楽曲はネットにアップしても、CDやストリーミングで販売してもOKで、収益は全てリリースしたアーティストに提供される仕組みとなっている。
私達ももちろん楽曲をリリースしたり、ライブをやって収入を得る側にいますが、プロデュースや楽曲提供などで収益を得ることもできます。つまり私達は普段からアーティストやレーベルの皆さんに生活を支えていただいている立場でもあります。だから今はライブができないと困ってしまう仲間を助けるときだと思っています。 音楽ファンの方々も同じ曲で色々な歌、ラップ、楽器などのヴァージョンがどんどんリリースされたら自宅で楽しむ事ができます。些細なことですが少しでも盛り上がってくれればと思います。地球上全員で、共にこの危機を乗り越え、またライブ会場でお会いできる日が来るよう心より願っております。 origami PRODUCTIONSアーティスト、スタッフ一同詳細はこちら
Copyright (C) Qetic Inc. All rights reserved.





























![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



