1969年8月、マンソン・ファミリーによるテート・ラビアンカ惨殺事件が世間を騒がせてから半世紀が経ったが、事件とビートルズの関連性はいまも謎に包まれたままだ。ラビアンカ家の冷蔵庫には被害者の血で「Healter Skelter(原文ママ)」と書かれていたが、その重要性にスポットライトが当てられたのは裁判が始まってからだった。事件から1年後、チャールズ・マンソンと彼の信者が判事の前に姿を見せた時、検察のヴィンセント・バグリオシ氏は殺人の動機を、ホワイト・アルバムの歌詞をマンソンが曲解したためだと説明した。
ホワイト・アルバムがリリースされたのは事件の数カ月前、1968年11月。
「チャールズ・マンソンは”ヘルター・スケルター”を、黙示録の四騎士と関係があると解釈したんだ」と、マッカートニーは2000年の著書『ビートルズアンソロジー』の中で述べている。「それが何か、僕はいまだにわからない。聖書の『ヨハネの黙示録』に出てくるのは知ってるけど――読んだことがないから知りようがないね。でも彼はそういう風に解釈した……そして、世の中の人々を抹殺しなくては、と思い至った……恐ろしいことだよ。
「自分とは何の関係もない」と、ジョン・レノンは1980年プレイボーイ誌とのインタビューでこう言った。「マンソンはポール死亡説を思いつく連中や、『ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ』の頭文字がLSDだから、アシッドについて書いた曲だと決めつけるような奴らの最たる例にすぎないよ」
「チャールズ・マンソンのような怪しい輩と結びつけられるのは迷惑だ」と、ジョージ・ハリスンも『ビートルズアンソロジー』の中で述べた。
「僕はシャロン・テートや(テートの夫)ローマン・ポランスキーと知り合いだっただろ。本当にあの時はつらかった」とリンゴ・スターが語る。
マンソンが語った人種闘争=ヘルター・スケルター
マンソンは後年、ビートルズに傾倒していたという説を否定するようになったが(「俺はビング・クロスビーのファンなんだ」と1985年に宣言――だが、60年代初期にマンソンと同じ房にいた囚人らは、彼がビートルズに取り憑かれていたと証言している)、信者らとはビートルズについてイヤというほど話してきたので、ビートルズでもっとも実験的なアルバムに対する彼の曲解は裁判中ずっと話題にのぼっていた。バグリオシ氏が刑事起訴されなかった者も含め、マンソン・ファミリーのメンバー数名に話を聞いてみると、ホワイト・アルバムにもとづく彼の教義や、世界の終末を描いた『ヨハネの黙示録』と無理やりこじつけていたという説明が、どれも一貫していたことが判明した。
「この音楽は革命を、体制を覆す無秩序な力を引き起こしている」と、1970年マンソンはローリングストーン誌に語っている。「ビートルズは潜在意識下で(この後の展開を)知っているんだ」
「チャーリーは初めから、ビートルズの音楽が重要なメッセージを――我々に向かって――発信していると信じていました」。マンソン・ファミリーのメンバーだったポール・ワトキンス氏は自著『My Life With Charles Manson』の中でこう書いている。「彼は、ビートルズのアルバム『マジカル・ミステリー・ツアー』が自分の哲学の本質を表現していると言っていました。基本的にチャーリーの目的は、我々全員を服従させるようプログラムすることでした。自我を捨てさせること。
マンソンがホワイト・アルバムを知ったのは1968年12月。凍えるようなカリフォルニア州の砂漠地帯を逃れ、ロサンゼルスに一時滞在していた時だった。大晦日にデスヴァレーに戻った彼は、仲間たちにアルバムを聴いた感想を聞いて回った。「ビートルズの言ってることに気づいたか?」。バグリオシ氏の著書『Helter Skelter』にもあるように、ファミリーのメンバーの1人ブルックス・ポストン氏は、マンソンから質問を受けた時のことをこう振り返っている。
ホワイト・アルバムがマンソンを虜にした理由
ホワイト・アルバムはたちまちマンソン・ファミリーの間に浸透していった。アルバムがリリースされる前、マンソンはスーザン・アトキンスを”セディ・メイ・グルツ”と改名していたが、アルバムの中に「セクシー・セディ」というポップな曲が収録されていたため(もともとは、ミア・ファローを誘惑したとされるマハリシ・マヘーシュ・ヨーギー氏にちなんで”マハリシ”というタイトルがつけられていた)、自分が先を見越していたかのような気になった。彼はバラード「アイ・ウィル」の歌詞――「君の歌が大気を満たす/歌っておくれ、君の声が聴きたいんだ」――を、自らアルバムを制作して、我こそはイエス・キリストの再来だというメッセージを世に広めろと命じられたと解釈した。
マンソン・ファミリーは、イングランドに電報や手紙を送ったり電話をかけたりして、人種闘争が来る前に仲間に加わるようビートルズを誘ったと言っているが、実際にはバンドと接触することはなかった。そこで彼らはマンソンのアルバム制作に乗り出した。マンソンはプロデューサーに、ビーチボーイズとも仕事をしたこともあるドリス・デイの息子、テリー・メルチャーを希望していた。メルチャーはシエロ・ドライブ10050番地に住んでいたが、マンソンとの関係を絶ってシエロ・ドライブの家から引っ越したため、レコーディングは実現しなかった。その後すぐに入居したのが、ローマン・ポランスキーとシャロン・テートだった。
その間ずっと、ホワイトアルバムの曲はマンソンの中でどんどん大きな存在になっていった。バグリオシ氏が『Helter Skelter』の中で書いているように、「ロッキー・ラックーン」――マッカートニーとレノン、ドノヴァンがインドで思いついた”ロッキー・サッスーン”という名のカウボーイから生まれた、お茶目でメロドラマ風の楽曲――は、マンソンにとっては暗にアフリカ系アメリカ人の蜂起についての物語だった(マンソンは”クーン”という響きが気に入っていた)。「”ロッキーの復活”――復活、つまり蘇るってことだよ」とマンソンは1970年、ローリングストーン誌に語った。「黒人の男が再び権力の座に戻るのさ」。また、おそらくレノンが手掛けた中でもっとも意味深な曲「ハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン」も、バグリオシ氏の言葉を借りれば、マンソンには「ビートルズが黒人連中に、銃をとって白人と戦えと言っている」という意味になった。
マンソンが特に好んでいたのが、「ブラックバード」「ピッギーズ」「レボリューション1」「ヘルター・スケルター」「レボリューション9」の5曲だ。マンソンの信者らはのちに、彼がアルバムの最終曲のタイトルを『ヨハネの黙示録』9章になぞらえていた、と証言した。『ヨハネの黙示録』9章には、底なしの地獄の穴が世界にぱっくり口を開け、天使が神にむかってラッパを鳴らすまで、長い髪をした擬人化したイナゴの害が発生し、不信心な人々を苦しめる、と書かれている。ファミリーの一員だったグレッグ・ジャコブソン氏は『Helter Skelter』の中で、マンソンが聖書と「ビートルズの楽曲、メンバーの口から発せられたパワーを比較していた」と述べた。
「ブラックバード」は、マッカートニーが手がけた心揺さぶるアコースティックソング。市民権運動の黒人女性たちへの応援歌も、マンソンの中ではアフリカ系アメリカ人が体制に果敢に挑む歌として響いた。ワトキンス氏がバグリオシ検事に語ったところでは、「ブラックバードが真夜中に歌っている/折れた翼で飛ぼうとして……君はただ、立ち上がる瞬間を待っていた」という歌詞を、マンソンは「黒人たちが立ち上がり、さっそく取り掛かって事を起こすよう、ビートルズが仕向けているのだと解釈していました」。「”立ち上がれ”というのが、チャーリーにとって重要な言葉のひとつでした」とジャコブソン氏は検事に語ったが、これがマンソンの動機を確立する決め手となった。ラビアンカ家の壁にも「立ち上がれ」という血文字が書かれていたからだ。
「ヘルター・スケルター」作曲の本来の意味
「ヘルター・スケルター」はもともとピート・タウンゼンへの挑戦状として書かれた曲だ。ザ・フーのギタリストがメロディメイカー誌とのインタビューで、「恋のマジック・アイ」を史上もっともワイルドな曲だと評したのがきっかけだった。「僕の闘志に火をつけて腰をあげるには、あの一言で十分だった」と、のちにマッカートニーは語っている。「それで本腰をいれて、史上もっともやかましいヴォーカル、もっとも騒々しいドラムにしようと思って書いたのが”ヘルター・スケルター”だ」。彼はまたこうも語っている。「おふざけで書いた曲だよ……僕はノイズが好きだからね」。裁判でのマンソンの発言によれば、彼はヘルター・スケルターを一般的な意味でのカオスと解釈した。彼にとってもっとも重要なテーマだったことは、マンソン・ファミリーの隠れ家のひとつスパーン牧場のドアに”ヘルター・スケルター”と書かれていたことからも明らかだ。だが、ファミリーの一員だったポストン氏によれば、マンソンは『ヨハネの黙示録』の地獄の穴からファミリーが現れたことを指していると考えたようだ。
「(”ヘルター・スケルター”が)意味するのは、文字通り混乱だ」と、マンソンは裁判で述べた。「誰かと戦争することじゃない。他の誰かを殺すことじゃない……ヘルター・スケルターは混乱なんだ。混乱があっというまに自分たちを取り囲む……」
「体制が急激に世の中をぶち壊しているから、音楽が若者に体制に立ち向かえと命じているなんて、まるで陰謀じゃないか?」と彼は続けた。「音楽は日々語りかける。だけど、聴く側がバカで、トンマで、世間知らずだから、音楽など聴きもしない……俺が企てた陰謀じゃないぜ。俺の音楽でもない。俺は音楽が語ることに耳を傾ける。音楽が『立ち上がれ』とか『殺せ』と言ってるんだ。なぜ俺のせいにする? 俺が曲を書いたわけじゃないのに」
だが、作り手には曲の意味は事理明白だった。「僕はヘルター・スケルター(遊園地の滑り台のこと)を、頂点からどん底へ落ちる象徴として使ったんだ――ローマ帝国の浮き沈みをね」と、かつてマッカートニーはこう言った。「物事の終焉、没落。なかなか洒落たタイトルだと思われてもいいはずだったのに、マンソンがあの曲を旗印に掲げてしまったものだから、あれ以来あらゆる類の不吉な前兆、という意味になってしまった」
お次は「ピッギーズ」。フォークとナイフで外食する上流階級の人間を描いた、ハリソンによる遊び心あふれる1曲だ。彼がこの曲を最初に書いたのは1966年。ホワイト・アルバムのレコーディング中に、レノンが「奴らに必要なのは最高級のおしおきだ」という歌詞を加えて完成した。だが、マンソンにとっては違う意味を持っていた。「マンソンはこの歌詞を、黒人が豚、つまり体制に最高級のおしおきをする、と解釈したんです」とジャコブソン氏はバグリオシ氏に語った。スーザン・アトキンスはのちに、シセロ・ドライブの家のドアにシャロン・テートの血で”pig”と書いた。ファミリーはラビアンカ邸の壁にも”豚に死を”という血文字を残し、フォークとナイフで一家を殺害した。
マンソンが受け取ったレノンのメッセージ
「マンソンの事件はすべて、豚についてのジョージの曲と、イギリスの遊園地についてのポールの曲から生まれたものだ」とレノンはかつてこう言った。「とくに何の関連もないし、少なくとも俺とは無関係だ」。だが実際には、マンソンはホワイト・アルバムに収録されているレノン作曲の2つの「レボリューション」にも独自の解釈を加えている。
「レボリューション1」は、グルーヴの効いたロックな1曲。たしかに、パリの学生運動やテト攻勢、中国の毛沢東共産主義の世界拡大など、政治革命に関するメッセージもいくらか織り込まれている――が、マンソンの耳には届かなかった。最初のコーラスが始まるや、レノンはこう歌い出す。「破壊について語るとき/俺をのけ者にしても、仲間にしてもいいんだぜ……わかってるか」と。
「あえて両方(”のけ者”と”仲間”)入れたんだ。自分でもはっきりしなかったからね」とレノンは言った。「殺されるのはゴメンだからな」。マンソンにとっては、それまでどっちつかずだったビートルズが、今はっきり暴力革命にGOサインを出したことを意味していた。マンソンにとって「みんな計画を知りたがってるぜ」という歌詞は、自分がメッセンジャーになり得ることを彼らに伝えなくては、というメッセージだった(彼はそのあとの対句を聞き逃したようだ。「だが、もし悪意に満ちた連中のために金が欲しいっていうなら/俺が言えることはただひとつ、ブラザーちょいと待ちなよ」)
とはいえ、マンソンがもっとも感銘を受けた「レボリューション」は「レボリューション9」だった。レノンが手がけた8分強の実験的音楽。20ものサウンドエフェクトを駆使して作った、アヴァンギャルドな音楽の旅。シベリウスの交響曲第7番や、「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」のオーケストラの多重録音パートもサンプリングされている。レノンはこの曲を当時付き合っていたオノ・ヨーコと共作し、ハリソンが自分のラッキーナンバー”9”をタイトルに加えた。「”レボリューション9”は、もし何か起きるとすればきっとこうなるだろうと僕が実際に考えた、無意識の未来予想図だ。革命の下書きみたいなもんさ」とレノンは『ビートルズアンソロジー』の中で述べている。「ただただ抽象的。ミュージックコンクレートにループ、そして人々の叫び声」。ニューヨーク・タイムズ紙はこの曲を、2枚組アルバムの中でもとくに「曲とも呼べない駄作」で、「偶然の代物」だと評した。
マンソンにとってはこれぞアルバムの真骨頂だった。ジャコブソン氏によれば、彼はこう考えた。「これから起こることを、ビートルズなりに予告しているんだ。彼らなりの予言なんだ。『ヨハネの黙示録』9章を直接たとえているんだ」。マンソンはマシンガンの発射音の奥に、豚の鳴き声と「立ち上がれ」と言う男性の声を聞いたと言われている。バグリオシ氏も自著の中で、この曲を聴いて驚いたと書いている。「実際に自分でも聴いてみた後、もし本当にそうした闘争があったなら、こんな風に聴こえたかもしれないな、と思いました」 だが、マンソンにとっては自明の事実だった。
ホワイト・アルバムはマンソン・ファミリーの日常生活のBGMになった。曲に隠されていると思しきメッセージを読み解き、マンソンの残忍かつ怪しげなビジョンの地獄絵にどう当てはめられるかを考えた。ワトキンス氏が言うには、マンソンは「ピッギーズ」「ヘルター・スケルター」「レボリューション9」――とくに、「レボリューション9」のマシンガンのパート――に、何度も同じコードが繰り返されているのを聴き取った。どういうわけか、それがマンソンの心にヒットした。
「音楽は全員にメッセージを送っている」と、かつてマンソンは言った。「音楽からメッセージを受け取ったからといって、頭のイカれたふりをする必要などどこにある? 音楽が『虹の彼方に』と言うなら、虹の彼方にいくまでよ」
結果的に「へルター・スケルター」は多くの人に知られる曲となった
1970年にローリングストーン誌がマンソンに接触した際、記者は複数のメッセージがつながる理由を説明してくれ、と頼んだ。彼はホワイト・アルバムの曲から何曲か選ぶよう言い、記者は「ビッギーズ」「ヘルター・スケルター」「ブラックバード」を選んだ――そこにマンソンがおまけとして「ロッキー・ラックーン」を加えた。彼は紙の上にそれぞれの曲のタイトルをさながら記事の見出しのように書き出し、「ヘルター・スケルター」の下に波線を、「ブラックバード」の下には鳥の鳴き声と思しき記号を2つ描いた。「この下の部分が潜在意識だ」と彼は言った。「それぞれの曲の最後には小さな印があるんだよ、いくつかの音がね。”ピッギーズ”の場合は”ぶうぶうぶう”とか、ちょっとした音。そういう音が全部”レボリューション9”で繰り返されているんだ。”レボリューション9”ではこういう音がすべてひとつに収まって、暴力による白人社会の転覆を予見しているってわけさ。”ぶうぶう”って音のすぐ後に、マシンガンの”タカタカタカタカッ!”って発射音が聞こえるだろ」
ビートルズが本気で革命を意味していたと思うか、という質問されると彼はこう言った。「潜在意識的なものだと思う。彼らが本気だったかどうか、俺にはわからない。でもそこにあるんだ。潜在意識の現れなんだよ」
あまりにも突拍子過ぎるので、バグリオシ氏はマンソンおよび共犯者を立件するにあたり、型破りな手法で陪審にアプローチする必要があると悟った。「普通なら、裁判では延々と証言を繰り返すのは避けるようにしている。陪審を敵に回すことになりかねないからだ」と彼は自著の中で書いている。「だが、マンソンのヘルター・スケルターの動機はあまりにも常軌を逸しているので、講釈する証人が1人しかいないとなると、陪審は誰も信じてくれないだろうと思った」。陪審には審議までに、2つのことをするよう求められた。ひとつは殺害現場に足を運ぶこと。もうひとつはホワイト・アルバムを事前に聴いておくことだった。
1971年1月25日、陪審はマンソン及び3人の共犯者に有罪評決を言い渡した。その年の4月、判事は被告らに死刑判決を言い渡したが、1972年にカリフォルニア州が死刑を撤廃したため終身刑に減軽された。
翌年以降、「ヘルター・スケルター」は――こんな事件がなければ、ビートルズの曲の中でも忘れられた存在になっていたかもしれない、滑り台についての隠れた名曲――意外にも、ビートルズの中でもっともカバーされた曲のひとつとなった。「この曲は、チャールズ・マンソンによってビートルズから奪われた」とボノは、U2が『魂の叫び』でカバーする以前にこう述べた。「俺たちが奪い返してやる」。エアロスミスやスージーズ・アンド・ザ・バンシーズ、モトリー・クルー、オアシス、ホワイト・ゾンビ、サウンドガーデン、ボン・ジョヴィ、ザ・キラーズなど、さまざまなアーティストがこの曲をカバーしている。誕生のきっかけを作った張本人――ロジャー・ダルトリー――もしかり。その名もHeltah Skeltahというヒップホップ・デュオや、マンソン・ファミリーと名乗るグループ、D.O.C.が『ヘルター・スケルター』というタイトルのアルバムをリリースしているし、アイス・キューブやエミネム、リル・ウェイン、ビッグ・パン、デス・グリップスらの曲では、”ヘルター・スケルター”が恐怖の象徴として描かれている。ビデオゲームや漫画、複数のTVドラマのタイトルにも使われている。
だが最も驚くべきは、マッカートニー本人が2004年を皮切りにこの曲を演奏するようになったことだろう。以降コンサートのセットリストの常連となり、昨年は野外フェスDesert Tripで2ステージともこの曲を演奏した。マッカートニーが演奏するこの曲のライブ音源はグラミー賞すら受賞している(ちなみに、この曲がグラミーにノミネートされたのはこれが初めてではない。1984年、The Bobsのアカペラバージョンがノミネートされている)。
「ボブ・ディランは、『抱きしめたい』の歌詞のI cant hideをI get highだと思っていた」とマッカートニーは『ビートルズアンソロジー』で、「ヘルター・スケルター」との絡みでこう述べた。「ちょっとした愉快な解釈の違いは以前からあったけど、どれも無害で、くすっと笑えるものだった……でも、そういうささいな解釈のあと、とうとう最高に恐ろしい解釈が現れた。あの時点から全ておかしくなった。でも僕らのせいじゃない。僕らに何ができるって言うんだい?」
チャールズ・マンソンはただのイカれた奴
「誰もがハッとした。ラブ&ピースやサイケ満載のアルバムで、いきなりこんな暴力的な曲が出てきたんだから」と、リンゴ・スターは言った。「実際、本当にさんざんだった。ロサンゼルスの誰もが『大変だ、いつかは我が身だぞ』と感じていた。悪人がつかまったのがせめてもの救いだ」
「もうひとつ僕がいらっとしたのは、マンソンが殺人犯としてはもちろん、長髪と口ひげ姿のイメージを塗り替えたことだ」とハリスン。「それまで長髪と髭といえば、散髪に行かないとかひげを剃らないことだった――なんかむさくるしい、というだけだったのに」
「事件が起きた時に自分が何を考えていたか、覚えてないな」とレノンは1970年、ローリングストーン誌に語った。「彼が口にした多くのことは真実だ。彼はこの国が生んだ鬼っ子、彼を作ったのは僕らだ。彼はそういう行き場のない鬼っ子どもを集めた。もちろん、正真正銘イカれた奴だけどね」
「ピッギーズ」や「ヘルター・スケルター」に関しては? 「彼はネジがイカれてるよ。神秘的なものを勝手に読み取るような、ビートルなんちゃらファンと同じさ」とレノン。「僕らはこの手のことを、軽い気持ちで受け流してきた。知恵の働く人は僕らのことを理解してくれるし、象徴主義的な若い世代はそこに何かを見つけたがる。僕らも時には真剣にとらえることもあるけど、でも”ヘルター・スケルター”が刺殺とどう関係するのか、僕にはさっぱりだ。そんな歌詞はどこにも見当たらない。あれは単なるノイズなんだ」
















![医療機器販売の(株)ホクシンメディカル[兵庫]が再度の資金ショート](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FTsr%252Fa8%252FTsr_1198527%252FTsr_1198527_1.jpg,zoom=184x184,quality=100,type=jpg)
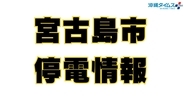











![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)


![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






