先週、2人のラテンミュージックのビッグスターがYouTubeのカウント方法をめぐって火花を散らした。2000年代に数々のヒットを飛ばしたレゲトンの大御所ドン・オマールは、ラジオ番組『Alofoke』に投稿し、自称人気アーティストは実際には再生回数を金で買っているのだと仄めかした。
翌日、YouTubeでの人気記録で4回もギネスブックに認定されているOzunaが同番組に電話。ドン・オマールは「意見できるほど、大して活躍していない」と反撃し、こう付け加えた。「ぶつくさ言うのはやめて、とっとと仕事にとりかかれ」
今月初めにローリングストーン誌も詳しく報じたように、YouTubeにはGoogle広告を使って再生回数を伸ばすという合法的なやり方が存在する。アーティストは最大10万ドル払えば、自分たちのビデオを短い広告として、他の動画の再生前に流してもらえるのだ。ユーザーが広告をクリックする、または一定の時間閲覧すれば、再生回数としてカウントされる。たとえユーザーが実際にそのビデオを検索したわけでなくても、だ。
金曜日、YouTubeはこの種の広告による再生回数の取り扱いを変更する計画を発表した。「業界のさらなる透明化のために」と同社はブログに投稿。「……今後、有料広告の再生回数をYouTubeの音楽ランキングには一切カウントしません。
だが、こうした変更が反映されるのはランキングと24時間再生回数のみ。閲覧件数を増やすための有料広告は今後も継続される。また、動画に公開される視聴回数カウンターには、有料広告の再生回数も反映される。
なので、YouTube公認の閲覧件数購入に批判的な人々が、同社の新ポリシーは見せかけにすぎないと考えるのも無理はない。「何にも変わりませんよ」 YouTubeのルール変更について尋ねられたあるラテンレーベルの関係者はこう答えた。「結局のところ、YouTubeが(再生回数を)認めないとしても、アーティストは依然世間に向かって『ヘイ! これ見てよ!』と言い続けるでしょう。同じことです」
YouTubeは2つの気持ちの間で板挟みになっている。かたや、数百万の再生回数が金で買えるということは、YouTubeのカウント方式の信憑性が疑われることになる。「全てのアーティストの成功や偉業が正しく評価され、称賛される場所として、YouTubeがあり続けること、それが我々の目標です」と同社はブログでこう述べた。
だが同時に、別の関係筋が「(YouTubeの)ストリーミング数を稼ぐ真っ当な方法」と呼ぶGoogle広告の類は、YouTubeにとって確実な収入源だ。ポップミュージック以外でも広く使われている。それゆえ、YouTubeのポリシー変更は問題の上っ面を撫でただけで、実際には大元の原因は手付かず状態だ。
7月、YouTubeのペイパービュー・ポリシーに対して非難が集中した。インドのラッパーBadshahの新作ビデオが、24時間で7500万件もの再生回数を記録したのだ。表面的には新記録だ。だが、ラッパーは再生回数を増やすために相当の金を払っていた。この件については彼自身もInstagramで大っぴらに認めており、YouTubeも彼の業績を公認していない。新ルールのもと、BadshahはYouTubeの再生記録から正式に除外されることになる。
だが、再生回数はBadshahのアカウントには視聴回数として公開されている。それが商業力として間違った印象をあたえ、ラッパーがマーケティング戦略に利用することも考えられる。今月初めにとあるラテンレーベルの社員も言ったように、「24時間で1000万件や2000万件の再生回数! ――そんなのありえない」
リスナー獲得をYouTubeに大きく頼っているラテン音楽業界の一部では、こうした間違った情報が懸念材料になっている。関係筋によれば、アーティストやレーベルは動画公開後最初の24時間の再生回数を増やすために、たっぷり予算を割いているという。新人アーティスト――あるいは、6桁もの宣伝費を割けない人々にとっては、前途多難な状況を作り上げている。誰もが注目を集めようと必死だが、「メジャー(レーベル)がYouTubeに5万ドルも投入する中で、どう対抗しろと言うんです?」と、とある関係者は問いかける。
業界の全ての人々がやきもきしているわけでもない。ダディー・ヤンキーやニッキー・ジャムといったスターを輩出したPina Records社のラフィ・ピナ氏は、月曜日Twitterに投稿。YouTubeの再生回数を買うことは珍しくもなんともないと仄めかした。「今や誰もがデジタルストリーミングで、自分たちの商品を幅広い層に売り込む時代だ」と、ラテン音楽情報サイトRemezclaには英文翻訳の彼のコメントが掲載されている。「基本中の基本だよ。諸君、投資したまえ」
Ozunaも『Alofoke』への電話でPinoのコメントを繰り返した。「垣根を越えて自分の商品をアピールしたいなら、ある程度マーケティングはするべきだ」と本人。
YouTube公認の再生回数購入に批判的な人々も、広告戦略としての効果は認めている。「ツールとしては有用です」と、別の関係者も言う。「ですが、手元に金があると悪用してしまう」YouTubeのポリシー変更は、今後の悪用の可能性を絶つまでには至らない。



















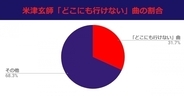


![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








