本作は、一聴すると彼らのルーツである轟音ギターと浮遊感のあるメロディが戻ってきたように感じられる。
同時にリリースされたのが、2010年発表の1stアルバム『TOY』のリマスター再発盤。現在では入手困難となっていた本作に、当時の未発表曲も加えられ、15年の時を経て鮮やかに蘇った。あらためて聴く『TOY』と『HIGH HEART』を並べてみると、変化と不変、その両方が浮かび上がってくる。
表現者としての焦燥感と、地に足のついた創作への姿勢。インディペンデントな活動を続けるPLASTIC GIRL IN CLOSETが、ふたつの作品を同時に世に送り出した今、彼らは何を思い、どこへ向かおうとしているのか。高橋祐二(Vo/Gt)と須貝彩子(Vo/Ba)に、じっくりと話を訊いた。
ー前作『DAWN TONE』から、オリジナルアルバムとしてはちょうど5年ぶりくらいになりますよね。この5年間、特にコロナ禍も挟んでの時期だったと思うのですが、どんな活動をされていたのでしょうか。
高橋:2020年の2月頃までは、月1回くらいのペースで東京へ行ってライブをしていて、それを10年以上続けてきました。でもコロナ禍に入ってライブが難しくなり、そのタイミングで一度ライブ活動を止めたんです。ちょうどその頃に制作していたのが前作『DAWN TONE』で、2020年の夏にリリースされました。これは、僕たちにとって初めてライブをせずにリリースした作品です。
ー『DAWN TONE』は、それまでのプラガがやってきたシューゲイザー的なサウンドとは、かなり異なる印象でしたよね。
高橋:そうですね。「音楽ってなんだろう?」とあらためて考え、和音やコードについて勉強しながら作ったアルバムでした。すごく気合いを入れて作ったぶん、演奏も難しくて。これまでは1曲の中でコードは4つか5つくらいだったのが、転調も含めてかなり複雑な構成にチャレンジしていましたね。
でも、そうやって全力で作り上げた直後にコロナ禍でライブができなくなって、ふっと肩の力が抜けてしまって。10年以上ずっと走り続けてきたなかで、少し疲れもあったんだと思います。もしそのまま突っ走っていたら、きっとどこかで限界が来ていた。
ーなるほど。
高橋:その後はスタジオにもあまり入らず、ライブもせずに、ただ黙々と曲を作ってバンドでレコーディングをして、という日々が続きました。そうやって時間をかけて、じっくり完成していったのが今回のアルバムです。それと、期限に縛られることもなく、できた曲をその都度シングルとして発表していた時期もしばらくありました。テーマにとらわれず、ただ音楽を楽しんで作る、そんなスタンスで取り組んだ作品です。
ーサウンド的には「シューゲイズへの回帰」とも言えますか?
高橋:今回は、先行シングルを5曲リリースしていますが、そのうち「Baumkuchen」や「Troublemaker」、「Lovers」などはアルバムにも収録されています。ただ、これらはいずれも典型的なシューゲイズサウンドではなくて。「Baumkuchen」はマッドチェスターっぽさもあるし、「Troublemaker」は当初スウェディッシュポップを意識しながら作った曲。最初から”シューゲイズに戻ろう”という意識はなかったんですよね。あくまで、その時々の好奇心で、いろいろなタイプの曲を自由に作っていったという感覚でした。
ただ、「Ramune River」を作った時に、久しぶりに”これは完全にシューゲイズだな”と思えたんです。ディストーションをしっかり効かせた王道のシューゲイズサウンドで、その曲がきっかけとなり、今回はジャンルが混在するアルバムというより、シューゲイズでサンドイッチするような構成にしたら面白いかもしれないなと。つまり、アルバムの前半に歪んだギターのシューゲイズ曲を多めに置いて、中盤はポップでカラフルな曲を並べて、後半でもう一度シューゲイズに戻っていく、という流れですね。
ーとはいえ、曲の骨子というか、根本的な部分には前作を経たからこその要素が色濃く反映されているように感じました。たとえば今作でも、ディミニッシュやオーギュメントのコードが印象的に使われていて、従来のプラガのポップセンスとはまた違うアプローチが見えたというか。
高橋:まさにその通りで、”原点回帰”という言葉はセールスポイントとして使っていますが、実際には”以前のサウンドに戻った”という感覚は自分たちでもあまりなくて。たとえば、ディストーションの有無といった表面的な違いはありますが、それ以上にディミニッシュやオーギュメントの響き、そこに対するベースのルートの置き方など、前作がなければ思いつかなかった発想がたくさんあります。
それと、前作では「音符の配置の美しさ」や「歌との関係性」にも強くこだわっていました。たとえば歌をしっかり聴かせるために、88鍵盤のピアノで曲を組み立てる。それにより、メロディとコードがぶつからないように設計する。そんなふうに意識した結果、音色は控えめでアレンジも淡白というか、少し無骨な仕上がりになったと思います。今作はそうゆう理論的な部分も意識しつつ「これはマッドチェスターっぽく」「これはスウェディッシュっぽく」みたいな、10代の頃に持っていた”音楽への好奇心”も加えて表現できました。
ー複雑なコード進行を用いることで、シューゲイズ的なサウンドへのアプローチも、これまでとは違った変化が出ているように感じました。
高橋:そうですね。たとえば「Troublemaker」のように、転調があったり、少し変わったコードを多く使ったりしている曲では、同じノイズのレイヤーを一貫して流すのが難しい。なので、シューゲイズ感をどう出すかという点では、曲ごとにかなり考えました。調が変わらない曲は”音のループ感”や”空気感”を作りやすいのですが、転調があるとそれが成立しにくくなる。5曲目の「Cant Stop My Heart」なんかは、まさにその例で、1つの調にとどまらず、サビの途中で転調したり、モーダルな動きを取り入れたりしています。でも、それでもシューゲイズ的な音像をしっかり作れたと思っています。
ー具体的には、どのようにして成立させたのでしょうか?
高橋:ふわっと包み込むようなノイズのレイヤーを、いくつかのキーに合わせて個別に用意して、それを小節ごとに切り貼りしているんです。つまり、転調に合わせてノイズのキーも都度切り替えていった。それがすごく効果的でした。
以前のアレンジでは、たとえ曲の中で転調があっても、ノイズのレイヤーはひとつで最後まで突っ走ってしまうことが多くて。そうすると、コード感とぶつかって空気感が崩れてしまうことがある。
でも今回は、調性に合わせてノイズを丁寧に配置したことで、「Cant Stop My Heart」のような転調の多い曲でも空気感を壊さずに済んだ。アルバム全体のバランスも、ディストーションの質感やギターの入れ方を調整することで、うまく整えられたと思います。
ー須貝さんはベースのアプローチについて、今回はこれまでと違う点などありましたか?
須貝:前作と比べると、今回はかなりシンプルになったと思います。この10年ほど、いろいろな挑戦を重ねてきた時期だったので、ベースラインもわりと凝ったものが多かったんです。祐二さん(高橋)からも、難しめのフレーズをリクエストされましたし。でも今回は、アレンジ自体はヘヴィですが、聴いた印象としてはとてもシンプルに仕上がっているなと感じています。
ーボーカル面では、今回新たに試みたことや、これまでと違うアプローチはありましたか?
須貝:前作では、しっかり声を張って発声することを意識したのですが、今回はジャンルの方向性もあって、力を抜いて歌うことを意識しました。
高橋:僕も同じですね。前作を作っていた時は、アルバムの路線もあって「ウィスパーボイス一辺倒ではダメだ」という考えがあったので、当時はしっかり声を張ってガッツリ歌っていたんです。いわば”J-POP的”というか、「ポップスとして成立させるための意思」が強くあった。バンドをもっと大きくするためには、地声でしっかり歌うことが必要なんじゃないか?という気持ちもありました。
ー1曲目の「Pool」は、〈終わりゆく夏〉〈焼けた校庭〉〈幽霊と稲光〉といった言葉から「夏の情景」が強く浮かび上がります。
高橋:そうですね。夏の刹那的な感じが、この曲の核になっていると思います。歌詞だけ見ると、ただ風景を並べただけのように見えるかもしれませんが、あえて心理描写を省き、情景だけで感情を伝えたかった。「Pool」というタイトルは、例えば学校のプールのような場所ではなく、”地球そのものが巨大な水たまり”というイメージ。生き物が繁栄し、やがて死んでいく。そのサイクルの中で、夏という季節は虫や生き物が一斉に現れて、一番エネルギーに満ちている。でも同時に、その終わりが近いことも感じさせるんですよね。
僕は田舎に住んでいて、毎日田んぼ道をランニングしているのですが、そうした自然のリズムの中で、夏の儚さをよく感じています。空を見上げたとき、「ああ、地球って本当に青い星なんだな」と実感することがあって。その青さや空気の透明感、水の中にいるような感覚……そうしたものが、自然と”プール”という比喩に繋がっていきました。
ーとても詩的な感覚ですね。
高橋:それからこれは、アルバムタイトル『HIGH HEART』にも関わってくる話ですが、生き物って本来、種を残して死んでいくものですよね。でも、たとえば自分が子どもを残さずに亡くなったとして、思考や感情、意思はいったいどこに行くのだろう?と考えることがあるんです。個としての意識は消えてしまっても、文化や記憶のようなものが、どこかに漂っているかもしれない。そういう「個と星の関係」や「受け継がれていくもの」そして「受け継がれないものの行方」といったテーマが、この曲やアルバム全体に自然とにじみ出ている気がします。
ーその感覚は、何か特定の本やテーマからインスピレーションを受けたものですか?
高橋:いえ、特定の思想や作品に影響を受けたというよりは、毎日田んぼ道を走っているなかで自然と芽生えた感覚ですね。繁栄と衰退、そして終わり。そういう要素が、夏という短い季節のなかに凝縮されている気がします。
地元はこの曲のミュージックビデオにも登場するように、農業区域のかなり田舎ですが、そういう場所にいると、いろいろと考えさせられるんです。たとえば、今草刈りをしてくれているおじいさんたちがいなくなったら、いったい誰が手入れをするんだろう?もう朽ちかけている建物は、このまま誰にも壊されず朽ち果てていくのではないか?とか。”もう戻らない風景”について、よく思いを巡らせてしまいます。
でも、こういう”終わりの感覚”って、実は地球全体で共通しているのかもしれない。すべてのものは、いつか終わる。そういう感覚を、「夏」という季節を通じて感じている人は多いと思うんです。この曲は、そういった空気を言葉で説明しすぎず、感じてもらえるような曲にしたかった。結果的にその想いが、アルバム全体のテーマにも繋がっていった気がします。
ー他にも、例えば「Worlds End」といった楽曲の中にも、終末的なムードを感じます。
高橋:タイトル通り”終わり”を描いていますが、ここでの”終末”は社会や人間の文明に対するものではなく、もっと広い視点をイメージしています。たとえば、「もし星に意識があったとしたら、どんなふうに物事を捉え、何を願うだろう?」というような、少しぼんやりとした感覚を歌詞に込めました。
ーでは、「Ramune River」についてはいかがでしょう。〈国道の音と虫の声〉〈灯籠流し〉など、”彼岸”の気配や死生観に触れているような印象も受けます。
高橋:また似たような話になりますが、”過ぎ去っていくもの”を考えると、どうしても死や記憶といったテーマに行き着いてしまうんですよね。「自分は何を残せるのだろう?」とか。ただ、たとえ個人が亡くなっても、他者との関わりのなかで何かが受け継がれていくことはあると思っています。
もちろん、死は怖いし寂しさもあります。でもそれだけで終わらせず、「じゃあその先をどう繋いでいけるか」ということを前向きに捉えたかった。寂しさや儚さはあるけれど、消極的なトーンにはしたくなかったんです。「過去が最高だったとしても、未来にはもっといいことがある」と思えるように、生きている限り楽しいことをやっていきたい。そんな思いを込めた曲です。
ー一方で、「Vicious Cycle」や「Troublemaker」では、シーンや”評論”に対する皮肉や風刺のようなニュアンスも感じられました。
高橋:たしかに”評論家”という言葉は出てきますが、評論家を直接指しているわけではないんです。どちらかというと、社会全体の空気やムードへの問題提起というか。最近、何かが起きたときに、その背景をよく知らないまま判断してしまうような風潮が増えている気がしていて。もちろん、分からないことがあるのは当たり前だし、真相に辿り着くのは難しい。もう少し立ち止まって考える余白があってもいいんじゃないかと思うんです。
ーSNS時代ならではの、瞬間的な反応への違和感とも言えるかもしれませんね。
高橋:同時に、音楽業界そのものにも”使い捨て”的な構造を感じることがあります。アーティストがヒットチャートの流れの中で、常に”更新”されるような立場に置かれていて。でも、ひとりの表現者の才能や個性って、本来もっと時間をかけて育てていくものだと思うんです。そういう余白があれば、もっと面白い作品が生まれていたのではないかなと。
僕らは、幸運にもそういった競争的な場所から少し距離を置いて活動してこられました。でもだからこそ、外から見えることもあるし、表現する側も受け取る側も、もっと”刹那的な消費”ではない関わり方ができたら、作品の見え方も深まり、もっと音楽が楽しくなるんじゃないかと思っています。
ー今回のアルバム『HIGH HEART』は、バンドにとってどんな位置づけの作品になったと感じていますか?
高橋:これまでは、どちらかというと”挑戦の時期”だったと思います。常に何かを模索しながら、手探りで進んできた感覚があった。でも今回は、そうした流れがようやく一つのかたちに”着地”した、そんな手応えがあります。これまで試行錯誤してきたこと、挑戦してきた要素が、ようやく自然にまとまった。そんな”集大成”的なアルバムだと思っています。
ー今回、1stアルバム『TOY』のリマスター再発もありました。ちょうど15年前の作品になりますが、改めて当時の自分たちを振り返ってみて、変わった部分、変わらない部分についてどう感じましたか?
高橋:リマスター作業に入る前は、「当時は演奏も楽曲もまだ拙かっただろうな」と思っていたんです。でも実際に聴き直してみると、「あれ? 意外といい曲だな」と思える部分が多くて(笑)。演奏も「ちゃんとできてるじゃん」と、少し驚きましたね。
もちろん、前作では音楽的に挑戦したことや、新しく学んだこともたくさん詰め込みました。でもそれとは別に、「変わっていない部分もちゃんとあるんだな」と。実際に『TOY』と新作を並べて聴いても、そこまで大きな違和感がないんです。自分たちでは「変わってきた」と思っていても、根っこの部分は意外とそのままだったんだなと、あらためて思いました。
ー須貝さんは『TOY』を改めて聴いて、どう感じましたか?
須貝:今聴いてもやっぱり『TOY』はかっこいいなって思いました。
ーそして、ここまで活動を続けてこられた理由、支えになったものは何だったと思いますか?
高橋:やっぱり一番は「悔しさ」ですね。負けん気というか、「もっとできたんじゃないか」という感情が、自分たちを突き動かしてきたと思います。アルバムを作り終えても、毎回「まだ伸びしろがある」と思ってしまう。
ー「悔しさ」がモチベーションとは意外です。
高橋:前作では音楽理論を学んで、”できるようになった”ことは確かに増えました。でも、初期の作品にはセオリーとして「やらない方がいい」とされているような手法も多くて、それを理解しないまま使っていた部分もあった。だからこそ、他のアーティストが素晴らしい作品を出しているのを聴くと、「なんで自分たちはそれができないんだろう」って思うし、その悔しさやもどかしさが活動を続けてこられた大きな理由だと思います。
「もっと聴かれたいのに」とか「なぜ評価されないんだろう」と思うこともあります。でも同時に、”評価されない理由”を自分たちでわかってしまう。その悔しさが、結果的にモチベーションになっていて。それに、「やりたいことが尽きない」というのも大きい。今も「これ全部、死ぬまでにやり切れるかな……」って思うくらい、まだまだやりたいことがあるんですよ。それを他のバンドやソロプロジェクトに分けなくても、PLASTIC GIRL IN CLOSETという名前のままで全部できるという自信があるし、実際にそれができている。
昔から「どんなジャンルでも自分たちの色になる」と思っていて、この名前でずっとやっていきたいと思ってきました。前身バンドから今の名前に変えたときも、「ソロ的なこともこの名前でやっていけたらいいよね」って話していたし、そういう柔軟さがあるからこそ、『A.Y.A』のような作品も自然に作れた。”ソロっぽい”けど、あえて名前を変えずに出せる。それが、このバンドの強みだと思っています。
ー須貝さんはいかがですか?
須貝:前身バンドの頃から、ずっと祐二さんと一緒にやってきました。最初はスタジオで一緒に曲を作っていた時期もありましたが、今はもう完全に”ワンマンバンド”という形になっています。それでもずっと続けてこられたのは、祐二さんの作る曲が本当に好きだから。それに尽きますね。
<リリース情報>
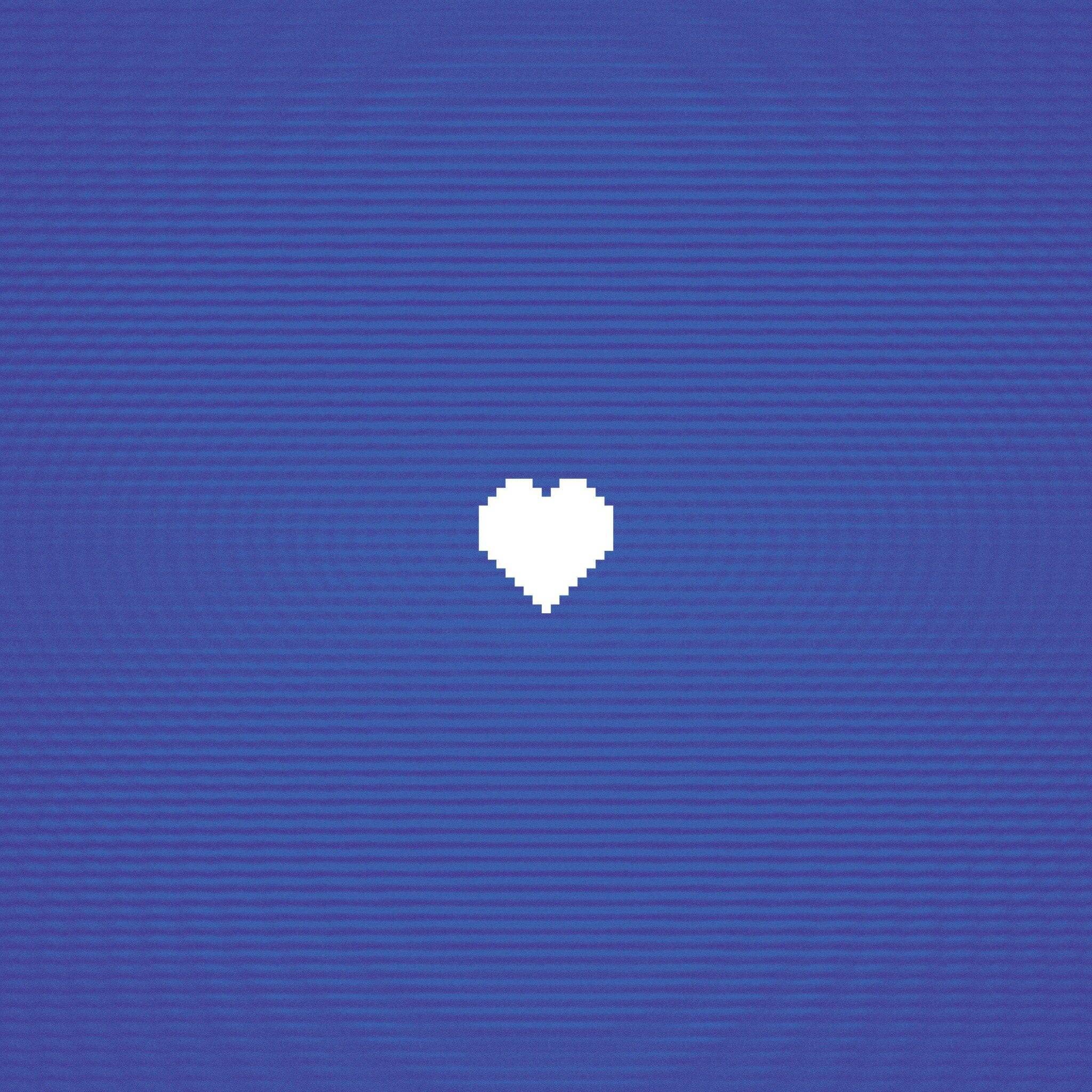
PLASTIC GIRL IN CLOSET
『HIGH HEART』
発売日:2025年8月20日
=収録曲=
1. Pool
2. Vicious Cycle
3. Medicine
4. Lovers
5. Cant Stop My Heart
6. Echo
7. Baumkuchen
8. Now
9. Trouble Maker
10. Ramune River
11. Worlds End
PLASTIC GIRL IN CLOSET
デビューアルバム『TOY - Remastered』
発売日:2025年8月20日
=収録曲=
1. Stars Falling Down
2. Black Bear Magcup
3. Labyrinth
4. Like A Strawberry
5. Raincoat
6. Sweet Shine
7. Kinder Garden
8. Radio Love
9. Halfway
10. Sleepwalk
11. Weekend Yawning
12. Sherbet
13. Favorite Song -Bonus Track-
14. Cut Your Hair -Bonus Track-
Official HP:https://plasticgirlincloset.com/














![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








