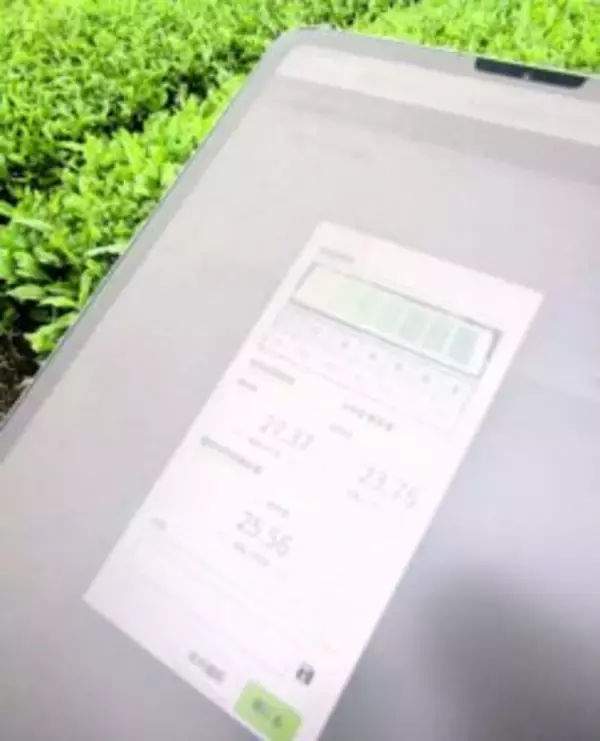
市場での茶価低迷による経営圧迫や後継者不足などの課題を解決し持続的な生産を目指すとともに海外展開を視野に入れた動きとなる。
5月15日、清飲記者会の視察取材会に応じた佐藤貴志製品開発部副部長(前:農業技術部)は「生産者さまにとって一番の収益源である一番茶の需要が減っている。我々としては、茶産地育成事業や製品開発で生産現場の崩壊を回避し、ともに成長できるようなことを考えている」と力を込める。
海外展開に向けては、GAP認証100%取得や減農薬・有機栽培の強化を働きかける。
「有機栽培を推進していくと、農薬を使えなくなることから、現在、機械メーカーのほか大学や県の試験場と開発に取り組んでいるのは、温度調節した蒸気を当てて、茶葉の芽につく害虫を防除する機械。品種の開発も行政と進めている。お茶の樹にも耐病性に差があり、強い耐病性を持つ品種を見つけ出したい」と語る。
アプリを活用したAI画像解析 持続的生産に資する農業DXの取り組みとしては、アプリを活用したAI画像解析がある。
一番茶の収穫時期、アプリを入れたスマホやタブレットで新芽を撮影すると、芽の堅さや繊維量、アミノ酸といった重要指標の推定値を算出。これらの数値が摘採に適しているか否かの判断材料になるという。
「基本的に芽を伸ばせば、収穫量は上がる一方で旨味は減ってしまう。芽伸びと旨味の見極めが重要なポイントであり、熟練の方であれば手触りで判断できるが、多くの生産者は芽を持ち帰り電子レンジで乾燥・粉砕して専用の分析器で繊維量とアミノ酸量の2つを主な指標にして収穫時期を見極めているのが実情」と説明する。
摘採期の見極めは、多くの生産者にとって手間暇かかる上に、専用の分析器に要するコストが負担になっている。
「決して安い機械ではなく、使用頻度も収穫時期に限られるため、生産者にとって大きな負担になっている」と指摘する。
AI画像解析はこれらの負担を軽減するものであり、今もデータを蓄積しながら学習し精度を高めている。

将来は、営業支援ツール「アグリノート」との融合を視野に入れる。
「アグリノート」は、衛星画像で畑の面積や品種、肥料の投入具合といったコンディションを把握するクラウド型栽培管理システム。2023年、ウォーターセルと資本業務提携して導入開始した。
「農業適否判定システム」の運用も開始して、海外向け原料の生産性向上とトレーサビリティの高度化を図っていく。
海外展開を見据え、抹茶原料の碾茶(てんちゃ)の栽培も推進していく。
旭俊也仕入部部長は「農林水産省をはじめ、農産県である鹿児島県を中心に輸出に対する支援が非常に手厚くなっている。
環境配慮の取り組みとしては、茶畑の畝間への「バイオ炭」の散布試験を行っている。
バイオ炭は、GHG排出量の削減だけではなく、土壌改良といった生産性向上が期待されている。



















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
