42歳を迎えるにあたって、自身の「老い」と共に、果たすべき役割の変化を振り返る
連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第43話
大学生の頃は「40歳まで生きれれば充分」などと中二病的な妄想をしていた筆者。時は経ち、ウイルス研究者としてプレーヤーから研究プロジェクトを率いるマネージャーの立場となり、G2P-Japanの発足・主宰でその役割はますます広がっていった。そしてオミクロン株(BA.1)の研究で忙殺される中、共に働くプレーヤーたちの成長を目の当たりにする。
* * *
■「41歳」の1年を振り返る
昭和57年生まれ、41歳の私にとって、令和5年は本厄の年であった。大きな事故も悲劇もなく、初めて受けた人間ドックでもさしたる異常も見つかることなく、まもなく42歳の誕生日を迎えようとしている(余談だが、これの初稿を書いている2024年の始め、ちょっとした「災難」に見舞われているのだが、それについてはまた後日触れるとして)。
1年前を振り返ると、「41歳」になる自分がうまくイメージできなかった。というのも、7話や42話で紹介したように、内向的だった大学時代の私は、よく友人たちに「40歳まで生きれれば充分」などとうそぶいたりしていたから。そしてその理由は、「ジョン・レノンが40歳で暗殺されたから」だ。
ロックの世界には、「27クラブ」というものがある。そこには、カート・コバーンやジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリンなどの、27歳で死んだロックスターたちが名を連ねている。
歳を重ねるにつれ、そのような中二病的な妄想はもちろん霧散したわけであるが、「40歳」という数字だけはずっと心のどこかに残っていた。ともすると、ということが頭をかすめていたのである。
■「プレーヤー」から「マネージャー」へ、変遷する役割
42歳を迎えるにあたって、これといった抱負などをここで述べるつもりもないが、自身の「老い」と共に、果たすべき役割が移り変わってきたことを振り返るには良い機会かな、とも思い、今回のコラムの筆をとった。
研究室生活を始めた大学4年生の頃や、京都に移った大学院生の頃はもちろん、自分の研究が100%。しいて言えば、周囲との交流から生まれた物事や私生活へのエフォートが5~10%残されているくらいで、生活と頭の中のほぼすべてが、自分の研究のことだけで占められていた。
ポスドク(博士研究員)の期間も、基本的にそれは変わらず。実験スキルも上達し、自分の好きなことだけに没頭できる、いわゆる「プレーヤー」としての全盛期が、一般的にはポスドクの時期なのだと思う。しかし私の場合、ポスドクとしての期間が3ヵ月だけだった。
少しずつ私の中でのエフォートバランスが変化してきたのは、特定助教から助教になった頃である。自分の研究費でポスドクを雇用するようになり、「チームをマネージする」ということが私のエフォートの中心になる。俗に言う「プレーヤー」から「マネージャー」への転身、である。
やがてそのマネージの対象が、雇用しているポスドクだけではなく、指導を担当する学生も含まれるようになる。東京に異動し、自分の研究室を主宰するようになると、マネージするのは人だけではなく、研究室の設備やルール、そして、研究室を運営するための費用などまでが対象になる。
そしてコロナ禍。G2P-Japanを発足・主宰するようになると、マネージの対象は、北海道から九州まで散らばる、それぞれの研究室を運営するPI(研究者主宰者)たちとの連携も含まれるようになる。初めはほんの数人で始まったG2P-Japanは、今や10人以上のPIたちが連携し、総勢80人以上のメンバーが参画する大所帯となっている。研究の世界に足を踏み入れたばかりの20歳そこらの頃からすれば、これはもはや想像をはるかに超えた世界である。
■2022年1月、新しい変異株発見!
「マネージャー」としての役割を果たす中での喜びのひとつに、「プレーヤーの成長」というものがある。
――時は2022年初頭。2021年11月末に突如出現したオミクロン株(BA.1)のスクランブルプロジェクトを終え、その論文の「リバイス(改訂)」依頼の連絡を待っている頃の話である。(注釈:時系列としては、この連載コラム17話の直後の話です。なので時間のある方は、17話を読んでから以降を読み進めると、臨場感が増すと思います)
怒涛のスクランブルプロジェクトを乗り越え、オミクロン株(BA.1)の論文をクリスマスの夜に『ネイチャー』に投稿。
そして、年明けの仕事始め。疲れは完全に抜け切らないもののラボに出勤し、久しぶりに自分のデスクに座ってひと息ついた私のところに、そろそろと特任助教(当時)のIがやってきた。
I「佐藤先生...」
私「おお、あけましておめでとう。どうした?」
I「お話があるんですが...」
私「? もったいぶって、一体何?」
I「ちょっとお伝えしたいことがあるのですが...」
私の隠しきれない疲労感を慮り、なかなか切り出せずにいたのだろう。やがて意を決したように、Iが続けた。
I「次の変異株が見つかりました」
――私にはよく意味がわからなかった。次の変異株? BA.1株が出現してまだひと月ばかりで、しかももうこれだけ世界中で広がっているのに、もう次の変異株? 何言ってんの? そんなことある?
仮にもしそうだとしても、当時の私たちは、日本チーム主導の論文と、並行して共同研究していたイギリスチーム主導の論文を、両方とも『ネイチャー』に投稿した直後で、抜けきらない疲労困憊の中にあった(17話)。これからは、そのふたつの論文の「リバイス(改訂)」の作業が控えている。
動転した私の口をついて出たのは、こんな一言だった。
「俺を殺す気?」
※後編はこちらから
文/佐藤 佳 写真/PIXTA














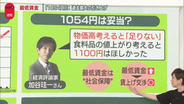



















![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークブラウン/ブラックRYST5040H(ABR/BK4) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/413mi56isML._SL500_.jpg)





