エヌビディアやTSMC、ブロードコムといった企業の躍進の裏には、かつて隆盛を誇った企業の没落が見て取れます。その代表格が長らく半導体業界の売上高トップ2が指定席だったインテルとサムスンです。
かつての「2強」はなぜ没落してしまったのでしょうか。今回は2社の栄枯盛衰の歴史と現状を深掘りします。
連載「AI時代の半導体メーカー列伝」▼第1話
2025年8月27日: 【知識ゼロから学ぶ】なぜエヌビディアはAI時代の覇者になれたのか
▼第2話
2025年9月5日: ブロードコム、SKハイニックス、TSMCがAI半導体の「勝ち組」になれた理由
(執筆:平岡 乾)
盛者必衰の理を地で行くインテル哀史
まずはインテルについて紹介します。1990年代半ばから2000年代にかけてのコンピューター/IT業界は「ウィンテル」連合の支配下にありました。
マイクロソフトが提供するOS「ウィンドウズ」と、「インテル、入ってる」でおなじみのインテル製CPUが、民生パソコンのデファクトスタンダードとなって独占状況を築き、「ウィンテル」という造語が生まれました。
そのウィンテル体制の終焉(しゅうえん)を告げる象徴的な出来事が2024年に起きました。マイクロソフトのパソコン「Surface(サーフェス)」に搭載されるCPUが「Snapdragon(スナップドラゴン)」、つまり、スマホ向けで有名なクアルコム製に置き換わったのです。
クアルコム製プロセッサを搭載したウィンドウズPCの新カテゴリー「Copilot+ PC」

背景として、マイクロソフトが出資しているOpenAIの生成AIを活用する際、AI処理機能(NPU)に長けているのがスナップドラゴンであったことが挙げられます。これには、マイクロソフトによる「インテル切り」という見方もありました。
マイクロソフトも一時はモバイルシフトに遅れるものの、ビジネスモデルを変革して見事に方向修正した一方、インテルは環境変化に対応できず、過去20年近くも「没落のマーチ」を続けてきました。
その道筋を三つのステージに分けて解説します。
第1に2000年代後半、アップルがインテルにスマホ用CPUの供給を依頼するも、そのポテンシャルを理解できない当時のインテルのCEOがアップルの依頼を断るという世紀の判断ミスによって、スマートフォンという巨大な魚を取り損ねてしまいます。
第2に2010年代にAI(人工知能)やモノのインターネット(IoT)のブームが来ると、業界のスポットライトはインテルからGPUを手がけるエヌビディアへと移り変わる。
こうしてモバイル市場やAIという時代の成長機会を逃したインテル。2020年代に入ると、本丸でも火の手が上がるようになりました。絶対に落とせない主力ビジネスでもシェアを失い始めたのです。
第3にインテルの本丸であるパソコン・サーバー用のCPUも不具合や性能不足が続き、AMDにシェアトップの座を奪われる寸前までシェアを失っています。
ちなみにAMDはCPU業界でナンバー2とはいえ、2010年まではインテルがシェア9割、AMDのシェアは一桁台でした。野球に例えるなら、首位インテルと2位のAMDには20ゲームほど離されている状況でした。それがまもなくシェアで逆転しそうな状況です。
ちなみに、日米ともAmazonでCPU販売ランキングを見ると、トップ10のうち9製品がAMDで、インテルが1製品がランクインするにとどまっています。
2022年から慢性的な赤字が止まらず、大規模なリストラと投資延期を繰り返しています。直近では米政府やソフトバンクグループからの出資の動きが見られるなど、もはや単独での再建は厳しい状況です。
興味深い点があります。インテルを追い詰めているAMDを率いるリサ・スー氏は台湾系アメリカ人、インテルに代わって時代の寵児となったエヌビディアのトップ、ジェンスン・ファン氏も同様に台湾系アメリカ人です。
そして、AMDとエヌビディアが半導体の製造を委託しているのはTSMCという台湾企業。台湾系企業または台湾にルーツを持つ人々によってインテルは業界の盟主としての地位を譲る形になったといえます。
先端分野で連戦連敗のサムスン
サムスンといえば、日本の総合電機メーカーを次々追い越し、スマホから家電、ディスプレイパネル、半導体まで、あらゆる分野で世界シェア1位または2位の地位を確立した最強の総合電機メーカーでした。
半導体事業についても複数の領域を手がけており、
NAND型フラッシュメモリ(ストレージ)でシェアトップ、イメージセンサーでもソニーに次ぐ2位と、あらゆる分野でのシェアがトップクラスという化け物ぶりでした。
そんなサムスンは「1」のプロセッサ領域において悲願の首位を目指すべく、打倒TSMCに向けてエース人材をファウンドリ事業に投入してきました。しかしながら、その試みは報われませんでした。
2021~2022年には、クアルコム向けの先端半導体(4nm世代)の量産に苦戦。歩留まり(良品率)は30%程度と大変低く、結局、クアルコムはすでに歩留まりを高めているTSMCに生産委託先を切り替えました。しかも、TSMCが作った半導体チップの方が2割ほど高性能だったことも判明しました。
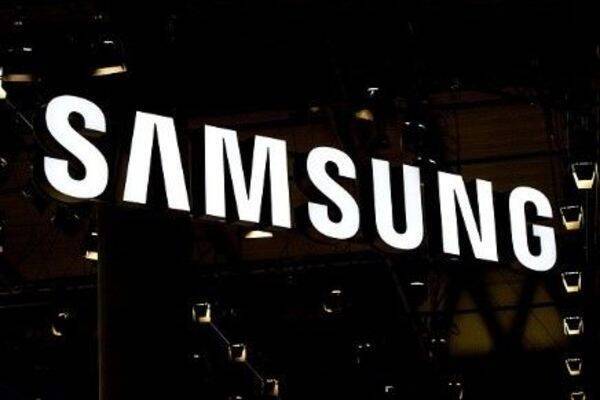
TSMCにまざまざと力の差を見せつけられた後、泣きっ面に蜂とばかりに2023年、サムスンの本丸にも火の手が上がります。稼ぎ頭のメモリ事業に暗雲が立ち込めたのです。前回の記事で紹介したように、SKハイニックスが乾坤一擲(けんこんいってき)のHBM(高帯域メモリ)開発によって躍進。
サムスンは打倒TSMCにのめりこむ一方で、以前は市場拡大が見通せなかったHBMへの投資がおろそかになったといわれています。結局、得るものは少なく、失うものばかりだったのが痛いところです。
直近の2025年4-6月期の同社の業績では、半導体部門の営業利益が前年同期比94%減の約4,000億ウォン(約430億円)に落ち込みました。
もっとも、単独での生き残りが厳しいインテルのように経営危機に陥っているわけではありません。サムスンは捲土(けんど)重来を期すべく、トランプ政権が半導体に100%の関税をかけようとしている動きにいち早く対応し、米国での生産投資を打ち出すことで、アップルやテスラとの取引強化を狙っています。
(トウシル編集チーム)






















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
