
基本的にストーリーや設定には一切関与していないと語る漫画『ゴールデンカムイ』のアイヌ語監修者の中川裕氏だが、アシㇼパの父・ウイルクと、その仲間であるキロランケの設定には深く関わったという。『ゴールデンカムイ絵から学ぶアイヌ文化』(集英社新書)より一部抜粋、再構成してお届けする。
ウイルクは「アムール川流域の少数民族」だった!?
私は基本的に「ゴールデンカムイ」のストーリーや設定には関与していません。それはもっぱら野田先生の専権事項で、私は「アイヌ語監修」の名目どおり、アイヌ語に関連する部分の監修を行うのがおもな役割です。
それでもいくつか、基本的な設定にからんだことがあり、そのひとつがウイルク(註:アシㇼパの父)の出自です。
ウイルクが樺太から北海道に渡って来たという設定は、連載当初から野田先生の頭の中にあったものらしく、またウイルクがアイヌ民族の出身ではなく、アシㇼパの眼が青いということにそれがつながっているというのも、早くからの展開で示されていたことです。

北海道白老郡白老町にある「UPOPOY」には中川氏も深くかかわっている 写真/Shutterstock.
そこまではよいのですが、それに関して野田先生から示されたのが、ウイルクが実はアムール川流域の少数民族だったという設定でした。
そこらへんにはいろいろな民族がいるので、青い目の住民もいるだろうという発想だったと思われますが、実のところこのアムール川流域に暮らしているのは、おもにトゥングース(ツングース)と呼ばれるグループの人たちで、ほとんどが見た目は和人と変わりありません。
トゥングースの中にもいろいろな民族がいて、清王朝を築いた満州族や樺太のウイルタもそのひとつですが、アムール川流域にも、ナーナイ、ウデヘ、ウリチ、ネギダールなどと呼ばれる人たちがいます。
ナーナイの出身者で最も有名なのは、狩りの名手として知られ、黒沢明監督の映画の主人公にもなったデルス・ウザーラでしょう。ハバロフスクの博物館の館長を務めたロシア人人類学者ウラジーミル・アルセーニエフの案内人として、シホテ・アリンの山中を案内し、その自然に対する知識と行動力でアルセーニエフの数々の窮地を救った人物です。

黒沢明『デルス・ウザーラ』(1975年)
なんとなくアシㇼパを髣髴(ほうふつ)とさせますね。彼のことは平凡社東洋文庫のアルセーニエフ『デルスウ・ウザーラ』(1987年)他で読むことができます。
いずれにせよ、アムール川流域に青い瞳を持つ民族はいなそうなのですが、もっと重大なことがあります。もし、ウイルクがウデヘやナーナイといった民族の出身であるのなら、アシㇼパは半分アイヌではないことになってしまいます。
さらに、アシㇼパがウイルクから教授された狩りの技術などは、アイヌのものではなく大陸の民族から受け継いだものだということになりかねません。それはアイヌのヒロインとしてアシㇼパを応援してきたファンとしては、あまり受け入れたい選択肢ではありません。
「漫画は意図していなくても、奇跡的に設定が嚙み合って展開して行く」
ということで、私は考えました。青い瞳を持っているがロシア人ではなく、樺太でアイヌ女性と結婚していてもおかしくはない立場の人とはどういう人か。そこで思いついたのがポーランド人です。
ポーランドは18世紀末に、近隣の大国であるロシア帝国、プロイセン王国、オーストリアによって分割され、一度消滅しました。そして19世紀初めにはナポレオンによってワルシャワ公国が成立しましたが、1815年のウィーン議定書によって解体され、その4分の3がロシア皇帝の領土となり、ロシア皇帝が国王を兼務するポーランド立憲王国となりました。実質的にロシアの支配下に置かれてしまったわけです。
1863年にはポーランド・リトアニア連合王国の復活を目指す人々が「1月蜂起」を起こしますがロシア帝国に鎮圧され、4万人がシベリアに流刑となりました。このシベリア送りになったポーランド民族主義者の中に、ウイルクの父親がいたと考えたらどうでしょう? 12巻116話で、インカㇻマッ(註:謎多きアイヌの女性)がそのような経緯について、アシㇼパに説明しています。

12巻116話より ©野田サトル/集英社
彼はその後シベリアから樺太に渡り、アイヌ女性と結婚してウイルクが生まれます。そして父親はウイルクに、ロシアへの怒りと、大国に支配された少数者がやがて味わうことになるだろう運命を語り聞かせて育てます。
1875年の樺太千島交換条約の結果、樺太がロシア領となり、自分の村が消滅していくのを目のあたりにしたウイルクは、その父の言葉を痛切に感じたでしょう。
このように設定すれば、ウイルクは樺太のアイヌの村で育った、ポーランド人とアイヌのハーフということになり、アシㇼパは4分の3がアイヌで、ポーランド人の血を4分の1持つ女性ということになります。ウイルクとアシㇼパの瞳が青いのも、ウイルクがロシア皇帝暗殺に関与することになるのもすべてこれで説明できる、我ながらよいアイディアだと、今でも思っています。
ちなみに、5巻48話で土方歳三(註:元新撰組「鬼の副長」にして脱獄囚)が永倉新八(註:新撰組時代からの土方歳三の同志)に向かって、ぽつりと「のっぺらぼうは日本のアイヌじゃない」と言っています。この時点ではまだ野田先生の頭の中では、ウイルクはアムールの少数民族という設定だったはずなので、「のっぺらぼうはアイヌじゃない」と土方に言わせてもおかしくはなかったのですが、ここで「日本のアイヌじゃない」と言ってくれたおかげで、その後が無事うまくつながりました。

5巻48話より ©野田サトル/集英社
野田先生がよく言うように、この漫画はあらかじめ意図していたわけでもないのに、本当に奇跡的に物語の設定がうまく嚙み合って展開して行くのです。
キロランケの出自と名前の由来
キロランケはアイヌの伊達男(だておとこ)という役割で活躍していますが、初登場してすぐに自分がアイヌではないことを話しており(6巻49話)、自分がアムール川流域の出身であることを示唆しています。ただ、野田先生の構想では彼は最初からタタール人だということになっていました。
タタール人というのは狭い意味ではテュルク系の一民族であり、広い意味ではロシア人を歴史的におおいに苦しめてきたモンゴル・チュルク系を中心とする人々の総称でもあります。
ロシアでは「タタールのくびき」という言葉もあり、13世紀前半から2世紀半にわたるモンゴル=タタールによるルーシ(現在のロシア・ウクライナ・ベラルーシ)支配を指しています。ロシア人にとってはタタール人というのは自分たちを脅かしてきた異民族の象徴のような名前なのです。
したがって、キロランケがタタール人であるという設定自体は大変適切だと思うのですが、あいにく、大陸の東の果てであるアムール川流域にタタール人がいたという話はあまり聞きません。

アムール川 写真/Shutterstock.
野田先生は、17巻164話で、彼に「タタール人として生まれたが、樺太アイヌの血も混ざっている。
なお、樺太アイヌが借金のかたにアムール川流域に連れ去られたというのは、史実として記録されていることで、江戸時代、樺太アイヌは山丹人(さんたんじん)と呼ばれるアムール川流域の人々と、毛皮交易をしておりました。それを「山丹交易」と呼んでいます。
アイヌはクロテンなどを獲ってその毛皮を山丹人と取引して、山丹錦と呼ばれる満州族の官衣や、絹織物などと交換していたのですが、毛皮が獲れないと山丹人は借金のかたにアイヌを連れ去ったということが、古文書に見えています。それを踏まえての設定ということになります。
さて、キロランケというのは実在のアイヌの人名を借用したものですが、これは彼が北海道に渡って来てから自分でつけた名前ということで、17巻164話で「俺の昔の名前は『ユルバルス』」と、本名を明かしています。

17巻164話より ©野田サトル/集英社
このキロランケのタタール語名を考えてくれというのも、この時点で野田先生から頼まれたことでした。といっても、私はアイヌ語の専門家であり、タタール語までは知りませんので、とりあえずタタール語の辞書を引いて、かっこよさそうな単語を探すことにしました。
最初に見つけたのは、「ライオン」を意味するアルスラーンですが、この言葉は勇者の名前として田中芳樹(よしき)さん原作・荒川弘(ひろむ)さん作画の『アルスラーン戦記』(講談社)でも有名ですし、『ナルニア国物語』のアスランも同語源で、あまりにも使い古されていますので、どうかなと思っていました。
すると、野田先生が「ライオンより虎がいい」というので、虎のタタール語名を調べたところ、ユルバルスという言葉が出てきました。実際に名乗らせてみたら、アルスラーンよりずっとキロランケにふさわしい、かっこいい名前に思われてきました。
ウイルクが「狼」なので、「虎と狼」というぴったりの相棒にもなったわけです。ただし、それはウイルクともども、連載開始当時においてはまったく想定されていない設定だったということになります。
文/中川裕
『ゴールデンカムイ 絵から学ぶアイヌ文化』
中川裕

2024/2/16
1,650円
560ページ
978-4087213027
累計2700万部を突破し、2024年1月に実写版映画も公開された「ゴールデンカムイ」。同作でアイヌ文化に興味を抱いた方も多いはずだ。本書はそんな大人気作品のアイヌ語監修者が、物語全体を振り返りつつアイヌ文化の徹底解説を行った究極の解説書である。


















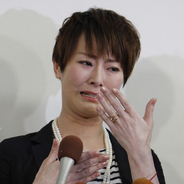



![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


