
2024年4月から9月にかけて放送された、NHK連続テレビ小説『虎に翼』。同作は男女不平等をめぐる多くの矛盾や不条理を真正面から扱い、話題を集めた。
上野千鶴子氏と、一橋大学教授の佐藤文香氏による対談をお届けする。※本記事は、2024年11月21日に丸善ジュンク堂書店池袋店で行われたイベントの内容を基に作成しています
実は「家父長制」という言葉は曖昧である
上野 こんばんは。こんなにも分厚い本に、よくぞご関心をお寄せくださいました。今の時代、本が売れません。翻訳書はもっと売れない。学術書はもっともっと売れない。そんな中で、こんな大ボリュームの翻訳書が出版されて嬉しいです(笑)。
今日はゲストに、一橋大学の佐藤文香さんを指名しました。佐藤さんが翻訳された本が『〈家父長制〉は無敵じゃない』です。簡単に紹介してくださいますか?
佐藤 はい。
上野 うまい具合に、この『〈家父長制〉は無敵じゃない』と、今回出版された『家父長制の起源』という本はお互いに補い合っているんです。「起源」というと、歴史をさかのぼってどう変化してきたかを考える時の概念です。学術用語で言うと「通時的」にどうだったのか、ということです。
それに対して、『〈家父長制〉は無敵じゃない』のほうは、家父長制というシステムが「そのつど、その場で」「たった今、あなたによって」再生産されていることを指摘した本です。
つまり、家父長制というのは盤石なものでもないし、永遠不滅でもないし、運命でもないというのが、両方を読むとよくわかる。しかも、皆さん自身も家父長制の再生産に荷担している共犯者なんだ、ということもよくわかります。
それにしても佐藤さん、最後に生き残ったのは「家父長制」という言葉でしたね。
佐藤 そうですね。
上野 「家父長制」という言葉はあいまいで、定義がはっきりしないということで、もともと評判が悪かったんです。家父長制という言葉が最初に出てきたころ、日本の学者はなんと言ったか。
「日本にはもう家父長制なんてありません。
でも、家父長制というのは時代と社会と文化に応じて、さまざまに姿を変えるものです。近代家父長制もあれば、前近代家父長制もあれば、中世家父長制もあれば、古代家父長制もある。イスラム家父長制もあれば、キリスト教圏家父長制もある。
こんなあいまいな概念、誤解を招くから使わないでおこうよということで、気の利いた学者たちは「“ジェンダー秩序”と呼び換えましょう」とか、「“ジェンダー体制”や“ジェンダーレジーム”と呼び換えましょう」なんて言っていたんだけど、結局それらの言葉は定着しませんでしたね~。
佐藤 上野さんは『家父長制と資本制』(現在は岩波現代文庫に収録)という本を1990年にお書きになっていますけれども、当時からやっぱり「家父長制」という言葉は評判が悪かったのですか?
上野 用語をめぐる論争がありました。でもね、今ではその辺の女の人たちの会話を聞いていると、普通に「家父長制がさ~」なんて言っている。あっ、もう完全に日常会話に定着した。最後に生き残ったのは「ジェンダーレジーム」ではなく「家父長制」だったなと。
こういう用語の問題がなぜ重要なのか。「家父長制」って言うと、ムラムラと怒りが湧いてくるでしょう。
「女より男のほうが強くて賢い」は、本当か?
上野 『家父長制の起源』では、ジェンダーにまつわる様々な「神話」を扱っています。「神話」とは何か。「根拠のない思い込みの集合」の別名です。例えば、「女より男の方が強くて賢い」とかね。……本当かよ、と。こういうことの大半って、ただの思い込みなんですね。
この本のタイトルには「起源」という言葉が入っていますが、男女の不平等は人類史が始まって以来ずっと続いてきたんだ、なんて言われたら、運命だから変えられないと思っちゃうでしょ。
「男女不平等、いつから始まったの?」って学生さんに訊くとね、男子学生はほとんど必ず、「だって原始時代からそうだったんですよね」って言うんです。えっ、妙に自信満々だけど、アンタ知ってるの? その頃に生きてたの? って思うんですが(笑)。
佐藤 (笑)。
上野 次のように言われることがあります。「男は狩りに出かけ、女は赤ん坊を抱いて洞窟で待っていた」。なぜかというと、人間は子どもをネオテニー(幼態成熟)で生むからです。
動物を考えてみてください。鹿とか馬なんて、子どもは生まれたら数時間でサッサと歩き始めるし、オムツもしなくて良いからね。ああいう風に生まれればよいのだけど、人間は手のかかる状態で生まれるので、母親は長期間にわたって子どもに縛りつけられてしまう。
そうなると、男が食料調達に出かけている間に、女は洞窟で子どもを育てなければならない。生き延びるためには長期にわたって男を繋ぎ留める必要があるから、人間の女は発情期を無くした。年がら年中、セックスできるようになったんだ、と。これが今まで信じられてきた「神話」、つまり思い込みです。
今回、私はこの『家父長制の起源』に解説を寄せました。そこに何を書いたか。
Nutrition Anthropology(栄養人類学)という学問分野があります。このところ、古代史の発掘調査はすごく精度が上がっています。発掘場所から人間の排泄物の跡が出てくることがある。そこから、当時の人たちが何を食べていたかということが同定できるんですね。
最新の調査の結果、わかったことは何か。古代の人たちは大型動物だけを食べていたわけじゃない。野営地周辺の植物性資源と、小動物もたくさん食べていたらしい。
男たちの狩りには当たりはずれがあって、手ぶらで帰ってくることもあった。当然ですよね。漁労をやっている民族についても、専門家から話を聞きました。遠洋航海で大物を狙いに行っても、うまくいかなくて手ぶらで帰ってくることもある。そういう博打(ばくち)みたいな男の狩猟を、腹を空かせてじっと待っているほど女はアホでも無力でもありません。
その間、女は居住地周辺の小動物を狩り、植物性資源もちゃんと採っていた。結局、みんなが生きていくための栄養の約6割は女性が採集したもので成り立っていた。こういうことが栄養人類学の成果からわかってきました。
女性がハンターや戦士をやっていたこともわかっています。槍が刺さった女の頭蓋骨も見つかっています。そして共同体の支配者もいたらしい。
『家父長制の起源』にはチャタル・ヒュユクという、トルコにある紀元前7500年ごろの遺跡が登場します。当時の日本列島なんて、まだ石器時代です。チャタル・ヒュユクには文明があって、どうやらそこで中心になった女神がいたらしい。といっても、本当に神様なのかどうかわからないから、今は女性像と呼ばれているようですが。
写真を見てください。どこか日本の土偶と似ています。おっぱいがあって、おなかが出ていてドッシリとした体格。両側には動物らしきものを従えています。こういうものが紀元前7500年ごろに崇拝の対象になっていた。
女が戦闘の神であるというのは、例えばギリシャ神話のアルテミスなんかがそうですね。それから、ヒンディー教の女神カーリー。怖いですね~。足下では男が踏みつけられています(注:夫であるシヴァ神だとされる)。世界中に、こういうものはいっぱいあります。
考えてみれば、日本も同じです。邪馬台国の卑弥呼。それから神功皇后も闘う女帝でした。女は指導者にも戦士にもなっていました。
女性が働くのに「夫の許可」が必要⁉
上野 家父長制は時代や社会とともに変わる、ということが『家父長制の起源』では論じられています。
例えば、日本の古代は「双系制」(注:女系と男系の双方を含むもの)だったと言われています。2024年の大河ドラマは、紫式部を主人公にした『光る君へ』。あの時代は通い婚でしたから、女の実家が強くないと、相手の男も出世できない時代でした。話は変わりますが、2024年下半期のNHK朝ドラ『虎に翼』、皆さん、観てました? 私は毎朝、早起きして観ていましたよ(笑)。
佐藤 日本中、大熱狂でしたね。
上野 オジサンはあまり観ていなかったらしいけどね(笑)。このドラマの中に、有名なエピソードがあります。戦前は、既婚女性は「無能力者」だったすごいよね! まず参政権が無い。選挙権を持っていない。選挙権が無いということは、国民としての権利が無いということです。
佐藤 契約もできませんでした。
上野 財産権が無い、所有権も無い、契約権が無い。日本の妻はセールスの人が来たら、「主人が帰りましたら、相談してお返事申し上げます」と言うことになっていました。夫が意思決定権を持っていますから。
「相談してお返事申し上げます」というのは、ふつうは体よく断るための婉曲語法だと言われていますけれども、実は戦前は、婉曲語法ではなくてそのものズバリ。夫にしか決定権が無かったんです。
『虎に翼』に影響を受けて、私もいろいろと調べてみたんだけど、妻が外に働きに出るのにも夫の許可が必要だった。驚きますよ。今でも女の人と喋っていたら、「夫の許可を得て外に働きに出ました」って言う人がいる。
佐藤 いますよね。はい。
上野 戦前と同じかよ、と。許可って何? じゃあ、もともと夫に禁止されていたわけ? って。実際にそれぐらい、家長権というものが強かった。
でも、これが日本の由緒正しき伝統だという風には勘違いしないでくださいね。日本の“家”制度における家長権というのは明治民法以降のもので、明治民法がモデルにしたのは「ボアソナード法典」というフランスの民法です。
あまり知られていませんが、フランス革命の後、なんとフランス女性の地位は、それ以前よりも低下しました。法的無能力者になってしまった。日本の民法はそれをそのまま真似したわけです。
明治時代、つまり近代になってから日本では妻の地位が下がった。じゃあ、それ以前はどうだったのか。中世女性史の研究者、脇田晴子さん(注:歴史学者・滋賀県立大学名誉教授)に教えてもらったことがあります。「中世の女性と、古代(平安朝)の女性、どちらの方が地位が高かったのですか?」。こう尋ねたところ、実に見事な答えが返ってきました。
古代(平安朝)においては、姉妹として、娘としての女性の地位は高く、妻としての地位は低かった。しかし中世の武家社会になってから、姉妹として、あるいは娘としての地位は低下し、妻としての地位は上昇したという説明でした。いったい、どういうことなのでしょう?
日本で経営者の女性比率が高い理由
上野 妻というのは、嫁いだ先の家にとってはよそ者でしょう。日本ってすごく不思議な国で、実は経営者の女性比率が世界的に見てもかなり高いんです。
なぜかというと、日本は各地に家業ビジネス(ファミリービジネス)が沢山あって、そのファミリービジネスの代表に後家さんがなる。
後家さんって言って、伝わるかしら? 夫に先立たれた妻のことね。元々よそ者だった、外から嫁いできた妻がその家の代表権を持てる。典型例が鎌倉幕府の北条政子ですよ。
中世には妻としての地位は上がった。妻の地位を基に、家の経営者として振る舞えるようになった。今でも日本は、家業経営者の女性比率がダントツに高い不思議な国なんです。
妻としての地位が上がったけれども、一方で姉妹として、娘としての地位が下がった。どういうことか。古代は、妻と娘も相続権を持っていました。やっぱりお金を握っている人は強いです。貴族の娘たちや姉妹たちは相続権を持っていて、財産を握ることができていた。それが彼女たちの力になった。ヨーロッパの中世も同じです。貴族の女たちはちゃんと相続権を持っていました。
ところが、日本では中世にそれが無くなって、もっぱら男性が握るようになってしまった。その男性、つまり夫がいなくなると、ようやく妻が権力を丸ごと継承できるわけです。
日本には「後家楽(ごけらく)」という言葉があります。後家になると楽になって、よいことだらけ。夫に早く先立ってもらって、息子をマザコンに仕立てておいて、息子が次の戸主に、つまり家長になると、自分は「家長の母」の座に就くことができる。そうなれば息子を陰から支配して、力を振るうことができる。これを私は「皇太后権力」と呼んでいます。皇太后権力というのはインフォーマルな権力です。
3年前の大河ドラマを覚えていますか? 『鎌倉殿の十三人』。鎌倉幕府の時代を扱ったけど、あのドラマ、よくマザコンの主人公がお母さんのところにお伺いを立てに行くでしょう。
そういう「皇太后権力」というものが、日本の“家”制度の中では女に対する、人生最後のご褒美として待っていた。だから、嫁としてのつらい務めにも耐えることができたんです。
今回、この『家父長制の起源』を読んで、それからシンシア・エンローさんの『〈家父長制〉は無敵じゃない』も改めて読んで、私はやっぱりつくづく思いました。家父長制は女の協力なしでは持続しません。どこかでご褒美をもらっている女たちがいて、彼女たちは体制の維持を望んでいるのでしょう。
家父長制の起源 男たちはいかにして支配者になったのか
アンジェラ・サイニー (著), 道本 美穂 (翻訳)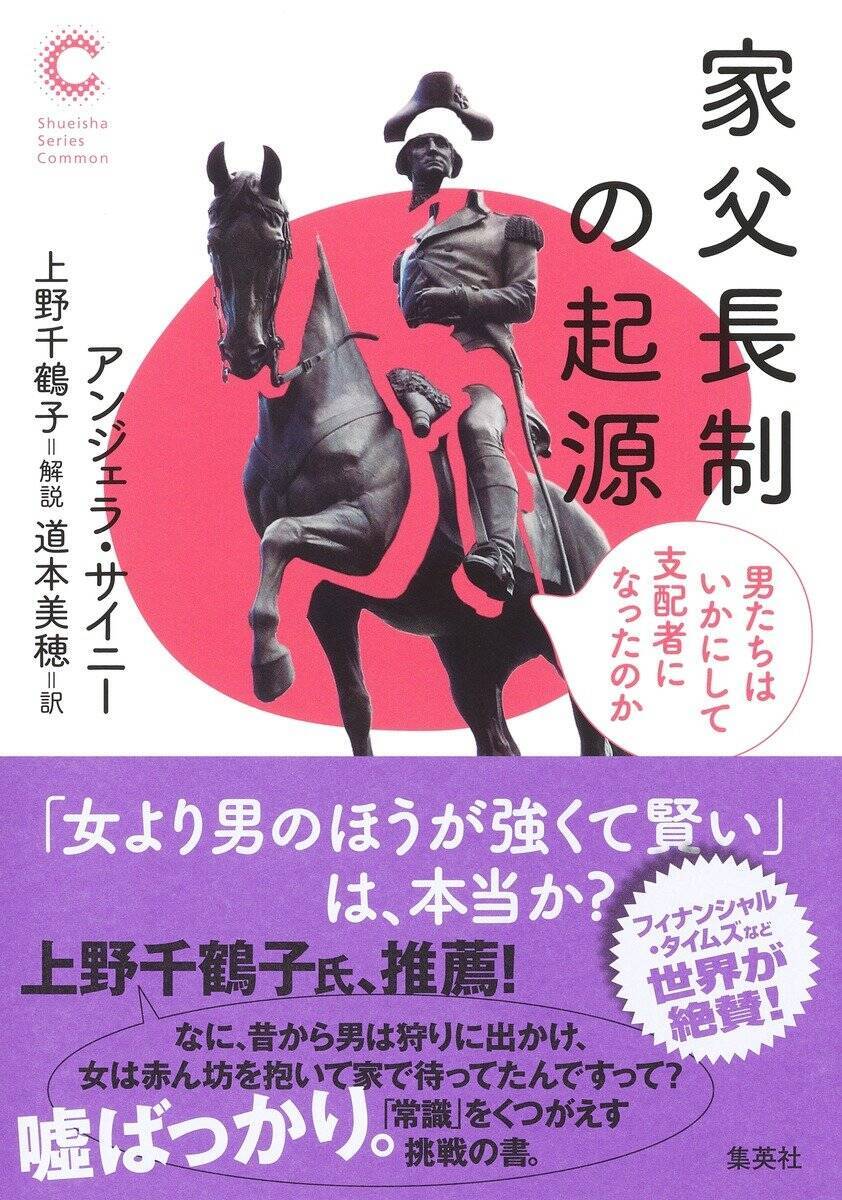
《各界から絶賛の声、多数!》
家父長制は普遍でも不変でもない。
歴史のなかに起源のあるものには、必ず終わりがある。
先史時代から現代まで、最新の知見にもとづいた挑戦の書。
――上野千鶴子氏 (社会学者)
男と女の「当たり前」を疑うことから始まった太古への旅。
あなたの思い込みは根底からくつがえる。
――斎藤美奈子氏 (文芸評論家)
家父長制といえば、 “行き詰まり”か“解放”かという大きな物語で語られがちだ。
しかし、本書は極論に流されることなく、多様な“抵抗”のありかたを
丹念に見ていく誠実な態度で貫かれている。
――小川公代氏 (英文学者)
人類史を支配ありきで語るのはもうやめよう。
歴史的想像力としての女性解放。
――栗原康氏 (政治学者)
《内容紹介》
男はどうして偉そうなのか。
なぜ男性ばかりが社会的地位を独占しているのか。
男が女性を支配する「家父長制」は、人類の始まりから続く不可避なものなのか。
これらの問いに答えるべく、著者は歴史をひもとき、世界各地を訪ねながら、さまざまな家父長制なき社会を掘り下げていく。
丹念な取材によって見えてきたものとは……。
抑圧の真の根源を探りながら、未来の変革と希望へと読者を誘う話題作。
《世界各国で話題沸騰》
WATERSTONES BOOK OF THE YEAR 2023 政治部門受賞作
2023年度オーウェル賞最終候補作
明晰な知性によって、家父長制の概念と歴史を解き明かした、
息をのむほど印象的で刺激的な本だ。
――フィナンシャル・タイムズ
希望に満ちた本である。なぜかといえば、より平等な社会が可能であることを示し、
実際に平等な社会が繁栄していることを教えてくれるからだ。
歴史的にも、現在でも、そしてあらゆる場所で。
――ガーディアン
サイニーは、この議論にきらめく知性を持ち込んでいる。
興味深い情報のかけらを掘り起こし、それらを単純化しすぎずに、
大きな全体像にまとめ上げるのが非常にうまい。
――オブザーバー
〈家父長制〉は無敵じゃない――日常からさぐるフェミニストの国際政治
シンシア・エンロー (著), 佐藤 文香 (翻訳)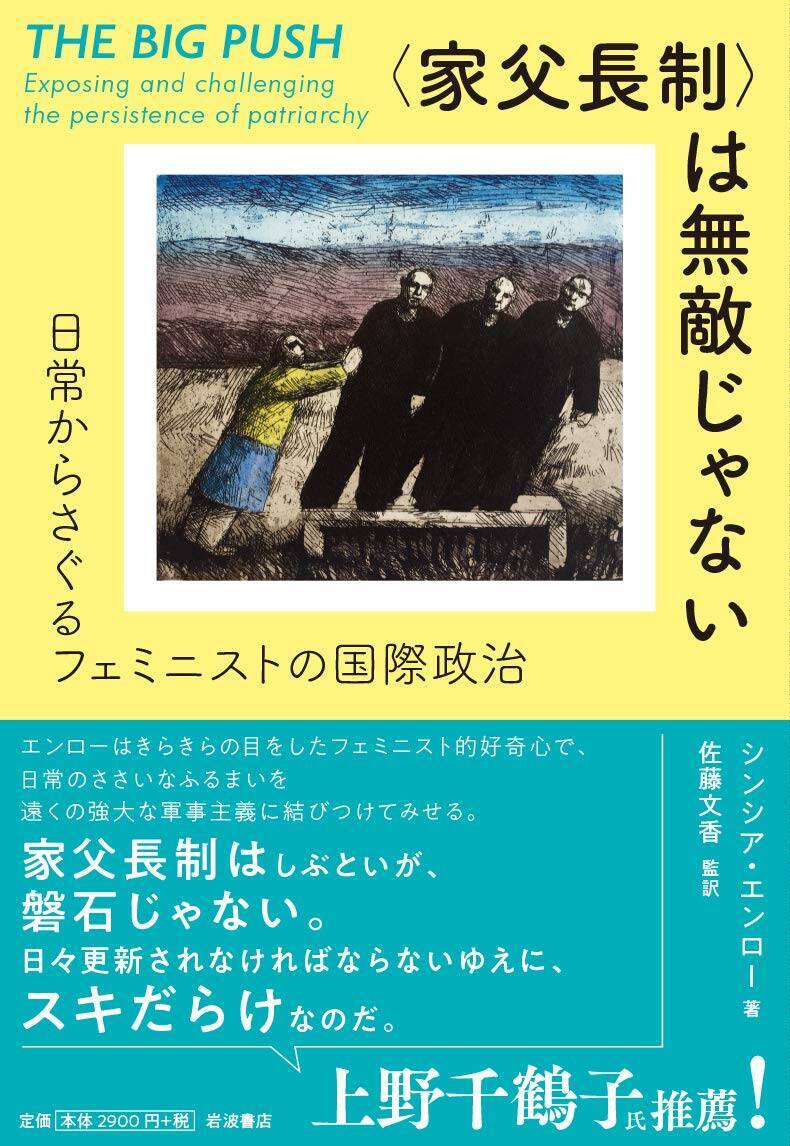


























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


