
「もしあなたが管理職で、部下に対して言葉を尽くさないとチームが成果を出せないのだとしたら、それは仕組みができていない証拠だ」そう断言するコンサルタントの田尻望氏。氏によると「成果を出すリーダーの多くは、いくつかのミーティングを除けば、部下との会話はほぼゼロである」という。
書籍『無言のリーダーシップ 付加価値を生む仕組みのつくりかた』より一部を抜粋・再構成し、できない部下がなぜできないか、その本質を見極めるフレームワークを紹介する。
4要素の問題分析 「感性」「感情」「知識」「技術」
あなたの周りに「できない部下」はいるだろうか。簡単な指示を取り違えたり、やる気をまるで感じられなかったり、上げてくる企画がどれもパッとしなかったり、一口に「できない部下」といってもタイプはさまざまだ。
私が現場で見てきた経験から、その本質を分析してみよう。あなたが「できない部下」を育成する必要があるとしたら、まずは彼らが次のどの要素に問題があってパフォーマンスを発揮できていないのかを見極めてほしい。これは私が様々な現場で効果を確認してきた分析フレームワークだ。
■感性:企画の面白さ、デザインの魅力、相手の反応を直感的に捉える力
■感情:恐怖、怒り、不安、やる気など、心理的な要素
■知識:商品や業界、顧客ニーズに関する論理的・情報的リテラシー
■技術:営業トーク、プレゼン資料作成、システム操作など、実践スキル
これを見誤ると、感情の問題(営業への恐怖や嫌悪感など)を知識不足と勘違いしてロープレ漬けにしてしまったり、知識の問題を「メンタルが弱っているせい」と勘違いして甘い言葉をかけてしまったり、問題と打ち手がちぐはぐになってしまう。
リーダーは、部下の「できない」要因がどの要素にあるのかを見極め、それに合ったサポートを提供する必要がある。
では、実際の現場ではどのような誤解が起こりやすいのか、いくつか具体例を挙げてみよう。
悪い例①怖くて話せない部下にロープレ漬け
私が指導に関わった営業部では、新人のEさんが「商談で毎回断られる」と落ち込んでいた。
上司は「じゃあ、もっとロープレをやろう。技術を高めればうまくいくはずだ」と毎朝ロープレをくり返した。
何度も練習を重ね、Aさんはロープレでは完璧に話せるようになった。しかし、いざ実際の商談となると、声が震えてうまく話せない。
このケースでは、「感情」の問題を「技術」の問題と誤解していた。営業に対する強い恐怖心がEさんの実力発揮を妨げていたのに、リーダーは「技術不足」と誤解し、Eさんをロープレ漬けにした。したがって、技術が向上しても恐怖心の問題は取り除かれず、結局うまくいかなかったのである。
恐怖心を取り除くアプローチが先
最終的に、リーダーはEさんを自分の商談に何度も同行させることにした。技術的には十分独り立ちできるレベルだったが、しばらくEさんを一人で商談に行かせることをやめたのである。すると、徐々に本番の雰囲気に慣れてきたEさんは、実際の商談でも少しずつ発言できるようになった。
リーダーはほかにも、次のようなアプローチでEさんの営業に対する恐怖心を取り除いていった。
■「失敗してもフォローするから大丈夫」というメッセージを明確に伝える
■商談のなかで「失敗しても何とかなる場面」を意図的につくる(信頼が構築された既存顧客との商談に同席させるなど)
これらのアプローチにより、「話せばなんとかなる」という自信を持ったEさんの成約率は劇的に向上した。もともと技術は十分だったので、感情の問題さえ解決できれば、優秀な部下だったのである。リーダーが問題の所在を勘違いすると、いくら指導しても成果が出ないため、部下の自信を奪うことになってしまう。
悪い例 ②知識不足を「モチベーションの問題」と誤解
私が観察した別のケースでは、部下Fさんが作成する提案書の詰めの甘さや雑さにリーダーが頭を抱えていた。リーダーは「なぜこんなにいい加減なんだ。やる気が感じられない」と考え、Fさんを厳しく叱責した。
しかし、よく話を聞いてみると、Fさんは「何をどう書けばいいかわからない」「過去の提案書の事例がなく、参考にできるものがない」という状態だった。つまり、知識不足が原因であり、モチベーションの問題ではなかったのである。
知識を与えればモチベーションも上がる
Fさんに「これが過去の成功事例だよ」「このフォーマットを使えばいいよ」と、具体的な知識を提供したところ、「なるほど、こうやって書けばいいのか!」と感激し、丁寧な提案書を作成するようになった。
このように、「やる気がない」のではなく「やり方がわからないだけ」というケースは意外と多い。部下にやる気がないと感じたら、まず次のアプローチをとってみてほしい。
■「何がわからない?」と知識の問題として質問してみる
■過去の成功事例やテンプレートを共有する
■「こんなふうに考えればいいよ」と、思考プロセスを教える
「なるほど、これならやれそう」と思えないことには、やる気は上がらない。自発的に動く「やる気のある部下」を育成するためには、まず適切な知識を与えることが大前提だ。
悪い例 ③「この部下、どうも提案がイマイチ」の正体は?
部下Gさんは、営業トークが上手で、商品知識も十分にある。しかし、どうも顧客とのやり取りがスムーズにいかず、提案が顧客に刺さっていない。リーダーは、「もっとプレゼン技術を鍛えろ」と指導したが、なかなか改善しない。
不思議に思ったリーダーは、Gさんの商談に同行することにした。すると、顧客の表情や声のトーンの変化に気づかず、一方的にスラスラと話すGさんの姿が目についた。つまり、「技術」はあるが、「感性」(センス)が不足していたのだ。
営業やマーケティングでは、知識や技術が十分でも、「場の空気を読む」「相手の関心を察知する」といった感性が弱いと、うまくいかない場面がある。
■視点を設定し、優れた人のプレゼンや営業を観察させる(「どのタイミングで何を言っているか」「提案時の顧客の表情」などを意識させる)
■顧客のリアクションを意識するトレーニングを行う(「相手が頷いた回数」「興味を持ったフレーズ」を記録させる)
■実際の顧客とのやり取りについてフィードバックする(「この場面では、顧客が違うことを期待していたのでは?」などと具体的に指摘する)
感性の問題を解決しないまま、知識や技術を与えても期待する効果は得られない。部下が何の問題を抱えているかを見極めるためにも、部下の商談やプレゼンなど、実際の業務に取り組んでいる様子をフラットに観察する機会をつくってみることをおすすめする。
部下の「できない」を4要素で分析し、適切な対処をすることが、結果的にリーダーの負担を減らし、部下が自発的に成長できる環境をつくるのだ。
文/田尻望
写真はすべてイメージです 写真/shutterstock
無言のリーダーシップ 付加価値を生む仕組みのつくりかた
田尻 望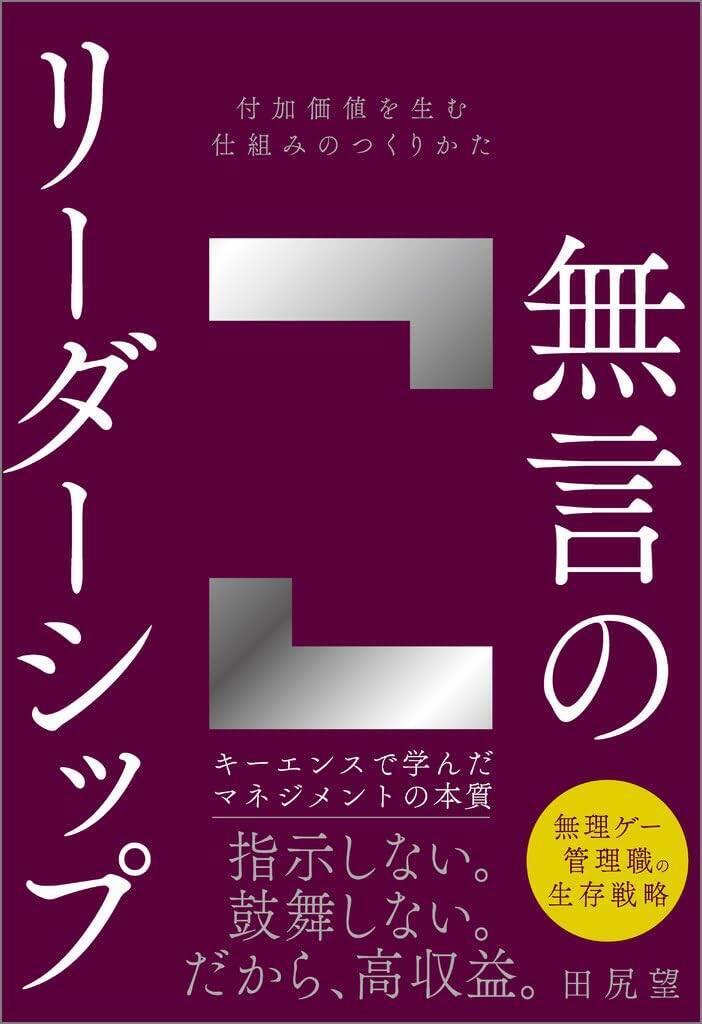
リーダーに「言葉」は要らない
◎ベストセラー『付加価値のつくりかた』『再現性の塊』『「キーエンス思考」×ChatGPT時代の付加価値仕事術』の著者最新作。
◎キーエンス本の火付け役である著者が、指示しなくても自然と成果が上がる「キーエンス×田尻」式のマネジメント手法を一挙公開!
成果を出すリーダーの多くは、いくつかのミーティングを除けば、部下との会話はほぼゼロである。一方、成果を出せないリーダーの多くは、口頭指示や質問などの対応に追われ、自分の仕事は定時後や休日に片付けることになる。
もし、あなたが言葉を尽くさないとチームが成果を出せないのだとしたら、それは仕組みができていない証拠だ。
「無言」になれるかどうかは、単に「しゃべる」「しゃべらない」の話ではない。
最小の時間と資本で、どれだけの付加価値を生み出せるかというマネジメントの根幹を問うテーマなのである。
(はじめにより抜粋)
[目次]
はじめに リーダーに「言葉」は要らない
序章 ここから始まる「無言」の構築
第1章 準備編:信頼と合意を築くマインドセット
第2章 問題解決編:目標達成を阻む壁を取り除く
第3章 仕組み化編:成功をくり返す、失敗をくり返さない
第4章 付加価値編:仕組みから付加価値を生み出す
終章 リーダー不要の組織へ
おわりに リーダーシップが苦手だった私がたどり着いた答え































![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


