
経営学者として組織や若者について研究する舟津昌平氏によると、Z世代をはじめとする若者には「肯定される側にはいなきゃダメだけど飛び抜けたらダメ」という心理が働いていることが多いという。その心理をもとに彼らのキャリア論を考えたときに、彼らが発する「成長」という言葉には違和感がある。
書籍『若者恐怖症――職場のあらたな病理』より一部を抜粋・再構成し、彼らが好んで使う「成長したい」という言葉の矛盾を明らかにする。
「成長したい若者」の謎
成長したい若者は「実在」するのか。この問題は既にある程度答えが出ている。
まずは構築主義的な視座から「社会的にそう思われていること」と実態が乖離している可能性がある。率直に言えば、「成長をしたい」若者がメディアその他によって作られていると考えうる。バズり目的、浅い印象論、あるいは面白おかしく切り取られることで、ないものがあるように語られる。間違ってはいないし残念ながら一部は正しいだろう。
問題はそれ「だけ」で終わらない。核心は、存在しないものが作られることではなく、作られたものがなぜかリアリティをもって受容され社会に根付いていく点にある。メディアが勝手に作っていると冷笑しながら、なんとなく受容して楽しまれてもいるはずだ。
実際に転職は別に増加していないにもかかわらず当たり前のものとして「一般化」している。一抹の真実性を感じるからこそ、作られた言説は社会に根を張るのである。
また、離職と離職志向は違うことにも注意が必要だろう。
バランスを崩したいですか?
成長したいと答える若者が実際に成長をしたがっているとは限らない。この一見意味不明な文を理解するためにエピソードを紹介しよう。
ワークライフバランスという概念がある。仕事と家庭(プライベート)がバランスできていることを意味する。働き方改革にともなって普及し、「若者はワークライフバランス重視」「だから飲み会も断る」といった言説が一般的に聞かれるようになった。
筆者も気になって「みなさんやっぱりワークライフバランスを重視しますか?」と学生に問うてみた。ちなみにワークライフバランスは非常に言いづらく5回くらい嚙んだ。
すると、かなりの割合で「重視」に手が挙がる。なるほどやはり…と思ったところで、ある学生から質問が飛ぶ。「すみません、ワークライフバランスって何ですか」。言葉を知らなかったらしい。
「? わかりました、ありがとうございます。意味はわかりました。でもそれって変じゃないですか? バランスできている状態をイヤって言う人いるんですか?」
ハッとさせられるような意見である。
ワークライフバランスは字義の通りワークとライフが「バランス」している状態を指す。そしてバランスは「うまくいっている状態」を意味として含む。だから若者に「ワークライフバランスを重視しますか?」と訊いて、否定的な答えが返ってくるわけもない。
「いや私はバランスを崩してでもどちらかを取りたい!」とはそうそう思わないだろう。片方をおざなりにするでなくバランスを取れているほうがいいだろと思うのは当然だ。
こうして若者は「ワークライフバランスを重視する」のである。ある概念への是非や志向を問うとき、往々にして「社会的望ましさ」が未然に潜り込んでいる。
また書籍『静かに退職する若者たち』の著者、金間大介氏は結論として、まず「意識の高い」若者は一部だが存在する(体感1~2割)と述べる。加えて知識やスキルの獲得におけるファスト化と平均値からの脱落への恐怖を成長志向の高まりの要因に挙げる。成長なるものが簡単に短期間で得られると理解(誤解)されており、「みんなやってるから」ととりあえず同意しておくわけだ。
こうして「みんな本当に成長したいとは思っていないのに、調査をしてみると成長を重視しているという結果が得られる」状況ができ上がり、成長神話が形成されていく。
他己肯定を求める若者たち
成長神話がウソとも言い切れないのは、若者自身が「他者との比較における不安」を吐露するからだ。若者を象徴するフレーズとして「ありのままでいたい」と「何者かになりたい」がある。
「ありのままでいたい」とは、まさに自分が自分らしくあるということだ。個性の尊重と発揮、自然体、他人に押し付けられないといったフレーズと密接である。
「何者かになりたい」は成長とも関連している。誰しも他者と比べて特別な存在になりたいのである。やや下火になってはいるもののSNSでいいねを求める傾向、「インスタ映え」という言葉が生まれた背景でもある。
昨今、自己肯定感という言葉がよく用いられる。通俗的な自己肯定感とは実質的に「他己肯定感」であろう。
若者のインスタ利用について調べたとき印象的な回答があった。
「イケてるグループに入ってはいるけど、イタくないというのがめっちゃ大事で」
肯定される側にはいなきゃダメだけど飛び抜けたらダメなのだ。本当かはわからないけどみんなが成長したいって言うなら自分もする側じゃないといけない。ただ別に本気ではない。成長できるっぽい気がすればそれでいい。
成長「実感」は実に便利な言葉である。実感に成長は必要ない。それっぽいワンデー研修で成長を実感することはたやすい。ただ現実的に1日で人は変わらない。
成長と成長実感の明確な違いは時間軸である。
「石の上にも三年と言うが最近の若者は三年待てない」みたいな話がよく聞かれる。これは、明確に若者側が間違っている。キャリア全体を見通したとき三年は短すぎる。三年で達成し完遂できる程度の成長は、キャリア全体で見れば些末である。志が低いならいいのだけど。
もちろん、特に若いときの三年はめざましい成長「率」をもたらす。ただ成長という時間のかかるものを念頭に置いておきながら「三年も待てませんよ、われわれは成長したいので」などと言うのは単純に自己矛盾である。
若者恐怖症ーー職場のあらたな病理
舟津 昌平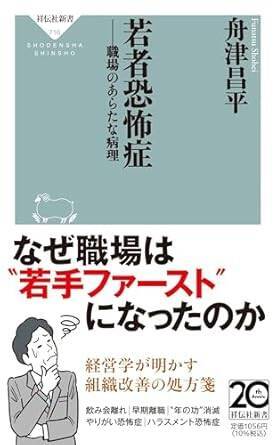
「若者がこわい」は、職場に潜むあらたな病だった。
気鋭の経営学者が読み解く“年の功”消滅社会の正体
「コンプラ大丈夫?」「それ、ハラスメントですよ」
こんな言葉が飛び交う現代の職場では、若者に対する漠然とした恐怖が広がっている。
少子化による超・売り手市場により、年功序列のパワーバランスは逆転した。
そんな時代、上司や先輩社員は若手への適切な指導や対話ができずに悩み、ときに「どうせすぐ辞める」「関わるだけ損」などと、距離をとってしまう。こうした空気が、職場に深刻なコミュニケーション不全をもたらしている。
本書では、経営学者・舟津昌平氏が、「飲み会離れ」「早期離職」「やりがい・成長」「ハラスメント」などのキーワードを手がかりに、職場で静かに進行する“若者恐怖症”の実態を明らかにする。
データと現場の声をもとに、通説の矛盾を暴き、世代間の不信やすれ違いの背景にある社会構造を読み解いていく。
部下のマネジメントに悩む管理職はもちろん、20代・30代にも、Z世代にも読んでほしい、
すべての働くひとに向けた、職場改善の処方箋。
【目次】
はじめに 老害になりたくないあなたへ
第1章 若者恐怖症─たとえば、飲み会恐怖症
第2章 若者論の交通整理─Z世代をたらしめるもの
第3章 そして何が問題なのか─神話の喪失、竹槍と学徒動員
第4章 離職恐怖症─若者はすぐ会社を辞めるのか
第5章 やりがい恐怖症─若者は成長しないといけないのか
第6章 ハラスメント恐怖症─若者はなんでもハラスメントって言うのか
第7章 持病とつきあっていく─いっしょに恐怖を飼い慣らす




























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


